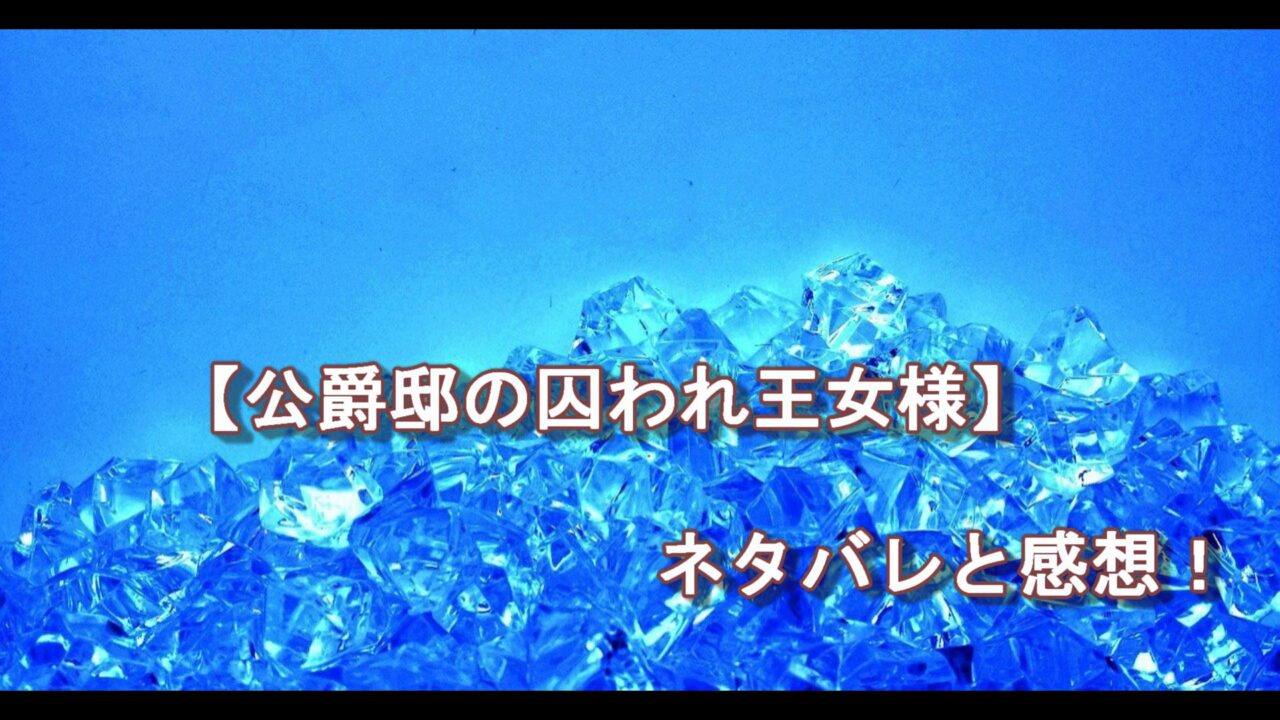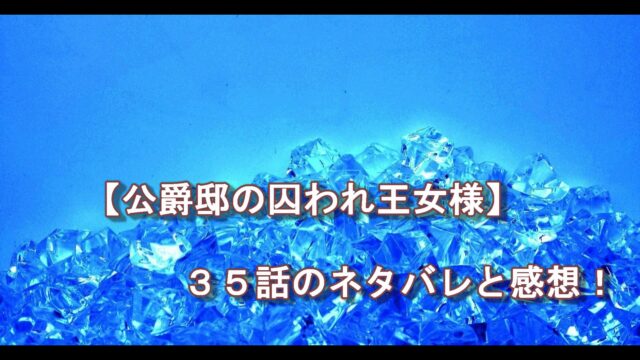こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
今回は73話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

73話 ネタバレ
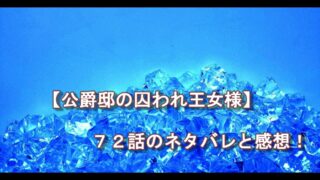
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- いつの間にか15歳③
ハイデンの秋の祭りに合わせてマクシミリアンが首都に来たのは、夫人のブリエルとその母親であるウッズ夫人のためだった。
ウッズ夫人の病状はかなり回復しており、現在、彼女はハイデンの住居地域で一人で暮らしているという。
何度かブリエルは彼女と一緒に暮らしたいと願い、セリデンに招待もしたが、ウッズ夫人はいつも丁重に断り、首都での暮らしが便利だと答えた。
マクシミリアンはブリエルがいつも母親を大切にしていることを知っていたため、秋の祭りのように「家族」が一緒に過ごす日に、ウッズ夫人と一緒に時間を過ごすために首都にやってきた。
「公爵様、前回申し上げたことをお考えいただけましたでしょうか?」
ウッズ夫人は公爵の義理の母の立場でありながらも、いまだにマクシミリアンを主人のように扱った。
彼がどれほど謙遜しても、彼女は長い間身につけてきた習慣でどうすることもできないと。
しかし、マクシミリアンが見る限り、彼女には・・・何か別の考えがあるように思えた。
「我がブリエルの親族を探す件のことです。」
「まったく、母上も!そんなことはもう良いではありませんか。」
ブリエルの懇願にもかかわらず、ウッズ夫人は穏やかな態度を崩さなかった。
「探さなければ。必ず探さなければならない。その人たちを。君が立派に成長した姿をどれほど見たいと願っているか。」
「・・・そんなことはないでしょう。」
ブリエルは母親に会う前の記憶が全くなかったが、それを残念に思ったこともない。
明らかに、自分を育てられない未熟な人々が無責任に子どもを手放したのだろうと思っていた。
新聞を見れば月に一度はこのような話、つまり無責任な親が子どもを見捨てるという記事が載っているではないか。
「君がどれほど良い服を着ていたかは知らないけど、話しぶりからしてもきっと愛されていたと思うよ。私は君が普通の子どもではないと確信している。」
「どうせ彼らには私が必要なかったから捨てたのでしょう。」
「事情も知らないのに、そんなふうに言うべきではないわ、ブリエル!」
「私は彼らの事情には興味がありません。私の母はここにいらっしゃる方なのですから。」
ブリエルはウッズ夫人の隣にぴったりと寄り添った。
彼女は座って腕を組み、頭を軽くうなだれていた。
「お願いです、公爵様。」
ウッズ夫人は愛しい娘をそばに置きながら、公爵にじっとした目で訴えかける。
「公爵様、この老人の願いを聞かないでください。生涯の願いなのです。」
「ウッズ夫人、恐らくお分かりかと思いますが・・・。」
彼はウッズ夫人のそばから離れないブリエルをじっと見つめた。
彼女は普通よりもはるかに子供っぽい表情で甘えている様子だ。
「その件は奥様の意思が最優先されるべきです。軽はずみに始めてしまうと、かえって傷つける結果になる可能性もあります。」
「そんなことにはなりません。この老人を信じてください。」
ウッズ夫人はきっぱりと言い切った。
「ブリエルは私に会う前から間違いなく両親の愛情をたっぷり受けた子供でした。そうでしょう?」
「あり得ません。当時のブリエルをご覧になった公爵様も、同じように考えられたと思いますよ。」
公爵は再びブリエルを見つめる。
視線が合うと、彼女はかすかに顔を伏せた。
まるで望んでいないということを物語るかのようだった。
「お母様、いずれにせよ探す方法がありません。新聞や雑誌に『公爵夫人の親族を探しています』と広告を出すわけにもいきません。」
「十数年前は、王家と魔法師団との関係が悪くない時期でした。もし生活に余裕がある家族だったら、魔法師団に親の血を依頼して調査をお願いすることができたでしょう。」
魔法を利用して血液に含まれる情報を分析することで、家族関係を証明することができた。
裕福な人々が不慮の事故で子どもを失った場合、魔法師団にその血を頼って子どもを探すことを申し出ることもある。
「本当なんですか?もしかしたらそこで見つけられるかもしれませんね!」
「ですが、10年も経っているんですよ、お母様。もし私がそんな立派な家族の娘なら、既に魔法師たちが探していたでしょう。彼らは万能なんですから。」
「いや、それでも一度調べてみてもらえないかな?ね?」
「どうせ何も出てこないでしょう。無駄骨を折るだけですよ。」
「やってみよう。お願いだよ、娘や。これが私の一生の頼みなんだ。」
ウッズ夫人が強硬な態度を崩さないと、ブリエルはどうすることもできず、視線を伏せる。
そして条件を付けた。
「魔法師団から何も出てこなければ、お母様にも諦めてもらわないといけません。」
「・・・」
「私はただ・・・お母様がいてくれるだけでいいんです。他の人を親として望んだりはしません。」
「それでも公爵夫人になった以上、相応の親がいなければ・・・。」
「お願いです、お母様!」
ブリエルが甲高い声をあげる。
ウッズ夫人はブリエルの震える背中を優しく叩きながら言った。
「はあ、分かった、分かったわ。私も約束するわ。だから、さあ、早く行きなさい。」
結論を出したウッズ夫人は二人を急かし、その場から送り出した。
「こんな家に長居するのはよろしくない」と付け加えながら。
マキシミリアンとブリエルは、もう少し留まりたいと願ったが、夫人の強い意志に逆らうことはできなかった。
彼らは三番目の城壁の中に戻る馬車に乗り込んだ。
祭りの喧騒に満ちた道を行く小さな馬車の中では、出会ったばかりの二人の間には微妙な距離感がある。
彼らが「正式な結婚生活」を始めてから、すでに5年が経っていた。
そろそろ互いの存在に慣れるべき頃合いだが、それでもまだぎこちなさが残っているようだった。
緊張感のある接触に、張り詰めた空気が漂った。
「セリデンへ・・・。」
マキシミリアンは窓の方に身体をそらし、か細い声で言った。
「帰り道に魔法士の城を経由した方が良いと思います。」
「本当にそこへ行くのですか?」
驚いたブリエルは、彼を鋭く見つめた。
近い距離が気まずかったのか、彼は再び視線を足元に落としてしまった。
「もし公爵様にも私のような高貴な両親がいれば良いのですが・・・。いや、申し訳ありません。」
「ウッズ夫人は・・・。」
マキシミリアンは答える代わりに、ウッズ夫人の話を持ち出す。
それがブリエルにとって、さらに重苦しいものに感じられたのはなぜだろうか。
「ただ、あなたを守る人を一人でも見つけたかっただけです。」
「・・・」
「夫人がそのような心配をされるのは、私が・・・あなたを危険な場所に巻き込んでしまった責任があります。本当に申し訳ありません、ブリエル。」
「それは、公爵様が謝ることではありません。私が選んだことです。この場を守ると決めたのは私です。」
ブリエルは涙をこらえるように目に力を込め、マキシミリアンをしっかりと見つめる。
その瞬間、まるでかすかな記憶がよみがえるように、マキシミリアンはウッズ夫人の言葉を思い出していた。
『君がどんなに上等な衣装を着ていたか分からない。君が普通の子ではないと確信している。』
いや、正確には夫人が話していた、彼女の幼い頃の姿・・・彼が覚えているある可憐な少女の記憶がよみがえってきた。
ある日突然行方不明になり、永遠に再会できなくなった少女、シィシィ。
その少女のことを話すとき、人々はこんな風に・・・。
彼は両目に力を込め、マキシミリアンをじっと見つめた。
「・・・あ。」
彼の頭の中で突然、思いがけない考えがよぎった。
「公爵様?」
「私が間違っていました。」
「え?」
「いや、その・・・。」
こんなに愛らしい人を目の前にして、どうして他のことを考えることができただろうか。
「何か深くお考えだったようですが、もしかして私が邪魔をしてしまいましたか?」
「いえ、私はただ、あなたの純真さが・・・好きで・・・。」
彼はその言葉を大事そうに口にしながら、どこか愛おしそうに見つめていた。
そう、本当に真心からそう感じていたのだ。
その瞬間、ブリエルは何かを悟ったような声を上げた。
「はっ!」
何かがうまくいったかのように、彼女は手をぱちんと叩いた。
彼女を好きだという告白の言葉を忘れたかのように、マキシミリアンは彼女を振り返って見つめた。
「それにしても、ここからまっすぐ魔法使いの城に向かえば、クラリスが本当に喜ぶでしょうね!」
「・・・え?」
なぜそんな考えが突然浮かんだのか、自分でも分からなかったが、マキシミリアンはすぐさま彼女を追いかけ、クラリスに関する話題を広げる。
彼女は魔法使いのノアとシネットに、祭りで会おうと招待を送っていたが、何らかの理由で断られたと聞いた。
彼らに会えなかったことを思うと、首都に戻ることがどれほど心残りだったのか想像できない。
「もう半年も経ちましたよね? 魔法使いのシネットとクラリスが会えていない期間というのは。」
「確かに、そうです。」
「二人を再び会わせることができるのなら、魔法使いの城に行くのも悪くない選択肢ではありません。」
「本当にそうですね。二人が一緒にいる姿を見ると、本当にかわいらしいと思います。」
「そうですか?」
マキシミリアンは、初めて敬意を持ったようにウッズ夫人の言葉を受け入れざるを得なかった。
彼がノアとクラリスを初めて見たとき、彼らは胸の中に納まりきらないほど小さく、ただその存在だけで愛らしいと称賛されたものだった。
しかし、今では少し様子が変わってきていた。
半年ほど前、彼がクラリスのそばに立つノアを見たとき、妙な違和感を感じてしまった。
なぜなのかは分からないが、そういうことだ。