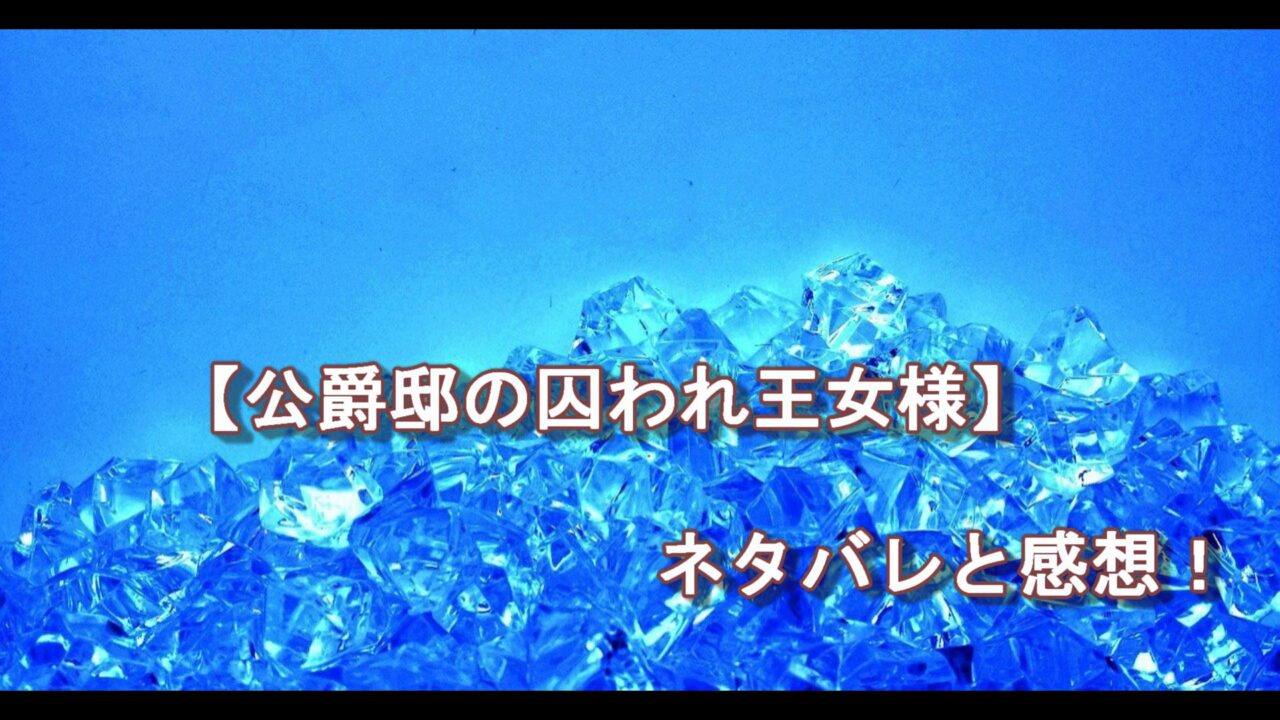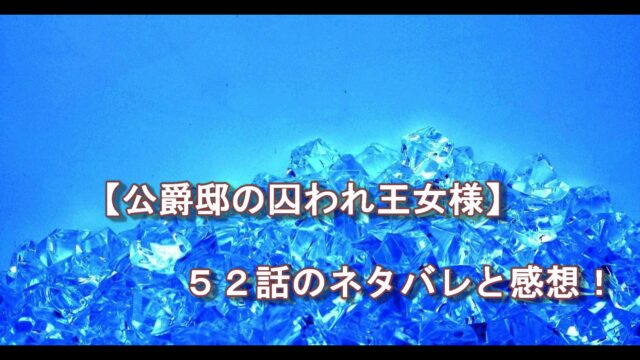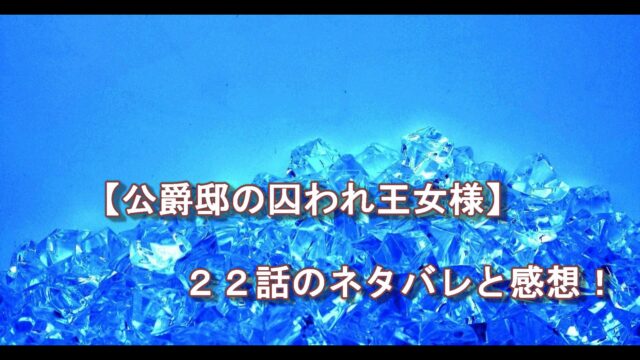こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
今回は75話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

75話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 魔法使いの城
ノアはクラリスが9歳だった頃から12歳になる年まで、「崩れたゴーレム」の現場で研究を続けていた
しかし、どれほど優れた魔法使いであっても、石や鋼鉄を操るゴーレムマスターには敵わず、それ以上の大きな成果を上げることはできなかった。
強大だったゴーレムマスターの力が染み付いた石は、他のどんな力を加えても微動だにしなかったのだ。
結局、彼の持つ魔力で崩れたゴーレムに残っていた魔力を調査し、その石の隙間には王室の宝物といくつかの遺体が存在していることを確認しただけだった。
3年前、ノアは「これ以上実質的な研究は進められない」という結論に至り、一時的に北側の城壁から他の魔法使いとともに撤退した。
いや、むしろ研究そのものを放棄したと言えるかもしれない。
クラリスは、研究を愛してやまないノアがそのような決断をしたのは、ひょっとすると自分のせいかもしれないと推測している。
もしかすると、ノアが研究を続けるという意志を示した場合、ゴーレムマスターを見つけようとする魔法使い団の意志が高まることを危惧したのではないかと心配しているのだ。
もちろんノアは「絶対にそんなことはない」と否定したが。
しかし、ノアが魔法使いの城に戻って以降、二人は以前のように頻繁に会うことはなくなっていた。
それでも、時折ノアがセリデンにクラリスを訪ねてくることがあった。
しかし、ノアが17歳となり、魔法使いとして前途有望になった後は、実際に会う機会が極めて少なくなってしまった。
たまに手紙で近況を伝え合うことはあったものの・・・。
(早く会いたい、ノア。)
クラリスはすでに半日以上走った馬車の中で窓枠にもたれ、景色を眺めていた。
まだ魔法使いの城は見えてこない。
(ノアが住む場所に行くのは初めてだわ。)
毎回会うたびに、少しずつ背が伸びていたノアが、今回はどれほど変わっているのか。
少しだけ期待もしていた。
王都ハイデンから西へ向かい、馬車で丸一日半走り続けると、セイファス王国で最も高いとされるヘルバン山脈にたどり着く。
魔法師団の本拠地と呼ばれる「魔法使いの城」は、この山脈の絶壁中腹に建てられたもので、かなり高い崖を越えなければその入口に到達することはできない。
馬車の窓越しにその巨大な建物を見上げたクラリスは、ここが果たして邸宅ではなく「城」と呼ばれるのも納得した。
しばしば物語の本に登場する「城」とはまさにこのようなもので、いくつもの鋭く突き出た青い屋根が絶壁の先端に堂々とそびえ立っていたからだ。
圧倒されるような感動を覚えたクラリスは、ノアに会ったら必ず一言言うと決めた。
これまで彼は「魔法使いの城は人が住む場所ではない」と主張し、まるで怪物が棲む洞窟のように表現していたのだから。
「こんなに美しい場所だなんて。」
案内を受けて中に入ると、室内の光景にクラリスの心はさらに高揚した。
「高価そうな大理石がたくさん!とても綺麗・・・。」
美しい石が芸術的な形で加工された内部は、まるで天国そのもののように感じられた。
どこを見ても、まるで何かを語りかけてくるような石ばかりだ。
クラリスは思わず手を伸ばして軽く挨拶でもしたくなる衝動を抑える。
これまで隠してきた彼女の本性を、ここでさらけ出す必要はないと思ったからだ。
「こんにちは、クラリス嬢。」
マクシミリアンの背後で周囲を見回していたクラリスに、一人の男性が話しかけてきた。
彼は玄関から公爵夫妻を迎えた魔法使いで、ノアと同じ白いローブを身に着けていた。
唯一の違いは、その頬に目立つほど深い傷跡があることだった。
「こんにちは。」
クラリスはできるだけ怯えている様子を見せないように、その傷跡が印象的な男性に目を向け、礼儀正しく挨拶を返した。
「アルステア・アストです。以前、セリデンでお会いしたことがあるのですが、覚えていらっしゃいますか?」
「え?申し訳ありません。アルステア・アス・・・ト?」
記憶がないことを謝ろうとしつつ、その名前を繰り返したクラリスは、言葉に詰まりそうになった。
目の前の男性は、ノアがとても敬愛していた師匠だ。
彼はすでにこの世を去った人物だが、クラリスは「魔法使いアスト」としてその名を聞いたことがある。
「ノアがきっと、彼の父のことをあなたに話していたのですね?」
「はい、とても尊敬されていた方だと伺っています。そしてそのご子息であるあなたも、非常に素晴らしい魔法使いだと。」
「ノアが私についても何か話していたのですか?それは意外ですね。」
「ええ、かなり昔のことですが。」
恐れを完全に振り払ったクラリスは、少し気を緩めて肩に垂れている白いリボンをそっと触りながら答える。
「将来、魔法使い団の団長になる方だと聞いています。あ、今から団長様とお呼びしたほうがいいでしょうか?」
ノアがそのように話していたのは、もう4年前のことだった。
クラリスは、魔法使い団の団長がどのように選ばれるのかは知らなかったが、時間が経った今、その人が団長になっているのだろうと思っていた。
「うーん・・・。」
アルステアは少し困ったような微笑を浮かべた。
「ノアが私のことをそんなふうに話しているなんて、思いもしませんでした。」
「え?」
「いいえ、正直に言うと、まだ団長の座は空席なんです。魔法使い団のトップの地位が、いまだに誰にも引き継がれていない状態なんですよ。」
「あ。」
クラリスは少し腰をかがめて顔を伏せた。
「無礼を働いてしまいました。申し訳ありません。」
「いやいや、そんなに謙虚になる必要はありませんよ。お褒めの言葉を頂けて光栄です。」
その時、彼らのそばに灰色のローブを身に着けた魔法使いたちが数名近づいてきて、オルステアだけに向かって深く一礼した。
その様子から、貴族の公爵に対して彼らが同じように敬意を示すことはほとんどないのだろうという暗黙の了解が見て取れた。
クラリスは、こういった魔法使いたちの態度が少し不快だったが、公爵夫妻はまるで気にも留めていないようだ。
「採血室の準備が整いました、アスト殿。」
「そうですか? ありがとうございます。」
オルステアは公爵を振り返り、言葉を続けた。
他の魔法使いたちとは異なり、オルステアは公爵に対しても非常に礼儀正しく振る舞っていたため、クラリスは彼に少し好感を持つ。
「それでは、公爵様と公爵夫人には私と一緒にお越しいただきましょう。ただ・・・血を採取する様子は幼いお嬢様が見るにはあまり良くないかもしれませんが、どうされますか?」
「クラリス、まずは魔法使いのシネットに会ってきてくれるか?」
公爵は視線をクラリスに向けて、彼女の意向を尋ねる。
「私だってノアに会いたいですけど、公爵夫人にとって大事な場面ですよね。私が側にいなくても大丈夫でしょうか?」
「もちろん大丈夫よ!」
公爵が返答する前に、ブリエルが先に答えた。
「何よりも魔法使いアスト殿が言った通りです。若いクラリスには見せるべきではない、と。」
クラリスは自分がまだ幼いと思われていることに抵抗を感じた。
しかし、生々しい血の場面については本能的に拒絶感を覚えた。
それは幼い頃に経験した戦争の後遺症かもしれなかった。
「それでは私は魔法使いのシネットと一緒にいますね。」
「その方が私も安心できます。後で挨拶するつもりですが、魔法使いシネットによろしくお伝えください。」
「分かりました。」
アルステアはすぐに大広間に控えている魔法使いに指示を出し、クラリスを案内するよう命じた。
「こちらの魔法使いについて行けば大丈夫です。ノアの部屋は遠くありませんので、あまり時間はかからないでしょう。」
クラリスはお礼の挨拶をした後、案内を任された灰色のローブをまとった魔法使いについていった。
「ご案内いただきありがとうございます、魔法使い様。」
親しみを込めてお礼を述べたにもかかわらず、魔法使いはただ軽く頷いただけで、黙々と先を進んだ。
「ま、魔法使い様!もう少しゆっくり・・・。」
クラリスは一生懸命ついていこうとしたが、すぐに距離が広がってしまった。
「・・・貴族は体力訓練もしないのか?」
彼がちらりと振り返りながら投げかけた質問に、クラリスは息を切らしながら、ようやく答える。
「えっと、私は・・・貴族ではありません。」
彼女の答えに反応して、灰色のローブをまとった魔法使いは驚いたようにフードを脱いだ。
クラリスはようやく彼の顔をはっきり見ることができた。
彼は背が高く、一見すると年上の大人に見えたが、顔立ちはクラリスに少し似ているか、やや年上の少年のようだ。
「君、セリデン公爵の娘じゃないのか?」
どうやら彼は魔法使いの城の外の事情には疎いらしい。
外の世界では、セリデン公爵に跡継ぎがいないという事実を知らない者はいないのだが。
「クラリスと言います。公爵様の娘ではありません。私は・・・。」
彼女の言葉が終わる前に、彼は視線をそらし、何か思慮深い表情を浮かべた。
「幼い頃から働いていたようだね?公爵家のわがままな娘かと思ったが、もっと慎ましい子供だったとは。」
「え?」
「全く、貴族というのは、こんな幼い子供の助けも借りられない役立たずばかりなのか。」
「いえ、私は・・・子供じゃありません。十五歳です。」
クラリスは反論したいことがたくさんあったが、とりあえずそのことだけを言及した。
「十五歳?僕と同い年だって?」
彼は再び驚いたように彼女の前に立ち、じっと彼女の身長を測るように見つめた。
「成長状態を見る限り、食事も十分に与えられていないようだね。」
「え?いや、私はちゃんと食べてます・・・。」
「嘘だ。乾いたパンか、せいぜい水に浸したものを食べさせられているんじゃないか?」
「いえ、そんなことありません。」
「主人だからといって遠慮する必要はないさ。ここはどうせ貴族たちの威光から解放された空間なんだから。うん、安心していいよ。」
「本当に違います。私、二人とも本当に大好きなんです。」
「そんな馬鹿なことを言うな。」
彼はクラリスに振り返りながら、片方の唇をわずかに上げて嘲笑った。
「化け物に情を注ぐ貴族たちは本当に愚かだな。」
「化け物?」
「そうだ、魔法使いノアの眷属が人間ではないというくらいは知っているだろう。それにこれほどまでに情を注げるとは。」
クラリスはまるで背中を殴られたかのような衝撃を受けた。
彼女は以前、ノアが自分を「化け物」と称する言葉を耳にしたことがあった。
もっとも、ここ数年はそんな話を聞かなくなっていたため、ほぼ忘れかけていたのだが。
「奴のやつれた顔を初めて見た日のことを忘れることはない。あの哀れな目をして・・・」
「・・・。」
「公爵があの野郎に何か不幸があったら知らないが、君が望むなら会っている間は一緒にいてあげるよ。怖がらなくていい。」
笑いながら近づいた彼は、クラリスの髪を撫でようと手を伸ばす。
クラリスは顔をそむけ、一歩後退してその手を避けた。
「えっと、他の人に髪を触られるのが嫌なんです。」
「おや、そうかい?ごめんね。可愛らしいね。でも本当に15歳なの?」
「それより道を案内してください。」
この魔法使いと話をしている時間は無駄にするだけだった。
クラリスは無意味なやりとりで時間を浪費したくなかった。ノアに会う時間も限られていたのだから。
「わかったよ、行こう。」
幸いなことに彼はそれ以上何も言わずに再び先に立って歩き出した。
クラリスは安堵しながら彼の後について行った。
「・・・この先から道が少し複雑になるんだ。」
振り返った魔法使いが手を差し出して言った。
「掴まるかい?」
「いえ。」
「その方がいいんだよ。もし君が道に迷ってしまったら困るだろう?」
どうやらこの魔法使いは、クラリスの意見に耳を傾けるつもりはまったくないようだった。
「なんだい?手をつなぐのも嫌なのかい?」
「はい。」
「そう見えるなんて随分生意気だね。公爵家の主従らしいやり方だ。」
彼は今にも許可を求めることなくクラリスの腕を掴もうとした。
しかし、普段からマキシミリアンによる「安全教育」を徹底的に受けてきたクラリスの反応は一層素早かった。
彼女は剣術を習得することはなかったが、「許可なく触れる」行為を試みる男性への対応は見事だった。
彼女は「緊急時の対処法」として唯一の技術を徹底的に訓練されている。
反復訓練の利点といえば、状況が迫ったときに身体が先に反応するという点だった。
繰り返された訓練の成果を示したかった彼女の右足が、力強く床を蹴り上げた。
クラリスの意図を察した魔法使いが慌てて体を引こうとしたが、すでに遅かった。
彼はまさに死に近い苦痛を味わうことになった。
彼女の足から放たれた強力な力が彼の中心を直撃し、彼は地面に近づいていった。
クラリスはついに公爵からの長年の教えを実行できたことを示し、満足そうな笑みを浮かべた。
だが彼を攻撃したその直後、彼女の身体がなぜか宙に浮き上がるような感覚がした。
驚いた彼女は下を見下ろした。
地面から浮いたままの両足はもがき、彼女の体は徐々に後ろへと引っ張られていった。
そして、しばらくして――。
クラリスは誰かの手に支えられ、優しく地面に着地することができた。
そして、その場で横を振り向くと――。
見慣れた猫の仮面が目に入った。