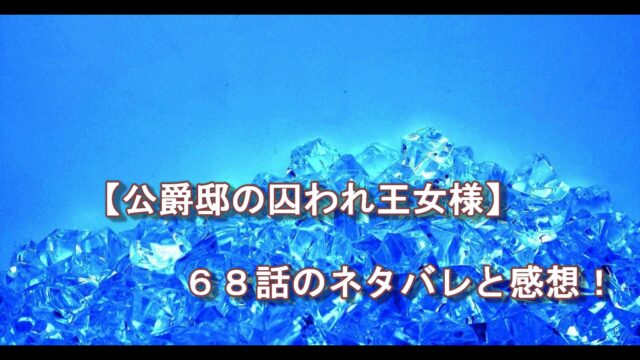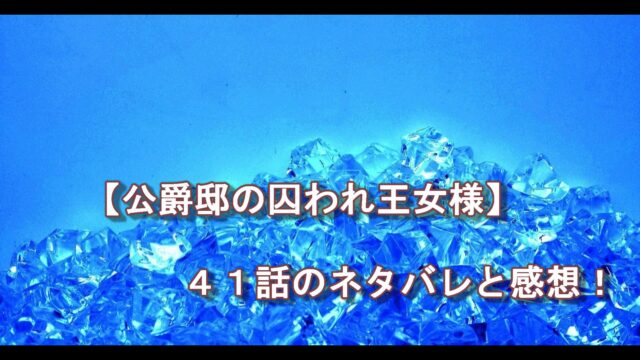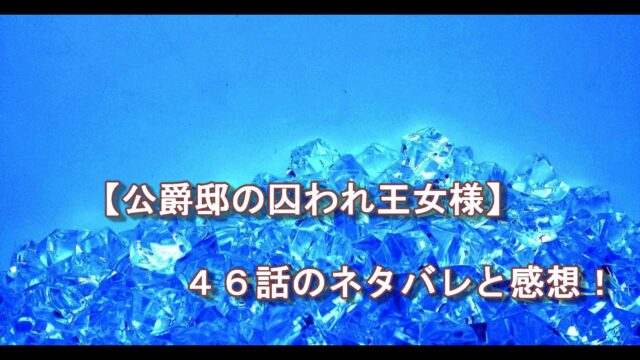こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

96話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 贈る花⑦
クラリスが夫人と一緒に応接間で会話をしている間、ノアとヴァレンタインは別の場所でぼんやり座っていた。
最近、彼らは何かとよく会話をするようになっていたが、それはあくまでクラリスがいるときに限られていた。
しかし、彼女がいないと、彼らはソファの端に座ったまま、お互いに目も合わせず、話しかけることもなかった。
しばらくの沈黙の後、最初に口を開いたのはノアだった。
「……少女が遅いな。」
少し気になったのか、ノアは彼女が去った応接間の扉を何度もちらちらと気にしていた。
「そうだな。」
ヴァレンタインが淡々と答えたため、ノアはじっと彼を見つめた。
「友達だと言いながら、なぜ心配しないんだ?」
「お前は友達だと言いながら、信じてないのか?」
「信じることと心配することは別問題だよ。」
「ほとんど同じようなものだ。お前は階段を一段上がるのにも苦労する犬のように、いつも気を揉んでいるじゃないか。」
「そんなことはない。」
「いや、あるぞ。お前が無意識に心配しながら、つま先をそわそわ動かしているのを何度見たと思う?」
「・・・」
ノアは反論できなかった。
それは幼い頃から続いてきた習慣だったからだ。
セリデン公爵が「クラリスが騎士団で危険な目に遭わされるのではないか」と心配していた時、ノアは「一緒に見守ります」と答えたことがある。
それ以来、ノアはクラリスが階段を降りるときに、必ず足元を確認するようになった。
だが今ではすでに習慣になってしまっていた。
「でも、ヴァレンタインも大して変わらないよな。」
「俺が?ばかばかしい……。」
「礼拝堂を掃除するときに使う、あの二段のはしご。知らない間に修理されていたの、知ってたか?」
掃除をする人の中で、そのはしごを使って装飾品を拭くのはクラリスだけだった。
最初はグラグラしていたはしごが、次の日からはすっかり安定していたのは、ヴァレンタインの細工によるものだった。
「あ、あいつがうっかり落ちたら、手間が増えるだろ!」
「たかが少し揺れるくらいの低いはしごから、十歳の子供だって落ちないよ。それなのに、俺が心配しすぎだって言うのか?」
「ま、とにかく! 俺は友達としてやるべきことをやっただけだ。この友情を理解しないなんて、まったくもって嘆かわしい!」
「いや、君のその誇らしげな友情に気づかなくても——」
クラリスと俺の間には、長い年月をかけて築かれた堅固な友情がある。
「傲慢だな!今、全部言っちまったな……!」
ヴァレンタインが立ち上がり、鋭い声を上げたその時、ちょうど応接室の扉が開いた。
侯爵夫人が戻ってきたのだ、クラリスと一緒に。
大声を出していたヴァレンタインは驚き、ぎこちない笑みを浮かべた。
気まずそうに口元がピクピク震えている。
「ふ、夫人……お帰りなさいませ。我々はずっとここで、お待ちしておりましたとも。」
どうにか誤魔化そうとするが、そんな言い訳が通じると思っているのだろうか?
「本当にです!とても熱い友情を……。」
クラリスは相変わらず「良き紳士」を装っているヴァレンタインを見かねて、彼を助けることにした。
「嘘だって、もうお伝えしましたよ。だから、もうやめていいんですよ。」
「……何?」
ヴァレンタインは驚き、クラリスと夫人を交互に見つめた。
「お、お前!そんなこと、俺たちの許可もなく勝手に白状しちゃって、どうするつもりだ?!」
「でも、いつまでも嘘をつき続けるのも変でしょう? 最初の頃は、まったく求愛しているようにも見えなかったんですよ?」
「嘘をつくな!誰が聞いても、あまりに衝撃的すぎて寝られなくなるような話だったじゃないか!お前も試しに言ってみろよ!」
ヴァレンタインはノアの肩をつかんで揺さぶった。
ノアは深く息を吐き、椅子から立ち上がると仮面に手を触れながら、淡々と答えた。
「若者なら、真実を語って帰ってくるものだと思ったんですよ。」
「ふざけるな!」
だがヴァレンタインは彼の仮面のすぐ前まで顔を近づけ、怒りを滲ませた声で叫んだ。
「お前、ただどこかへ行って、馬鹿みたいにぼーっとしてただけなんじゃないのか?!」
「そんなことはない。」
「はぁ、気が狂いそうだ……。」
夫人と視線が合うと、一瞬本性を露わにしたことが恥ずかしかったのか、ヴァレンタインは凍りついたように姿勢を正し、礼儀正しく腰を折った。
「さ、騒ぎを起こして申し訳ありません、侯爵夫人。ただ、我々の楽しみや娯楽のためにしたことではないということだけはお伝えしたいのです。」
「もちろん分かっていますよ。私が失望するのではないかと、気を遣ってくださったのですね?」
「そう受け取っていただけるなら感謝いたします。」
「ええ、とても楽しいひと時でした。お二人のおかげで、今日は特別な日になったようです。」
クラリスはクノー侯爵夫人の前に立ち、丁寧に礼をした。
「夫人、そろそろ我々はお暇するのがよろしいかと存じます。」
「残念ですが、もうかなりの時間が経ちましたし、それが良さそうですね。」
「そうですね……ああ……。」
別れの挨拶をしようとした夫人は、何かを思い出したのか、しばし躊躇った後、クラリスの両手をそっと握った。
「もしかして……来週もまた来てもらえますか?」
クラリスは、来週がちょうど彼女の娘セシリアの三十歳の誕生日であることを思い出した。
その日を境に、侯爵夫妻が娘に譲った爵位は、正式に家門の後継者へと引き継がれることになる。
そんな大事な日に……自分がここにいても本当にいいのだろうか?
「ああ、ごめんなさい。勉強でお忙しいところ、私のわがままを……。」
「いえ、行きます!」
夫人が少し残念そうな顔をしたので、クラリスは慌てて答えた。
「週末なら王都に行く予定です。少し時間を作って伺うのは難しくありません。いいえ、絶対に行きます。大切な日ですから、ぜひ来てほしいです。そうでしょう?」
「そう言っていただけて……ありがとうございます。」
クラリスが微笑むと、夫人は応接室のベルを鳴らした。
執事がやって来て、クラリスの外套と帽子を丁寧に手渡した。
その間に、侯爵夫人はノアとヴァレンタインの前に歩み寄った。
ヴェールをそっと唇に寄せ、クラリスには聞こえないように、小さな声で囁いた。
「では、私の娘を求める騎士様方に、三つ目の問いをさせていただきましょうか?」
ノアとヴァレンタインは、しばし互いを見つめ合った。