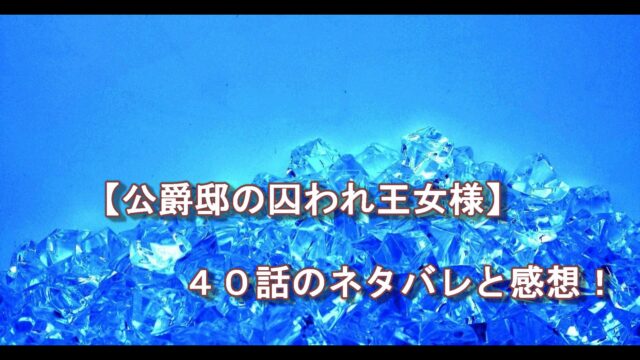こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

103話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 本当の身分③
バレンタインがクラリスのそんな顔を見てきたのも、もう6年目になる。
最初は、グレジェカイア出身の子どもが雪を珍しがるのは当然だと思っていた。
しかし、毎年のように雪が降るたびに、目を輝かせて喜ぶクラリスの姿を見ていると、むしろその反応の方が不思議に思えてきた。
一体、何がそんなに嬉しいのか。
雪が降れば、馬車の運行は不便になり、さまざまな業務にも支障が出るというのに……。
彼は深く息をついて待った。
毎年、クラリスが繰り返す、その幼いような感動の言葉を。
「王子様、雪が積もるでしょうか? ああ、どうか積もりますように!」という願いを口にするつもりだった。
「……よく積もらないといけないのに。」
「え?」
彼の予想とはまるで違う言葉が返ってきたことに、バレンタインは驚きを隠せなかった。
「はい?」
するとクラリスも、思わず驚いた表情で彼を見つめた。
ガラス窓にぎゅっと押し付けていたせいで赤くなった鼻先をさすりながら。
「どうして急に今まで言わなかったことを言うんですか? 毎年同じ言葉を繰り返していたのに、違うことを言うなんて。」
「だって……去年、王子様が私におっしゃったじゃないですか。」
クラリスは過去を思い出すように、視線をゆっくりと左へ向けた。
「雪が多く積もりすぎると、私に恵みを与えてくださる神殿の方々が大変になると。あの方々を支えるすべての人々も含めて。」
バレンタインは腕を組みながら、自分がどうしてそんな話をしたのか思い出そうとした。
その時、彼はクラリスとチェスをしていた。
いつものように、ほとんどバレンタインが勝っていた。
クラリスは眉間にしわを寄せ、どうにか彼に勝つ方法を探していた。
その真剣な顔は、とても滑稽だった。
しかし、雪が降り始めた途端、その間抜けな表情はどこかへ消えてしまった。
クラリスの意識は、彼とのゲームではなく、窓の外を舞う雪の粒に完全に奪われていた。
バレンタインが呆れてチェスの駒を下ろしたとき、クラリスは知らず知らずのうちに、凍った窓にぴったりと寄り添い、もっと雪が積もればいいのにと願っていた。
だから、あんな言葉を口にしたのだろう。
少し照れくさい気もした。
その話を聞いたクラリスは、頬を赤らめ、恥ずかしそうにしていた。
バレンタインは、それを少し……気まずく感じた。
「私はですね、王子様。」
いつの間にか、彼女は再び窓の外を見つめていた。
バレンタインは、理由のない罪悪感を抱き、ただ口をつぐんだまま、彼女の話に耳を傾けるしかなかった。
「その話を聞いて、私は本当にたくさん考えさせられました。そして……」
少しの間、黙っていたクラリスは、やがて控えめな微笑を浮かべ、口を開いた。
「やっぱりバレンタイン王子は、とても優しい方だと確信しました。」
「……。」
「普段の王子は、ちょっと意地悪に見えることもあります。でも、こうして美しく降る雪を前にしても、周りの人々の気持ちを考えているのですね。」
いや、それは……違う気がする。
バレンタインは、なんとなく良心の呵責を覚えた。
彼はクラリスが言ったことに対して大げさな意味を持たせようとしたわけではない。
ただ、彼女が目の前にいるのに、他のことに気を取られているクラリスが嫌だっただけだ。
実際、彼は兄や貴族たちの不便さについては何も考えていなかった。
望んでいたのはただひとつ。
クラリスがあの降り積もる雪の向こうではなく、自分の方を見てくれることだった。ただそれだけを……。
『ん?』
そういえば、少し前にも似たような考えをしなかったか?
クラリスがノアの名前を口にしたときのことだ。
『……何だって?』
こう考えると、バレンタインはずっと前からクラリスの関心を引きたくて、子どものようにふるまっていたように見えるではないか!
つまり、彼が望んでいたのは、ただ一緒にいる人からの気遣いを……。
「礼儀」という言葉に、彼は思わずまた動揺する。
『そんなに礼儀を振りかざして、心にもない言葉を並べて、彼女を困らせるつもりか?』
自分の言動が、王室の臣下がとるべき礼儀に反しているのは明らかだった。
いや、王室や臣下という大層な言葉を使うまでもない。
「相手を困らせない」というのは、人間関係における最も基本的なことだ。
それなのに、彼は顔を赤らめ、困惑したクラリスをじっと見つめていたのではないか。
彼はすぐにでも、この事実を正直に認めて謝罪しなければならないと思った。
「クラリス。」
真剣に名前を呼ぶと、彼女は驚いたように大きく目を見開き、彼を見つめた。
「……はい?」
同時に、「ドン」という音が響いた。
本当に何かがぶつかったわけではなかった。
ただ、彼の心臓が一瞬止まりそうになった錯覚……いや、もしかしたら本当にそうだったのかもしれない。
突然、頭の中が混乱し、呼吸さえまともにできなくなった。
『馬車が事故でも起こしたのか?』
彼が妙な様子を見せたのか、クラリスが前に身を乗り出してきた。
「王子様、どこか具合が悪いのですか?」
心配そうな顔がすぐそばに近づいた。
その淡い紅色の唇から漏れるかすかな息遣いが、彼の頬にかかるのがはっきりと感じられるほどに。
「……っ!」
バレンタインは、自分でも気づかぬうちに全身がビクリと震えた。
彼がかろうじてできたことといえば、ただ目の前で自分を案じて見つめるクラリスを呆然と眺めることだけだった。
『……こいつ、こんなに可愛かったか?』
抱きしめたいという衝動が、あまりにも自然に胸に湧き上がるほどに。
彼は震える指先で自分の袖をぎゅっと握りしめた。
そうでもしなければ……どうしても耐えられない気がした。
その瞬間だった。
ギィッ、パキン!
馬車に何かが激しくぶつかり、割れる音が響いた。
馬車の外側に取り付けられていたランプが、吹雪の風に煽られ揺れたかと思うと、ついには馬車の壁に激突し、砕け散ったのだ。
一瞬にして光を失った馬車の内部は、闇に包まれる。
「……っ!」
クラリスが驚き、息を呑む音が聞こえた。
馬車の走行中にランプが壊れるのは、それほど珍しいことではない。
しかし、クラリスにとっては初めての経験だったのだろう。
そもそも悪天候の日は、彼女が外に出ることさえ制限され、守られて育ったのだから当然だった。
やがて、淡い月明かりだけが頼りの暗闇に目が慣れ始めると――驚きに満ちた表情のまま、強張ったクラリスの顔が見えた。
「ただ、風でランプが割れただけだよ。」
ヴァレンタインは特に気にする様子もなく、さらりと言って微笑んだ。
「わ、私は……。」
クラリスは震える声で、ようやく言葉を紡いだ。
「襲撃……かと思いました。」
だから悲鳴も上げられず、息を詰めることしかできなかったのだろう。
「じゃあ、ちょっとはいいんじゃない? 騎士たちの腕も試せるしさ。」
「……それでも。」
「それとも、俺がお前一人も守れないと思ってる?」
「そんなこと……。」
やっとクラリスが少し笑った。
さっきまでの怯えが和らいできたようだった。
「そんなこと言いながら、結局は私を守るために動くんでしょう? ヴァレンタインって、そういう人じゃないですか。」
「うん。」
おそらく、いつものヴァレンタインなら、こんな状況で深く考えずに「当然だろう」と答えていただろう。
しかし今は、なぜか違った。
何と言えばいいのか。
クラリスが綺麗に見えたし、胸が高鳴るのを感じていたので、そんな軽口を叩く気になれなかった。
「……そうじゃない。」
そうして漏れた言葉は、自分でも驚くほど落ち着いていて、柔らかかった。
「え?」
「本当にこんな切迫した状況で、君に冗談なんて言わないよ、クラリス。」
そう言った瞬間、彼の手は自然と彼女の手を握っていた。
かじかんでいたせいか、ほんのり冷たく、白くなった指先が目に入った。
「はぁ……。」
震えていたクラリスが、なぜか少し笑った。
「私が無事じゃなきゃいけないんですよね。王宮との約束ですから。」
「うん。」
ヴァレンタインは、クラリスのこうした言い回しが嫌いだった。
明らかに型にはまった言い方だ。
だからヴァレンタインは、普段からこうした話題を避けてきた。
それは……ヴァレンタインがどうにかできる問題ではなかったからだ。
「いや、そういうことじゃなくて、ただ……」
お前が大切なんだ。
ヴァレンタインは、自然に口から出そうになった言葉に自分でも驚いた。
『しまった。』
彼は、そっと握っていた彼女の手を急いで離した。
驚きで顔が熱くなるその瞬間も、手の中に残った感触を忘れないようにと、拳を固く握りしめた。
『大切だなんて。』
自分が守らなければならないこの女の子が?
川であれこれと身体に泥を塗りつけていたあの女の子?
駄目だと思いながらも、彼は否定できなかった。
『こんな……馬鹿な。』
彼はこの純粋な感情の名前を知っていた。
小説を読むときに最も嫌いな場面で、こんな厄介な感情が突然吹き出してくることがよくあったからだ。
「……はあ。」
しかしヴァレンタインは認めざるを得なかった。
彼はクラリスに惹かれていた。
『なんてことだ!馬鹿らしい!』
その結論に至った瞬間、彼はどうしても湧き上がる欲望を抑えることができなかった。
「……王子様?」
再び聞こえたのは、愛らしい声。
その声が誘惑するかのように耳に響いた。
もちろんクラリスにそんな意図がないことは、誰よりもヴァレンタインがよく分かっていた。
その事実に何となく苛立ちを感じたヴァレンタインは、苛立ちを抑えたまま顎を手で支え、クラリスをじっと見つめながら言った。
「……やっぱりお前が戦う方がマシだ。お前の頑固さには誰も勝てないからな。」
「まあ、さすが王子様らしいご意見ですね。」
そんな言葉を聞いて、クラリスは予想通りの反応を見せてクスクスと笑う。
その仕草はどこか子供のようで、ヴァレンタインは無意識に『かわいい』と感じてしまった。
もちろんすぐにその感情を振り払おうと冷たい態度で対処したが、それでも内心では彼女に対する興味を完全に消し去ることはできなかった。
「さて、もう静かに行こう。」
ヴァレンタインは腕を組みながら窓の外を見やった。
雪が暗闇の中でますます強く降り積もり始めていたが、それが彼にとっては何となく気分を落ち着けるようだった。
――どうせ、雪が降ればクラリスはきっと喜ぶに違いない。