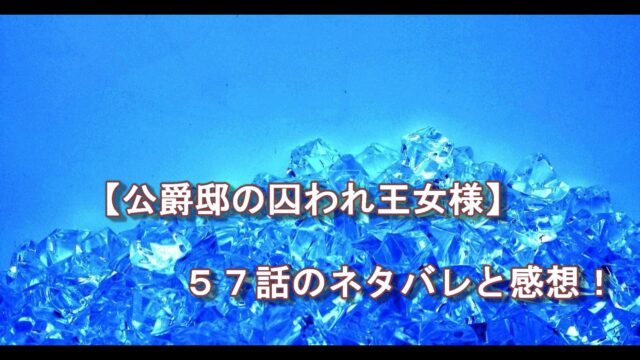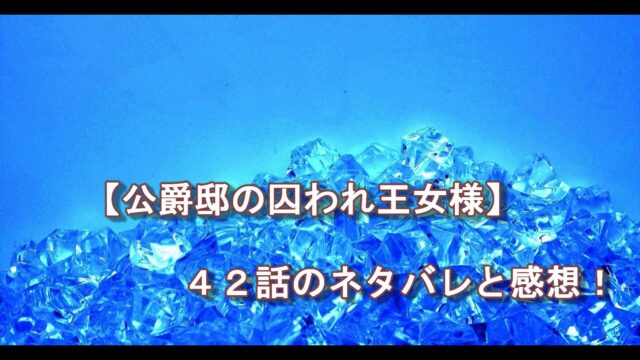こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

110話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 強襲
デビナは焦っていた。
ブリエルを放っておかないと決めてからというもの、物事がうまくいかなかった。
マクシミリアンがどうにかしてデビナの作戦を察しているかのように、夫人のそばを離れない。
一度は直接勇気を出して、祝福の贈り物を渡すという理由で訪ねて行ったこともあったが……
その時もマクシミリアンは恥ずかしがる様子もなく、しっかりと夫人のそばを守っていた。
『あの子はマクスの子じゃないって言ってるのに!』
デビナは喉まで出かかった言葉を必死に飲み込み、ただ微笑むしかなかった。
信頼できる人物を通じて手に入れた毒を使う暇もなかった。
もしもブリエルの正体がすべての人に知られる日が来たらどうしよう?
不安が頭の中で爆発しそうになっていたある日、 彼女の元にまた手紙が届いた。
もしかして父のものかと慌てて受け取ったが……。
「エビントン・ベルビル。」
封筒に書かれた名前を確認した彼女はため息をついた。
この間抜けな試験生は、クラリスと友達になったという話をこれでもかというほど忠実に報告してきていた。
こうして時折「友情レポート」を送ってくるのだが、 その中身はいつも大したものではなかった。
ちょっとした手助けのことや、食べ物を分け合った話などばかりだ。
クラリスとのあの親しげなやり取りと友情に目を奪われ、デビナはただ呆然とするばかりだった。
ビリッ。
デビナはエイビントンの手紙をびりびりと破いた。
そんなくだらない話など聞くつもりはなかった。
ところが、ひらりと落ちた手紙の切れ端から……
「……ん?」
ある一文がデビナの目に留まった。
「[公爵夫人様も週末には……]」
エイビントンが言うとは思えない内容に、彼女はエメラルド色の瞳を何度もぱちぱちと瞬かせ、再び読み返した。
「申し訳ありません。急に王妃様に呼ばれて、あなたに付き添えませんでした。」
後悔に沈むマクシミリアンの謝罪に、ブリエルは頭を下げた。
「大丈夫です。ちょっと出かけただけですし。もう、公爵様は私に過保護すぎるんですよ。」
「……いえ、そんなことはありません。」
「いえいえ!私、ヘイリーにも聞いたんです。ノラが妊娠していたとき、歩くたびに後ろからついて行って、すごく心配そうにしてたって。」
「それが普通の執事なら、きっとそう答えたと思います。」
ブリエルは目をぱちぱちさせて反論した。
「いえ! 確かに心配はしてたけど、毎回一緒に行動するほどしつこくはなかったって言ってました。」
「私は……あなたを一人の成人女性として守っているんです。」
果たして本当だろうか?
ブリエルは、これまで彼がしてきた心配事を冷静に思い返してみた。
ベッドから落ちる危険があるからと、必ず彼の隣で寝ることを勧めてきた。
階段を上り下りする時は、必ず彼の手を取ること。
物を渡すために腰をかがめたりせず、マクシミリアンが拾ってくれるのを待つこと。
どう考えても、九歳の頃のクラリスを守っていたマクシミリアンを思い出さずにはいられなかった。
「どう考えても、成人女性として保護されるのはおかしいですよね。」
「それなら、愛する妻として守ってくださってもいいのでは?」
マクシミリアンの問題はまさにこれだった。
そんなことを言いながらも、表情に一切変化がないのだ。
しかも彼らの周囲を通る使用人にまでこんな話が聞こえるかもしれないのに、気にせず平然と恥ずかしいことを言ってのけるのだ。
「ああ、もう!」
一人で恥ずかしさに耐えきれなくなったブリエルは、顔を赤くしたまま黙るしかなかった。
以前はこの恥ずかしさが嫌いで少しは反発していたが、返ってきたのは次のような答えだけだった。
「私はあなたを心から深く愛しています。それはあまりにも当たり前のことです。これを声に出して伝えるのに恥じる必要はありません。」
それに対してブリエルはこう返した。
「公爵様、他の人が何て思うでしょうか?」
「もうセリデン邸で私があなたを愛していることを知らない者はいません。」
……まあ、それはそうかもしれない。
でも、それにしても。
恥ずかしい言葉をこんなに堂々と広間で言われると、ブリエルは恥ずかしさのあまり死にそうだった。
そして、もう一人、死にそうな人がいた。
ブリエルはそばで書類を持って待機していたクエンティンをちらりと見た。
すでに真っ白になってしまった彼は、体を小刻みに震わせながら、天井の模様を一つ見つめていた。
そういえば、少し前に招待状を一通受け取っていたそうだ。
時々手紙を送って助言を仰いでいた若者たちが、首都で結婚する予定だという。
まるで恩師のように慕われていた後輩たちの結婚式に、参加しないわけにはいかないのか、クエンティンは柱に丁寧に貼られた案内表示を見るたびに、ため息をついていた。
「結婚式に一緒に行ってくれる優しいお嬢さんが、天からひょこっと降りてきてくれたらいいのに」などと。
そんな寂しさを、何事もなかったようにそばに置いた補佐官を愛していると言う、公爵様だなんて。
ブリエルは、クエンティンがいつかこの仕事を辞めるのではないかと心配になっていた。
彼女はマクシミリアンの前にそっと近づき、背伸びして彼の耳元にささやいた。
彼は凍ったような耳を差し出した。
「どうか、センクレア様をよろしくお願いします。」
すると今度はマクシミリアンがブリエルの耳元でそっと答えた。
「ええ、よくやっていますよ。今回も十分な出張費と成果報酬を……」
「もう、お金の話じゃないってば。」
「……?」
「なんだか寂しそうなので、結婚式に一緒に行く相手とか……」
ちらりと振り返ったクエンティンは、天井の模様はもう見終えたのか、今は床の模様を見つめていた。少し青ざめて。
「ご心配なく、奥様。」
マクシミリアンはようやくブリエルの意図を理解したようで、誠実そうに声を潜めて言った。
「私はクエンティンが望むならいつでも一緒に行く覚悟があります。私は彼を家族のように思っていることをご存じでしょう?」
……いや、それはちょっと……クエンティンも望んでいない気がする。
ブリエルはまた「そういう話じゃない」と説明しようとしたが、口をつぐんだ。
クエンティンの待ち時間が長くなるのが、どうにも申し訳なくて。
「どうぞ行ってらっしゃいませ、公爵様。私もちゃんと留守を守っておきますから。」
ブリエルは一歩後ろに下がりながら、彼に手を差し出した。
マクシミリアンは彼女の手の甲に口づけをした。
「行ってまいります……。」
挨拶を交わした彼は、こらえきれないような青ざめた顔でコートを手に取った。
「やはり、騎士団を率いて行かれるのではなく、ベンス卿くらいはお連れになる方がよろしいのでは?」
「ハイデン郊外でもないですし、第二城壁の外の家に行くだけなのに、騎士を大勢連れて行く人なんてどこにいます?バレンタイン王子殿下ですら、そんなことはなさいませんよ。」
そもそも第二城壁は貴族たちのための居住区域だった。
出入りが厳しく制限されているのはもちろん、出入関係する人物すべてを名簿にしっかり記録しておいたので、新たな問題が起こることはなかった。
「それでも……やっぱり心配です。」
「ご心配なく。いくら臨時の馬車とはいえ、王宮から貸し出してくださったものですよ。世界でこれ以上安全な移動手段はないでしょう?」
ブリエルはそっとマクシミリアンの肩を両手で押し出した。
「ですから早く安心して行ってきてください。」
マクシミリアンは最後まで「騎士……」と未練がましく言いかけたが、結局は奥様に押し出されるようにして屋敷の外へと出て行った。
午後になると空は次第に暗くなり、ひんやりとした風が吹き始めた。
「どうも雪混じりの雨が来そうですね、奥様。」
ロザリーがそわそわしながらブリエルのそばをうろうろしていた。
彼女もまた、ブリエルのことを気遣うあまり、マクシミリアンを引き止める側だ。
「大丈夫です。雨が降っても、そんなに不便じゃありません。お腹が出てきたわけでもないし。」
「何をおっしゃってるんですか! 今が一番大事な時期ですよ。もしも滑りやすい道で転んだりしたら大変なことになりますよ。ああ、やっぱり、ウッズ夫人をここに呼ぶべきでした。」
ロザリーはウッズ夫人がここにいれば、ブリエルを家の中でしっかりと引き留めてくれるだろうと期待していたようだった。
けれど、それはブリエルの意思を理解していなかったから出た言葉だった。
「私は今日、必ず侯爵夫人にご挨拶して、お悔やみを伝えに行きます。」
「せめて明日はどうでしょう。お天気が少しでも良ければいいのですが。侯爵夫人には私から早めに連絡を入れておきます。」
「そうしないでください。」
ブリエルはロザリーの手首をそっとつかんだ。
「待ちくたびれている方をこれ以上お待たせしたくありません。私とクラリスが一緒に行くとお伝えしたら、とても喜んでくださいました。」
「ああ。」
「私と似たような事情を持つ方だとおっしゃっていましたよね。きっと今日は私たち同士で話が通じる部分があると思います。」
「奥様……。」
「何よりクラリスに親切にしてくださったじゃないですか。これからもそうしてくださるとおっしゃいましたし。子どもの保護者として一度お礼を伝えるのは当然の礼儀です。」
なぜかそれが“お母さん”の役目のように感じられて、実のところブリエルは今日の予定を密かに楽しみにしていた。
「わかりました。でも必ず暖かい服装をしてくださいね?奥様に何かあったらセリデン全体がとても悲しむでしょうから。」
「心配しないで。じゃあ準備しましょうか?」
ブリエルが席を立ち上がるとき――ノックと一緒に執事が「馬車が到着しました」と告げた。
天気が悪くて王宮の御者が少しもたついたが、予想より少し早く到着したようだった。
「すぐに出ます。少し待ってくださるようお伝えいただけますか?」
ブリエルは少しだけ謝って、支度を急いだ。
「ええ、ロザリー。クラリスの部屋にある青い宝石がついたブローチを持ってきてくれる?」
クラリスは私物の持ち込みを禁じる首都園の規則に従い、それをここに置いていった。
「侯爵夫人に会う日に身につけていけばクラリスも喜ぶはず。」
ブリエルは「ありがとうございます!」と驚いた顔をするクラリスを想像して、思わず微笑んだ。
粗い木材で作られており、特別な装飾や標識は一切なかった。
御者もまた商人たちと同じ服装をしていたので、このまま外に出れば、どこかの商会で荷物や書類を運ぶ馬車にしか見えなかった。
「すごいですね。」
ブリエルが感心すると、御者は誇らしげに微笑んで答えた。
馬車の中とは異なり、御者は宮廷の礼儀作法がしっかり身についている人だった。
「王族の方々が慈善院に行かれる際も利用される馬車です。」
「でも、そういう場所に行く時は、派手な馬車に乗るのは控えたほうがいいんですね。」
「はい、どこにいても目立たない優れた馬車です。」
少し周囲を見回した御者は扉を開け、ブリエルを中に案内した。
その後ろをロザリーが続いた。
「では、出発します。」
馬車は三番目の城壁の正式な出入口ではなく、主に商人たちが物品を納品する際に使う小さな裏門へと向かった。
普段と違う風景が面白くて、ブリエルは窓にぴったり張りついて外の景色を眺めた。
ほどなくして、「奥様、誰かが見たらどうするんですか!」とロザリーが凍ったカーテンをさっと引いてしまった。
「ご存知ですよね?奥様はとても大切なお方です。」
ロザリーは彼女の膝の上に毛布を優しくかけ、心配そうに眉間にしわを寄せた。
「わかりました、ロザリー。密かに馬車の中にいろってことですよね?」
ロザリーはようやく安心したのか、持ってきたカバンから編み物を取り出した。
生まれてくる赤ちゃんに帽子を作ってあげたいと言い、彼女は時間があるたびにこのように編み物をしていた。
「でもロザリー、この前は緑色で作りませんでしたか?青い木のようにすくすくと立派に育つといいなっておっしゃってましたよね。」
「そうでしたね。でも考えてみたら、赤ちゃんには奥様に似たきれいな青い瞳があるかもしれませんよね?」
だから青い帽子も別で作ることにしたのだった。
「それいいですね!じゃあ私は黒い羊を用意しようかな。」
「公爵様に似ているものを準備するってことですか?」
「はい、クラリスに似たピンクのマントも用意して、小さなリボンもつけてください。」
「赤ちゃんが家族みんなの色を身につけたら、きっとすごく可愛いでしょうね。」
「わあ、想像するだけでも……あれ?」
両足をバタバタさせながら可愛い想像を続けていたブリエルが、ふと動きを止めた。
少し前まで慎重に進んでいた馬車が、速度を上げて一瞬ガタガタと大きく揺れたのだ。
「奥様!」
ロザリーが凍りついたブリエルを引き寄せて抱きしめた。
幸い、激しく揺れる馬車の中でもブリエルが倒れたりすることはなかった。
「大丈夫です、ロザリー。床が高くないですから……。」
「だからゆっくり行けってあれほど言ったのに!」
突然スピードが上がって馬車が激しく揺れたため、ロザリーはカッとなって怒った顔で御者席につながる小窓を勢いよく開けた。
「すぐにスピードを落とせませんか?ここに誰が乗ってるかお忘れですか?」
城内では穏やかに走っていた御者は返事をしなかった。
いや、それが問題ではなかった。
明らかに御者しかいなかったはずの席に、今はもう一人、見知らぬ男たちが座っていたのだ。
「……っ!」
スルッ。
そのうちの一人の鋭い剣先が、ロザリーの首元を正確に狙った。