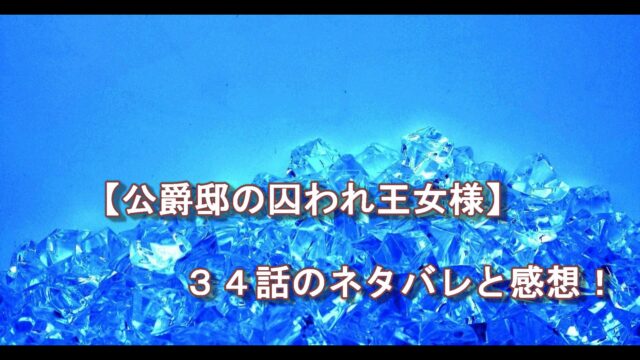こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

113話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 親娘
「死ね!」
絶叫に近いデビナの声で、ブリエルは長い夢から目を覚ました。
「……!」
しかし、それでも容赦なく迫ってくる刃はちょうどブリエルの首元の近くをかすっただけだった。
傷は軽くても、痛みがないわけではなかったはずなのに、ブリエルはピクリともせず、慎重に口を開いた。
「……前からご存知だったんですね。」
長い間ブリエルが自ら封印していた記憶。
名前と両親。
閉ざされた時間が長くて、すべての記憶がはっきりと思い出されるわけではなかった。
けれどブリエルは、自分がとてつもなく高貴な貴族の家門の娘であることは、わかる気がした。
大人の男性を自然に「様」と呼ぶのは、普段から子どものそばに仕える騎士がいたという意味だろうから。
「わたしの……両親は誰なんですか。」
「うるさい!」
彼女が再び刃を振り上げた。
しかしそれだけだった。
彼女の腕はそれ以上動かなかった。
動揺した彼女は自分の腕を見て、なぜ動かないのか声を上げるほどだった。
「動け!動けってば!」
何かがおかしくなっているのを察したのか、状況を見ていたデビナの「しもべたち」は静かに後退し、逃げ出してしまった。
ブリエルはこの奇妙な光景をただ見つめていたが、ようやくデビナの背後から誰かが勢いよく駆け寄ってきていることに気が付いた。
クラリスだった。
その背後には魔法使いのシネットもいて、ブリエルは全ての状況を理解した。
「奥さま!」
「クラリス……」
デビナを突き飛ばしたクラリスが彼女をしっかりと抱きしめた。
「奥さま……私、本当に……奥さまを失うかと思って……だから……ああ、よかった……」
クラリスは呆然として言葉も出なかった。
ブリエルは泣きじゃくる少女の背をゆっくりと撫で下ろした。
こうして抱いてみると、九歳のクラリスが腕の中にすっぽりと収まっているようだった。
『もう……すっかり大きくなったと思っていたのに。』
そのぬくもりに触れて、ブリエルはやっと自分の体がひどく冷えきっていたことに気づいた。
「ま、魔法……使い!」
彼らの背後、床にひざをついて頭を垂れていたデビナが叫んだ。
ようやくノアを見つけて状況を把握したようだった。
「王妃に向かって魔法を使うなんて、前王がこれを知っていて魔法師団を放っておくと思うのか!」
彼女の前に駆けつけたノアは返事もせず、鋭い視線で彼女を見下ろしただけだった。
「………」
「必ずこの件を問題にする。公爵夫人が魔法師の成果と結託し、反逆……!」
「その言葉を。」
彼女の言葉が終わる前に、すぐ背後から低い声が聞こえた。
マキシミリアンだった。
相手を認識したデビナが固まったとき、彼女のそばで武器を持っていた男たちが倒れ込んだ。
それは、デビナの命令でブリエルを襲っていた者たちだった。
遠くに逃げることもできず、全員取り押さえられた様子だった。
「この者が直接、弁明してもらいましょう。」
がっしりと捕らえられた男たちは、血走った目で、もがきながらも必死に何かを言っていた。
その声ははっきり聞き取れなかったが、公爵に許しを乞うような様子だった。
「マ、マクス!」
デビナは再び体を動かせるようになり、震えながら立ち上がった。
「これは誤解です。あ、あの人たちが私を陥れようとして……」
「そうですか。」
無感覚に答えるマクシミリアンの視線が彼女の手元へと向けられた。
デビナは、自分がまだ剣を握っていたことにようやく気づいた。
しかも、それがブリエルの血に染まっていることも。
「……っ!」
彼女は驚いて、その剣を床に落とした。
「ち、違います!私のじゃありません!ああ……公爵夫人が私を刺して……」
「その剣に付いた血が誰のものか、調べさせていただきます。」
彼の騎士が白い布で短剣を丁寧に包み、大切そうに持ち上げた。
デビナはマクシミリアンの腕にすがりついた。
「お願い、信じて!マクス、私はあなたの婚約者だったじゃない!」
デビナはマクシミリアンのことをよく知っていた。
彼はどんな瞬間でも、騎士の礼節を忘れない本物の王族だった。
だからといって、こんなにも弱々しい王妃が涙を浮かべて懇願しても……。
「……!」
しかし、その表情を見上げた彼の顔には……深い嫌悪の感情だけが映っていた。
それを隠す気もないようだった。
「二度と。」
彼はデビナを突き放し、腕を払いのけた。
まるで汚いものでも触れたかのように、冷たい目つきのままで。
「その不快な言葉は二度と口にしないでもらいたい。」
「……!」
ショックを受けたデビナは、体を動かすことさえできなかった。
「そして、なぜ私の妻がこんな目に遭ったのか――それもいずれ明らかになるだろう。」
「……そんな……」
デビナは溢れ出す涙を止められず、彼に向かって叫んだ。
「あなたのためだったのよ!私は……私は……あの女は誰とでも身体を……っ、くっ!」
その瞬間、彼の手がデビナの首元に向かって荒々しく伸びた。
今にも彼女を絞め殺そうという気迫だった。
側近の騎士たちが驚き、彼を止めに入った。
どんな状況であれ、臣下である公爵が王妃の首を絞めることは許されないというのが常識だ。
しかし、彼はしっかりとデビナの首を握りしめた。
ただ、それだけだった。
「公爵様、やめてください!」
すぐに聞こえたブリエルの声が、彼を止めたのだ。
「………」
マクシミリアンが振り返ると、彼女は騎士たちの助けを借りて分厚い外套を羽織ったまま、こちらを切なげに見つめていた。
「……私たち、もう帰りましょう。ね?」
「でも……」
彼はまだ完全に手を離すことができなかった。
込み上げる怒りを抑えきれず、指先が震えていた。
「公爵様。」
ブリエルの手を握ったクラリスもまた、同じ目で彼を見上げて懇願していた。
「……。」
二人を苦しめようとしたわけではなかったので、マキミリアンは彼女を押さえつけていた手をそっと離した。
緊張が解けたのか、デビナはその場に崩れ落ちた。
ゆっくりと歩いて戻った彼は、両腕を広げ、ブリエルとクラリスを一度に抱きしめた。
そして、ちょうどそのとき、雨がやんだ。
ブリエルとロザリーはすぐに医師の診察を受けた。
まもなく目を覚ましたロザリーには幸い大きなケガはなかった。
しかし、深く眠ったように意識を失っていたブリエルは、さらに一日が過ぎてからようやく目を覚ますことができた。
マクシミリアンは、彼女の身体に何か大きな異変が起きたのではないかと心配したが、幸いにも彼女自身もお腹の中の子どもにも特別な異常はなかった。
ただし妊娠初期なので、万が一に備えて安静に過ごすようにという助言を受けた。
「えっと……。」
ブリエルはためらいながら医者に質問を投げかけた。
「少しだけ外出してもいいですか?本当に短時間の外出なんです。」
医者はにっこり笑って答えた。
「もちろんです。それが今週でなければですが。」
「え?でも……。」
「では、ゆっくり休んでください。」
医者が去ると、ブリエルは涙ぐみながら隣に立っていたマキシミリアンを見上げた。
「侯爵夫人にお詫びしようと思うんですが、どうすればいいでしょう?」
「昨日の件はすぐに手紙を送って謝罪しました。何より少し前にクラリスと魔法使いのシネットが直接出向き、再び奥方に謝罪の挨拶をすることにしました。」
「ああ、本当に恥ずかしいことです。」
クラリスに親切にしてくれてありがとうという言葉を伝えるために夫人に会う予定だったが、むしろ子どもに対する約束が守られなかったことを伝えることになった。
「信頼できる子どもたちです。ご心配には及びません。」
「それは私もわかっています。」
「最初にあなたがその…… そうなったと教えてくれたのも、彼らだったんですよ。」
ブリエルはようやく、自分が非常に重要なことを知らずにいたのだと気づいた。
一体どうやってクラリスとマクシミリアンが彼女を見つけて来たのか、ということだ。
あまりにも一瞬の出来事で、もしかすると誰にも気づかれなかったのかもしれないと思っていたが……。
「魔法使いシネットとクラリスが遊んでいた時に、ブローチに追跡魔法をかけておいたそうです。侯爵夫人からいただいたものだと言っていました。」
「ああ。」
「異変に気づいた彼らは伝令を送って私に知らせてくれました。直接馬車を引いてあなたを迎えに行こうともしたんですよ。」
「それで、公爵様はどうやって……?」
「魔法使いのシネットが時々魔法の光を空に放って知らせてくれました。降り注ぐ雨のおかげで敵の目には映らなかったようです。」
説明を終えたマキシミリアンはしばし沈黙した後、そっと手を離した。
ブリエルは、彼が自責の念に駆られているのが辛かったので、そっと彼の手を握り直し、自分の頬に当てた。
彼には言うべき言葉があったから。
「いますよ、公爵様。」
彼女はゆっくりと目を閉じ、事件当日のかすかに浮かび上がった閉じ込められていた記憶の断片を慎重にたどった。
「もしかして……シシというお嬢様をご存じですか?」
「ああ……いいえ。」
理由はわからないが、マクシミリアンは少しどもるように答えた。
もしかすると、ブリエルが突然他人の名前を出したことで戸惑ったのかもしれない。
「そ、そうですか?急にすみません。」
ブリエルは失望した気持ちを隠すために、さらに明るく笑ってみせた。
自分が貴族かもしれないという考えが頭をよぎったとき、ブリエルはもしかしたらマクシミリアンのそばに、もう少し堂々と立てるのではないかと思った。
もちろん、マクシミリアンは彼女の出自について非難したことはなかった。
だが、他の貴族たちは……。
ブリエルが一人の時、こんなことをよく耳打ちしてきた。
「公爵様も気の毒よね。一時は最も輝いていた男性だったのに、今やあんな女としか結婚できないんだものね? かわいそうに。」
そんなことはないのに。
マクシミリアンとブリエルがこの婚姻を続けているのは――そして、本当に夫婦になると約束したのは……本当にお互いしかいないと確信があったからだ。
ブリエルが不安がるとき、彼はこんなふうに話したこともあった。
「軽々しくこういうことを想定するのはよくないことです。でも、もし私が……まだ王宮に完全に属しているとしても、私は必ずあなたを見つけ出して妻にしたでしょう。私が……あなたに惹かれないはずがないでしょう。」
誰が仮初めなど意味がないと言ったのか?
ブリエルはその言葉を言った人を探して問いただしたくなった。
それほどまでにマキシミリアンの確固たる告白は胸に深く響いていた。
『でも、だから何?貴族だろうが関係ない。公爵様と私の間には何も変わるものなんてないのに。』
他の人の言葉は変わるかもしれない。
けれど、それで変わる話なんてくだらないものだ。
彼女の人生に何の影響も与えなかった。
「……申し訳ありません、ブリエル。」
長く考え込んでいたブリエルに、マクシミリアンが静かに謝罪の言葉をかけた。
「え?」
「思い切ってあなたに嘘をつきました。もしあなたの話しているのが、クノー家の娘のことであれば……私はその子をはっきりと覚えています。」
彼はブリエルの銀髪をゆっくりと撫でながら、彼女の傍らに座った。
「シシィ……ですか?」
「はい、セシリア・クノー。彼女を大切にしていた人々は、彼女を“シシィ”と呼んでいました。」
ブリエルは、彼が話していたクノー家のセシリアという名前を再び繰り返した。
本当にその偉大なお嬢様が、自分なのだろうか?
彼女はなぜか、心臓の鼓動がどんどん速くなっていくのを感じた。
身分が昇格するかもしれないという単純な期待感からではなかった。
それよりも、心の奥深くにひっそり眠っていた記憶の一部が喜んでいるようだった。
「今回もあなたの誤解で辛い思いをさせてしまいましたが、6歳の頃の親しい友人を否定することはできないと思いまして申し上げました。」
「……え?」
『私、公爵様と幼なじみだったってこと?』
ブリエルは多少せっかちなのは分かっていたが、彼が話すセシリア・クノーがまるで自分のように思えてきた。
「はい……一応……先王陛下が私の婚約者として定めてくださって……。」
彼が口ごもりながら話を続けたとき、ブリエルは驚いて思わずその場から立ち上がってしまった。
「あ、失礼、そんな急に動かれては困ります。」
彼はおろおろしながら両手をどうしていいか分からず、結局は手をきちんとそろえて謝罪の言葉を続けた。
「わ、私が……間違っていました。」
「……え?」
突然何が間違っていたのかはわからなかったが、ブリエルはとにかく彼がセシリアを知っているということを確認しておきたかった。
「公爵様、もしかして……その子は私と同じ銀髪だったんですか?」
「……っ!」
すると、彼の顔色が青を通り越して真っ白に変わり始めた。
「そうですが、絶対に誤解しないでください!あなたとセシリアは明らかに違います!」
「あ……同じ銀髪ではなかったのですね。貴族のお嬢様と私を間違えるなんて……。」
「そうじゃない、本当に。」
マクシミリアンはしばし片手で額を押さえ、なんとか冷静になろうとしながらようやく答えた。
「私の元婚約者が多すぎて、あなたにご迷惑をおかけしてしまうかと思います。」
「……?」
「た、ただ、あなたに対して不埒な考えを抱いたことは一度もありません!それだけは本当です!」
ブリエルはようやくマクシミリアンがなぜあのような反応を見せていたのか理解した。
いくらなんでも、たった6歳のときの婚約者のことを、ブリエルが気にするはずもなく……。
『あれ、どうして……気にならないの?』
いずれにしても、彼にとって特別な少女がいたということだ。
王妃様と婚約していた事実を思い出すときには、彼が本気ではないとわかっていても、胸が締め付けられるように苦しかった。
ましてや、セシリアという少女は彼が大切に思っている存在だった。
マクシミリアンが誰かを「親しい友達」と呼ぶことはほとんどなかったのだから。
『全然いやじゃない。この感情って……』
ブリエルが自分を「セシリア・クノー」だと思っているからだろうか?
『ああ、もしそうなら。』
彼女はせっかちな結論を出そうとした自分をとがめてやめた。
それはとても危険な考えだった。
娘を失ったクノー夫人にとって、大きな失礼になるだろう。
今になってやっと思い出した曖昧な記憶を完全に信じることもできない上に、「シシィ」という頭文字がつく名前はいくらでもあるのだった。
カミール・カルトン、シャルリン・キャンデン、クリスティナ・シャメント……
すぐに思いつくものもいくつかあった。
『いや、何よりも……』
侯爵家の一角にある場所で、魔法師団の助けを借りないはずがなかった。
しかも必死に探していたのなら、なおさらだ。
『だから、たぶん。』
セシリア・クノーという名前に微かな親しみを感じるブリエルの心情は、きっと勘違いだろう。
どうにかしてマクシミリアンとつながりたいという欲望から来る……。
「ねえ、ブリエル。」
マクシミリアンが慎重に呼ぶ声に、彼女は顔を上げた。
彼女より体格が二倍はありそうな男が、どう言い訳すべきか分からずもじもじしていた。
なぜかかわいらしかった。
くすくすと笑いをこらえきれず、ブリエルは慌てた彼を安心させることにした。
「私は少しも怒ってませんから。」
でもなぜだろう。
そう言ったのに、どうも彼はさらにおどおどしているようだった。
「どうしたんですか?」
「こ、今回だけ許してくれたら、一生かけてこの罪を償います。」
「うーん、そんなに急にしどろもどろになると、もっと怪しく見えますよ、公爵様。」
「そ、そんな……!私、普段からあなたにはしどろもどろなんです!」
その険しい声に、口を押えていた少女が凍ったように両手で口を塞いでいた。
笑いをこらえるのに必死なのは一目瞭然だった。
ブリエルは、彼女たちが少し和んでいたので、お茶を取りに行ってもいいと告げようとした。
しかし、その前にノックの音が聞こえてきた。
執事だった。
彼はクラリスが来客と一緒に戻ってきたことを知らせた。
「お客様ですか?」
「はい、クノー侯爵夫人様が慰問にいらっしゃいました。」
「私が出迎えましょう。ご婦人は今は少し……」
マクシミリアンが先に立ち上がった。
たぶん少しでもゆっくり休ませてあげたかったのだろう。
ブリエルはベッドの端を握る彼の手をそっと握り返した。
「まあ、こんな状態じゃ失礼かもしれませんが、私は侯爵夫人をお見舞いしたいです。」