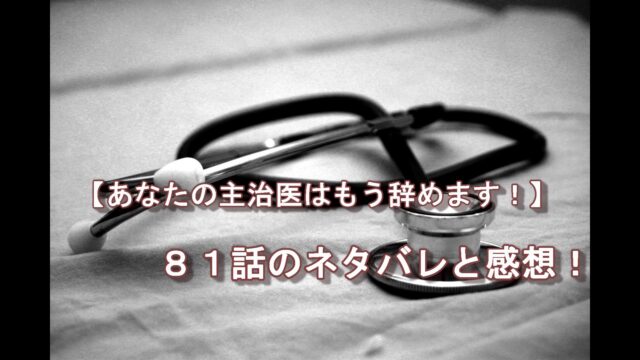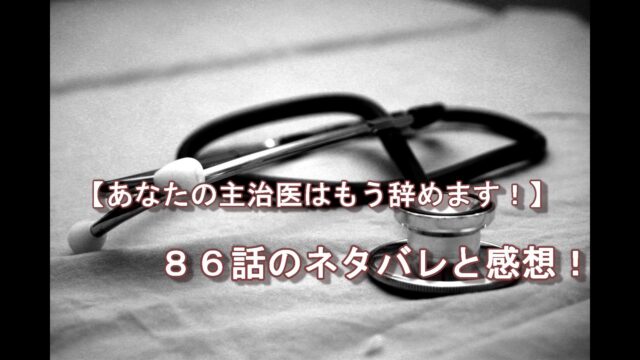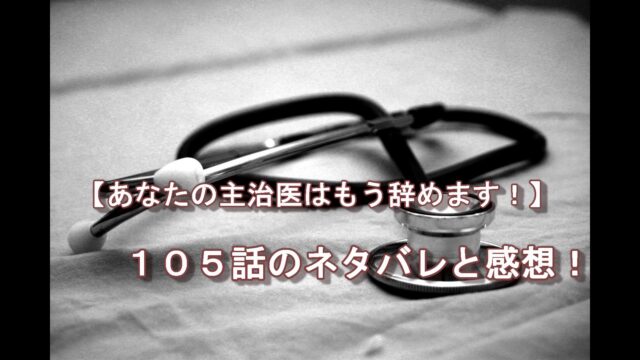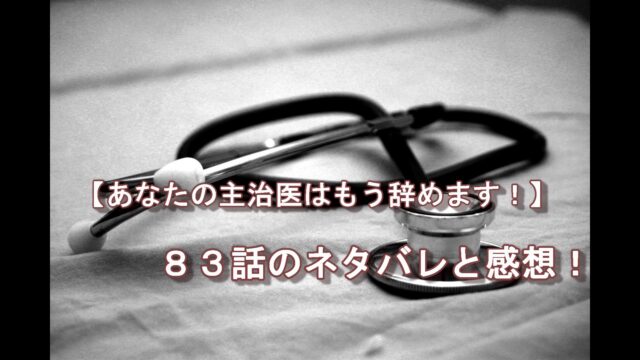こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

159話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- IF リチェがモレキン家に養子として入ったなら
赤みがかった髪の青年、ディエル・モレキンは朝からため息をついていた。
彼はちょうど十七歳になったばかりで、少年と青年の境界に立つ年頃だった。
しかし背丈が人よりも頭ひとつ分大きかったため、誰もが彼を大人だと見なしていた。
ディエルのそばに立っていた茶色い髪の少女が、彼をじっと見上げて問いかけた。
「久しぶりに家に帰るのに、なんでそんな顔してるの?」
まるで答えをすでに知っているかのように、少しからかうような口調だった。
「フェレルマン子爵のせいなの?」
「……うん。」
ディエルは頬をつねりながらため息をついた。
そして、気を揉みすぎて疲れ切った顔で背もたれに体を預けた。
「気分がよくないんだ。今日はそういう日だからね。」
今日は「両親の日」だった。
だからアルガの助手であるディエルは、久しぶりに休暇を取り、モレキン邸に来ていたのだ。
けれど両親に会いに来たにもかかわらず、心の優しい彼はアルガのことを気にかけ続けていた。
「幸い、特別な予定もなくて公爵邸にいるようだから。」
「そうだね。一日中公爵邸で一人憂鬱にしてるよりは……。」
そして、ディエルの隣で何気なく話している少女の名はリチェだった。
彼らは今、セレイオス公爵邸からモレキン家の邸宅へと一緒に向かっている最中だった。
「むしろ、お父さまを探しに行く道中だったらよかったのにね。」
リチェはディエルを見上げ、思いやりのこもった声で言った。
「そうしたら、兄さんの気持ちも少しは楽だったんじゃない?」
その言葉に、ディエルはなんとも言えない表情を浮かべた。
「……どうして?」
「わからない。」
リチェが眉間にしわを寄せて問い返すと、ディエルはただそう答えるしかなかった。
「ただ……君に“お兄ちゃん”って呼ばれるたびに、なんだか胸に響くんだ。」
「なに、それほど妹が欲しかったの?“お兄ちゃん”って呼ばれる私が、そんなに可愛い?」
「いや……そういう“可愛い”って感情じゃなくて……。」
ディエルは真剣な顔で言った。
「なんというか……絶対に聞けるはずのない呼び方を耳にしたような気分?ちょっと夢みたいなんだ。ただ、不思議で……。」
半年前まではただの赤の他人だった二人が、今では兄妹のようになった経緯は次の通りだった。
リチェはモレキン家に養子として迎え入れられた、十一歳の少女だった。
もともとは数字に強いという保育院教師の推薦で、ペレルマン薬草商会の事務会計を任される予定だった。
だが、末娘を欲しがっていたモレキン夫妻は下級保育院でリチェを見るなりすっかり気に入り、愛らしい上に利発そうな彼女を見てあちこちで自慢したのは言うまでもない。
それまで末っ子だったディエル・モレキンがペレルマン商会の仕事を手伝い始めて落ち着いたこともあり、「本当に良い時に来てくれた」とモレキン夫人は涙ぐむほどだった。
「はじめまして。よろしくお願いします。」
リチェもまた少し緊張した面持ちで、モレキン邸にて新しい家族へと挨拶をした。
ある日突然、リチェ・エステルがリチェ・モレキンになったことは、今でもはっきりと覚えている。
実のところ、その日はただ保育院を出て村の医師の助手として過ごしたかっただけなのに、皆が「モレキン家の養女の座をどうして断るの!?」と背中を押すものだから、半ば強制的に行くことになってしまったのだ。
モレキン夫妻が良い人たちだということは分かっていた。
それでも初めて会う人たちだったので、緊張して落ち着かない気持ちはどうしようもなかった。
モレキン夫人は家族を一人ひとり紹介しながら、「実はね、うちには末っ子の息子が一人いるんだけど、今はこの屋敷にいないのよ」と、少し寂しそうに言った。
「ディエル・モレキンといって、セレイオス公爵邸の主治医アルガの助手なの。」
リチェもアルガや、フェレルマンの名前くらいはよく知っていた。
帝国全土にその名を轟かせている名医であることは、当然のことだった。
彼があまりにも几帳面で、助手を頻繁に入れ替えるという噂も、セレイオスの領民なら誰でも知っていた。
『十六歳くらいになったら、私も志願してみようか。』
とはいえ、十一歳の子供を受け入れてはくれないだろうと分かっていたので、まずは近所の診療所で経験を積んでみるつもりだった。
もし診療所で地位を固められれば、いずれ志願の機会もあるだろうと考えていた。
どうせ自分は余った駒だろう、とそう思って過ごしていた時――モレキン夫人が軽く手を打ちながら口を開いた。
「それでもディエル、あなたにも新しい家族ができたってことなのよ。そうね、久しぶりにみんなで外出するのもいいわね。」
こうしてリチェはモレキン邸に来てからまだ五日も経たないうちに、セレイオス公爵邸へ行くことに。
「ディエル!」
ディエルはセレイオス公爵邸にあるアルガの研究室にいた。
彼らは平民だったため応接室を使うことはできず、当然ディエルのいる場所へ行くしかなかった。
モレキン夫人はその研究室で末息子だというディエルをしっかりと抱きしめた。
「本当に久しぶりね。元気にしていたの?」
「まあ、なんとかやっていますよ、お母さん。」
ディエルは少し疲れた顔で言った。
「仕事の強度は低くはありません。」
「それでもやりがいはあるだろう?根気がある君がこうして耐えているだけでも、私たちは決して悪い場所ではないと思えるのよ。」
「根気だなんて!ただ苦痛に耐えているだけです。」
「根気」という言葉に苛立ったディエルは、思わず声を荒らげた。
「今どれだけ忙しいか分かりますか?エルリア草とテタスの葉を仕分けているところなんです。これ、本当に大変で細かい作業なんですよ……!」
もちろんモレキン夫人はそんな愚痴を聞く気はなかった。
そこで彼女は、同行していた栗色の髪の少女を紹介した。
「手紙に書いた通り、この子が君の新しい妹だよ。挨拶に来たんだ。」
「おお、君がリチェか。会えて嬉しいよ。」
リチェはきらきらした目で研究室を夢中になって見回していたが、おずおずとディエルと握手を交わした。そして慎重に尋ねた。
「手伝ってあげようか?」
「……え?」
「エルリア草とテタスの葉を仕分けるんでしょ。」
「ああ、君はとても優しいんだね。」
ディエルはにっこり笑ってリチェの髪をそっと撫でた。
「でも大丈夫だよ。これは専門知識があってもすぐに間違えやすいし、とても大変な作業だからね。君の善意だけで十分だ。」
「優しくて善意にあふれているのは確かだけど、それだけでやっていけるって話じゃなかったの。」
リチェの何気ない言葉に、ディエルは思わず目を瞬かせた。
……もともと優しい子が、自分で「優しい」なんて言うものだろうか?
「水に浸けてみたら少し楽になるよ。エルリア草は水を含むと膨らんで、形がガラッと変わるから。」
「……え?」
ディエルは眉間にしわを寄せた。
だが、小さなビーカーに水を入れ、エルリア草とテタスの花びらを一緒に浸けてみた。
結果を見たディエルの目が大きく見開かれた。
ディエルが不思議そうにリチェを見ていると、彼女は肩をすくめた。
「本に書いてあるの。」
「いや、いったいどの本に……?」
「『ルヌニ基礎薬草学』第11章、各注24番。」
ディエルはこの状況で何に一番驚くべきか少し考え、結局一番驚くべき点を口にした。
「わあ……その事実をフェレルマン子爵が知らないはずがないのに、どうして僕に教えてくれなかったんだろう?」
そのときだった。
研究室の扉の方から冷たい声が聞こえてきた。
「お前が仕分けをすれば教えてやると言ったはずだ。『ルヌニ基礎薬草学』は、すでに君が読み終えた本じゃないのか?」
30代半ばくらいに見える、若々しい人物がいつの間にか研究室の中に入ってきていた。
茶色の髪をひとつにまとめ、鋭い印象を持ちながらもなかなかの美丈夫。
リチェは一目で、この人物がこの研究室の主、アルガ・フェレルマンだと察した。
「で、でも……」
まるで弱点を突かれたような顔をしながらも、ディエルは最後まで言い訳をした。
「ヒントでもくだされば、すぐに気づいて理解できたはずなんです!」
「だが、その分すぐに記憶から消えただろう。苦労してこそ、本は丁寧に読み込むべきだという教訓も残るのだよ。」
「でもこれ……重さと匂いだけで分けたら、時間がかかりすぎますよ!」
「それはお前の事情だ。」
リチェはその一言でアルガの性格を察することができた。
みんながアルはの指示に従い、一、二か月で芽が出る理由も十分に納得できた。
ディエルは最後に、言い訳するように反発した。
「でも、誰が注24番まで全部覚えますか!」
「この子どもが覚えたではないか。」
アルガはリチェを見てくすっと笑った。
ディエルは依然として納得がいかないという顔をしていたが、これ以上言い返せないのも事実だった。
リチェはしばらく目を伏せていたが、やがてディエルの肩を持ってやった。
「私は天才だからです。」
研究室の中に一瞬、静寂が広がった。
最初に反応したのはモレキン夫人だった。
「そうね、そうよ。うちのリチェは本当に賢いって、保育院の先生たちもみんな言っていたわ。」
ディエルもまた、少女の自尊心を傷つけたくなかったのか、すぐに彼女を庇うように口を開いた。
「うん。とにかく君のおかげで苦労せずに済んだよ。本当に聡明な子が僕の妹になったんだな。」
しかし、子どもの自尊心を守る気などまったくない人物が一人いた。アルガである。
「ふん、天才だなんて。そんなの誰にでも付けられる称号じゃない。」
「私は“誰でも”じゃありませんけど。」
アルガはくすっと笑い、無造作にトングを操った。
そして眉を吊り上げ、皮肉を込めて言った。
「生意気な小娘が偉そうな口を利くな。だがこういうのは骨身にしみて覚えさせなきゃならん。基準を教えるのが、本当の大人の教育ってもんだ。」
そう言いながら、腕を深く突っ込み、ざらついた薬草の中から五つを丁寧に選び取る姿は、どう見ても“立派な大人”というより子供じみて見えた。
薬草を選び終えた彼は、自分と背丈ほどしか違わないリチェのエメラルド色の瞳を見つめ、ぶっきらぼうに言った。
「名前を言ってみろ。」
リチェはすぐに答えた。
「タルダリ草、アラム草、ベヒ花、ヒラテの根、エミンの蔦です。」
アルガの眉間がわずかにひそめられた。
彼はもう一度立ち上がり、今度は足を引きずるようにして棚の上段から別の薬草を五つ取り出した。
答えはやはり素早く返ってきた。
「シャレ花、セビウォンの葉、デイジーアップル、ジカナの木の葉、ミョンジ草の実です。」
「な、な……何だと?」
アルガの顔に「信じられない」という色がはっきりと浮かんだ。
その後もしばらくの間、彼は医学知識について質問を続けた。
リチェが今まさにディエルに挨拶を済ませたばかりの養女だということなど、まるで気にも留めていない様子だった。
リチェもまた楽しげに、次々と質問に答えていった。
ほぼ三十分ほどの問答が終わったころ、アルガは眼鏡をぐいと押し上げながら真剣に問いただした。
「お、お、お前……どうしてこんなことまで知ってるんだ?」
「だって私、天才ですもの。そう言ったじゃないですか。」
リチェがそう言ったとき、ディエルは内心で声を上げて笑った。
出会って間もないリチェを特にかばう気持ちがあったわけではなく、ただアルガのうろたえた顔を見るのが面白かったのだ。
モレキン夫人もまた、くすっと微笑んでいた。
この子もまたアルガの目に留まったことは明らかだった。
いつもディエルの顔を見られないと不満をこぼしていたが、モレキン夫人にとっては、自分の子がペレルマンの組織で重要な役割を任されていることが嬉しかった。
この才覚なら、リチェも十数年もすればペレルマン組織の一員として名を上げられるだろう……そんな心地よい想像をしていた時だった。
しばし思案に沈んでいたアルガは結論を出した。
「お前、セレイアス公爵邸で私の助手になれ。」
その言葉に、ディエルもモレキン夫人も思わず口をぽかんと開けてしまった。
――いや、ついさっき養子として迎え入れられ、今日ようやく家族に挨拶をしたばかりの十一歳の子どもを、すぐさま自分の助手にするなんて……。
リチェも驚いたように目をぱちくりさせた。
「……え?」
アルガはディエルをちらりと見て、すべてが納得できたように顎を引いた。
「どうせここにはディエルも滞在しているんだ。だから適応するのも楽だろう。」
リチェは目を泳がせながら、モレキン夫人の表情をうかがい、困惑していた。
「で、でも養父母様が……。」
「じゃあお前はそのくだらない遊びで時間を潰すつもりか?この天才医師のもとで過ごす代わりに?その才能を無駄にするのか?天才は天才医師から学ぶべきだろう!」
突然の一喝だった。
モレキン夫人は内心で大きくため息をついた。
アルガがリチェをすぐに助手として迎え入れた理由は分かる気がした。
彼はいつも行方不明になった娘を探すのに忙しく、そのために聡明な助手を求めていたのだ。
その事情を知っていたからこそ、惜しくはあっても無理に反対はできなかった。
「……リチェの意見が一番大事でしょう。」
リチェを気に入っていたモレキン夫人は少し寂しさを覚えたが、それでもリチェ自身が望むなら、自分のそばに無理やり引き止めておくつもりはなかった。
リチェはしばらくためらった後、答えた。
「私は……嬉しいです。もともと夢も医者でしたから。」
リチェにとって、細かな会計事務を任されるよりも、アルガのもとで働ける方がずっと魅力的だった。
アルガは群を抜いて優れた医師であり、彼の助手となることはリチェにとって大きな意味を持っていたのだ。
天才医師のもとで助手として過ごせるなんて、とても貴重な経験だった。
しかも、この研究室は想像を超えるほど素晴らしかった。
希少な薬草があふれていて、リチェはすでにこの研究室にすっかり魅了されていた。
「当然だ!よく決めたな!」
アルガはリチェの肩を軽く叩きながら、にっこり笑った。
「セレイアス公爵邸で過ごすといい。良い部屋も用意してやるからな。」
リチェはおずおずと小さくうなずいた。
その後ろで、ディエルは心の中で小さくつぶやいた。
『あまり良い選択とは言えないけれど……まあいいさ。元気でやっていこう。』
こうして、リチェはモレキン夫妻に養子として迎えられた後、ほどなくしてセレイアス公爵邸へと居を移すことになった。
ディエルに初めて挨拶をしに行った場で決まったことなので、リチェが実際にモレキン夫妻と過ごした時間はそれほど多くなかった。
結局、書類上では家族になったが、実際には簡単に親しくなれる関係ではなかった。
そしてしばらくして、リチェはアルガが与えた「良い部屋」の正体を知ることになった。
それは、アルガの行方不明の娘のために公爵夫人イサベルが用意してくれた部屋だったのだ。
その部屋はなんと、小公子エルアンの部屋のすぐ隣でもあった。
リチェはその事実を知ってから、何度もその件について感謝を伝えたいと思ったが、アルガの性格が気まぐれで突発的だったため、なかなかタイミングをつかめなかった。
そして結局、後になってからはもう二度と口にしないことにした。
アルガと少しずつ親しくなっていくにつれて、リチェはかえって彼に対して遠慮が深まり、心の奥底の率直な話はできない関係になっていったのだった。