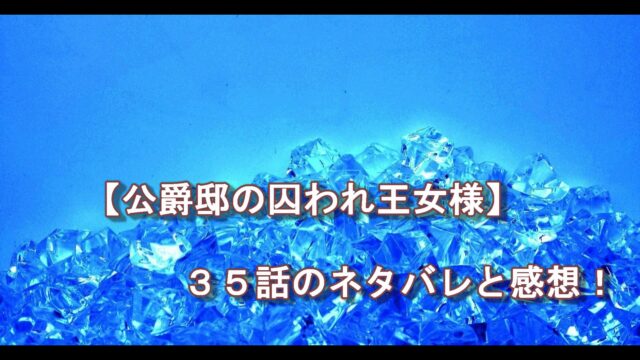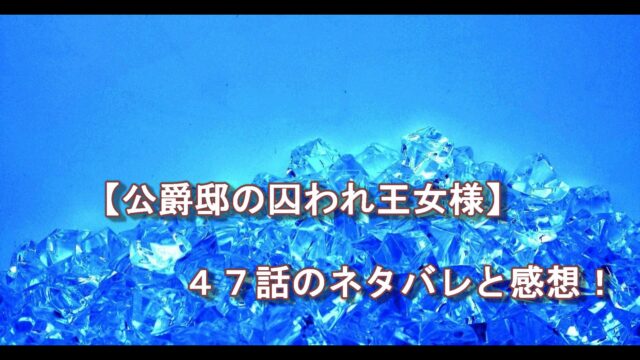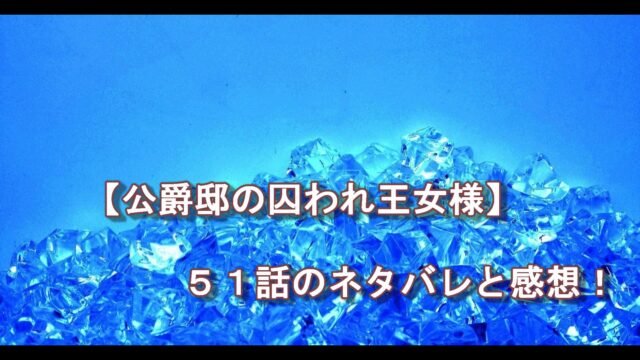こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

121話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 王子の悩み
この国でただ一人の「王子様」であるバレンタインは最近、受験勉強を怠けていた。
そのおかげで、最近の月末試験は完全に失敗したが、実のところそんなことはどうでもよかった。
彼は恋愛小説を研究していた。
面白いからではなかった。
その本を読んでいると、体中がムズムズするような感覚に襲われ、頭の上に冷水をぶっかけて正気を保ちながら読まなければならないほどだった。
それでもその小説を読む理由はひとつだけだった。
自分の気持ちと比較するため。
バレンタインは、クラリスに対してある程度特別な感情を抱いていることは分かっていた。
ただし、それが小説でよく語られる「唯一の」ものなのか。
あるいは、しばしば胸を打つ「衝動的」な感情に過ぎないのかの判断がつかなかった。
彼自身はおそらく、後者に近いのだろうと考えていた。
最初からあんな女の子を本気で好きになるわけがないじゃないか。
いつも両手は傷やあざだらけで、暴力的なのはもちろん、頑固さだって相当なものだ。
それだけじゃない!
彼はクラリスへの不満が尽きなかった。
自分よりも大して美人でもないくせに、たまに驚くほどきれいに見せて人を惑わせるじゃないか。
いったい何の化粧品を使っているのかはわからないが、人を惹きつける香りを漂わせることもあった。
……。
彼はいつの間にか本にまったく集中できず、何時間もクラリスのことばかり考えていたことに気づいた。
『今度は読書まで邪魔するなんて!』
彼はクラリスへの不満に新たな一行を加えた。
その時、彼の頭の中に何の前触れもなく、ある学習がひらめいた。
本当に役に立つことなど一つもない厄介ごとであるのは明らかだった。
彼はまったく集中できない小説をパラパラとめくった。
すると、ふと目に留まった一文があった。
『あなたの気持ちを確かめたいんですか?』
こんな陳腐な展開がまだ続いているとは。
バレンタインは短くため息をついた。
なぜなら、この小説の男性主人公がまったくはっきりしない性格だからだ。
幼い頃に出会ったヒロインに一目惚れし、十数年たってもその気持ちに気づかず、「友達」としてそばにいるなんて、
誰が見ても惚れていて、その場から離れられないのが明らかなのに。
それなのにこの愚か者は、まだ自分の気持ちを確かめようとしているのだ。
何を言ってるんだか。
恋愛がそんなに甘いものか?
好きならすぐ走って行って、花でも気持ちでも何でも差し出しても足りないくらいだろうに。
「ほんとにくだらない小説だな。」
彼は呆れて、何一つ役に立たない小説だと思いながらも、次の内容をつい読んでしまった。
[お互いをじっと見つめながら手を握ってみてください。]
ちなみに筆者は剣術法の専門家だった。バレンタインは大きく息をついた。
[その瞬間、手のひらに伝わる温もりが本当に貴重なんです。]
パタン。
彼は本を閉じた。
やっぱり他の本を参考にする方が良さそうだと思った。
どうしようもない男主人公が出てくる小説を図書館に返却したあと、彼は通りかかったユジェニーを呼び止めた。
「マクルド。」
「……はい?」
彼女は何か本能的な不快感を覚えたのか、眉間にしわを寄せて彼を見返した。
だが、彼女を見るたびに何とも言えない不快感を覚えるのはバレンタインも同じだったため、やはり眉間にしわを寄せた。
「クラリス、見ましたか?」
「はい、見ました。」
返答はそれだけだった。
バレンタインは「全く無愛想なやつだな」と思いながら、質問を変えた。
「どこで見たかを聞いているんだよ。出題者の意図くらい少しは読み取ってみたらどうだ?」
「王子様は出題者ではありません。いちいち出てきて意図まで読み取らなければならないほど、私たちは親しくありません。」
「親しくないから、こうして遠慮なく会話できるんじゃないですか。話が長引くのを防ぎたいんじゃないですか?」
「はい、最初に王子様が正しい質問をしてくださっていたら、そうなっていたでしょう。」
どうして一言もやり返さずにいられるものか!
バレンタインは、他に聞きたいことを思い出したのか、再び尋ねた。
「クラリスがどこにいるか教えてくれるかい?親愛なるマクレード嬢。」
「親愛なるはやめてください。」
ユジェニーはうんざりした顔でそう答え、指先で自習室の方を指した。
「左側の窓際にいます。」
「ちなみにありがとう、あ?」
「はい、わかれば十分です。」
そして先に一歩進んでいったユジェニーは、ふと何かを思い出したように立ち止まり、バレンタインを振り返って言った。
「徹夜したみたいです。」
「なんだって?」
「ですから、部屋に戻るようお伝えください。」
彼女はそう言い残して、他の受験生たちが呼んでいる方へとスタスタと去っていった。
『なんだ、急に?』
クラリスが夜を徹して勉強していることを、なぜバレンタインに報告しなければならないのか。
初めから彼がそんなことを尋ねたこともなかったのに。
彼はブツブツ言いながら自習室へ向かった。
二重の扉を押し開けると、ふとクラリスへの言葉が頭に浮かんだ。
――夜を徹して勉強することに、明確な勉強法などない。
それは、徹夜した自分に一瞬だけ酔いしれる満足感を与えるだけで、次の日をまるまる台無しにする危険があった。
『まあ、クラリスなら三晩くらい徹夜しても問題ないだろうけど。』
彼はいつもより少し人が少ないように感じる自習室をぐるりと見回した。
ユジェニーが事前に場所を教えてくれたおかげで、運よくすぐにピンクの髪の彼女を見つけることができた。
彼女はぼさぼさの髪をどうにかすることもできず、机に頭を伏せていた。
『……ひどい、ほんとに。』
また難しい問題を考えているのか、髪をかきむしるような仕草をしていた。
その様子があまりにも冴えなく見えたので、バレンタインは少し安心した。
なぜなら、彼が読んだ恋愛小説によれば、恋に落ちた男性主人公の多くは、そんな冴えない姿を見ても「かわいい」と錯覚するものだからだ。
『やっぱりこの気持ちは衝動だったんだな。』
そう思って安心した彼は、クラリスの隣に座って背中を軽くぽんぽん叩いた。
「何の問題でそんなに悩んでるんだ?」
軽い声で尋ねたが、クラリスは何も答えなかった。
代わりに深いため息をつきながら、うつ伏せだった顔をこちらに向けた。
「……?」
バレンタインは、突然現れたその表情に戸惑った。
『……寝てる?』
自然に浮かんだ疑問は、実に明白だった。
夜を徹して勉強したのだから、昼寝に落ちるのは当然ではないか。
そう思いながらも、彼はそんな当たり前のことさえ思い出せず、クラリスの顔をぼんやりと見つめていた。
机に伏して赤く染まった頬だとか、かすかに閉じられた両目とふわりと乱れたまつ毛、そして少し結ばれた唇にまで視線が至った。
『かわい……』
思わず考えなしに浮かんだ言葉。
その瞬間、はっと正気に戻ったバレンタインは、急いで襟元を正した。
可愛いだなんて、どこが?
真っ赤な吹き出物や、寝ていて腫れぼったい顔のどこに美しさがあるというのか。
よく見ると、徹夜のせいで疲れきった目元まで乾いてしょぼしょぼしているではないか……。
『噛みつきたくなる、かわいいな。』
彼はくだらない場面で高鳴る心臓を片手でぎゅっと押さえた。
そしてまたしても事故が起きた。
本当に、遠慮なく誰にでもバシバシ叩いてくるんだから。
『こんなことまで暴力的だなんて。ああもう……。』
彼はなぜか全身の力が抜けて、クラリスの隣に一緒に横たわった。
こうしていると、クラリスがなぜ眠ってしまったのか分かる気がした。
背中に降り注ぐ陽射しがとても温かく、心地よかった。
まるでそのまま溶けてしまいそうな気分になるほど。
すぐ近くで深い寝息が聞こえてきた。
その穏やかな音はとても愛おしくて、思わず耳を澄ませた。
それに合わせて、クラリスのふわふわした髪がかすかに揺れた。
その様子を見るのがなぜか心地よかった。
ぼんやりとしたまま、つい見つめ続けてしまうほどだった。
『……あ、唇まで……動いた。』
何かを食べる夢でも見ているのだろうか。
淡いピンク色の唇がわずかに開いて閉じる、その短い瞬間に、彼は思わずふっと笑ってしまった。
こうなると、こんなに可愛い顔をしていったい夢の中で何をしているのか気になってきた。
いや、それよりもバレンタイン自身がその世界に登場しているのかを知りたかった。
もしそうなら、夢の中の彼らは手を取り合っていたかもしれない。
出会った場所で温もりを分かち合いながら、大切に思い合って。
「……そうだったらいいのに。」
そんな思いが込み上げて、じっと見つめていたその瞬間。
うっすら閉じていたまぶたの奥で、かぼちゃ色の瞳がぱちりと開いた。
互いに顔を寄せ合ったまま、視線がぶつかり合う、数秒間。
バレンタインは、今にも告白が漏れそうな唇をきつく結んで、勢いよく身を起こした。
少し怪しい行動を見たせいか、近くに座っていた受験生たちが一瞬彼らの方を見た。
もちろん大したことではないと分かったのか、すぐにまたそれぞれ勉強に視線を戻したが。
眠りから覚めたクラリスは少しぼんやりした目で目をこすった。
「王子……様?」
「お、お前……!」
こんなふうにいきなり目を覚ますのはどこにあるんだ?
そう思いながら何か言いかけて、バレンタインは口をつぐんだ。
万が一、自分の寝言を聞かれていたら困るのはバレンタインだからだ。
「……で、よく寝られたか?」
バレンタインは無難な返事を考え出した。
少なくとも彼はそう思った。
しかし、じっと自分を見つめるクラリスの目は、なぜかとても疑わしそうな光を放っていた。
『まさか聞かれた……?』
彼が顔を近づけたままクラリスの顔をじっと見つめていたことを――
『……それは……ちょっとまずいな。』
彼がクラリスにドキドキしているという事実は秘密にしておかなければならない。
恥ずかしいから!
世の中に人がいなくて、よりによってあの乱暴な女を好きになるなんて……!
「王子様、何か隠してますよね?」
「……っ!」
どうしてバレたんだ?
「王子様が私に優しく声をかけるときって、いつもそんな感じですし。」
幸い、彼女はバレンタインの内心を完全に見抜いていたわけではないようだった。
彼が小さく戸惑っているうちに、クラリスはカバンの中から小さな手鏡を取り出して覗き込んだ。
「少なくとも顔には落書きされてないですね?」
「いや、僕がいくらなんでも……っ」
眠っている子の顔にそんなことをするかと問おうとしたバレンタインは、黙り込んだ。
やった。
正確には、やったことがある。
彼は、勉強中に居眠りしていたクラリスの額に「バレンタインの部下」と書いたことがあった。
それは12歳くらいのときのことで、その落書きを見たクラリスがどれほど悔しくて泣いたか、なだめるのに苦労した記憶があった。
「……またやるつもり?お前、俺が顔に『クラリスの主人』って書いてから泣き止んだくせに。」
「それは泣き止んだんじゃなくて、怒ったんですよ。」
「だから結局は『主人』という単語を消して『子分』って書き直したら満足そうにしてたじゃないか、お前。」
「当然です。」
ずる賢い天才がからかわれるのは当然だった。