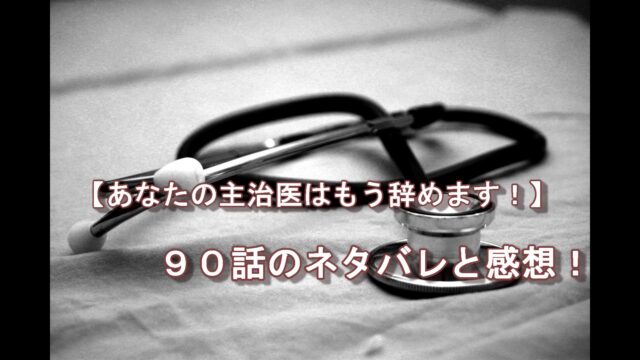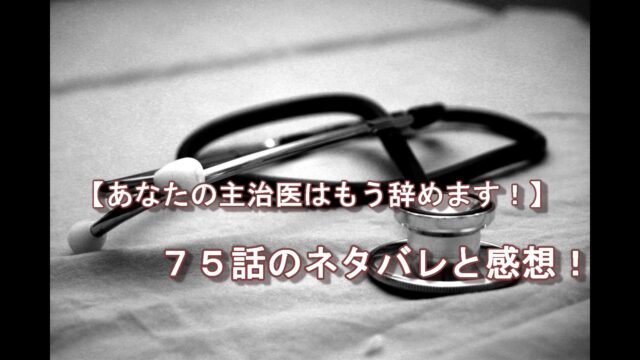こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

155話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 主治医が苦しければ
結婚式の日、私たちは皆、父の忍耐強さに感嘆した。
結婚式が進む間、彼は泣かなかったのだ。
正直、誰もが父は私の結婚式の最中に大号泣するだろうと予想していたが、それは意外だった。
もちろん、結婚式が終わって来賓を見送った後、父はこらえていた涙を堰を切ったように流しながら嗚咽した。
「うぅ、うぅぅぅ……リチェ、お前がこんなふうに行ってしまったら、いったい私たちはいつまた会えるんだ!」
「すぐ会えるよ、お父さん。」
私はお父さんの肩を軽く叩いて言った。
「新婚旅行から帰ってきたばかりなのに、すぐに通常出勤されるんですね。」
「ううぉぉぉぉぉぉ……」
私の手を握りしめてむせび泣くお父さんをそっと引き離したのは叔母だった。
「落ち着けよ、人間。私に一発くらう前にそのへんでやめとけ。」
叔母は誰も言えなかったことをぶつぶつとつぶやきながら私に言った。
「リチェ、行け。一週間後にまた会おう。」
「お父さん、この前お話しされていたあれ、しっかり見てきますね。」
お父さんはすすり泣きながら、最後にはしっかりとこぶしを握りしめた。
「ううっ、ひっ……出産の過程はしっかり見ておくんだよ……うぅぅぅっ。」
こうして私は、結婚式を終え、エルアンと新婚旅行に出かけることに。
新婚旅行には、侯爵家の数名とジケルも同行した。
私たちの新婚旅行先は、南部のイルビアだった。
というのも、エルアンが幼い頃、5年間療養していたまさにその場所だったのだ。
「はぁ……イルビアですか。」
ジケルはため息をつきながら呟いた。
エルアンに尋ねたところ、ジケルはイルビアの公女であるセリアナと微妙な関係にあるという。
互いに好意を持ちつつ、身分の違いに悩んでいるようだった……
「誰かに似ているね。」
エルアンは冗談っぽく話し、私は以前セリアナに嫉妬したことが思い出されて恥ずかしくなり、顔を赤らめて話題を変えた。
「新婚旅行、すごく楽しみです。」
新婚旅行先を決める時、意見の衝突はまったくなかった。
私たち二人とも完全に合意して決めたからだ。
「私の人生にあなたがいなかった5年間…… 毎日あなたのことを考えながら、戻ってくる日だけを指折り数えてた。」
エルアンは甘い声でささやいた。
「会いたくて死にそうだったのに、ただ空だけを切なく眺めるしかなかった。あの時は本当に辛い時期だったよ。もう一度行って、君との思い出で上書きできたらどんなにいいかと思う。」
もちろん私も満足してそう答えた。
「サルサリーフ専用容器、これは実物を見ると本当にすごいですよ。お父さんもとても不思議がってました。また南部に行きたいくらいです。私も気になります。」
ふたりは少し違う考えを持っていたようだけれど、どちらも望んでいる場所は同じだったのだから、それでよかった。
「すごくワクワクする。ナンブはまた避暑地としてとても良い場所だよ。海が目の前に見える別荘を予約しておくね。他に望むことはある?」
「では、ひとつお願いしてもいいですか?」
「言ってごらん。ハニームーンにぴったりのどんなロマンチックな見どころでも、美味しい料理でも、甘いサービスでも……」
「薬草専用容器の製造工場を見学したいんです。可能でしょうか?」
正直に言えば、半分は冗談だったが、半分は本気だった。
ナンブに住むイリビアは植生が大陸とはまったく異なり、珍しい薬草も多く、それをこの目で直接見るという事実に胸が高鳴った。
そしてもう一つ、イリビアへ新婚旅行に行くということは、考慮すべき要素が一つあった。
船に乗って、かなり長い時間海を渡らなければならないということだ。
「私、船に乗るの初めてなんです。」
私は甲板に出て、揺れる海を見つめながらわくわくして言った。
前回ラベリ島に行こうとしたときは天候の悪化で失敗し、メイリス公国へ行くときは陸路を使っていた。
「すごく素敵!」
海風は涼しく、波が船にぶつかってはじける様子は見事だった。
日差しにきらめく海を見ていたとき、隣にいた年配の女性がにっこりと笑いながら先に親切に話しかけてきた。
「お嬢さん、イレビアへ向かう航路は初めてかい?」
「はい!海風が爽やかで気持ちいいですね。」
「ほら、西側の甲板に行けば、遠くにイルカの群れが見えると思いますよ。一度行ってみてください。」
「イルカですか?わあ、ありがとうございます。」
イルカと聞いただけで心臓がドキドキした。
私は元気よく会話を続けた。
「イレビアへ向かう航路をご存じなんですね。」
「仕事の都合で主に帝国に滞在していますが、元々イレビアに本家があるんです。それに今回は、私が実の娘のようにかわいがっていたジョカの結婚式があるので。」
老婦人はほほ笑みを抑えきれずにいた。
「新婚夫婦みたいで、とてもお似合いですね。うちの姪も結婚して幸せに暮らさなきゃね。」
「遠くからお祝いに駆けつける叔母さんもいるくらいだもの、もちろん幸せに暮らすわ。」
私たちは感謝の挨拶をして、老婦人の教えてくれた西側の甲板へ移動した。
西側の甲板には誰もおらず、開放感があった。
遠くに岩礁らしきものが見えるようだった。
私は目を細めてエルアンに話しかけた。
「船って、思ったよりそんなに大きくないですね?」
「海賊が掃討されたとはいえ、まだ南部との交流が活発ではないからね。」
エルアンは私を抱き上げて、あの遠くにいるイルカの群れをもっとよく見せてくれながら言った。
「くそっ、あの海賊たちさえいなければ……。運がよければ一度くらいは君に会えたかもしれないのに。」
彼の低い声には、じわじわと怒りが滲みはじめていた。
「いや、もしそのとき僕がもう少し年を取っていたら。海軍に志願して海賊もジェイドもまとめて一掃してやったのに。」
「……うん、エルアン。」
私は彼の髪を撫でながら言った。
「もう本当に昔の話だし、5年間イレビアにいたって言っても、実際に何か被害を受けたわけでもないじゃない。なのにどうしてそんなに怒る必要ある?」
「どうして怒ってないさ。君が成長していく姿を見られなかったんだから。」
エルアンは悲しそうな表情で私をぎゅっと抱きしめた。
「14歳のリチェのほっぺたがどれだけ愛らしかったか、15歳のリチェの身長がどれだけ小さかったか、16歳のリチェの髪がどれだけ長かったか、僕は一生知ることができないんだよ。」
「…………」
それは私自身も覚えていないことであり、今教えてあげることもできなかった。
エルアンは私の首にそっと自分の唇を重ねながら、まるで補うように言葉を続けた。
「でも被害を受けてないって……どうしてそんなにひどいことを言うの。」
私の腰を抱いた手に力がこもるのを見て、何かを望んでいるからこそこうして空気を和らげようとしているのだと思った。
「仕方ないですね。じゃあ、今からでも実物を見せてください。」
「そうだよ。でもね、リチェ。」
エルアンは私の髪を撫でながら、潤んだ瞳で言った。
「海は……実は船室からでもよく見える。」
「え?」
「船室から君は海を見て、僕は君を見ていたいんだ。ほんの少しの間だけ。」
私は結局、エルアンに抱きかかえられるままになった。
イブリアへ向かうこの遊覧船で私たちが使っている部屋は一番広くて快適だった。
なぜか部屋に置いてある家具などがすべて私の好みに合っていたため、エルアンがすでに選んだのだろうと思ったが、あえて詳しく聞くことはしなかった。
二人きりになると、彼の愛情表現はさらに濃くなった。
「う……ただ会いたいって言って入ってきたんでしょう?」
私は海が見える窓のそばに横になっていられたが、実際には海の景色はあまり見られなかった。
波のように押し寄せるエルアンのせいで、正気を保つ余裕がなかったからだ。
彼はいつだって、私に世界一優しくて甘い態度を見せながら――どの部分においても、じっと私を見つめてくることはなかった。
「これは反則だよ……」
「まったく、リチェ。」
彼は平然とした様子で余裕あるように話したが、隠しきれない焦りと欲望が指先の一本一本に込められていた。
「見るだけだなんて言ってないよ。」
色っぽく目を細めて笑うエルアンとは違って、私は服を整える余裕もなく息が詰まってしまっていた。
そしてその熱気に戸惑い、私は静かに震えるように凍りついていた。
「船に乗ってからどれだけ経ったと思ってるの……本当に理性がないわ。」
「当然だよ。」
エルアンは私の下唇を痛くないようにくわえながら、そっと囁いた。
「君が目の前にいるのに、どうして理性が保てるんだ?」
再び熱い身体に包まれながら、私は体が震えた。
「私の妻、私の奥さん、私の人……。これからはこう呼んでもいいんだよな。」
耳元で囁くエルアンのささやきが甘く響いた。
「だから、僕は今日、世界で一番幸せだった。」
その言葉を聞いて、ついに私は彼をしっかりと抱きしめるしかなかった。
「これから毎日毎日、こうして君を抱きしめるよ。」
「あぁ……」
だけど、エルアンのその言葉は悲しい現実にもなれなかった。
次の日から、私はひどい船酔いを始めたからだ。
私はほとんど食事ができず、気持ち悪くてずっと横になっている状態だった。
船に乗ったことがなかったので、自分が船酔いする体質だとは知らなかった。
お父さんが昔、私を探してあちこち走り回ったときに船酔いしたという話は聞いたことがなかったから、事前にあまり気にしてもいなかった。
それに、私は船酔いを「ちょっとする」程度ですらなかった。
薬をどんなに飲んでも効果は微々たるものだった。
その程度の効果もなければ死んでいたかもしれないというほどだ。
ここまでくると本当に体調不良を深刻に考えざるを得なかった。
いつも健康で頑丈だった私が、こんなにも特異なほどにぐったりする体質だったとは想像もできなかった。
「リチェ、戻ろう。」
ぐったりしている二日目、エルアンは力の抜けた私の手をしっかり握って言った。
「南部に行くより、戻る方が早い。」
「今は海が大荒れなのに、どうやって戻るんですか?」
力のない私の質問に、エルアンはあまりにもあっさりと答えた。
「船を回せばいいんだ。」
「……この船には私たちだけが乗っているわけではないんですよ。」
「望むだけの物質的な補償を……」
「エルアン。」
南部で何不自由なく育ち、礼儀教育もまだ不十分なエルアンに対し、保育園で育ち、素直で正しく育った私は落ち着いて言った。
「時間はお金で買えません。絶対にダメです。」
「でも、君がこんなに苦しんでいるのに……」
「クジラを見せてくださったご婦人の気持ちを考えてみてください。姪の結婚式に出られなくなるのは困りますよね?」
「………」
エルアンは黙々とスープをかき混ぜた。
そして私の髪を撫でながら、悲しそうに言った。
「むしろ僕が代わりに病気になればよかったのに……」
今すぐにでも船を引き返したいが、自分の意思ではどうにもならないことを我慢している表情だった。
「本当に、どうして方法がないんだろう……。僕も君のように天才医者だったらよかったって、今ほど切実に思ったことはないよ。」
その心配に満ちた目を見て、私は苦笑しながら言った。
いつも誰かの病気を心配して治療していたのは私の役目だったのに。
「あなたは、私が病気になるたびに、どうにかして治してくれるじゃない」
「でも、私は本当に無力だよ。」
「エルアン。天才医師でも船酔いは治せないの。だからもうそんなに辛く思わないで。水を少しちょうだい。」
エルアンは医学の知識はなかったが、理解力はあった。
私の一言で、彼は冷水からぬるま湯、ぬるい水、熱いお湯まで用意してきた。
「実は船酔いよりもっと心配なことがあるの。」
私はぬるま湯を飲みながら言った。
「船酔いを和らげるために、今お腹の中に強い薬草をたくさん摂ってるの。でも、それを摂らないのも私には辛すぎて……」
エルアンは真剣に鍋をかき混ぜながら、心配そうにした。
「でもこれくらいの量だと、突然ショックがきて意識を失うこともあるんですよ?」
「……えっ?」
「そうなったら、驚かずにお医者さんを呼んで、このメモを渡して治療するように言ってください。特別に難しいことじゃありません。」
私は力なく、横に置いてあったメモを手渡した。
そこにはこれまで私が服用してきた薬草の種類と量が日付ごとにきちんと整理されていた。
「大したことないから、絶対に、絶対にあまり驚かないでくださいね。わかりました?」
もし私が倒れたらエルアンがどうなるかが目に浮かんだので、私は必死に頼んだ。
「わかった、心配しないで。」
エルアンは私の髪を撫でながら穏やかに言った。
「驚かないよ。君の言う通りにうまく対処するよ。安心して食べて、横になって。」
もちろん、その穏やかさを信じるのは簡単ではなかった。
エルアン・セルイヤーズは……今、私が船酔いしているというだけで、満員のこの船を引き返そうとした人だったのだ。
「エルアン。」
「うん。」
「万が一、私が南部に着いた後に倒れても、その地域の医者を全部呼び集めたりしないでください。簡単な治療なので、ほとんどの医者がうまく処置できますから。」
「……うん。」
返事が少し遅れたのを見て、「呼べる限りのすべての医者を呼んで来い」と命令したのは明らかだった。
そして、その「すべての医者」に含まれる可能性のあった、平民医者出身の私は冷静に釘を刺した。
「それと、『お金はいくらでも払うから、とにかく助けてくれ』みたいな大げさなセリフもやめてください。その程度のショックではないですから。私が恥ずかしいです。」
「……うん。」
またしても返事は少し遅れた。
明らかに難病や死を連想させるような大げさな反応をすると予想していた私は、今回もその予想が的中した。
もちろんエルアンは、自分が呼べる限りの最高の医者を呼ぶだろうが、それは仕方がなかった。
私が知っているエルアンであれば、イリビアの親しい貴族に頼んで、実力が保証された主治医を呼ぶに違いないからだった。
「ショックが来たら、どんなに処置がうまくても3日から5日ほどは目を覚まさないはずです。絶対に医者を急かさないでください。」
「リチェ。」
エルアンは思い浮かべるだけでも心が張り裂けそうだという表情で、苦しげに言った。
「本当に医者を呼んで、君のそばに置いておいて、何もせずにただ待ってるだけでいい? でもあまりにも、あまりにも不安だったらどうするの? 3日たっても目を覚まさなかったら?」
「うーん……」
それはとても鋭い質問だった。
エルアンは、私が足をもつれさせても慌てるほどだったのに、私が意識を失っていたら、自分が正気を保てなくなるのが目に見えていた。
いくらなんでも「誰でもいいから医者に任せておいて」といった私の現実的な助言は…
「じゃあ、いっそお父さんに伝書鳩を送ってください。」
私は安心させるように彼に微笑んで言った。
「お父さんなら、これは本当に何の後遺症もないって分かってるし、お父さんが“大丈夫”って言えば、エルアンも安心するでしょう?」
伝書鳩はとても短いメモしか届けられない代わりに、速度は一般の書信とは比べものにならないほど速かった。
エルアンはそれ以外にも、私の指示をいくつか受けた後、夜でも昼でもひたすら真心を込めて私を看病してくれた。
「昔、ずっと昔に――」
夜が深まると、船室に設けられた大きな窓からは銀河が見えた。
痛いものは痛いし、降り注ぐ星明かりが美しいのは美しいことだった。
「すごくつらかった夜、君が夜通し私の手を握ってくれたよね。」
その星明かりを背にして、エルアンがしみじみと語った。
「正直、君が手を握ってくれたからって治るわけじゃなかったけど、治った気がするって嘘をついてもいいくらい、すごく安心できたんだ。」
あのとき私よりも体が細くてひょろひょろだった少年が、こんなにも健康になって、今では私の手を握ってくれていた。
「翌日、目を覚まさないかもしれないって思って、夜が怖かった。君は夜よりももっと怖いものから私を守ってくれるって言ってくれて、君さえそばにいてくれれば、私は一晩中でも平気だったんだよ。」
私は何の気力もなかったが、微笑むしかなかった。
「リチェ、君をとても愛している。僕の心配さえ負担になるかもしれないけど、僕にできるのはこうして手を握ることだけだよ。」
私はエルアンの手をぎゅっと握って答えた。
「エルアン、聞いてください。」
エルアンの大きな瞳が静かに私を見つめた。
「これまでの人生で、こんなに苦しかったのは一度だけです。」
私も忘れていたほど昔の話だった。
「12歳のとき、保育園で…… 傷んだ食べ物を食べて、一晩中下痢で苦しんだことがあるんです。」
「うん。」
「夜中に先生たちの眠りを妨げることもできず、だからといって助けを求められないルームメイトたちを起こすこともできなくて、一人で布団の中で声を殺してしくしく泣いてました。」
「……どうしてそんなことを。」
「ただ、保育施設の生活ってもともとそうなんです。何でも自分のことは自分でしなきゃいけないって。だからあの夜、一人で具合が悪かったんですが……それがすごく寂しくて。」
「………」
「それから私は健康にはとても気をつけて、一度も病気になりませんでした。具合が悪いときに一人でいるのは、本当に心細いですから。」
私はくすっと笑いながら、エルアンの頬を撫でた。
「……誰かがそばにいる状態で苦しんだのは初めてです。もちろん、痛いのはとても、とても嫌だけど……あのとき幼いエルアンの夜を見守ってあげられてよかったと思います。」
「……」
「今、私は身体は辛いですが、一人で苦しむときとは比べものにならないほど心が満たされているから。」
そうして私たちは毎晩、静かにそんな話を交わした。
「戻ったら、あの頃の観察日誌を見てみよう。エルアンがすっかり元気になって忘れていたけど。」
「観察日誌?」
「患者を見る時に観察日誌をつけるのは主治医の基本です。幼い頃のエルアンに関する記録です。」
「……うん。一緒に見よう。」
お互いがいなかったそれぞれの夜と、そのときの思い出のような話をお互いに語り合った。
私たちが向かった初日は絶望だったが、だからといってすべてが悪いわけでもなかった。
そして……。
結局、南部に到着して地面を踏む直前にショックで倒れてしまった。
私は倒れる直前に最後の思考をした。
『私が予想していなかった変数があったのかな……。エルアンが私の言うことを聞いて、平凡に何事もなく過ごしてくれたなら……。』
やたらとおとなしい南部の医師たちに迷惑をかけるわけにはいかなかったからだ。
夜がしんしんと更けていく。
エルアンの腕に支えられ、彼の手の温もりを感じながら、ある程度は落ち着くことができた。