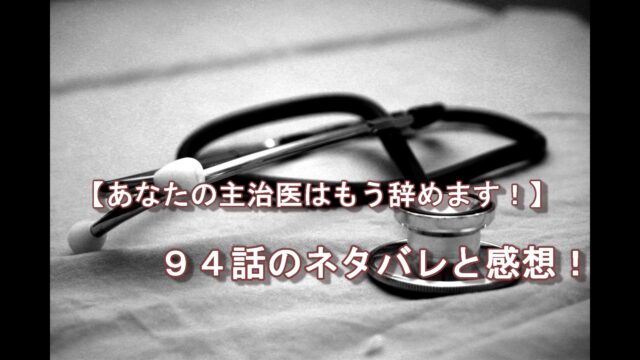こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

163話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- ユリアの宴会③
宴会は初めてでした!
宴会場はとても美しく、華やかに着飾った人々があちこちに集まっていました。
「毎日こんな宴会があったらいいのに」と思うくらい、素敵な光景でした。
「エルアン、セドリアンはどこにいる?」
私たちを見つけるやいなや、父は雷のように近づいてきて、母は周囲を見渡しながら尋ねました。
きっと、私は母が、兄は父が連れてくることになっていたのでしょう。
「長老が直接連れて来られるはずよ。」
「はぁ、面倒だな。」
お母さんはこめかみを押さえながら、少し呆れたように言いました。
「明らかにセドリアンと薬草の話をしたくて、お父さんが先に手を打ったんでしょうね。でも今日がセレイアス城で開かれる宴の日なのに、夫婦が同時に入場できないなんて。」
「まあ……。」
お父さんは優しく微笑みながら答えました。
「幼いお前とは医学の話はできなかったから、セドリアンとはそういう話をしたくなる気持ちもあるんだろう。」
「そう言われると、何も言えないけど。」
私はすでにあちこち見回していたので、母と父が何を話しているのかよく聞こえませんでした。
今日の午後、私と鬼ごっこをしていた貴族の子どもたちが向こうに集まっていたのです。
「あそこへ行って、また楽しく遊ぼう」と思いながら見ていた時、母と父の会話が耳に入ってきました。
「エルアン、主な養育者はあなたなのに、なぜ子どもたちは私の方をもっと好きなのかしら?それに、あなたは子どもたちによくしているのに。」
「それは当然のことだよ、リチェ。」
「当然ですって?」
「君は僕よりずっと可愛くて美しくて優しい。誰だって僕より君を好きになるのは当たり前じゃないか?」
「う……うーん……それはそうだけど、それでも……」
「もちろん少し寂しいのは事実だけど、たとえ子どもでも、私より君の方がずっといいと思うよ。それは本当だよ。」
私の手を握っていた外祖母が、深いため息をつきました。
「私の従兄弟は本当にエリザベスに似ているわ。」
「おばあ様ですか?」
「そうよ。あの子は死ぬまでずっと同じだった。食べるのが好きで、口下手で。お前のお父さんもリチェの前だと単純さでは長寿風鈴並みなんだよ。」
どう考えてもお父さんに似ていない方が良い選択のように思えました。
「でも、お父さんとセドリアンはどうしてあんなに合わないんだろう?」
お母さんは口元をかすかに笑みで歪めながら時計を見つめていました。
「もう宴会が始まっているのに……まもなく私が挨拶もしなければならないし。何かあったわけじゃないよね?いずれにしても誰かを向かわせないと。」
「私が行きます!」
私は手をパッと挙げて叫びました。
ちょうどセドリアンに会って、自分の剣を自慢したい気持ちもあったのです。
「私がみんなを連れてきます!」
「うん、そうか? 今すぐ行って戻れば、挨拶までには間に合いそうだな。」
母は一度私の頭を撫でてから、ひとりで行かせてよいものかと言いたげに周囲を見回しました。
するとちょうど、私たちに必要な人が近くにいたのです。
「お嬢様、ご一緒しましょう。」
今日ひときわ格好よく装ったディエルが手を差し伸べながら言いました。
そうして私はディエルと一緒に、宴会場からセドリアンの部屋へと出発したのです。
宴会場からセドリアンの部屋まではかなり離れていて、回廊をしばらく歩かなければなりませんでした。
「ところでお嬢様、その剣は何ですか?」
「外祖母がくださったの!」
「……セイリン様が?」
私はディエルの前で、とても誇らしげに剣を習った通りに振り回してみせました。
私の剣がヒュンヒュンと音を立てるたびに、ディエルは体をすくめて後ろへ下がったのです。
「どう?私、上手でしょ?」
「心配になるくらいには上手ですね。もう剣を少し収められますか?」
「わかった。でもね、ディエル。私、外祖母に似てるみたい!剣術の才能があるんだって!」
私が得意げに言うと、ディエルは深いため息をついてぶつぶつ言いました。
「なんという悲劇か……。もし性格まで似ているのなら、お嬢様と長く平穏に過ごすのは難しいでしょうね。」
私はその言葉に返す言葉がありませんでした。
なぜなら、大きな眼鏡をかけて小鳥のような髪色をした、小柄な女性が数人の侍女を従えて、ちょうど向こうから姿を現したからです。
「おっと。」
もちろん私は初めて見る人でしたが、ディエルは彼女を見るなり驚いて、慌てて恭しく礼をしました。
「わ、我が帝国の皇太子妃殿下に謁見いたします。」
皇太子妃?
そういえば、ずっと前にお母様とお父様が皇太子妃について何か話していたのを聞いたことがある気がしました。
――「ジェイド皇太子殿下、ご結婚なさるとか?皇后陛下とジェンシー公妃様が直接お見合いを取り計られたそうよ。」
――「僕も聞いたよ。まるで花の台座にぴったりの新しい靴のようだって。知恵と愛国心だけを備えているそうだ。」
――「……エルアン、正しくて美しい言葉を使いましょう?優しくしようと約束したじゃない。」
「おや、セレイオス城の使用人か?道に迷ったようで……。宴会場はどこだ?」
「まっすぐ行って、角を二度右に曲がれば着きます。」
「おお、ありがとう。」
皇太子妃は眼鏡を押し上げながら、直接感謝の挨拶をし、ディエルは腰を深くかがめて礼をしました。
彼女はそのまま私たちの横を通り過ぎようとしましたが、私の顔を見ては足を止め、可愛いというように微笑みました。
「ふむ。この子は……セレイオスの姫君か?」
「はい。」
考えてみれば、あまりにも不思議で礼を尽くすことさえ忘れてしまったんです。
すべて習ってきたことなのに。
後で乳母が知ったら叱られるに決まっています。
私は急いでスカートの裾をつまみ、片膝を折って挨拶しました。
「帝国の皇太子妃殿下に謁見いたします。ユリア・セレイアスと申します。城の宴会にお越しいただき、心より歓迎いたします。」
「そうね、公女。帝国を伝染病から救った私たちのリチェ嬢のお祝いの宴なのだから、当然皇室からも来て感謝を伝えなければならないわ。」
皇太子妃の瞳が眼鏡の奥で、月光のようにきらめきました。
「皇太子殿下は今、アオト山脈で山岳偵察中のため来られず、代わりに私が参りました。」
「……ああ……山賊討伐だなんて、ご心労が大きかったでしょう。」
たまにお父様が領地周辺に出没する盗賊を直接討伐しに行くと、お母様の顔色が良くなかったのです。
口では「エルアンに会う盗賊が気の毒よ。全然心配いらないわ。」とおっしゃっていましたが、内心では心配していることがはっきりと分かりました。
だから私はそう言ったのですが、皇太子妃は面白がるように微笑みました。
「ふふ?それ、私が差し向けた者たちよ。」
「えっ?」
「皇太子殿下は帝国にとって非常に大きな人材です。頭さえ無事なら……。でも心配はいらないわ、公女。」
皇太子妃が目をきらめかせて言葉を続けました。
「くだらない信念を掲げて尊大に振る舞う皇太子よりも、熱心に行動する皇太子が百倍マシよ。まして私はとても賢くて、しかも愛国心にあふれているのだから。」
言葉があまりに早くて全部理解できたわけではありませんでしたが、とりあえず私はスカートをつまんで礼をしました。
「だから帝国の未来については心配いらないわ、公女。私はこうした子どもたちを見ると必ず安心させてあげたくなるの。子どもは希望に満ちた未来を描きながら生きていかなければならないから。」
皇太子妃は後ろからついてきた侍女に声をかけ、私に砂糖菓子をひとつ渡してくれました。
少し風変わりな人ではありましたが、どうやら良い人のようでした。
とはいえ、私はまだ六歳。心配事は尽きません。
帝国のことまでは心配しなくてもいいと分かって、本当に安心しました。
今まで帝国のことを心配しようなんて考えたこともなかったのですが。
「とにかく、才能というのは良いものだよ、公女。時代が才能ある皇太子妃を求めているおかげで、家門の後ろ盾のおかげもあって、私が皇太子妃の座にまで上がれたんだから。」
皇太子妃はまた大きく笑い、道を教えてくれてありがとうと言いながら、もう一度挨拶をして私たちの前から姿を消しました。
正直、彼女が言ったことを全部理解したわけではありません。
けれど一つだけ、心に残った言葉がありました。
「才能は良いものだ」と……。
確かに、お母様も天才で、お兄様も天才だと言われています。
だから才能というのはきっと良いものなのでしょう。
「ディエル……私も、『私は天才だから』って言葉……なんだか壮大な運命の絵が見えるよう。」
ディエルはしばらく黙っていたが、ため息をついて答えました。
「どうして?」
「私はこれまで数多くの天才たちの……いや、天才のふりをした人々の世話をして生きてきたんだ。三代目にして、やっとそこから抜け出したいと思っていたのに。」
そんな会話を交わしながら、私たちは兄の部屋にたどり着きました。
案の定、兄は外祖父と共に持ち込まれた医学書を読みふけり、夢中になっていました。
しかも兄は髪に手を通すことすら忘れていて、着ている服も普段着のままでした。
ディエルが口元に笑みを浮かべて言いました。
「うーん……セドリアン様?どうして何の準備もしていなかったんです?」
「おじいさまと本を一冊一緒に読んでいたら……」
「ええ、その机と楽器が目に浮かぶようですね……。興味津々の令嬢たちを退屈させるフェレルマン子爵様が……」
ディエルがため息まじりに言い、私は少し背伸びをして新鮮な気持ちで言いました。
「お母様が心配してるの。お母様の祝賀の宴に遅れちゃったんだって。」
「なんだって?これは……!リチェが心配してるだなんて!」
その言葉に、びっくりして反応したのはおじいさまでした。
「どうしようか?ああ、私が主犯だったとは……。まるで幼い頃の自分を見るようで、娘の宴を台無しにしてしまうなんて……。」
「そこまで台無しってわけじゃないけど……。」
立ち上がってそわそわするおじいさまを見ながら、私は心の中で思いました。
おじいさまに似ていると言われるのも……あまり良いことではないのかもしれません。
「行こう、行こう!」
「はあ、でもセドリアン様は宴の準備もできていないのに!」
ディエルが心配そうに口を挟むと、兄はうなずきながら答えました。
「いや、いずれは僕もあのような表彰を受けることになるはずだ!」
「だからできるだけ早く出席しないとね。お母様が挨拶の言葉を述べなきゃいけないんだから。」
そうして私たちは慌ただしく再び宴会場へ向かいました。
宴会場に到着すると、残念ながらお母様の歓迎の挨拶はちょうど終わったところでした。
お兄様はちゃんと準備もせずに駆けつけたせいで、当然ながら姿も見えません。
よく考えてみれば、私たちがお兄様を迎えに行く途中で皇太子妃様に会ってしまったせいで、かなり時間を食ってしまったんですよね。
しかも宴会場にいたはずの令嬢たちの姿まで、すっかり消えてしまっていました。
さっき一緒に遊んでいた子たちと、また遊びたいと思って嬉しくなったのに、みんなどこに行ったのかわからなくて辺りを見回していると、お父さんが優しく教えてくれました。
「子どもたちはみんな庭に行ったよ。そこで走り回って遊びたいんだって。」
「あ、本当ですか?私も行きます!」
私は嬉しくて声を上げました。
ちょうど午後に鬼ごっこをしていて途中で別れてしまったから、続きをやりたかったんです。
「鬼ごっこしなくちゃ!」
「じゃあ剣は置いていきなさい、ユリア。そんな風に持ち歩いていたら無くしてしまうよ。」
「嫌だ。置いていかない。」
お母さんが心配そうに言ったけれど、私は絶対に剣を手放すことができず、私はすねてしまいました。
「じゃあ鞘師(さやし)に行って、固定用のベルトを作ってもらおうよ。」
私が駄々をこねると、父がにっこり笑って私を抱き上げました。
私は父に抱かれたままセドリアンを見て言いました。
「まず庭園にいるわ。ついてきて。」
セドリアンもわかっているというように頷きました。
ディエルが「送って行きます」と言ったけれど、セドリアンは「子ども同士で遊ぶのに大人がついて行く必要はない」と厳しく言い、ひとりで宴会場へと向かってしまいました。
さらには「私はもう十七歳だからね」という言葉まで付け加えたのです。
私は再び部屋に戻って、リボンの腰帯に剣をしっかりと結びつけました。
「まあ、子どもたちは宴会場の外で走り回って遊ぶほうがずっと楽しいでしょうね。」
私に一生懸命ダンスの作法を教えてくれた乳母は、少し笑いながら私の衣装の乱れを整えてくれました。
お父さんは私の頭を撫でながら言いました。
「この年頃の子どもが宴会場でおとなしくしていられるはずがない。自分のやり方で宴会を楽しめばいいのさ。」
そうして私は腰帯に剣を差したまま、嬉しくて庭へ駆け出しました。
お父さんが付き添うと言ってくれましたが、「大人がついて行ったら台無しだ」と言ったお兄ちゃんの言葉を思い出して、私は断りました。
六歳でも、私なりの矜持があるんです。
でも、少し離れたところで父がこっそり後をつけてくるのを感じました。
はぁ……お父さんは過保護がひどすぎます。本当に。
そして庭園に到着したときのことです。
「嘘つくなよ、お前がセレイアス公爵だって?」
子どもたちの集まりが兄を取り囲み、問い詰めていました。
「礼服も着てないし、髪だって乱れてるじゃないか?」
兄はさっき子どもたちと遊んでから着替えてもいなかったし、今も宴会の準備のための身支度はまるでできていない状態でした。
だから子どもたちは、兄が本当にセレイアス公爵だなんて信じられない様子だったのです。
「おかしいな。」
お兄ちゃんは呆れたように皮肉っぽく笑って言いました。
「まさかセレイアス公爵を崇拝するような大それた奴がいるなんて思ってないだろうな。」
澄んだ緑の瞳は母に似ていたけれど、基本的にお兄ちゃんは父に似ていて背が高かったのです。
その瞬間、みんながお兄ちゃんの辛辣な言葉に互いに目を見合わせました。
どうやら私が行って助けてあげなければならない気がしました。
私はちょこちょこと駆け寄りながら叫びました。
「みんな、なんでそんなことしてるの!何してるの?」
お兄ちゃんのすぐ前に立っていたのは、バラス公爵家の令息でした。
子どもたちはぎょっとして私を見ました。
彼はしばし動揺した表情を浮かべた後、兄に向かってさらに声を荒げました。
「まさか……顔が整っているからセレイアス公爵令嬢に気に入られた召使いなのか?」
私は思わず口を開けたまま固まってしまいました。
少し前に「私はイケメンが好き」と言ったばかりだったので、変な誤解をされてしまったようです。
「だからといって、こんなふうに他人を侮辱するなんて駄目よ!」
「ふん……愚かなら、せめて口を閉じていればいいものを。まあ、その程度の知能もないのだろうがな。」
「なんですって!」
なんと、そう言ったのはバラス公爵の嫡男だったのです。
お兄ちゃんの首元を掴むなんて、どういうことなの?
お兄ちゃんはいつも本ばかり読んでいるから、喧嘩なんて得意じゃないのに!
その瞬間、私の頭の中に響いたのは、外祖母の言葉でした。
――「それでも血縁だからって、ジメジメと小言を言ったり、みすぼらしい姿を見せられると腹が立つんだよ。罵るのも私の役目だってね。まあ、そんなものさ。」
最近私に冷たくしたとしても、私以外の誰かにお兄ちゃんが殴られるのは嫌でした。
だから私は腰帯に差していた剣を素早く抜き、あっという間に剣鞘ごとバラス公爵家の令息の腕を叩き落とし、そのまま腰を狙って打ち込みました。
これは、祖母から教わった通りの言葉でした。
「恐れ多くもセレイアス公爵の命を狙うつもり?」
私は兄の前に立ちふさがりながら剣を突き出し、問いかけました。
バラス公爵家の嫡男を含めた子どもたちはもちろん、兄もあまりに驚いた表情で私を見つめていました。
「ゆ、ユ、ユリア?」
兄は呆然とした顔で尋ねました。
「剣を……いつ習ったんだ?」
けれど私はその問いに答えることができませんでした。
少し離れたところから、私をこっそりつけてきていた父までもが駆け寄ってきたからです。
父もまた驚きのあまり、他の子どもたちには目もくれず、私の肩をしっかり掴んで問いただしてきました。
「ユリア?その剣は今日プレゼントでもらったものじゃなかった?いつの間にそんなに手慣れて……」
「あ。」
私は肩をすくめて、にっと笑って見せました。
そして堂々と答えたのです。
「だって、私は天才ですから。」
その言葉には、お兄ちゃんでさえも反論できませんでした。
その日以来、父と外祖母の仲はさらに悪化しました。
私の剣の腕前が「自分に似たのだ」と、お互いに言い張って喧嘩を始めたのです。