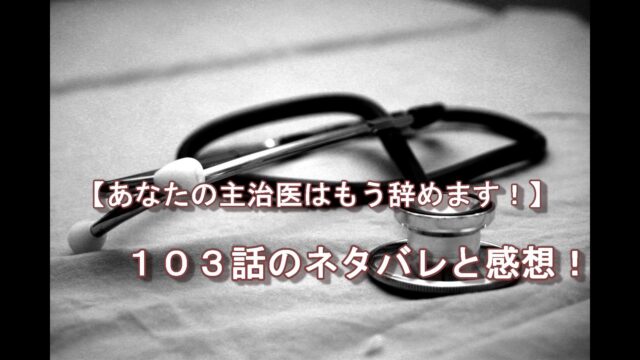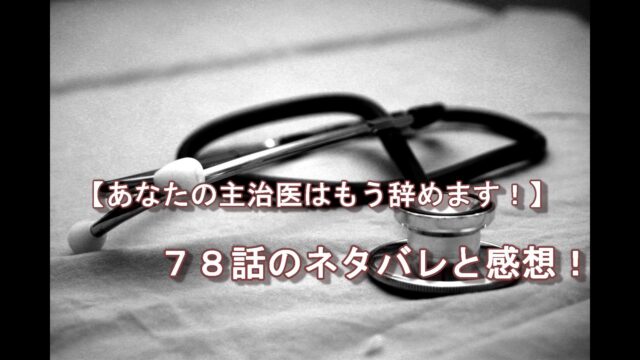こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

167話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- ラベリ島
「久しぶりに二人で旅行に来るといいですね。昔を思い出します。」
ラベリ島は大陸から行くのが難しく、それゆえ美しいことで有名な場所だった。
エルアンと私は結婚式に出席したあと、船が出るまでしばらく滞在することにした。
私が乗り物酔いしやすい体質だったため、島で十分休んでから行こうというエルアンの提案によるものだ。
それももっともなことで、そうでなくてもラベリ島には頻繁に来られる場所ではなかったので、この機会に親戚たちへ挨拶することにしたのだ。
ラベリ島は狭く、人々同士が親密に繋がっていた。
だから私にも歌の友達がたくさんできた。
そうして首都から離れ、こんな余裕のある暮らしをしているうちに、本当に長く滞在したいという気持ちになった。
もっとも、子どもたちのことを考えれば長く留まるわけにはいかなかったのだが。
「お父さんも来られたらよかったのに。」
「そうだな。」
顔も知らない親戚だったが、母の方の結婚式だったので、向こうは父にも一緒に来てほしいと言った。
だが、父はやや困惑した表情で断ったのだった。
最初の頃、父は私たちがラベリ島に行くたびに絶対に同行しようとはしなかった。
最初は母の親戚たちが父に対して距離を置いているように思われたが、直接会ってみるとそうでもなかった。
むしろ、少し気まずそうにしながらも父が一人で避けているような雰囲気だった。
皆が「いや、あれほど妻を愛していた人なのに、どれほど悲しいことだろう」といった反応をしていたところを見ると、母の親戚たちは父が母をどれほど深く愛していたかについて、特に疑問を抱いていないようだった。
「いや、一体どれほど切実に愛していたら、ラベリ島の人々まで父の気持ちを知っているんだ?」
とにかく、今回も私とエルアンだけがラベリ島に来ることになった。
「これ……ペレルマン邸宅の庭にある木々ととてもよく似ているね?」
エルアンはラベリ島で育つ特有の植物たちを眺めて微笑み、私がふっと笑って答えた。
「はい、母がラベリ島を懐かしがって、祖父が庭全体をラベリ島の植物で満たしたそうです。」
「……ああ。」
エ르アンは沈んだ表情で答えた。
「もしかして羨ましい? 公爵邸にももっと大規模に作ってあげようか。この旅行の記念にもなるし。」
「いいえ、結構です。」
ここで少しでも同じような植物園が公爵邸にできでもしたら、と思うと私は慌てて手を振った。
「ただ、そういう物質的なもので記念するより──ここでしか作れない特別な思い出のほうが、より記憶に残るものですから。」
もともと私はそうした感傷的なことに大きな意味を感じるほうではなかった。
だが、エルアンが本当に目を輝かせて木でも抜いて帰ろうとしそうだったので、とりあえず止めることにした。
「実際、ここは大陸のどこよりもちょっと違うでしょう?」
母がラベリ島出身というただそれだけで、帝国の社交界では大きな人気を博していたという。
だが実際に来てみると、誰もがラベリ島を称賛するのも納得できた。
帝国の他の地方とは確かに雰囲気が違っていた。
まず服装からして明らかに軽やかだ。
袖が紐で結ばれただけのワンピースを誰も気にせず着ているほどだった。
街中で気軽に着て歩ける場所なんて、大陸中探してもラベリ島のほかにはないだろう。
最初は私もエルアンも少し気恥ずかしかったが、ラフな服を着て出歩いてみると、暑い気候にとても快適で涼しかった。
派手な花柄のワンピースを着て、ココナッツを片手に海岸を歩いていると、まるで別世界に来てしまったように思えた。
「服装からしてとても楽で……だからこそ、もっと自由になれる気がします。」
もちろん、こうした服に関しては貴族も平民も特に差はなく、誰でも同じように着ていた。
服からくる威圧感が生活に影響を与えるのか、ラベリ島ではほかの地域に比べて、貴族と平民のあいだに不自然な隔たりが少ないように思えた。
「リチェ、あまり自由すぎてはだめだ。」
エルアンは少し不機嫌そうに眉をひそめた。
「ここの男たちはどうも軽薄すぎて気に入らないんだ。」
「なにを……ただ、私たちに親切にしているだけでしょう。」
「どうだか。」
よその島に来てその独特な文化をどうこう言うつもりはなかったが、エルアンはとりわけここのウェイターたちが気に入らなかった。
レストランで料理を注文する際、大きな花を耳に飾った男たちが習慣的にウィンクをしてくると、まるで地獄の使者を見るかのような表情を浮かべたものだった。
セレイオスの文官ですら、あんな顔はしなかっただろうと何度も言って聞かせても、エルアンはその表情を変えようとしなかった。
それもそのはず、彼はすでに大きな怒りを無理に抑えて必死に心の奥へ押し込めていたからだ。
「夫と旅行に来た貴婦人に、あんな態度をとるなんて……。」
「それでもエルアンにも公平にウィンクしてくれるじゃないですか。」
「それが余計に腹立たしい。」
「まぁ……相手も喜んでやっているんでしょう。」
エルアンの無表情な顔を見ながら、そのウィンクが資本主義的な意味合いを持つことを一目で見抜くことができた。
そんなこともあったが、外祖母は「お前の父親もまったく同じことを言っていたよ!瞬きをパチパチさせるのはまるで鳥のようで、本当におかしかったんだ!」と大笑いするだけだった。
大陸の人々はそれを「とても上品だ」と互いに真似して笑い合うほどで、ラベリ島の人々にとっては全く気にすることでもないようだった。
そのため、エルアンはただ耐えるしかなかった。
もちろんエルアンはこうした状況に本当に慣れていなかった。
首都では、エルアンが私をひどく大事にしていると誰もが知っていたため、すべての男たちが気をつけて接していたからだ。
だがここは大陸から離れた辺境の島であり、そんな噂すら届いていなかった。
だから通りすがりの男たちは、何のためらいもなく私にウィンクをしてきたのだ。
エルアンも内心穏やかではなかったが、それでも大きな騒ぎを起こすことはできなかった。
とはいえ、妻の前で嫉妬のあまり本気で怒り出すほど無礼ではなかったからだ。
「エルアン、もしかして……」
しかし彼だけの激しい反応に、私は額をひそめながら、合理的な推論をひとつ口にした。
「私が散歩に出るたびに一緒についてくるのって……あのウェイターたちを牽制してるってことですか?」
「まぁ……」
エルアンは否定もせず、気まずそうにくすっと笑った。
「きっとあの中の一人はお前に言い寄ってくると思って、気が気じゃなかったんだ。親切そうに見せかけて笑ってるけど、妙な下心くらいあるかもしれないし。」
かつて必死に嫉妬心を燃やしていた過去があるせいか、エルアンはますます他の男たちを警戒していた。
「君は可愛くてきれいな上に、頭までいいから本当に心配なんだ。」
「そんなエルアンこそ。」
「僕は顔立ちが冴えないから大丈夫だよ。」
「あなたは自己認識が本当に素晴らしいですね。」
そんなやり取りをしながらエルアンと散歩していたとき、少し離れたところで私の同年代の女性が手を振っているのが見えた。
「リチェ!こんにちは!」
「まあ、エナ!」
ふんわりとしたワンピースを着て現れたエナは、この地に来て私ができた友人のひとりだった。
母のいとこの縁者だと聞いていたが、結局は他人ということだ。
それでも社交的な御令嬢だったので、私とはかなり良い関係を保っていた。
ともあれ、赤い髪を高く結い上げたエナが私たちに近づき、にっこり笑いながら先に声をかけてきた。
「こんにちは!素敵な時間を過ごしていらっしゃいますか?お散歩中ですか?」
「はい。ラベリ島は本当に美しいですね。」
青い海には陽光が反射して宝石のようにきらめき、華やかな植物たちは異国的な色彩を放っていた。
なぜ人々がラベリ島を最高のリゾート地として憧れるのか、その理由がわかる気がした。
訪れる回数は多くなかったが、来るたびに本当に美しかった。
「毎日一緒に散歩しても、この道は本当に素敵ですね。」
私がにっこり笑って言うと、ラベリ島で生まれ育ったエナは誇らしげに笑った。
「褒めていただいてありがとうございます。」
「ちょうど夕日を見ながらカクテルを飲もうと思っていたんですけど、ご一緒しませんか? 一杯ご馳走します。」
ラベリ島の人々はティータイムをあまり持たず、その代わりに海辺でカクテルを飲むのが習慣だった。
当然受け入れてくれるだろうと思っていたが、エナは私の提案を丁寧に断った。
「大丈夫です。実は少し体調が優れなくて。散歩もいいですが……よければ、明日の小さな行事にいらっしゃいませんか?」
カクテルを一緒に飲むのは自然と無くなったが、話題はすぐに移った。
「小さな……催しですか?」
「明日、海で水泳大会があるんです。ラベリ島ではなかなか大きな行事ですよ。」
「まあ、海で泳ぐんですか?」
私はすぐに興味を引かれ、両手を合わせたまま尋ねた。
エナが親切に説明した。
「はい。若い男性たちが1年間鍛錬した成果を披露するので、見応えがありますよ。」
「そうなんですね。もしかして、とんでもない賞品とかが出たりするんですか?」
「特別なものはありませんが……それでも大勢の人の前で、自分のレディに栄光を捧げられる機会になるんです。それだけでも、カップルにとっては一生の思い出になるんじゃないですか?ラベリ島では本当に意味のある行事で、優勝者とその栄光を受けた女性には“栄誉のレディ”という称号がつくんです。」
見るからに若者たちの活気に満ちた行事のようだった。
エナは頬を赤らめながらも積極的に続けた。
「セレイアス公爵ご夫妻が来てくだされば、きっと優勝者も、その栄光を受けるレディも、とても喜ぶと思います。」
まあ、客観的に見れば――ラベリ島でセレイアス公爵位を持つ私たちは、極めて特別な存在なのだ。
元々自由な雰囲気の人々だったので、あまり堅苦しく接することはなかったが、皆が私たちを尊重してくれていた。
私はエナの好意に感謝し、柔らかく答えた。
「参加します、エナ。とても面白そうです。」
「えっと……もしかして奥様にご無理をお願いしてしまったのでは?他にご予定があるとか……。」
「いいえ、全然です。それに本当に興味があるんです。私は泳ぎがまったくできないので、泳ぐ男性たちを見るのはとても素敵だと思います!」
「では、そのとき我が家の観覧席にいらっしゃいませんか?ご一緒に!」
そして私は、エナと他愛もないおしゃべりを交わすうちに、エルアンの目が輝いていることを見落としてしまった。
若者たちが一年を通じて待ち望む大イベントらしく、水泳大会が開かれる浜辺はとても美しく飾り立てられていた。
エメラルド色の海が押し寄せる白い砂浜に、色とりどりの仮設テントが張られていた。
降り注ぐ日差しの下、水着姿の男たちが小麦色の肌を誇りながら体をほぐしている光景は、正直かなりの壮観だった。
そしてエルアンがその水泳大会に参加しているのだと私が知ったのは、大会当日のことだった。
「こ、これは一体どういうことなんですか、エルアン?」
私は水着姿のエルアンを見て慌てて尋ねた。
「リチェ、私は南部で5年を過ごしたんだ。」
エルアンの鍛えられた筋肉が太陽の下できらめいた。
真っ青な海を背に、エルアンは少年のようににっこり笑った。
「たくさんの海賊を海の底に沈めたりもしたんだ。海で泳ぐのは得意なんだよ。」
「でも、いくらなんでも……。」
私は混乱しながらも、自分が慌てた理由を順に整理して口にした。
「まず、参加申し込みはすでに全部締め切られたと聞きましたけど。」
「お金と権力さえあれば、こんな非公式の大会なんて参加者が一人増えるくらい大したことではない。」
「それに、普通は独身の男性が思い出に残るプロポーズのために出場するんだそうですよ。」
「だからといって既婚男性が出場してはいけないという決まりもなかったよ。」
「大体は二十歳前後の男性が多く出場しているみたいですけど。」
「それは単なる慣習であって、正式な年齢制限があるわけじゃなかったな。」
エルアンは平然と答えた。
「それに、外部の人間が参加するのも初めてではないらしい。運営側も特に難色を示していなかったぞ?」
「……本当ですか?」
「そうさ、リチェ。よく考えてみろ。それに一生の思い出を作るチャンスじゃないか?」
そのときになってようやく、エルアンがこの大会にわざわざ参加した理由がわかった。
「ただ物質的なもので記念するよりも……ここでしか作れない特別な思い出の方が、ずっと記憶に残るものですから。」
そうだ、結局間違っていたのは私の方だった。
エルアンは私の言葉を聞き流すような人ではなかった。
むしろ、あまりにも鮮明に覚えてしまうからこそ、問題なのだ。
「特別なものなんてなくても……それでも多くの人の前で、自分のレディに栄光を捧げる機会だろう?」
エナがその言葉を口にした時から、エルアンはすでに決心していたのだろう。
私は島の若者たちのように気軽な水着姿のエルアンを見て、思わず笑みをこぼした。
帝国の大貴族、セレイアス公爵家がこんなラフな姿で、平民でも参加できる大会に全力で臨むなんて……。
『本当に見応えがある。』
私は陽光に輝くエルアンの引き締まった体を目に焼き付けながら言った。
「だからラベリ島の若者たちが、一年中楽しみにしている行事なんですね。」
「それはあいつらの勝手な都合だ。俺はラベリ島の男たちがどうにも気に入らない。何人か叩きのめせるなら、それで十分だ。」
「でも、それでも……」
「なんだ、俺が優勝できないと思ってるのか?それでそう言うのか?」
エルアンは余裕の笑みを浮かべて言った。
「なら、俺に勝てばいいだけの話だ。そうすれば、あいつらにとっても一生の思い出になるだろう。セレイオス公爵に勝ったんだからな。」
――確かに、その言葉も一理あった。
ラベリ島は何しろ海に囲まれた土地で、この島の若者たちは息をするように泳ぎながら育ってきた。
だから、何年も泳いだことのないエルアンが必ず勝てるとは限らなかった。
もちろん、こんなに多くの男たちの中にいると、体は多少圧迫されるけれど……。
私は引き締まったエルアンの体をもう一度目に収めてから、そっと首をかしげた。
「ねえ、リチェ。」
そして私の視線を逃さなかったのは、やはりエルアンだった。
「かっこいい?」
彼は長いまなざしを艶めかしく揺らしながら、一歩近づいてきた。
いずれにせよ、彼は私の視線が自分に注がれている間、決してそれを手放さなかった。
彼が私の頬に軽く唇を寄せた瞬間、そこから海の爽やかな香りが広がった。
「優勝して帰ってきたら、もっとかっこいいだろう?」
いたずらっぽく笑うエルアンの顔に、久しぶりに「負けん気」というものが浮かんでいるのを見て、私はあえて止めないことにした。
考えてみれば、エルアンよりずっと若い、二十歳を過ぎたばかりの青年たちが大勢いるのに、まさかエルアンが優勝するなんて思えなかったからだ。
むしろ、もしエルアンが勝ってしまい、ラベリ島の若者たちを皆失望させてしまったらどうしようと心配する、自分勝手な老婆心のような気さえした。
「優勝できなくても慰めてあげますからね。」
いろいろな可能性を考え、合理的な結論を出した私は、彼の肩にそっと手を置いて微笑んだ。
「だから、ほどほどに頑張ってください。」
「お前が他の泳いでる男たちに目を向けない程度に、一生懸命やることにするよ。」
どうせこうなったのなら、エルアンと楽しい思い出でも作ろうと、私は思い切って彼の頬に口づけをした。
「危なくはないんですよね?」
念のため心配そうに尋ねると、エルアンはにっこり笑いながら答えた。
「うん、深いところまでは行かないそうだ。あそこに浮標が見えるだろう?あそこまでを十往復するんだって。」
「じゅ、十回ですか?」
絶対的なスピードも重要だが、持久力も大きな要素になるほどの相当な距離だった。
しかも十往復だなんて、途中で退屈してしまいそうだ……。
「私は3番の浮標だよ。聞いたところによると、5番の浮標を割り当てられた男が有力な優勝候補らしい。」
つまり、浮標を一つずつ割り当てられて、海岸のゴールまで往復する形式のようだった。
「六ヶ月前に二十歳になったばかりの若者だってさ。まったく、子どもみたいなもんだよ。」
いずれにせよ、その有力な優勝候補はエルアンよりみんな若い、ということだった。
その時、選手たちを呼ぶラッパの音が高らかに響き、エルアンは私の頬にもう一度口づけをして、白い砂浜へと駆けて行った。