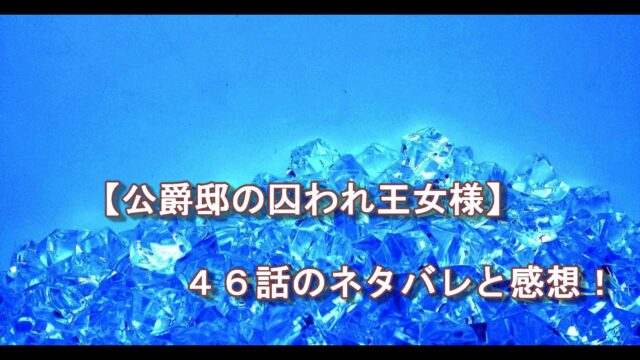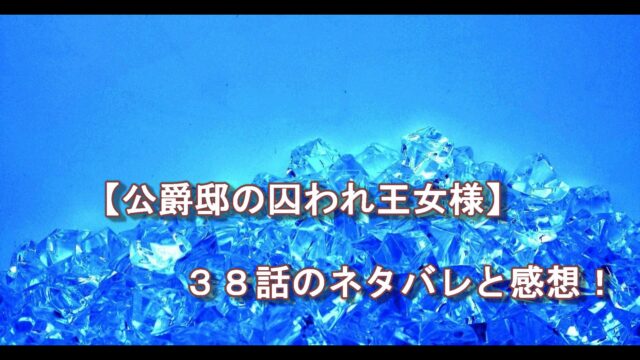こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

135話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 罪人の身
最悪だ。
ノアは部屋に戻るなり、壁に額を打ちつけた。
痛かったが、どうせ自分はどうしようもない人間だ。
これくらいの罰は受けて然るべきだろう。
仮に、三十回ほど打ちつけたところで、ユジェニがやって来て騒音の苦情を入れてくれなければ、止めるつもりはなかった。
――ああ、本当に。
彼は深く息を吐き、額を壁に預けたまま、ゆっくりと目を閉じる。
「……何をやってるんだ、俺は」
そう呟いた声は、誰に聞かせるでもなく、静かに部屋の中へと溶けていった。
「……俺は、聖人なんかじゃない」
仮面を外したまま、ノアは少し前の出来事を思い返していた。
廊下で、クラリスが泣いていると気づいた瞬間から、彼は正気ではなかった。
喜びの涙を流す彼女を見たときは、それでも――きれいだ、と思えたのに。
けれど、何かに傷つき、今にも崩れそうなその姿を前にした途端、胸の奥まで引き裂かれるような感覚に襲われた。
『……一度だけ、抱きしめてもらえない?』
あの切実な言葉を耳にしたとき、礼儀も理性も、考える余地はなかった。
気づけば彼は、クラリスを部屋へ連れて行き、強く抱きしめていたのだから。
彼女が抱えてきた悲しみが、どうか自分に移ってくれますように――そんな願いだけを、必死に抱きながら。
「……少なくとも、あの時までは。俺は、最低な人間じゃなかった」
問題は――クラリスが、少しずつ落ち着きを取り戻しはじめてからだった。
――そこから、始まってしまったのだ。
いや、正確には――彼が仮面を外した、その瞬間から。
顔を覆ってくれていた物理的な隔たりがなくなったことで、胸の奥から湧き上がる、正体の分からない衝動を、もう抑え込めなくなっていた。
(しかも……少女は、無防備にも近づいてくる)
無自覚にノアへ身を寄せたり、すっぽりと体を預けてきたり。
そのたびに、彼は内心で悲鳴を上げる羽目になっていた。
髪の隙間からふわりと漂う、甘いミルクの香り。
見上げてくる澄んだ瞳。
触れ合ったまま、くすぐったそうにもぞもぞと動く、その気配。
――ああ、もう。
思わず、ノアは自分の髪をぐしゃりと掻き乱した。
こんな状況になってしまうと、皮肉なことに、妙に良すぎる記憶力が災いする。
あの時の感触。
あの時の距離。
あの時の、息遣い。
鮮明すぎるほどに蘇るそれらの記憶が、彼自身の、あまりに個人的で、どうしようもない欲を――静かに、しかし確実に、煽り立てていた。
――ああ、神よ。
まさかクラリスを相手に、こんな退廃的な思考を抱いてしまうなんて。
自分の内面が、ここまで汚れてしまっていると知ったら、彼女はどれほど深く傷つくだろう。
そのことを思うだけで、胸が締めつけられる。
だからこそ、こんな感情は決して悟られてはならない――そう強く思う一方で、別の考えも、はっきりと浮かび上がってきた。
きちんと、クラリスに伝えなければならない。
彼女の額に口づけたあれは、祝福などという生易しいものではなかった。
――それは、クラリスを欲する気持ち、そのもの。
彼女を想う欲望が、確かにそこにあったのだ。
ならば、正直に打ち明けるべきだ。
そして、謝らなければならない。
純粋とは言えない、数えきれないほどの感情を抱えてしまったことを。
そのすべてを包み隠さず、差し出すように。
そして、最後に――慎重に、願いとして言葉を添えるのだ。
どうか、この無作法な獣を……警戒し、距離を取ってほしい、と。
――警戒。
その言葉を思い浮かべた瞬間、胸にわずかな鈍痛が走った。
それでも――正しい判断だ。
もし少し前と同じことが繰り返されれば、その時のノアは、もう耐えきれないだろう。
唇に触れたあの柔らかな感触を、すでに知ってしまったのだから。
――少女を……守らなければ。
ノアは深く息を吐き、机から身を起こして天井を仰いだ。
翌日。
ノアは、クラリスと二人きりで話せる機会が訪れるのを、落ち着かない気持ちで待っていた。
言うべき言葉は、すでに決めてある。
『一緒に修道院の馬厩へ行かないか?司祭様の許可は取ってある』
なぜ馬厩なのかと言えば、理由は単純だ。
昨日、クラリスが――はっきりと、そう言ったからである。
学んではならないものを望んでいる――彼女は、そう口にしていた。
ノアは、クラリスにとって禁じられている学びについて、ある程度は把握していたが、その大半は“魔術”に関するものだった。
そして、もう一つ――「乗馬」がある。
快活なクラリスは、幼い頃から馬の話題になると目を輝かせてきたが、今では、その憧れを抑えきれないほどに膨らませているようだった。
馬に乗りたいと、泣きじゃくるほどなのだから。
――まったく。
うちの少女は、考えることも、望むことも、つくづく可愛げがある……
いや、学ぶ機会そのものを奪われていれば、誰だってあんなふうに切なくなるだろう。
ノアは、クラリスが一時的に(保護の名目で)預けられている立場である今だからこそ、彼女を馬厩へ連れていき、せめて美しい馬を見せてやりたいと思った。
きっと彼女は、「私が乗馬を学びたいって、どうして分かったの?」なんて、無邪気に笑ってくれるに違いない。
そう想像しただけで、ノアは思わず肩をすくめてしまった。
クラリスのことなら、何でも分かっている――そんな自信が、いつの間にか胸に芽生えていたのだから。
あまりにも――誇らしかった。
ノアは、クラリスが通り過ぎるのを待ちながら、中央庭園の周囲をそわそわと歩き回っていた。
自室へ戻らなかったのは、万が一にも彼女から「……入ってく?」などと誘われてしまうのが怖かったからだ。
そんな甘い誘いを、ノアが拒めるはずもない。
下手をすれば、昨日の再来になりかねない……。
――やめろ。考えるな。
彼は高鳴る胸を手のひらでぎゅっと押さえつけた。
そのとき、玄関のほうからざわめきが聞こえてきた。
何かあったのだろうかと、修道士見習いたちが固まって様子をうかがっている。
新しい受験生でも来たのかと思ったが、開いた玄関をくぐって現れたのは、王宮に仕える侍従たちだった。
彼らは司祭たちに深く腰を折って挨拶すると、見習いたちの間を抜け、階段を上っていく。
ヴァレンタインもいない、今の王宮神殿に――どうやら、ただならぬ用件が持ち込まれたらしかった。
――ここで、いったい何が起きている?
胸に小さな違和感を覚えたノアは、他の修道士見習いたちに紛れるようにして、侍従たちの後を追った。
彼らが向かった先は、ヴァレンタインの私室だった。
司祭が扉を開けると、侍従たちは迷いなく部屋の中へ入っていく。
「何の用だろう……?」
「王子殿下に、何かあったのかな?」
見習いたちはヴァレンタインの部屋の前に固まり、ひそひそと囁き合う。
「ノア」
少し遅れて事情を知ったらしいクラリスが、ノアの衣の裾をきゅっと掴んだ。
「ねえ、どういうこと?どうして王子殿下の部屋に、王宮の侍従が来てるの?」
「僕にも分からないよ。たぶん、王宮と修道院の間で、何か話し合いがあったんだとは思うけど……」
言い終わらないうちに、扉が再び開いた。
侍従たちが、今度は廊下へと姿を現す。
その手には、ヴァレンタインが使っていたトランクと、数冊の書物が抱えられていた。
――嫌な予感が、胸の奥で静かに広がっていった。
すぐに立ち去ろうとしていた侍従たちは、予想以上に多くの修道士見習いたちが集まっているのに気づき、わずかに驚いた様子を見せた。
小声で何かを相談し合ったあと、その中で最も年長に見える侍従が一歩前に出て、はっきりと告げる。
「ヴァレンタイン王子殿下は、これより修道院での修学をおやめになります」
――そんなはずがない。
「ありえない……」
クラリスが、かすれた小さな声でそう呟くのが聞こえた。
ノアも、その気持ちは同じだった。
ヴァレンタインは他人ではない。
何より、クラリスをここに残したまま、黙って先に去るような人物ではない。
いや、仮にそうなるとしても――彼なら、まず真っ先にクラリスにだけは別れを告げていたはずだ。
ヴァレンタインにとって、クラリスはそれほど大切な存在だった。
それは、ノアが彼女を思う気持ちと、何一つ変わらない。
「殿下は、皆さまに直接ご挨拶できないことを、大変心苦しく思っておられます」
侍従は淡々と続ける。
「しかし、ここで過ごした日々を、殿下は心から大切にしておられました――」
その言葉が、胸に静かに刺さった。
――そう考えている、と殿下は仰っていました。そして、いつか皆さまと再びお会いできる日を、心より願っておられるとも。
その言葉を聞いた瞬間、修道士見習いたちの表情が一斉にこわばった。
王室の侍従の前では、誰一人大声で口にすることはできない。
けれど胸の奥では、皆が同じ思いを抱いていた。
――王子殿下が、こんな言い方をなさる方だろうか。
『共に学んだ日々を、生涯の誇りに思う』そう言って、笑ってくれる人だったはずだ。
「それでは、修道士見習いの皆さまのご健闘をお祈りいたします」
深く一礼を残し、侍従たちは回廊を抜けて去っていった。
その背中が見えなくなるまで、誰一人として動けなかった。
ノアは、いまだ自分の袖を握ったままのクラリスを見下ろす。
彼女の顔は、痛いほどに強張っていた。
――ヴァレンタインの身に、何かあったのではないか。
そう考えずにはいられない、不安を孕んだ表情だった。
翌日がちょうど週末だったのは、不幸中の幸いだった。
クラリスは朝早く、公爵家から差し向けられた馬車に乗って王都へ戻ってきた。
彼女が到着した時刻、マクシミリアンはまだ本宮におり、ブリエルは医師による定期検診を受けている最中だった。
ロザリーが「奥さまのところへ行かれますか?」と穏やかに声をかけたが、クラリスは静かに首を横に振る。
「お二人には、私が先にヴァレンタイン王子殿下のもとへ伺うとお伝えください」
「今すぐですか?殿下とご一緒に戻られなかったのですか?」
「……はい。少し、事情がありまして」
そう答えると、クラリスは服の内側に忍ばせていたペンダントを取り出し、はっきりと見えるよう胸元に掲げた。
王室の庇護下にある者であることを示す証だ。
これさえあれば、第三聖壁内部の立入禁止区域を除き、王都のほとんどを自由に行き来できる。
「行ってきます。長くはかからないと思います」
そう言い残し、クラリスは踵を返した。
胸の奥に残る不安を、振り払うように。
「気をつけて行ってらっしゃい」
ロザリの見送りを受け、クラリスは別宮を後にした。
「……モチ」
人通りの少ない場所まで来ると、彼女はそっと声をかけ、ポケットから小さな存在を取り出して口元に運んだ。
「王子殿下に、何かあったわけじゃないわよね?それ以外で、ここで変わった噂はある?」
「コォ。(ない)」
モチはクラリスの肩へ軽やかに飛び移ると、彼女の衣に付いた飾りを、まるで掴むように嘴でくわえた。
「コォ」
「……この辺り、ずいぶん静かね。王宮の敷地だから、他より落ち着いているのは分かるけれど……」
彼女は周囲の石壁に視線を巡らせる。
セリデン邸の外壁と内壁がそうであったように、王宮の内側を囲む石垣にもまた、**『王に選ばれた石』**であるという、静かな誇りが宿っていた。
それらは王家に忠誠を誓い、ゆえに――――余計なものを寄せ付けない。
クラリスは、理由もなく胸の奥がざわめくのを感じ、無意識に歩調を早めた。
普段から親しくしていなければ、彼らは見聞きした出来事をわざわざ伝えてはくれない。
それでも、クラリスが何度も行き来していれば、「夜更かしは体に毒だぞ」と小言を言う石もいれば、「王家への感謝を忘れるな」と、鈍く低い音で響く石もあるはずだった。
――それなのに。
どこからも、何の音もしない。
「……だから、やっぱり……」
彼女の胸に、嫌な予感が沈殿する。
――彼らが声を出すことすらできない何かが、この周囲にいる、ということじゃない?
不安に駆られ、そっと周囲を見回した、その時。
「おや。こんなところで会えるなんて、素敵な偶然だね?」
背後から、楽しげに弾むような声がかかった。
その声の主を、クラリスは一度たりとも忘れたことがない。
彼女はその場でぴたりと足を止め、ゆっくりと――本当にゆっくりと、振り返った。
まだ冬の名残を抱えた冷たい風が、頬をかすめ、乱れた髪をさらりと揺らす。
その先に立っていたのは――彼女の記憶に、はっきりと焼き付いている、あの笑みだった。
――やっぱり。
「こんにちは、僕の庇護者」
六年前と、ほとんど変わらない。
薄く整った微笑を浮かべたままのサイファス王が、そこに立っていた。
少し前、温室でこっそりと姿を見かけたことはあった。
だが、こうして正面から向き合うのは――あの日以来、初めてだった。
「……で……は」
喉が貼り付いたように、言葉がうまく出てこない。
凍りついた身体を叱咤するように、クラリスは深く頭を下げた。
慣れ親しんだはずの礼法が、ひどくよそよそしく感じられる。
背筋が、ぎこちなく強張った。
――怖い。
それが、正直な感情だった。
ライサンダーは、彼女にとって恩人だ。
今の暮らし、今の自由、そのすべては彼によって与えられたもの。
首元に揺れるネックレスが、その証だった。
罪人の身でありながら、第三城壁の内側を自由に歩ける――それ自体が、彼の庇護の証明に他ならない。
……それでも。
胸の奥に湧き上がるのは、感謝よりも、安堵よりも、まず先に――抗いがたい恐怖だった。
もしかすると、「こんにちは」と声をかけられた瞬間に、彼女の視線が揺らいだのは――その言葉そのものではなく、底知れぬものを孕んだ微笑のせいだったのかもしれない。
「毎回、金と教師の話ばかりで終わると思っていたが……」
低く、ねっとりとした声が、耳の奥に残った。
彼は一歩踏み込み、クラリスを値踏みするように見下ろした。
視線だけで、全身をなぞられる感覚。
それだけで、背筋が冷たくなる。
「随分と成長したな。社交の場に連れて行っても、見劣りはしないだろう」
その言葉に、彼女は反射的に身を強張らせた。
「……十五です、陛下」
震えを抑えながら、必要最低限の答えだけを返す。
「そうか。時間というのは残酷で、同時に実に都合がいい」
意味を測りかねる笑み。
冗談めいているようで、その実、逃げ場のない圧を孕んでいた。
クラリスは悟った。
この男にとって自分は、人ではなく“所有物”の延長線上にあるのだと。
恐怖は、感謝よりも先に胸を満たした。
クラリスは、自分が感じている恐怖の正体を理解していた。
それは、向けられている視線そのものではない。
――その向かう先だった。
ライサンダーは、敵意を隠していない。
だがそれが、彼女個人に向けられているのなら、ここまで心を凍らせることはなかったはずだ。
問題は、その刃が――セリデン公爵夫妻へと、明確に向けられていることだった。
それは奇妙で、そして不穏だった。
公爵夫妻は、王家に忠誠を誓う、由緒正しき貴族。
表立って敵視される理由など、思い当たらない。
それなのに、なぜ。
(理由が何であれ……慎重に答えなければ)
クラリスは、言葉を選ぶ。
もしここでの返答ひとつで、王が裏で公爵夫妻を追及することになれば――その責は、自分に返ってくる。
「……セリデン公爵様は、私を“罪人”として扱っております」
淡々と、事実だけを口にした。
「ほう?」
ライサンダーの口元が、わずかに歪む。
「罪人、か。ずいぶんと律儀な貴族だな」
試すような視線が注がれる。
「では――二人きりで、何か特別な“指導”でも受けているのか?」
言葉の端に、わざとらしい含み。
クラリスの喉が鳴った。
「……どのような“指導”を、おっしゃっているのか……」
問い返す声は、震えを抑えるのに精一杯だった。
沈黙が落ちる。
ライサンダーは、しばらく彼女を見つめていたが、やがて興味深そうに息を吐いた。
「なるほど。知らぬふりが上手いのか――本当に知らないのか」
そのどちらであっても、彼にとっては“使える”という判断なのだろう。
「いいだろう。今はそれで構わん」
そう言って、視線を外す。
だが、去り際に残された一言が、クラリスの胸を強く締めつけた。
「だが覚えておけ。“誰が、誰を守っているのか”――その構図は、いずれ必ず崩れる」
背筋を冷たいものが走った。
この男は、知っている。
そして、待っている。
クラリスは、無意識に拳を握りしめた。
(私は……駒にされている)
だが同時に、もう一つの事実も、はっきりと理解していた。
(――それでも、守らなければならない人たちがいる)
恐怖は消えない。
それでも、逃げるわけにはいかなかった。
「……処刑の“想定”だよ」
ライサンダーは、あくまで軽い調子でそう言った。
「お前が跪き、命乞いをしている。その背後で、王が裁定を下す――ただ、それだけの話だ」
その言葉に、クラリスの呼吸が一瞬止まる。
比喩だと、理屈ではわかっている。
だが、その声色には、冗談とは思えない重みがあった。
「そんな顔をするな」
彼は楽しげに、しかし冷ややかに続ける。
「まさか“助かる可能性がある”などと、甘い想定をしていたわけじゃあるまい?」
クラリスは、揺れる視界の中で必死に首を振った。
「……そ、そんなことは……考えていません」
声は、かすれていた。
沈黙。
ライサンダーは彼女を見下ろし、しばらく考えるように目を細めた。
「いい返答だ」
その一言に、背筋が凍る。
「立場の違いがわかっている。それだけで、お前は“賢い駒”だ」
賢い――その言葉が、救いではなく評価として使われていることが、何より恐ろしかった。
「覚えておけ」
低く、確実に言い切る。
「上に立つ者に話すときは、最後まで、曖昧さを残さずに言葉を選べ」
逃げ道を断つような忠告。
クラリスは、乾いた喉で必死に答えた。
「……はい」
それだけが、今の彼女に許された返事だった。
ライサンダーは満足そうに視線を外す。
「いい。今日の“想定訓練”は、ここまでだ」
その場を離れながら、最後に振り返って付け加える。
「生き延びたいなら――誰が剣を握り、誰が跪いているのか。常に、正しく見ていろ」
残された静寂の中で、クラリスはしばらく、動けずに立ち尽くしていた。
(これは……忠告なんかじゃない)
はっきりと、理解した。
(――脅しだ)
だが同時に、もう一つの事実も、胸に刻まれていた。
(それでも私は、まだ“生かされている”)
恐怖に足が震えながらも、彼女は、ゆっくりと背筋を伸ばした。
生きるために。
守るために。
選ばされる未来から、逃げないために。
「いいよ。」
彼はようやくクラリスの顔から手を放した。
ほとんど投げ捨てるのと変わらない勢いだったため、彼女はそのまま床へと崩れ落ちる。
ライサンダーは倒れ伏したクラリスを見下ろしながら、自分の手をゆっくりと握りしめた。
「手が……痛むな」
そう呟き、彼はほんの一瞬、どこか物悲しげに微笑んだ。
だが、それも束の間だった。
「お前は熱に浮かされて死ぬ」
「陛下のお言葉……その通りです」
「その日を待つことだけが、私の唯一の楽しみだ。ああ、本当に――お前が美しければ美しいほど、皆が熱狂するだろう!」
彼は再びクラリスを見下ろし、満足そうな笑みを浮かべる。
「どうか、この輝かしい祝祭に反旗を翻す者が現れませんように」
「誰もいません!それは当然の……ことですから」
「それなら好都合だな。もしお前の処刑が滞りなく執行されなければ――お前の名を冠して処刑される者は山ほどいる。本人はもちろん、家族も、部下たちも含めてだ」
彼は指先で、ゆっくりと円を描いた。
クラリスの目には、それがまるでセリデン全体を囲い込む輪のように映る。
「全員だ。一人残らず、丁寧にその首を刈り取ってやる。――お前の代わりにな」
一音一音に力を込めて告げるたび、クラリスの顔色はみるみるうちに青ざめていく。
その変化を、彼はひどく愉しげに見つめていた。
「さて……どうすればいいか、分かっているな?」
クラリスは、即座に答えた。
「わ、私は……必ず、疫病にかかった日に死にます」
「そうだ。お前は私の娯楽のために死ぬ。違うか?」
「わ、私は……」
クラリスは震えながら、座っていた場所から立ち上がった。
クラリスはライサンダーの前に身を屈めた。
「陛下のご娯楽のために、私は死にます」
「お前を助けようとする者は、どうなると言った?」
「……本人はもちろん、家族や部下たちも……すべて処刑されます。陛下の御手によって……」
「正解だ」
彼はクラリスの頭に手を置き、撫でるようにしてから、「よくやった」と、褒め言葉を与えた。
それは、生まれて初めて向けられた称賛だった――ただし、恐怖以外の何ものでもない。
クラリスは震える手を隠すように、そっと自分の服の裾を握りしめた。
「ふむ……こちらへ向かっていたということは、私の弟のもとへ行く途中だったのか?」
「……はい」
「可愛い弟が喜ぶ顔が目に浮かぶな。気難しいあの子と、うまく付き合ってくれて感謝している」
「王子殿下は……とてもお優しい方です。本当に……」
「惚れた女をどうにかして喜ばせようとするのは、どんな男でもやることだろう?私だって、お前たちにその程度の労は惜しまないさ」
「……え?」
その言葉の意味が理解できず、思わず問い返したが、ライサンダーは肩をすくめるだけだった。
「分からなくていい。まだ幼すぎるのかな?こういう楽しみを知らないなんて。もっと大人になるべきだな」
彼は急に興味を失ったかのように肩を落とし、くるりと踵を返して別の道へ向かう。
その後ろを従者たちが静かに追い、やがてその場にはクラリス一人だけが取り残された。
「……コオ」
街路樹の陰に身を潜めていたモチが、そっと顔を覗かせる。
「ん?あ……大丈夫、大丈夫。わ、私……分かってるから……そんな話だったでしょ?」
「コオ……」
「平気だよ。本当に大事なのは、いつ死ぬかじゃない。そこまで、どう生きるかだもの」
クラリスは、わざと明るい声を作って答え、足取りも軽く前へ進んだ。
「とにかく、まずは王子殿下のところへ行こう。何があったのか、聞いてみなくちゃ」
「……コオ」
「侍従たちは王子殿下のご意思だって言ってたけど、私はあの言葉……信じてない」
彼らが残した言葉は、ヴァレンタインが吐くようなものではなかった。
そして何より、あの侍従たちは、ヴァレンタインに心から仕える者たちではない。
クラリスはこれまで何度も彼に付き従い、別宮へ出入りしてきたから、彼の配下である侍従たちの顔はすべて覚えている。
水路沿いをさらに進むと、やがて城壁の一角近くへと辿り着いた。
――ヴァレンタインが身を寄せているのは、この先だった。
彼は、この場所があまりに人目につかず地味だと不満を漏らしていたが、クラリスは洗練された青い外観と、大きなガラス窓が印象的なこの単層の建物を、とても気に入っていた。
クラリスがその前へ辿り着いたとき――ちょうどその瞬間、長いあいだヴァレンタインに仕えてきた、年嵩の侍従と真正面から鉢合わせてしまった。
彼女を見つけるなり、男は目を丸くして駆け寄ってくる。
――いや、ほとんど突進だった。
クラリスがヴァレンタインを訪ねるたび、彼は大騒ぎをして追い返そうとした人物だ。
その記憶がよみがえり、クラリスは反射的に一歩、後ずさる。
「あ、あの……えっと、王子殿下がご心配で……」
おずおずと声をかけた、その直後。
男は平素どおりの勢いで、怒鳴り声を上げた。
「なぜ今になって来たんだ!」
「……え?」
――違う。いつもと、様子が違った。
普段なら、罪人であるクラリスを忌み嫌うような目で睨みつけるはずなのに。
今日の彼の視線は、どこか切迫していて――そして、焦っているようにも見えた。
――切迫している、そんな色を帯びていた。
「まったく……王子殿下が、お前にどれほどの恩を施してきたと思っている!それなのに、今さら顔を出すとは!」
「王子殿下に……何か、あったのですか?」
「何があった、だと!?ちっ……お前があの、疫病神みたいなグレジェカイアの残党だってことは承知しているが……」
男は絶望を刻んだ顔で額を押さえ、深く息を吐いた。
「とにかく……医師は、“大丈夫だ”と言ってはいたがな」
「お医者様が呼ばれるほど、具合が悪かったんですか!?」
「そうだ、この薄情者が……王子殿下は――」
侍従は怒鳴りかけたところで言葉を飲み込み、しばし逡巡した。
罪人であるクラリスに、王子殿下の病状を詳しく話してよいものか、迷っている様子だった。
「……どうか、教えてください」
「……王子殿下はな」
重々しく、言葉を選ぶようにして、彼は続けた。
「食事を……ほとんど、口にされていない」
「え……?きょ、今日は?今も……?」
侍従は、重々しく頷いた。
「今はそんなことを話している場合じゃない。さあ、こっちへ来い」
「……え?」
「まったく、ぐずぐずするな!」
侍従は焦った様子で別宮の中へと足を向け、クラリスも慌ててその背を追った。
彼は手近な使用人を二、三人呼びつけ、トレーに温かいスープと柔らかいパンを用意させた。
クラリスがその場で戸惑って立ち尽くしていると、侍従は苛立ったように彼女を振り返る。
「何をしている。王子殿下のもとへ、早く持っていかないか」
「えっ……わ、私がですか!?」
思わず声を上げるクラリス。
第三城壁の内側で、王族に仕える役目を担うことは、きわめて名誉なことだ。
まして罪人の身である彼女に許されるはずがない。
「そうだ。お前が持っていけば、少しは召し上がるだろう。王子殿下は……お前を――」
侍従は顔を深く歪めたまま、言葉を途中で切った。
――言葉を、飲み込んだ。
クラリスは彼の心情を理解した。
王族の侍従が、罪人と王子を「友」として認めたいはずがない。
「……入ってこい」
その促しに、クラリスはトレーを押した。
ほどなく辿り着いた、固く閉ざされた扉の前で、彼女は一瞬ためらい、そっとノックをする。
――返事はない。
後ろを振り返ると、ついてきた侍従はすでにドアノブに手をかけ、回していた。
許可もなく入れ、という意味だろうか。
それは礼を欠く行為のはずだが――
厳格なはずの侍従がこの判断を下した以上、悠長に作法を気にしている場合ではないのだろう。
クラリスは意を決して扉を開いた。