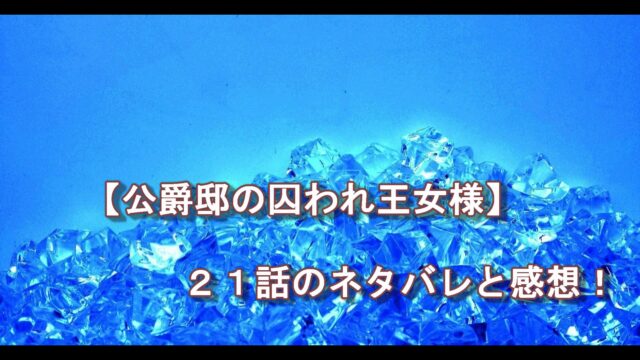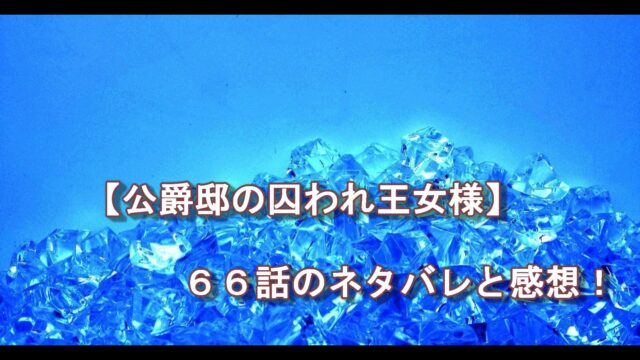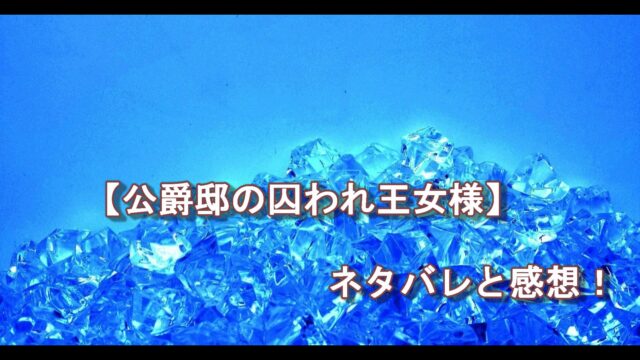こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

136話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 罪人の身②
高い位置に太陽がある時間帯だというのに、部屋の中は夜のように暗い。
人の気配は、ほとんど感じられなかった。
――もしかして、眠っているのだろうか。
クラリスは物音を立てないよう注意しながら、トレーを押して部屋の中へ足を踏み入れた。
長いあいだ動きのなかった空気が、淀んだまま彼女の頬を撫でる。
「……出ていけ」
闇の向こうから、ヴァレンタインの掠れた声が響いた。
クラリスは思わず足を止め、声のした方へと顔を向ける。
部屋の奥、最も隅に寄せ集められたような濃い闇が、そこにあった。
彼女は開け放たれていた扉を、そっと手で押し閉める。
トレーをその場に置いたまま、音を立てないように彼へ近づいていった。
「出ていけ!聞こえないのか、今すぐ……!」
叫び声には、懇願――いや、切迫した拒絶が色濃く滲んでいた。
まだ、誰にも会いたくないのだろう。
それでもクラリスは、その願いを叶えることができず、静かにその場に留まった。
――なぜだろう。彼が、泣いているような気がした。
訪ねてきた相手の足取りが、侍従のそれとは違うのだと、彼はようやく悟ったらしい。
蒼い瞳が、ゆっくりと彼女を捉える。
この濃密な闇の中でも、彼はクラリスを見分けた。
「……お前……」
いつもと同じ呼び方に、クラリスは胸を撫で下ろしながら、彼と同じく“いつもの答え”を返す。
できるだけ、距離を詰めたままで。
「はい、王子殿下」
距離が縮んだからか、それとも暗闇に目が慣れたからか。
そのときになって、ようやく彼の姿が輪郭を帯びる。
乱れた髪。
留めることすらされていない衣服。
そして――鮮紅の血が伝う手の甲。
まるで、掻きむしったような傷。
あれは、おそらく自分でつけたものだ。
あまりにも深い苦悩を、誰にも頼らず、ただ一人で飲み込もうとした――その痕跡だった。
クラリスは、荒れて傷だらけの彼の手を、このまま放っておくわけにはいかないと判断した。
「お薬を……取ってきますね」
このままでは、彼の手に消えない痕が残ってしまう。
自らを傷つけた証が長く残るのは、決して良いことではなかった。
クラリスがくるりと身を翻した、その瞬間。
熱を帯びた手が、彼女の足首を掴んだ。
「い、行かないで……!」
切迫し、追い詰められた声とともに。
「……お願いだ」
彼は、とうとうクラリスの足元に縋りついていた。
「王子殿下……」
一体、何があったというのだろう。
あれほど自信に満ちていたヴァレンタインが、ここまで自らを痛めつけるほどに。
彼の手のひらから流れていた赤い血は、いつしかクラリスの足首にも移っていた。
掴む力は、次第に熱を帯び、強く、深くなっていく。
まるで、彼女と一つになろうとするかのように。
「…………」
クラリスは、そっと身を低くした。
互いの顔が近づいた、そのときになってようやく、彼は足首を掴んでいた手をゆっくりと離す。
「行きません」
クラリスは真正面から彼を見つめ、はっきりと答えた。
「どこにも行きません。ここにいます」
同じ意味の言葉を繰り返すたび、ヴァレンタインの表情から、張りつめていたものが少しずつ剥がれていくのが分かった。
だからこそ、クラリスは彼の前に腰を下ろし、床の上で向かい合った。
しばらくの間、ただ互いの顔だけを見つめ合う。
やがて、わずかに落ち着きを取り戻したようなヴァレンタインが、重たげに口を開いた。
「……お前を」
掠れた声だった。
「考えていた」
「……私を、ですか?」
彼は力なく、こくりと頷いた。
「……地下牢に、行ってきたんだ」
「……あ……」
クラリスは、どこか痛みを含んだ笑みを浮かべた。
「……ごめんなさい」
自分の存在そのものが、彼に無意味な思考を強いてしまった――そんな気がしてならなかった。
「どうして、お前が……!」
ヴァレンタインは、荒々しく声を張り上げる。
彼が突然声を荒らげることには、もう随分慣れたつもりでいた。
それでも、今回は少しだけ、胸を突かれた。
「どうしてお前が謝るんだ!どうして……!」
吐き捨てるような口調とは裏腹に、彼の瞳からは堪えきれなかった涙が零れ落ちていた。
「お前が何をしたっていうんだ……?どんな罪を犯したっていう……!一体、なぜ……!」
「私は……反逆の血を引く者です、王子殿下」
それは、いつも用意してきた答え。
けれどクラリスは、それを声にすることができなかった。
口にすれば――きっと、彼をさらに深く傷つけてしまう気がしたから。
「……くそ……」
込み上げる嗚咽を堪えきれず、彼はそのままクラリスの膝に額を預け、声を殺して泣き始めた。
クラリスは戸惑いながらも、正直なところ、少しだけ……ありがたいとも感じていた。
けれど、そんなことを口にできるはずもなく、ただ黙ってヴァレンタインの広い背を撫で続ける。
「クラリス、僕は……」
彼は彼女の膝に顔を埋めたまま、ぎゅっと服の裾を掴んだ。
白い布地が血で赤く染まっていく。
それでもクラリスは、気にも留めなかった。
「……罪人たちに、剣を向けた」
「王子……殿下?」
彼は、耐え難いというように首を縦に振る。
「こ、殺戮を……生きている人間を、僕が……」
その瞬間、彼の全身が激しく震え出した。
「……あ……」
「……彼らと、目が合った。恐怖に満ちた視線を向けられて……そのとき、僕は……」
震える腕を伸ばし、彼は必死にクラリスの腰を抱き寄せた。
まるで、そこに縋りつかなければ生きていけないかのように。
「……お前のことを、考えた」
どんな“クラリス”を思い浮かべたのか――分かる気がした。
処刑の恐怖に怯える人々を前にして、やがて同じ運命を辿る、熱に侵された彼女の姿を重ねたのだろう。
「そうしたら……それなのに、僕は……」
「王子殿下……」
「……胸を裂かれるみたいで……それでも、止められなかった……ごめん……ごめん、クラリス……」
彼の腕に力がこもり、クラリスは息苦しさを覚えるほどだった。
「……あのときの感触が、まだ……手に残っている。熱くて……脈打って……ああ、くそ……」
絞り出すような声で、彼は吐き捨てる。
「お前を、あんな場所へ送るなんて……絶対に、許されるはずがない」
「…………」
「お前、怖がりだろう! こんなに小さくて、か弱いくせに……!」
彼はようやく、彼女を抱き締めていた腕を解き、顔を上げた。
涙と怒りに歪んだその顔が、すぐ目の前まで迫る。
クラリスは、せめて彼が少しでも笑ってくれればと願いながら、言葉を紡いだ。
「でも、王子殿下は……私のことを“強情だ”って言ってたじゃないですか」
それは、彼がふざけてからかうときに、いつも口にする言葉だった。
だからこそ、少しでも気持ちが和らげばと願ったのだ。
けれど――彼の表情は、まったく変わらなかった。
それどころか、かえって深く傷ついたようにも見えた。
「……きっと、方法がある」
「……え?」
「お前を殺すなんて、あってはならない。断じてだ。クラリス……私にとって、お前がどれほど――」
言いかけたところで、彼は何かに気づいたように、ふっと言葉を止めた。
「……?」
そして、どういうわけか――彼はようやく、いつもの不敵な笑みを浮かべた。
片方の口角だけを吊り上げた、どこか危うい笑い方だ。
「……本当に、どうかしてる」
そう呟きながら、彼はクラリスの髪の間で緩んでいたリボンを、指先でそっと引いた。
数本の髪が、そのまま彼の手に絡みつく。
前の祝祭で、彼が半ば強引に買わせたものだった。
「お前、本当に残酷だな」
それは、言葉だけ聞けば責める響きだった。
けれど――リボンに顔を寄せる彼の表情は、まるで別の感情を語っているように見えた。
彼という存在には、決して似つかわしくないほど、あまりにも穏やかで、優しい色を帯びて。
「……王子殿下と、一緒にいたじゃないか」
涙に濡れたままの蒼い瞳が、じっとクラリスを捉えていた。
「それで、そんなことしたわけ?はぁ……ほんとに」
彼はリボンの端を唇の近くへ引き寄せた。
なぜか――「……可愛すぎて困るな」とでも呟きそうな仕草だったが、クラリスは聞き間違いではないと確信していた。
可愛い、だなんて。
もう子どもでもないのに。
たぶん彼は、「生意気で困る」と言うつもりだったのだろう。
普段なら、いつもそういう言い方をするから。
「聞きました。王子殿下、今日は何も召し上がっていないって」
「うん、食欲がなくてさ」
「それじゃ、お身体に障ります」
「……無駄な心配だ」
彼はクラリスのリボンを、何度も名残惜しそうに指で弄んでから、ようやく手を離した。
それでも、もっと触れていたいとでも言うように、視線だけがしつこくそこに残る。
「私が王子殿下を心配するのは、当然です」
「……友だち、だからか?」
「……はい」
「……うん」
彼の唇が、またわずかに歪んだ。
笑いを堪えているようにも、あるいは必死に何かを飲み込もうとしているようにも見える。
「……まあ、悪くないな。友だち、か」
「ええ、そうです。友だちは、いいものですよ」
「……だな、確かに」
そう言って、彼はふっと全身の力を抜き、クラリスの肩に額を預けた。
「……寄りかかることも、できるし」
そして彼は、心を整えるように、ゆっくりと息を吐いた。
――こういうときは、背中でも叩いてあげた方がいいのだろうか。
クラリスは、両手の置き場が分からず、少しの間だけ戸惑って、上げたり下ろしたりを繰り返す。
「クラリス」
その名を呼ばれ、彼女ははっとして、両手を彼の背にそっと回した。
「……え?」
「さっき言ったこと、本気だ」
「…………」
「君を殺すなんて、あり得ない」
「……そんなこと、言わないでください」
クラリスは、怯えを押し隠すようにそう答えた。
少し前に会ったライサンダーの警告が、まだ脳裏に鮮明に残っていたからだ。
「冗談だろ。兄貴たちが勝手に決めたことだ」
「違います。私はどうせ……」
クラリスは落ち着いた声で、九歳のときの話を語った。
十六歳まで生かしてほしいと、必死に頭を下げて頼み込んだのは、自分自身だったこと。
「私は、本当なら十二歳で死ぬ運命だったんです」
「ふざけるな!」
彼は強い口調で言い切ると、クラリスの腰を両腕で引き寄せ、きつく抱きしめた。
「そんな未来、認めるわけがない」
いつの間にか、抱き締められている側はバレンタインではなく、クラリスになっていた。
「絶対に駄目だ。絶対に……」
「王子殿下、お願いです、もうやめてください!私が決めたことを、そんなふうに……!」
クラリスは身を捩り、彼の腕の中から抜け出そうとした。
「関係ない!」
だが彼は、さらに強くクラリスを抱き寄せた。
乱れた髪の隙間から、その手が深く潜り込む。
「君は君の好きにすればいい。死にたいなら、好きに死ね!」
彼は荒い息のまま、しわくちゃになった赤いリボンを見つけ、再びその手で握り締めた。
「……でもな」
「俺は俺の好きにする。君を、生かす」
そして彼は、再びクラリスを強く抱き締めた。
――いや、違う。
それはまるで、彼女の命そのものを、必死に腕の中に閉じ込めようとしているかのようだった。
「……あいつは知ってたのか?」
久しぶりに投げかけられたバレンタインの言葉に、クラリスは小さく肩を震わせた。
その反応だけで、彼は答えを察したようだ。
「どうして……言ってくれなかった?俺より先に“友達”になったのは、あいつだったのに」
「そ、それは……」
クラリスが言葉を探している間に、彼女を抱いていた腕が、ようやく少しだけ緩む。
深い闇の中で、彼は再びクラリスを意味深な視線で見つめた。
「機会がなかった、ってわけでもないだろ」
「……」
「君は、そんな大事なことを隠せる性格でもない」
「……い、いえ。あります、王子殿下」
「じゃあ、どうして言わなかった?」
――それは。
理由が分からないわけでは、なかった。
――そうだ。
ノアが語ってくれた「未来」の話が、クラリスは好きだった。
本当に、それだけ……。
「……ああ、もしかして、それか?」
彼女の答えを待たずに、バレンタインは言葉を重ねた。
「白いローブの魔法使い――あいつなら、本当に君を救える、ってやつ?」
なぜだろう。
そんなふうに考えたことは、一度もなかったはずなのに。
まるで、ずっと隠されていた真実を突きつけられたみたいに、心臓がどくりと大きく跳ねて、そして沈んだ。
それはずっと昔――ノアとセリデンで、星を眺めていた夏の夜のことだ。
『私があの子に言おうとしていたのはね……つまり』
ゴーレムマスターだという事実が明るみに出たら、どうなるか――そんな話をしていたとき。
怯え切っていたクラリスに、ノアはこう言ってくれた。
『……一緒に逃げよう、って意味だよ』
『大陸は広いし、この世界には、魔法師団だけがすべてじゃない』
その言葉は、あの夜の星空みたいに、優しくて、遠かった。
「セファス王家の権力が及ばない場所だって、探せばきっとある。それに――僕は、空間と時間の制約すら超えた魔法使いだから」
そう言って、彼はクラリスが決して怖がらないように、軽く頭をとんとんと叩きながら、こんな約束をしてくれた。
『だからね。まずは、君の望むように生きなさい。万が一のときは――僕が、どこへだって連れていく』
あのときクラリスは、彼の言う「万が一」に、処刑という結末が含まれていないと、どこか無邪気に信じていた。
――でも、ノアは……。
なぜだか、彼は本当に、クラリスを生かすために動くような気がした。
空間と時間の制約を超えた魔法使い。
そんな彼なら、その気になれば、目的の一つや二つ、容易く叶えられるのだろう。
――もしかしたら、バレンタインの言う通りなのかもしれない。
ノアこそが、最も簡単にクラリスを救える存在。
それでも。
『それは……ダメ』
クラリスは、心の奥で、そう呟いた。
彼女は、少し前に対面したセファスの王――ライサンダーの言葉を思い出していた。
『お前を生かす道は、処刑以外にないだろう。お前一人だけじゃない。家族も、部下も……すべて含めてだ』
『一人ずつ、丁寧にだ。その首が落ちていくのを、代わりに見届けることになる』
それは、脅しですらなかった。
ただの“予告”だった。
彼は実際に、ひとつの国家の公爵ですら、「死ね」の一言で瓦解させられるほどの権力を持っている。
――クラリス一人の命と、セリデンの人々の命。
天秤にかけるまでもなく、その重さは明白だった。
クラリスは、そっとバレンタインの肩を押し、わずかに距離を取った。
彼が最後まで離さなかった赤いリボンが、二人の間で細く引き延ばされ、やがて――ぱらりと、バレンタインの手の上に落ちる。
『……ノアに言えなかったのは、別の理由があって』
クラリスは、そう心の中で続けた。
ノアなら、きっと助けてくれた。
誰かを犠牲にすることなく、すべてを覆す方法を探し続けただろう。
――だからこそ。
彼にだけは、言えなかった。
彼に“選ばせる”ことだけは、どうしても、できなかったから。
「……違うんです。ノアは、私に“未来”を語ってくれた、ただ一人の人だから」
「……は?」
「自分でも想像できなかった、私が十八になるまでの人生を、どう生きるかを……ノアは、本当に何気ない顔で話してくれたんです」
クラリスは、努めて軽やかに見せる微笑みを浮かべた。――本当に、なんでもないことのように。
「それが、嬉しかったんです。忘れたくないと思えるくらいに」
バレンタインは、言葉に詰まったように彼女を見つめ、やがて、深く息を吐いた。
「……まったく。君らしい、どうしようもない理由だな」
幸い、それ以上追及してくる様子はなかった。
「だから……ノアには、言わないでください」
「君は……あいつのこと、考えないのか?」
「……え?」
「いずれ、あいつが真実を知ったとき、どう思うか――そこまで考えての判断なのか、って聞いてる」
「…………」
クラリスは、答えられなかった。
「……考えてないだろ。そうだよな、君が死ねばそれで終わりだと思ってた。でも、あいつはどうなる?君に“十八、二十”なんて先の話をしていたあいつが、それをどうやって受け止めるか――考えたことはあるか?」
「わ、私は……」
クラリスは、ようやく口から零れた言葉を、最後まで紡ぐことができなかった。
――バレンタインの言う通りだった。
今のノアがくれる喜びが、ただ嬉しくて。
自分が消えたあとのことなど、考えたことはなかった。
「あ……」
「君は自己中心的だ。分かってるか?あいつに、どれだけ残酷なことをしているのか――分かってるのか!」
荒い声で吐き捨てると、バレンタインは、まるで自分のほうが傷ついたかのように、震える瞳を伏せ、勢いよく顔を背けた。
「くそ……」
「……ごめんなさい」
クラリスは、自分でも理由の分からない謝罪を、ただ口にした。
それは、彼に向けて差し出された。
なぜか――そうしなければならない気がしたから。
「……」
彼は答えなかった。
ただ、もう一度だけ、こくりと小さく首を縦に振る。
「……それから、差し出がましいのは承知していますが、王子殿下」
クラリスは、彼の正面へと歩み出た。
「お願いします。私の“最後”は……私自身の手で、決めさせてください」
赤いリボンを握りしめた彼の手が、細かく震えていた。
――決して、黙って見過ごすつもりはない。
その意思が、はっきりと伝わってくる。
クラリスは、彼を説得できる言葉を探し、口を開いた。
「私にとっては……とても大切なことなんです」
今、ようやく動き出したこの話は、もしかすると――バレンタインのためだけでなく、クラリス自身のために語られるものなのかもしれなかった。
「他の人には分からなくても……王子殿下なら、きっと分かってくださいますよね」
「俺が……どうしろって言うんだ……!」
彼はようやく顔を上げた。
怒りに満ちた瞳――だが、その奥には、確かに涙が滲んでいた。
「王子殿下」
クラリスは、今も震えが止まらない彼の手の甲に、そっと手を重ねた。
「私は……グレジェカイアの王女です」
「……」
「その国を愛していたかと問われれば……正直、そうとは言えません」
「……それなのに、なぜだ」
「それでも――誰かにとっては大切な故郷で、思い出が詰まった場所なんです。そして私は、その国の“最後の王族”ですから」
“最後の王族”――その言葉に込められた重みを、他の誰が分からなくとも、バレンタインだけは理解できるはずだ。
予感は外れず、彼の顔が強張る。
「私の死は、私一人のものではありません。それは……レジェカイアの定めです」
静かな声だった。
けれど、その一言は、重く、確かだった。
「それは――私が“最初で最後”に果たす、王女としての務め。そして、私にだけ許された……“私自身の選択”なんです」
クラリスは、彼の手を握る指に、わずかに力を込めた。
「ですから、バレンタイン王子殿下」
切実に、縋るように彼を見上げて。
「どうか……私が王女として、最後まで役目を果たせるようにしてください」
「……お前、本当に」
彼は歯を食いしばった。
「身勝手だな」
クラリスは何も言い返さなかった。
その言葉が、あまりにも正しかったから。
「俺が、なんでお前みたいな――……ああ、くそっ!」
荒々しく叫び、彼は自分の髪を掻き乱した。
「それで……リボンは返してもらいますね」
クラリスが、彼の手に握られた赤いリボンをそっと引く。
だが、彼はすぐにそれを強く引き戻した。
「駄目だ。……これは、渡さない」
「……やめてください。そのリボン……私にとって、とても大切なものなんです」
「…………」
一瞬、バレンタインの手から力が抜けた。
その隙を逃さず、クラリスは素早くリボンを取り上げると、慣れた手つきで自分の髪を結い上げた。
揺れる髪の間で、赤い色彩が静かに踊る。
バレンタインは、その強く鮮やかな色を見つめてから、再びクラリスの顔を見た。
彼女は、無理にでも笑顔を作った。
だが、彼の表情は依然として硬いままだった。
クラリスは、バレンタインが食事を終えるのを、この目で確かめてから、ようやく城を後にした。
帰り道、彼女は幼い頃から胸に抱いてきた決意を、ひとつひとつ数え直す。
――立派な、十八歳になって。
――そして、死ぬ。
その覚悟だけは、最初から最後まで、少しも揺らいでいなかった。
『私は、決して運命を変えない』
その事実に、惜しさを覚える必要はなかった。
そもそも、十八で死ぬと決めた“約束”がなければ、クラリスはあの日、処刑台で命を落としていたはずなのだから。
もしそうなっていたら――公爵夫妻とここまで親しく、穏やかな時間を過ごす幸福も知らなかった。
屋敷の外壁や内壁を指さしながら、セリデンの楽しい話に耳を傾けることもなかっただろう。
自分がもっと辛い状況にあるときでさえ、自分を気にかけ、心配してくれたバレンタイン王子と、“友人”になることもなかった。
そして、何より――
「ノア……」
いつの間にか、かけがえのない存在になってしまったその名を、クラリスはそっと唇に乗せた。
ただ呼ぶだけで、胸の奥が温かく脈打つ。
心臓が、幸福を思い出したかのように、静かに高鳴った。
――あのとき、もし死んでいたら……。
その先の言葉は、胸の内にしまい込んだまま、彼女は歩き続けた。
そんな感情が、この世に存在することすら、彼女は知らなかっただろう。
クラリスはそっと、両手を胸の鼓動の近くに重ねた。
確かにそこにある、温かく、静かな脈動。
「本当に……よかった」
小さく零れた声は、誰に聞かせるでもない独り言だった。
クラリスは静かに、自分が守りたいこの世界に言葉を捧げる。
「私、こんなにも幸せなんだもの。しかも……この気持ちが、どこから生まれたのかも分かっている。本当に、感謝しなきゃいけない」
――けれど、勘違いしてはいけない。
これ以上を望む欲は、この美しい世界に“歪み”を呼び込む。
それだけは、決してしてはならなかった。
「だから私は……与えられた時間の中で、精一杯生きる。出会った人を、景色を、出来る限り愛するの。たくさん、たくさん」
一陣の風が吹き抜け、クラリスの髪を優しく揺らした。
彼女はそれを手で押さえ、前を向いて、もう一歩踏み出す。