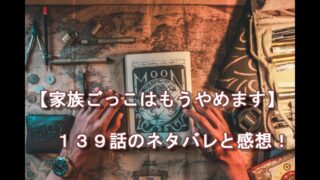こんにちは、ちゃむです。
「継母だけど娘が可愛すぎる」を紹介させていただきます。
今回は335話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

335話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 魔女狩り③
その時、人々が彼の周りに集まってきた。
人間と妖精たちだった。
ベリテが急いで駆け寄り、倒れていたブランシュを抱き起こした。
「ブランシュ、大丈夫?」
「ベリテ・・・どうしてここに・・・」
「連絡が取れなくて来たの。何かが起きている気がして。」
ギデオンは部屋の奥に隠れたベリテの居場所を探し出せなかった。
それが不幸中の幸いだ。
危険な状況にもかかわらず、ブランシュが目の前にいないことに、ベリテは何かがおかしいと直感していた。
セイブリアンが交渉を終え、宮殿に戻る途中で感じた感覚も同じ。
二人はアビゲイルとブランシュの話を聞き、宮殿とその一連の出来事を慎重に調査した。
セイブリアンはギデオンを引きずり出して床に叩きつけた。
そして、迷うことなく彼を突き刺そうとする。
「お父様、駄目です!」
ベリテの助けを受けて立ち上がったブランシュが慌てて叫んだ。
セイブリアンは静かに娘の方を見た。
冷ややかな沈黙が訪れる。
王と姫が向き合う中、血を流しながら震えるギデオンの瞳に一筋の希望がよぎった。
もしかしたら生き延びられるかもしれないという希望が。
「ブランシュ、この者は死なねばならない。」
セイブリアンは静かに言った。
ブランシュの善良さを理解していたが、この者を見逃すことはできなかった。
ただの善意だけでは王としてやっていけない。
悪に対抗するには厳格な判断が必要だった。
セイブリアンは娘が混乱しているだけだと思っていたが、ブランシュの視線には迷いがなかった。
彼女は罪悪感もなくはっきりと言った。
「はい。でもあの人は大妃(たいひ)と関わる事件の証人として必要です。生かして証言を聞き出さなければなりません。罰するのはその後でもできます。」
公主(こうしゅ)の青い瞳はセイブリアンとそっくりだった。
厳格で剣のような冷たい目。
それは単なる同情心や優しさではなく、セイブリアンの血を引く者ならではの冷静さだった。
刀を収めたセイブリアンの目に少しの落ち着きが戻ったものの、ギデオンを見下ろすその目には依然として軽蔑が浮かんでいた。
「ギデオンを連れて行け。絶対に殺さず、傷を治療しておけ。」
その命令に兵士たちはギデオンを引きずって行き、セイブリアンはアビゲイルのもとへ急いで向かう。
彼女は侍女たちの腕の中で横たわっていた。
魔力をほとんど使い果たし、黒く変色していた血管と瞳孔は元の状態に戻りつつあった。
ベリテが治癒の魔法をかけ、出血も止まっていた。
セイブリアンはこれ以上早く来ることができなかったことを悔やむように見えた。
自分を抑えながら、彼はアビゲイルを慎重に抱きしめる。
傷だらけのアビゲイルの姿を見て、セイブリアンの中で怒りと悲しみが湧き上がった。
彼は罪人のようにひたすら謝罪した。
「愛しい人、私があまりにも遅く来てしまいました。ごめんなさい。もっと早く来るべきだったのに・・・。」
アビゲイルは手を伸ばして彼の頬を優しく撫でた。
彼女の口元には薄い微笑みが浮かんでいた。
彼が助けに来てくれたことだけで、彼女の心は十分に満たされ、感謝の気持ちでいっぱいだったから。
彼を抱きしめてその唇に触れたいという気持ちがあふれたが、力が残っていなかった。
その気持ちを察したセイブリアンは、静かにアビゲイルの願いに応え、彼女の額にそっと口づけをする。
彼女は安らかな表情で目を閉じ、まもなく小さな寝息を立て始めた。
眠りについたようだ。
セイブリアンは微笑みを浮かべながらも、その笑顔の中には強い感情がこもっていた。
彼はアビゲイルの頬に何度も触れ、彼女の状態を確かめた。
そして、彼女を看病するため、侍女たちに引き渡した。
周囲の者たちに目を向けた。
「すぐに王妃と王女を宮殿に連れて行き、治療を施してくれ。私はここに残って状況を整理します。」
セイブリアンが宮殿に到着した時、王妃は「王が魔女に惑わされており、正しい判断ができない」と主張していた。
大妃の護衛兵はセイブリアンの直属の兵力より多く、さらに大半の兵力が外地に派遣されていたため、状況は複雑だ。
しかし、ベリテが率いてきた妖精の兵士たちがいる。
妖精たちの助けを借りて大妃の護衛兵は制圧されたが、まだ森には残党が潜んでいた。
セイブリアンは心の中でアビゲイルのそばにいたいと思いながらも、慎重にアビゲイルをベリテに託し、言葉を告げた。
「ブランシュとアビゲイルを頼む・・・お願いだ。」
その言葉には深い信頼が込められていた。
自分の命よりも大切な二人を託すことができる相手として。
頼れるのはベリテだけだ。
ベリテは驚きに目を見開いたが、すぐに口を結び、うなずきながら覚悟を決めた様子で彼女を抱きしめる。
まるで、自分の命に代えてでも二人を守るという決意が伝わるようだった。
セイブリアンは森に残り、ブランシュとアビゲイルは馬車で宮殿へ運ばれた。
周囲の医者や従者たちは混乱したアビゲイルの姿に呆然としていた。
ブランシュはその隣にぴったりと寄り添っていた。
ブランシュの顔や体にも大きな小さな傷跡がいくつも残っていた。
従者の一人が彼女の目を見て言った。
「王女様。王女様も治療を受けてお休みください。」
「お母様のそばにいます。」
ブランシュは頑として動かず、母の傍を離れることを拒んでいた。
彼女自身が痛みに耐えながらも、アビゲイルの傷を心配していたのだ。
無力感を抱いた医者たちは、どうすればいいのか途方に暮れる。
その隣に立っていたベリテもまた、ブランシュを静かに見守っていた。
ベリテが慎重に口を開いた。
「ブランシュ、お義母様は君が治療を受けないことをもっと心配するよ。」
「・・・」
「目を覚ました時、君が傷だらけのまま側にいたら、きっと辛く感じるはずだ。だから治療を受けて、戻ってきて。いい?」
ベリテの銀色の瞳には心配が浮かんでいた。
ブランシュはその目を見て、一瞬ぼんやりとした後、席を立ち上がる。
「分かった。すぐに治療を受けて、お母様の元に戻る。」
「そう、それでいい。さあ行こう。」
従者のベリテはブランシュと一緒に部屋を出た。
残された医師たちは深い息を吐きながらアビゲイルの容体を調べ始めた。
幸いにも致命的な傷はなかった。
大量の出血で疲労しているが、無理をして魔法を使った影響が見られる程度だ。
十分に休息を取れば、問題なく回復できる見込みだった。
その時、誰かが慌ててドアを開けて入ってきた。
「王妃は大丈夫か?」
セイブリアンが中に入るなり尋ねた。
足元に注意深く視線を落としながら、医師たちは慌てて礼をした。
「はい。出血は多かったですが、大きな怪我はありません。しばらく安静にしていただければ回復するでしょう。」
その言葉にセイブリアンはわずかに安心した様子を見せた。
そしてゆっくりとアビゲイルの枕元に近づき、優しい眼差しで彼女を見つめた。
「・・・なら、しばらく見守ることにする。アビゲイルのそばは私が守る。」
彼の声には、安心と共に圧倒的な威厳が含まれていた。
王の意志を否定する者はいない。
従者たちは静かに息を殺し、死角のないよう部屋を退出した。
アビゲイルの容体は安定しているものの、何が起こるか分からないという不安から、周囲はピリピリした空気が漂っていた。
彼女を守るため、周囲の人々は懸命に緊張感を持続していたのだ。
「王妃が大きな怪我を負わなかったのは幸いでした。」
「そういうことだ。もし帰還させられていたら・・・」
想像もしたくなかった。
どんなにセイブリアンが英雄であったとしても、従者たちは責任を逃れることはできないだろう。
「とにかく、これは一体何なのだ?王妃様が魔女だという話だし、大妃が私兵を連れてきたというのに。」
「まだ大妃の私兵が残っているかもしれないらしい。それが本当なら、反乱・・・」
その時、従者が振り返りながらも言葉を飲み込むようにして黙った。
隣にいた人物が不審そうに尋ねた。
「どうした?」
「王宮からは残りの私兵たちを制圧するよう命じられたはずなのに、どうしてこんなに早く戻って来られたのです?」
皆が口をつぐむと、奇妙な不安がその場を包んだ。
何かが明らかにおかしかった。
宮中は不気味なほど静まり返っていた。
王が戻ったというのに?
彼らは互いに視線を交わし、急いで王妃の寝室へと向かった。
無礼を承知しながらも、慎重に扉をノックした。
「陛下、中に入ってもよろしいでしょうか?王妃様をもう少し治療する必要があると思いまして・・・。」
だが、返事は返ってこなかった。
しばらく待った後、慎重に扉を開けると冷たい空気が漂ってきた。
開いた窓の隙間から風が吹き込んでいた。
つい先ほどまではしっかり閉じられていた窓だった。
寝台に横たわっていたはずのアビゲイル王妃の姿はどこにもなかった。
セイブリアンもまた、その痕跡を見つけることができなかった。
カーテンがそよぐ音だけがかすかに響き、遠くで聞こえるような風の音とともに、不吉な静けさをもたらしていた。