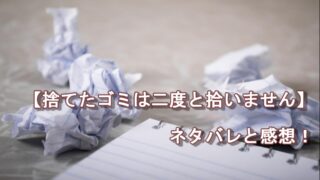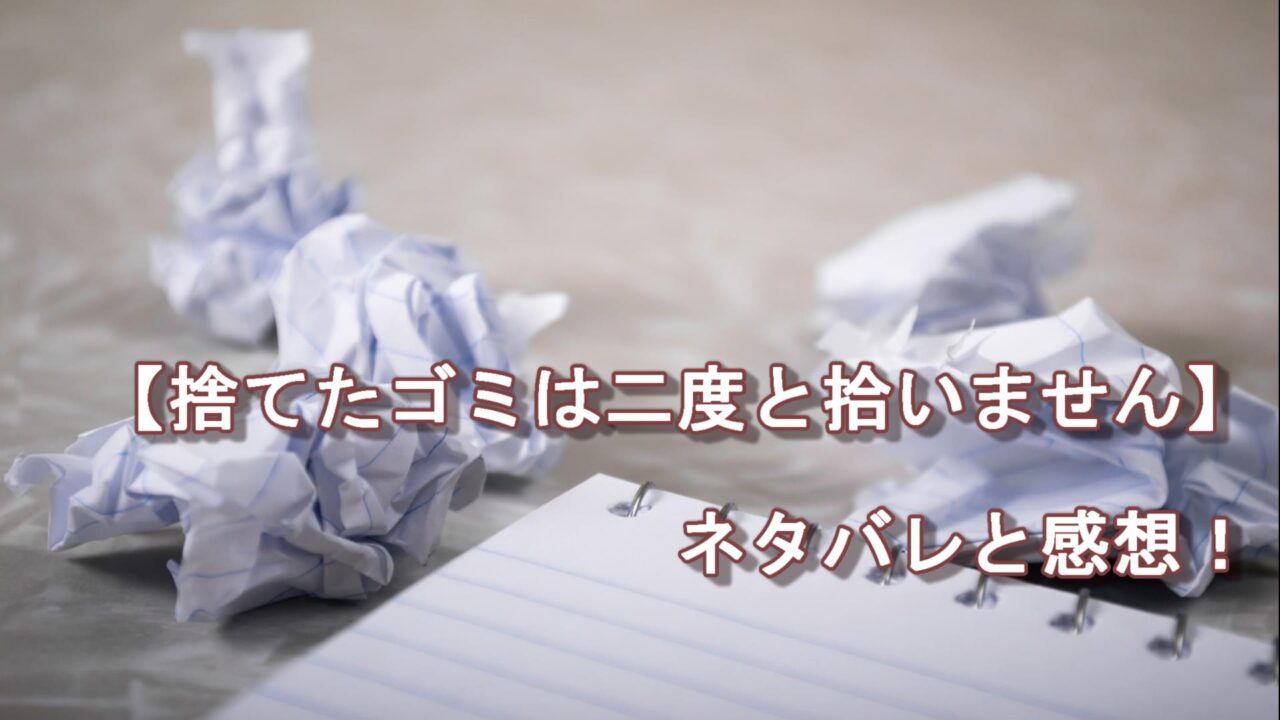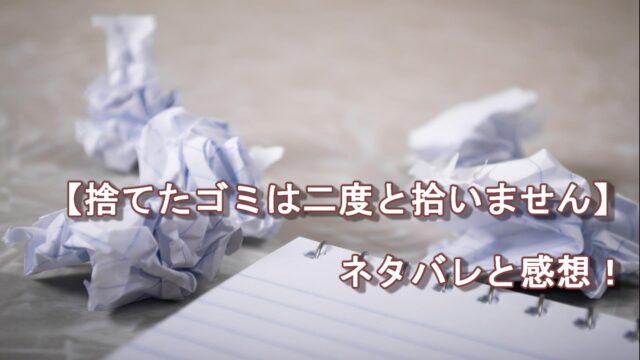こんにちは、ちゃむです。
「捨てたゴミは二度と拾いません」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

96話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 自覚②
約束通り、昼食を取った後、乗馬練習場へ向かった。
「わあ、天気が本当にいいですね。」
そして、デロンド男爵まで。
カリアンは思わず顔をしかめ、デロンド男爵に尋ねた。
「お前、なぜここにいる?」
デロンド男爵はニヤリと笑いながらカリアンを見つめた。
「なぜここにいるかって?僕も乗馬しに来たんですよ。」
「忙しくなかったか?」
「大丈夫です。忙しい仕事は終わりましたから。」
「……。」
カリアンは口をしっかり閉じていたが、再び開いたその時、馬厩の管理者がイレーナとネロを連れてきた。
「イレーナ。」
私は明るく微笑みながらイレーナに近づいた。
久しぶりに会うので、私のことを忘れてしまったのではないかと心配していたが、幸いなことにイレーナは何の迷いもなく私の手を受け入れてくれた。
「わぁ、アステル男爵。イレーナに乗るのですか?」
「ええ。デロント男爵もイレーナを知っていますか?」
「もちろんです。イレーナは陛下が過去の戦争に参加した際、記念品として連れてきた名馬なんです。」
つまり、それは名馬の中でも特に優れた馬という意味だ。
そんな馬を私が持つなんて、荷が重すぎると感じた。
「やはり、私はイレーナを……。」
「イレーナはすでにお前を主人だと思っている。」
私が何か言おうとするのを察したのか、カリアンはネロにすっと乗りながら言った。
「だから、お前が必ず連れて行かなければならない。さもなければ、イレーナは捨てられたと思って傷つくだろう。」
そんなことはできない。
私は戸惑いながらイレーナを見つめた。
彼の目が純粋無垢に輝いているのは、まるでカリアンの言葉が事実であると認めているかのようだ。
「では、乗馬してみようか。」
「陛下、私の馬は?」
デロント男爵の問いに、カリアンはくすっと笑った。
「それをなぜ私に聞くんだ?ベル、君が自分の馬のことを把握して連れてこなければならないだろう。」
「私の馬は宮殿には連れて入れないじゃないですか!」
「だが、皇帝の許可を受けた馬や馬車だけは宮殿に入ることができる。」
「許可をくださるんですか!」
「嫌だ。」
「じゃあ、陛下のお言葉を借りてください!」
「それはもっと嫌だ!」
「本当に、困った従者ですね!」
「ふっ。」
口げんかする様子が可笑しくて、思わず私も大きく笑ってしまった。
すると、周囲の視線が私に集中した。
……あれ、私の笑い声が大きすぎたかな?
私は少し気まずくなり、ぎこちなく笑いながら手で口を覆った。
デロント男爵とカリアンは互いに視線を交わした後、さっと視線をそらした。
「陛下が馬を貸してくださらないと言うなら仕方がありませんね。アステル男爵、一緒に乗りましょう。」
「え?」
「誰が勝手にイレーナに乗っていいと言った?」
カリアンが険しい表情で言うと、デロント男爵は気まずそうに笑った。
「それはアステル男爵の自由でしょう。イレーナの持ち主はアステル男爵なのですから。」
「なぜイレーナの主がレイラだと言うんだ?」
「それは陛下がくださったからですよ?数分前にそうおっしゃっていましたよね。まさかお忘れになりましたか?」
それは違う、と言わんばかりにカリアンは口を閉ざした。
険しい表情のままだったが、何も言わなかった。
そんな様子を見て、デロント男爵が私に尋ねた。
「アステル男爵、一緒に乗ってもいいですか?ちょうど侯爵に乗馬を教わるのにいい機会だと思うのですが。」
「駄目だ」
「そんなこと言うなら、馬を貸してくれませんか?」
カリアンは少し考えた後、馬を貸すことにした。
「そんなに馬に乗りたいなら、貸してやる。」
ネロから降りたカリアンは、ネロの手綱をデロント男爵の手に渡した。
「ネロに乗れ。」
デロント男爵の目が大きく見開かれた。
口もぽかんと開いてしまった。
「え、僕にネロに乗れと?あの恐ろしい馬に?」
「ブルルルッ。」
まるでデロント男爵の言葉を理解したかのように、ネロが鼻を鳴らして暴れる。
「ネロじゃなかったんだな。」
「違いますよ! そっくりじゃないですか!」
「もういい。」
カリアンは冷たく無視しながら私の肩をつかんだ。
「俺はレイラに乗馬を教えるつもりだ。その間、お前はネロと仲良くしておけ。」
・
・
・
「うわっ、ネロ! ごめん!」
思いがけずネロを任されることになったベルンは、慌てふためいて飛び跳ねた。
いや、正確にはネロに引きずられていたのだった。
ネロはベルンが気に入らないのか、まるで暴れ馬のように走り回った。
その間、レイラとカリアンの方へは近づこうとしなかった。
レイラが乗馬の練習をしていても、彼女が近づくとそちらに行かず、すぐに別の方向へ向かうほどだった。
やはりネロは賢い。
カリアンはネロを眺めながら薄く笑い、ふとレイラに視線を移した。
レイラの乗馬の腕前はまだ未熟ではあったが、以前よりはだいぶ上達している。
一人で何とか馬を操れるほどにはなった。
実力が上がったのなら喜ぶべきなのに、なぜか寂しさを感じるのはなぜだろう。
カリアンは、より一層レイラに視線を向けた。
「馬の乗り方を教えてあげられなくなったらどうしよう? そばにいて、優しくて温かい体温を感じられなくなったら?」
「アステル卿、お上手ですね。」
結局、厩舎の管理人にネロの手綱を預けたベルンは、馬のたてがみに流れる冷や汗を拭いながらカリアンの隣へとやってきた。
「この程度の実力では、今年の新年祭で行進に参加するのは無理そうですね。」
「そうだな。」
カリアンが淡々と答えると、ベルンは手綱をくるくると巻きながら彼に尋ねた。
「表情があまり良くないようですが、何かあったのですか?」
「確かに。」
確かにって何だ。表情があまり良くないけど。
「またアステル男爵が余計なことを言ったんですか?」
以前、カリアンが言った言葉を思い出したベルンが何気なく口にすると、カリアンの眉がわずかに上がった。
「レイラはそんなこと言わない。」
「言ったって聞きましたけど。」
「いつ。」
「前にそう言ってましたよ。」
「覚えてない。」
覚えてないだなんて、嘘だ。
表情を見れば全部覚えてるのがわかるのに。
「それでは、僕が言ったことを何も覚えていないんですか?」
「何の話?」
「僕、アステル卿に興味があるって言いましたよね。」
カリアンは、驚いて大きな音を立てながら体を回し、ベルンを睨みつけた。
視線は少し冷たかったが、これまで何度も同じ視線を浴びてきたベルンにとっては、何でもないことだった。
「これは忘れていないようですね。」
「それ、本気なのか?」
「本気だから、何度も言ってるんですよ。僕、本当にアステル卿のことが好きなんです。」
ベルンは、迷いのない真剣な表情でそう言った。
「ですから、男爵に気があるわけじゃないなら、邪魔しないで……。」
「ある。」
カリアンはベルンの言葉を遮り、再びレイラを見つめた。
「レイラに気があるから、お前は引っ込め。」
「今、何と……?」
ネロの手綱を渡されたときよりも、はるかに驚いたベルンの目が大きく見開かれた。
ベルンは自分の耳を疑いながら、カリアンにもう一度尋ねた。
「い、今、私の聞き間違いですよね? 陛下がアステル男爵に、き、気があると?」
カリアンは驚いたのか、なかなか言葉が出ず、声が震えた。
「答えてください、陛下。本当にアステル卿に気持ちが……」
「ああ、ある。」
「で、でも、それは単に臣下としての気持ちなのでは……?」
「レイラをひとりの女性として好きだ。これでいいか?」
ついにカリアンの口から衝撃的な言葉が投げかけられた。
まるで後頭部を殴られたような衝撃を受けたベルンは、頭を抱えて震えた。
「デロント卿?」
ちょうどその場にやってきたレイラは、ベルンが頭を抱えているのを見て声をかけた。
「大丈夫ですか?」
「大丈夫だ。」
返事をしたのはカリアンだった。
「ただ、愚かにも足をもつれさせただけだ。」
その言葉とともに、鋭い視線が向けられた。
“弱々しいふりをせず、さっさと立ち上がれ” という視線だ。
別に弱々しく振る舞ったわけじゃないのに……。
ベルンは悔しかったが、カリアンの視線があまりにも鋭く、何も言えなかった。
「私は大丈夫です。」
そして、カリアンの望み通り、まっすぐ立ち上がった。
「大丈夫」という言葉とは裏腹に、ベルンの顔色はあまり良くなかった。
レイラは最終的に馬を降り、ベルンのもとへと歩み寄った。
「本当に大丈夫なんですか?」
「はい、大丈夫です。」
「でも顔色が良くないですよ。熱があるんじゃないですか?」
熱を確かめるために、レイラが手を額に近づけた。
しかし、その前にカリアンがレイラの手を止めた。
「ベルン、体調が悪いなら侍医に診てもらえ。」
今回もカリアンは目で語っていた。
「すぐに消えろ」と。
ほんの少し前までは、自分の気持ちを否定し、「そんなはずはない」と断言していたはずなのに、まるで手のひらを返したように態度が変わっていることに戸惑いを隠せず、ベルンは内心苦笑した。
気持ちをぶつけるように、今考えていることを全部吐き出したかったが、そうすることはできなかった。
「はい、宮廷に報告しておきます。」
相手は皇帝であり、自分は皇帝の補佐官なのだから。
ああ、本当に面倒な身分制度だ。
もともと分かっていたことではあったが、改めて苛立ちを感じた。
ベルンは内心で悪態をつきながら、乗馬練習場を後にする。
ベルンがカリアンにこぼした言葉は、すべて真実だった。
レイラに気持ちがあることも、カリアンのせいでその気持ちを隠していたことも、もしカリアンがレイラに気持ちがないなら、自分が代わりにそばにいるつもりだったことも、すべて本気だった。
だからこそ、カリアンがレイラに想いを寄せていると知った今、もう自分の気持ちを押し通そうとはせず、陰から見守ろうと決心したのだ。
「これからは、レイラに必要以上に近づくな。」
……こんなふうに何度も抑えつけられたら、苦しくなってしまうじゃないか。
「必要以上に、どの程度ですか?」
カリアンはしばらく考えた後、自分の机を指さした。
「ここから。」
そして、ゆっくり歩いて一人用ソファの前で立ち止まった。
「ここまで。」
ベルンは呆然とした表情でカリアンを見つめた。
「それ以上近づくなということですか?」
「うん。」
「アステル男爵と私の机の距離の方がこれより短いんですけど?まさか私に机に座るなと言ってるんですか?」
「そうなるのか。」
まるで知らなかったかのように、カリアンはしばし考えたあと、本を机に置いた。
「では、今後ベルンは外宮での仕事に専念することになるな。」
もちろん、それは何の意味もない無意味な提案だった。
「ただ、執務室を広げていただけませんか?」
「それもいいな。」
カリアンはすぐに鐘を鳴らし、ラヘルを呼んだ。
「補佐官の執務室を拡張する。工事の準備をするように。」
「本当にそうなさるのですか?」
「望んでいたんだろ?」
「ただの冗談だったんですけど?」
「俺には本気に聞こえた。」
お前がそう聞きたいから、そう聞こえただけじゃないか!
ベルンは心の中で無言の叫びをあげた。
しかし、カリアンはそんなことにはお構いなしに、騎士団と補佐官執務室の拡張工事計画を立てていた。
皇帝の執務室よりも広くするという話を聞いたラヘルとベルンは、目を丸くするしかなかった。
「私はもう長く生きられないかもしれない。」
かろうじてカリアンを引き止めることに成功したベルンは、ほぼ脱力した状態でソファに座り込んだ。
一方、書棚の前に立つカリアンは、無心に本をめくっていた。
「奴隷制度の廃止はどのように進んでいる?」
保育園の事業を進めていたカリアンは、ベルンに奴隷制度を廃止する方法を調査するよう指示していた。
「今すぐ廃止するのは無理です。帝国に奴隷制度が深く根付いていることに加え、奴隷制度は慣習ではなく法律で定められているものですから。」
ベルンは疲れた表情を浮かべながらも、カリアンの質問に誠実に答えた。
「廃止するには貴族会議を開き、過半数の許可を得る必要があります。」
「貴族の過半数が許可する可能性は?」
「ほぼゼロに近いです。奴隷制度によって最も恩恵を受けているのが貴族たちですから。」
特に高位貴族たちは、多くの利益を得ていた。
「では、せめて子供たちだけでも奴隷にならないようにする方法はないのか?」
「難しいでしょう。子が親の身分を継承することは法律で定められていますから。」
「そうか。」
だから、無能な貴族があまりにも多いのか……。
カリアンは、ため息をつくように静かに息を吐いた。
「全部きれいに片付けられたらいいのに。」
「今は他にやることが多いから、後にしましょう。」
ベルンは優しく微笑みながら、机の上に山積みになった書類を整えた。
それらの書類を見つめながら、カリアンは独り言のように呟いた。
「皇帝も二人いればいいのに。」
「帝国の太陽が二つあるわけにはいきません。」
ベルンは簡潔に答えながら立ち上がった。
「そんなことを考えるよりも、補佐官をもう一人増やしませんか?それに、執務室を広げるなら、あと一人増やすのもいいですね!」
「うん。」
カリアンの反応があまりにも冷たかったので、ベルンは直感的に危機感を覚えた。
「そうすれば、アステル男爵も楽になるでしょう。」
カリアンの表情が一瞬で変わった。
「まともな人間を選んでリストを作ってこい。」
本当に、この考えまでは及ばなかったのに、こんなにも計算高くて抜け目ないとは。
「はい、承知しました。」
やはり、この世で最も偉大なものは愛なのかもしれない。