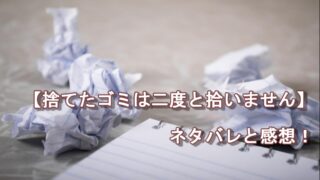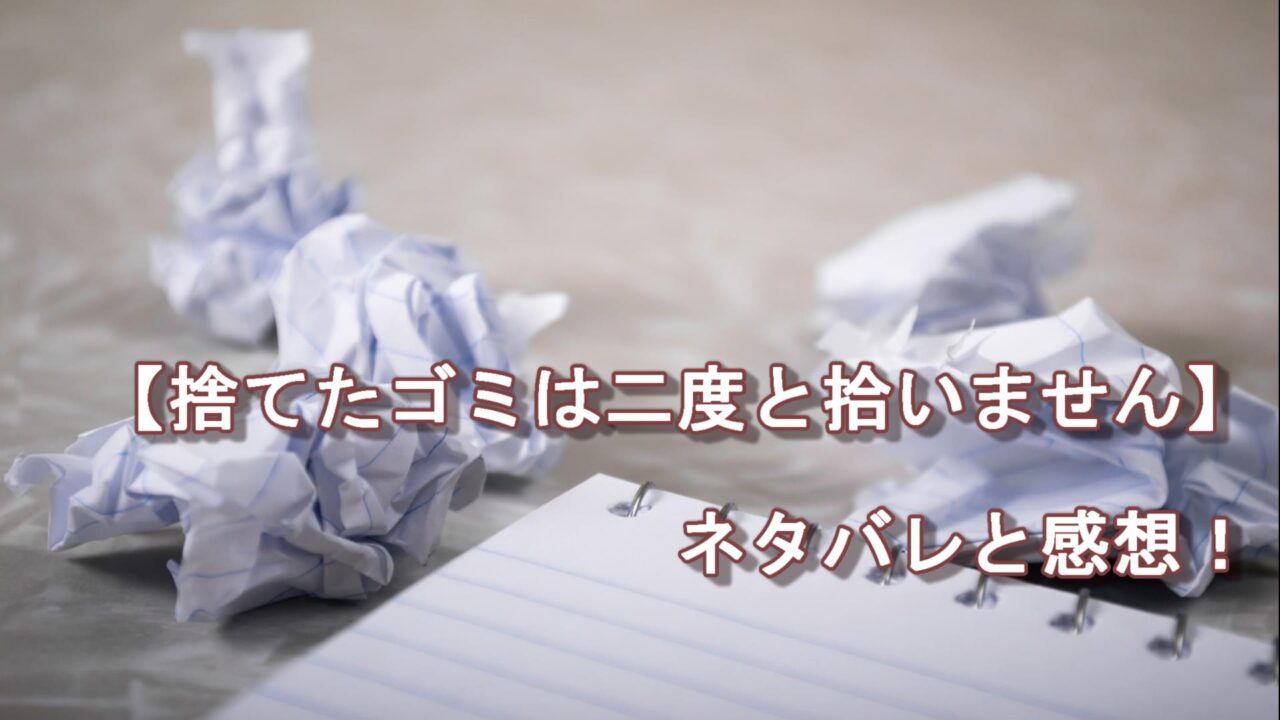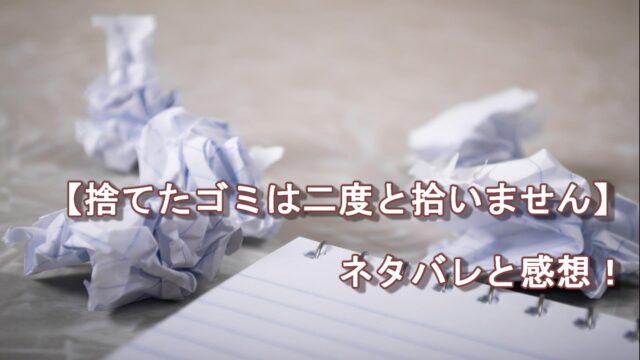こんにちは、ちゃむです。
「捨てたゴミは二度と拾いません」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

97話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 自覚③
「え?執務室を拡張するんですか?」
まるで夜中に雷が落ちたような衝撃だった。
これは一体どういう話なのか。
私は困惑しながらデロント男爵に尋ねた。
「突然、きれいな執務室をなぜ拡張するのですか?」
「それは私ではなく、皇帝陛下にお尋ねください。すべて皇帝陛下の計画ですから。」
デロント男爵はため息をつきながら、書類をめくった。
「あれ、おかしいな?」
「何か探し物ですか?」
「ああ、財務省から送られた書類がありません。どうやら外宮に置き忘れたようなので、取ってきます。」
「行ってらっしゃい。」
デロント男爵が出て行き、業務をしているとノックの音が聞こえた。
「はい、どうぞ。」
ドアを開けて入ってきたのはカリアンだった。
私は作業を中断し、立ち上がった。
「忙しいか?」
「いいえ。何かご用でしょうか?」
「新年祭で着る礼服を仕立てようと思っているのだが、この手のことには興味も知識もなくてな。」
カリアンは少し困ったような表情でそう言った。
「だから、君に服を選ぶのを手伝ってほしいのだが……少し時間をくれるか?」
皇帝の衣装を用意するのは、本来なら皇后または皇妃の役目だ。
しかし、カリアンには妻がいないため、自ら準備しなければならなかった。
以前の宴会の際も、彼が直接準備したと聞いていたのに、今回は私に選ばせるとは。
「わかりました。」
宮廷には専属のデザイナーがいるはずなのに、なぜ私に意見を求めるのか少し不思議に思ったが、それほど難しいことでもないので、素直に応じることにした。
「では、行こう。」
城の奥にある応接室に入ると、すでに待っていた宮廷デザイナーたちが丁寧に挨拶をしてきた。
「陛下にお目にかかります。」
カリアンは無言で毛皮を肩に掛けると、ソファに腰を下ろした。
私は後ろに立って待っていたが、カリアンが隣の席をポンポンと叩いた。
「時間がかかるだろうから、立っていないで座れ。」
「大丈夫です。」
「俺が大丈夫じゃない。だから座れ。」
押し切られる形で、私は仕方なく座った。
カリアンはデザイナーたちに手を動かして指示を出した。
「では、始めよう。」
宮廷のデザイナーたちがデザインカタログと生地の見本を持ってきて、カリアンの意見を尋ねた。
「レイラ、お前の意見はどうだ?」
カリアンが私に意見を求めた。
「私の考えでは……」
最近の流行スタイルを思い浮かべながら、慎重に考えた。
カリアンがデザインや服の選択を真剣に考えているのが伝わってきたので、私も手伝うことにした。
「素晴らしいですね。」
デザイナーが感心した様子で拍手をした。
「センスがとても優れていますね。女性貴族の方々は流行に敏感ですが、男性のファッションにはあまり詳しくない方が多いものです。でも、アステル子爵様は男性の服装にもお詳しいようですね。」
ウィリオット公爵邸にいたとき、フィレンの服を担当していたのだから。
服を選ぶことはすべてデザイナーに任せ、たまにオーダーメイドの服を注文してもよかったが、私はそうしなかった。
フィレンの婚約者であることを他の人々に見せたかった。
これほど努力していることを皆に知ってもらいたくて、些細なことでも自分で選び、世話をしようと努力した。
……すべて無駄になったけれど。
再びウィリオット公爵邸での出来事が蘇り、苦笑いが自然とこぼれた。
「過ちでした。」
苦笑いを抑えて明るく答えると、カリアンが見ていたカタログをパタンと閉じて言った。
「私が見ても、デザイナーよりレイラ、お前のセンスのほうが優れているようだな。」
「陛下!」
カリアンは冗談めかして言ったつもりだろうが、デザイナーの立場からすれば気分を害するかもしれない。
私はデザイナーの表情を気にしながら、彼をなだめるようにした。
幸いにも、彼は機嫌を損ねておらず、微笑んでいた。
「本当ですね。もし陛下の側近ではなかったら、すぐに私と一緒に働いてほしいくらいです。」
「おや、それは聞き捨てならないな。レイラは私の補佐官だ。軽々しく奪おうとしないように。」
「本当に残念です。」
全部冗談だとはわかっているけれど、それでも恥ずかしかった。
私はぽっと赤くなった顔を隠しながら、マントを深くかぶった。
おかげでウィリオット公爵邸での出来事はすぐに忘れられた。
「では、サンプルの衣装を試着してみましょう、陛下。」
デザイナーの勧めにより、カリアンは服を試着するためにカーテンの後ろへと姿を消した。
新年祭は1週間続くが、その間カリアンが着る衣装はざっと計算しても10着を超えていた。
そのすべてを仕立てなければならないので、私はカタログを見ながらカリアンの衣装を選んだ。
これは流行遅れだし、これは地味すぎる。
明るい色の皇帝陛下なのだから、地味な服は似合わない。
新年祭には外国の使臣が大勢訪れるのだから、皇帝としての威厳を示さなければならなかった。
「祭礼の時は、適度に上品な服装を選ばれるのがいいでしょう。」
新年祭では、帝国を守護するブルードラゴンに対して、一年間の帝国の安寧を祈る儀式が執り行われる。
その際に派手な衣装を着れば、むしろ大袈裟に見えてしまうだろう。
適度に力を抜いた装いが良さそうだった。
しかし、それでも皇帝の威厳を示すことは重要だ。
私は適切な衣装を探すため、カタログをめくっていった。
「ん?」
これは……陛下が着るには年齢層が低すぎるのでは?
カタログには、成人式前の18歳未満の少年たちが着る服と説明されていた。
デザイナーが間違えて持ってきたようだ。
私は見ていたカタログを置き、新しいカタログを手に取った。
10着以上の服を選ばなければならず、時間がかかった。
その服に合う帽子、靴、カフスボタンなどの小物を選ぶのにも、たくさんの時間を費やした。
そうしているうちに、気づけば窓の外はすっかり暗くなっていた。
昇った月が、時間がかなり経過したことを示していた。
「今日はここまでにしよう。時間を割いてくれてありがとう、レイラ。おかげでとても助かったよ。」
平服に着替えたカリアンが手首のカフスボタンを留めながら言った。
「それでなんだけど、今日は手伝ってくれたお礼に、新年祭で着るドレスを俺が仕立ててもいいか?」
「お気遣いなく。補佐官として当然の仕事をしたまでです。」
「これはどう考えても補佐官としての仕事とは思えないけど?」
カリアンが静かに私の前へと歩み寄った。
窓から差し込む月光によって、長い影が私の前に落ちる。
「これは明らかに補佐官の業務とは別のことだ。俺の個人的な頼みに、お前が特別に貴重な時間を割いてくれただけだ。」
「いいえ。業務時間なので大丈夫です。」
「その業務時間とやらが、もう3時間も過ぎている。夕食も食べていないじゃないか。」
確かにそうだけど、服を選びながら侍女たちが持ってきたパンとクッキーをつまんだから、お腹は空いていなかった。
この程度なら、夜食を軽く食べれば済む話だ。
「俺が気になって仕方ないんだ。」
断ろうとしたが、そんな私の気持ちを察したのか、カリアンが先に言った。
「だから、受け取ってくれ。頼む。」
たかが食事ひとつのことで、皇帝陛下に頼まれるなんて……
「わかりました。」
もう断ることはできなかった。
私が承諾すると、カリアンは満足そうに笑う。
なぜかはわからないが、とても幸せそうだ。
「好みのスタイルはあるか?」
「特にありません。」
カリアンがくすっと笑った。
「じゃあ、俺が変なものを渡して『これを着てこい』って言ったら、どうするつもりなんだ?」
そんなふうに言われると少し不安になるが、わざわざ今さらあれこれ要求するのも変な話だ。
私は無難な答えを返した。
「そんなことはされないと信じていますから。」
「……信じるよ、か。」
カリアンは私の言葉をじっと見つめると、笑いながら髪をかきあげた。
「そうか。お前が信じてくれる分、俺も最善を尽くして選ばせてもらおう。」
何か言い間違えた気がするのは、きっと私の気のせいだろう。
「では、サイズを測ろうか。」
カリアンが手を動かすと、デザイナーたちが寄ってきて私の体のサイズを測り始めた。
その間、カリアンはカタログを見ていた。
私の記憶が正しければ、それはさっき見たカタログのはず。
18歳未満の少年たちが着る服のカタログだった。
デザイナーがカタログの服をめくりながら、あれこれ話しているのを見ていると、ただ眺めているわけではないことがわかった。
『贈り物をするつもりなのかな?』
皇帝が自ら服を選んで贈り物をするほどの少年って誰だろう?
クラウド公爵夫人の息子はまだ5歳にもなっていないのに。
「刺繍がすべて終わりました。」
そんなことを考えていると、デザイナーたちが集まってきた。
カリアンが時計を見ると、軽くため息をついた。
「もうこんな時間か。馬車を出すから、宮殿の入り口まで乗っていけ。」
「大丈夫です。」
「俺が嫌なんだ。だから乗って行け。」
「わかりました。」
カリアンがここまで言うのに、拒否するのも気が引けたし、無駄に力を使いたくなかった私は、彼の提案を受け入れた。