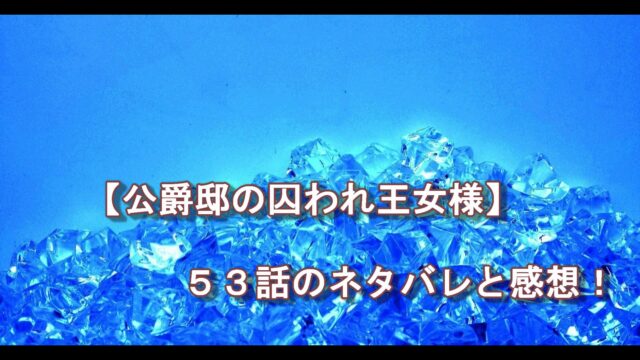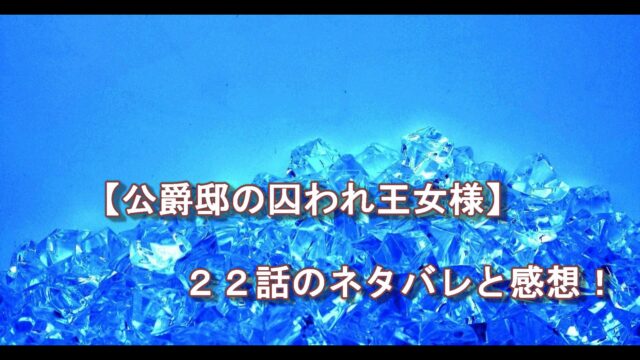こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

100話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 嬉しい報告③
その日の夜。
クラリスは、夕食の時間直前に帰宅したばかりのマクシミリアンを迎えに出た。
「お帰りなさいませ、公爵様。」
「クラリス。」
彼女を見つけた彼は、素早い足取りで近づき、目の前に立った。
そして、観察するような視線で彼女をじっと見つめ始めた。
「毎日ちゃんと食事はとっているのか?どこか痛むところや怪我は?やはり首都院の粗末な椅子は不便だったのではないか。」
彼がクラリスの生活を気にかけるのは、監督者としての責務を負う立場として当然のことだった。
クラリスもまた、彼の問いかけに対して誠実に報告した。
「食事は必ず時間を守ってとっています。幸い、どこも痛くもなく、怪我もありません。それに、首都院の椅子にはもう慣れました。」
「あの粗末な椅子に……。」
公爵は途端に険しい表情を浮かべた。
どうやら、クラリスの腰の健康が損なわれるのではないかと心配しているようだった。
『腰は……やはり身体の大切な部位だからな……。』
クラリスもまた、体の基盤が崩れるほど無理をして処刑台に立つような事態は避けたかったので、彼を安心させることにした。
「ご心配なく。運動もしっかりしているので。」
しかし、マキシミリアンはどうにも安心した様子ではなかった。
やはり、クラリスはもっと運動に励まなければならないと感じた。
「あっ、そうだ!私、今日ですね。」
クラリスは、公爵にも今日あった特別な出会いについて話そうとした。
何より、グレジェカイヤに関係する人物と会ったのだから、必ず報告する義務があった。
しかし、彼女の話が本格的に始まる前に、ちょうど使者がやってきた。
銀の盆に置かれた一通の手紙。
マキシミリアンがその手紙を受け取った途端、使者は退いた。
「……。」
再び二人きりになったが、クラリスは侯爵夫人に関する話を続けることができなかった。
マキシミリアンの表情が、手紙を見つめながら非常に深刻だったからだ。
もしかして、良くない知らせなのだろうか?
クラリスが不安を抱く中、彼は冷静に口を開いた。
「魔法師団から、血縁検査の結果が届いた。」
ブリエルが静かに結果を確認している間、クラリスは自分の部屋へ戻ることにした。
公爵は、一緒にいても構わないと同行を申し出たが、クラリスは丁重に断った。
それは、どこまでいっても『家族』の問題だったから。
誰かが彼女と一緒に結果を見るとすれば、それは公爵か、ウッズ夫人でなければならなかった。
「どんな結果が出たのだろう?」
しかし、気になる気持ちは抑えられず、クラリスは座ることもできず、落ち着かない様子で部屋を歩き回っていた。
「もしも、もしも本当に……宝石の言葉が正しかったとしたら……本当に……。」
公爵夫人は、実はクノー侯爵家の非常に高い地位を持つ女性となるはずだ。
「なんだか……すごくお似合いじゃない!」
ブリエルは聡明で素晴らしい人だから、突然与えられた侯爵の責務も完璧に果たせるに違いない。
たとえ、その責務に困難があったとしても問題はなかった。
夫人を愛するマキシミリアンが、全力で彼女を支えるはずだから。
「本当に素敵なことだと思う。」
クラリスは、ブリエルが時折、出自のせいで問題を抱えていることを知っていた。
たとえば、社交界のパーティーの招待から外されることもあった。
時には予定が一方的に取り消されたりすることもあった。
さらには、ブリエルが理不尽な扱いを受けても、公爵には一切打ち明けなかった。
もしクラリスが魔物たちの助けを受けていなかったら、彼女は一生この事実を知ることもなかっただろう。
この事実を遅れて知ったマキシミリアンは、激怒こそしたものの、何かが変わるわけでもなかった。
結局、ブリエル自身が「すべて受け入れるべきもの」と考えていたからだ。
ただ、彼女の出自が理由で、冷遇されるのは仕方がないとされていたに過ぎなかった。
しかし、彼女の隠された血筋が明るみに出て、彼女が名門貴族の庶子であり、さらにはある侯爵家の正式な後継者であることが判明したら……。
「公爵夫人に陰口を叩いていた者たちは、全員セリデンへ駆けつけて、平伏するに違いない!」
その光景を想像するだけで、胸がすく思いだった。
興奮したクラリスは、握りしめた拳を空中に向かって振り回していたが、ベッドの上で丸くなっていたモチが心配そうに「もし違ったら、どれほど失望することか……」と、慎重に忠告した。
ノックの音が聞こえた。
ロザリーが結果を伝えに来たに違いない。
クラリスは慌ただしく駆け寄り、勢いよくドアを開けた。
「どうなりましたか、ロザリー?!」
相手を確認することなく勢いよく問いかけたクラリスだったが、思わず驚いてしまった。
なぜなら、ドアの前に立っていたのは公爵夫人本人だったからだ。
それも、少し前に受け取った手紙の封をまだ開けていないままで。
「ロザリーではなくて申し訳ないわ。」
夫人はぎこちなく微笑みながら言い、クラリスはすぐに「いえ、そんなことは……」と言いながら、慌ててドアを開け直した。
「夫人の知らせを待っていました。」
「まあ。」
ブリエルはクラリスの部屋に入らず、一瞬腕を組んだ。
「私がそんな人間に見えましたか?」
「え?」
「つまり、大事なことを直接伝えに来ないような人に見えたってことです。」
「い、いえ、そんなつもりでは……。」
クラリスは頬を赤らめながら、長い髪を指でいじり始めた。
「でも、夫人は……まずご家族の方に知らせるべきかと。」
クラリスが戸惑いながら言うと、ブリエルはどこか悲しそうな表情を浮かべた。
まるで、心が痛むことがあったかのように。
ブリエルはようやく部屋に入り、クラリスの腕をそっと握った。
なぜか今日は、夫人の手のぬくもりがとても温かく感じられた。
「とりあえず座りましょう。」
二人はソファに静かに腰を下ろした。
ブリエルはクラリスの手を優しく取り、そっと手の甲を撫でた。
「課題はちゃんと終わりましたか?」
一瞬「課題?」と聞き返しそうになったクラリスだったが、すぐに先ほど自分が彼女に「自習課題がある」と言ったことを思い出した。
「全部やりました。さっきはごめんなさい。私、ちょっと変なこと言ってしまいましたよね?」
「ええ、少し変でしたよ。私が何か不快にさせたのかと思って心配しました。」
「そんなことあるわけないじゃないですか。」
クラリスは身を乗り出し、ブリエルの方を向き、情熱的に言った。
「私は夫人がとても好きです。だから、どんなことがあっても私を不快にさせることなんてありません。」
「もちろん、私もクラリスがとても、とても大好きですよ。」
クラリスは、ブリエルがしっかりと伝えてくれるのが心地よかった。
「だから、もし私に何か変化があったら、誰よりも先にクラリスに伝えたいと思っています。」
「はい……。」
ブリエルがとても温かく微笑んでいたため、クラリスは彼女が話そうとしているのが「血縁検査」のことではないかもしれないと考えた。
彼女は、その検査をあまり好んでいなかったのだから。
『じゃあ、一体何の話……?』
ブリエルをじっと見つめながら考えていると、クラリスは自分が宮殿に戻ってきたとき、ロザリーと交わした言葉を思い出した。
早く行ってびっくりさせてあげなきゃ。
まあ、それは困るわね。
そして、いつかセリデンが言っていた話も。
「つまり、この邸宅に子供ができるかもしれない、ってことだったんですよ!」
クラリスは無意識のうちに、ブリエルのわずかに膨らんだお腹にそっと視線を落とした。
「……もしかして。」
「すごく悩みました。クラリスにどう伝えたらいいのか。」
迷いながら口を開いたブリエルは、まだ握られたままのクラリスの手を優しく撫でた。
「そんな、ご心配なく、奥様!悩まなくても大丈夫です!私……本当に嬉しいんです!」
「でも、私はまだ何も言ってませんよ?ふふ。」
「早く教えてください!」
クラリスは目を輝かせながら、ブリエルにぐっと近づいた。
「女の子ですか?男の子ですか?」
「もう、クラリス!」
ブリエルはさらに大きな声で笑った。
「それは、生まれてみないとわからないことですよ。」
「あ……そうですよね。そういうものですよね? どうしよう、すごく気になります! 名前は? あ、それも生まれてからじゃないとわからないんですね?」
子供のことをあれこれ想像しながら興奮するクラリスだったが、最も大事な言葉をまだ口にしていなかった。
「本当におめでとうございます。私が奥様を抱きしめてもいいのでしょうか?」
クラリスは両腕を大きく広げたが、ふと動きを止めた。
もし奥様のお腹の中にいる子供に悪影響を与えたらどうしよう、という考えがよぎったからだ。
「クラリスが抱きしめてくれないと、私は悲しくなってしまいますよ。」
奥様はそう言いながらも、先に歩み寄ってクラリスをしっかりと抱きしめた。
彼女の淡いピンクの髪を優しく撫で、頭の上にそっと口づけを落としながら。
「……私は女の子だったらいいなと思います。奥様に似たら、きっととても可愛らしい女の子になるでしょうから。」
クラリスは奥様の胸に抱かれたまま、そうつぶやいた。
「そうかしら?でも私にはすでに娘がいるから、今度は男の子でもいいかなと思うの。」
「……。」
「お姉ちゃんを守る、クールな子もいいですし、お姉ちゃんの後ろに隠れる泣き虫でも可愛いでしょうね。そう思いませんか?」
クラリスは何も答えることができなかった。
彼女を家族の一員として受け入れて話してくれることが嬉しくもあり、また少し気恥ずかしくもあった。
「一緒に喜んでくれてありがとう、クラリス。」
「当然のことですよ。」
クラリスは目を閉じ、ブリエルの胸に少し深くもたれかかった。
「ついに、私の番が来たんですね。ずっと待っていました。」
「番……ですか?」
「はい、奥様がいつか言っていたように思います。私も、突然目の前に現れたこの子を……愛さずにはいられないでしょう。」
「……クラリス。」
そして、クラリスは抱きしめられたまま、そっと体を起こした。
「きっとそうなる運命だったんですよ!」
「ああ、本当に。」
ブリエルは両手で顔を覆ってしまった。
彼女の肩がかすかに震え始め、クラリスは慌てて声をかけた。
「お、奥様?」
「……そんなふうに言われたら、感動してしまうじゃない、クラリス。」
「え? でも、これは……奥様が以前おっしゃったことですよ?」
「こんなに昔のことを覚えていてくれたなんて、それだけで胸がいっぱいになるわ。本当に、クラリスは時々、人の心を驚くほど上手に奪ってしまうのね。」
クラリスは少しだけ、胸が詰まるような気がした。
先に心を奪われたのは、むしろ自分のほうだ。
こんなふうに、幼い子供にまで温かく接するブリエルを見れば、誰だって夏の日のキャンディのように甘く溶けてしまうに違いない。