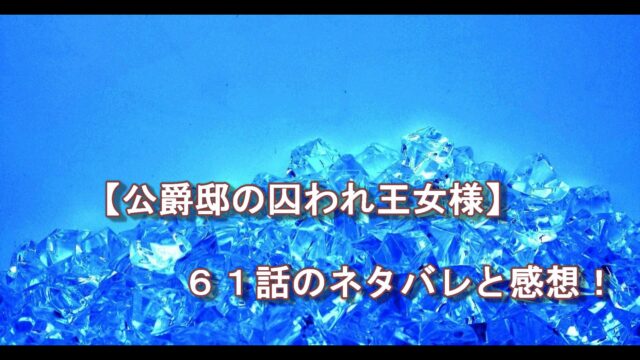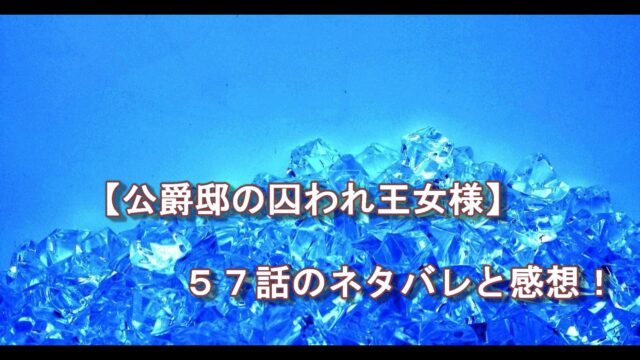こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

132話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 無責任な一言
「バレンタイン、どこかへ行くみたいだね。」
そう言ってノアが訪ねてきたのは、その日の夕方だった。
部屋の中で司祭服を一定の形に切り揃えていたクラリスは、全身に糸くずや布切れを貼りつけたまま、扉を開けた。
「王子様は、王都へ行かれるそうです。理由までは教えてくれませんでしたけど……どうやら、何も知らないふりをしていてほしい、ということみたいで」
「本当に知らないふりをしてほしいなら、せめて私にも一言くらい残していけばよかったのに。こんなふうに黙って行かれたら、余計に気になるじゃないですか」
ノアが不満げにぶつぶつとこぼすと、クラリスは小さく微笑んだ。
二人は、本当に少しずつ――けれど確かに、打ち解けてきているように見えたから。
その表情を察したのか、ノアは慌てて付け加える。
「もちろん、あの不親切な王子殿下がどうなろうと、私の知ったことじゃありませんけどね」
そう言いながらも、バレンタインが姿を消したと知った途端、様子を確かめに来たのは事実だった。
クラリスはそのことを思い出し、胸の奥にほのかな温かさを覚える。
彼らが親しくなってほしいと願っていたのは、彼女がずっと抱き続けてきた――小さくて、けれど確かな希望だったのだから。
「王子さまが戻ってきたら、三人で一緒に遠出でもしません?」
「遠出だなんて、ずいぶんかわいいことを言うね。」
彼は、礼拝堂を掃除していた頃のことを思い出したのか、どこか楽しそうに首を振った。
「三人だけの秘密にすればいい。」
――「三人」という言葉に、クラリスは改めて、その響きがとても愛おしく感じられた。
「ところで、君は一体、何をしていたんだい……?」
ノアは長い指で、クラリスの肩に付いていた布切れを一つ、そっと取り除いてやった。
もっとも、一つ取ったところで、彼女のぼさぼさとした様子が大きく変わるわけではなかったが。
「ええと……お守りを作っていたんです。思っていたより難しくて。あとは縫うだけなんですけど。」
「公爵夫人への贈り物?」
「ううん。正確には、これから生まれてくる赤ちゃんに作ってあげるつもりなの」
「勉強の時間を割いて、贈り物を作るってことですか?」
ノアが核心を突いたせいで、クラリスは思わず表情を曇らせた。
そうでなくとも、想像していた以上に時間がかかりそうだと感じていたところだったからだ。
「……それで、とりあえずモチが本を読んでくれているの」
クラリスはそっと身を引き、自分の机を示した。
広げられた布切れの間に、分厚い一冊の本が置かれている。
その本の上には、すでに切り離された四つの文字片が、きちんと並べられていた。
「朗読……大変だったみたいね」
なんとなく申し訳なくなって、クラリスは気まずそうに髪を指でいじった。
「仕方ないよ。誰かの助けを借りたっていいんだし、必要なら俺が手伝う」
「……本当?」
クラリスがぱっと目を輝かせて問い返すと、彼は少し照れたように視線を逸らした。
「それに、公爵夫人も、クラリスの勉強時間が減るのは喜ばしくないだろうしね。縫う布をいくつか選んで、僕に渡してくれたら……」
「ノアが手伝ってくれるなら、本当に助かるわ。散らかっているけど、入って。」
クラリスはノアの言葉を最後まで聞くこともなく、自分の部屋へと入っていった。
そして、かろうじて布切れがほとんど落ちていないベッドを、手のひらで軽く叩く。
「ここに座ってやればいいと思う。」
「……」
「針はどこだったかな。」
そう言いながら、彼女は引き出しを探り、新しい針を一本取り出した。
「ねえ、君。」
まだ扉の前に立ったまま、困ったように呼びかけるノアに、クラリスは駆け寄り、切り揃えた布を二枚、彼の手に押しつけた。
「とりあえず、水晶の欠片の形と、大理石の形があるんだけど……どっちがいい?」
見たところ、水晶の欠片は小さな破片同士をつなぎ合わせる必要があって、かなり手間がかかりそうだ。
一方、大理石は形自体は単純だけれど、表面にきちんと文字を刻まなければならない。
「あ、ノアは赤い石みたいな感じにすればいいかも……」
「大理石がいい!」
彼は即答すると、勢いよく大理石の図案をひったくった。
「本当?文字を彫るのが大変で失敗したらどうしようって心配してたんだけど、ノアが引き受けてくれるなら安心だわ。入って、ノア」
クラリスはそう言って、彼の手を引きながら部屋の中へ連れ込み、ぱたんと扉を閉めた。
「……あ、うん」
ノアは本当は一度自室に戻って裁縫道具を取ってこようと思っていたことを、結局言い出せないまま、ベッドの端にちょこんと腰を下ろすしかなかった。
「ノアが手伝ってくれるなんて、すごく嬉しい」
クラリスも自分の席に戻り、これまで縫い続けていた、くしゃくしゃの茶色い布をそっと持ち上げた。
彼女は、ノアが裁縫をとても上手にこなすだろうと、半ば当然のように思っていた。
そして、その予感はやはり正しかった。
ノアは、クラリスが布の上に大まかに描いた大理石模様を、驚くほど忠実に縫い取っていく。
――こんなこと、いったいどこで覚えたんだろう。
幼いころ、師に教わったのだろうか。
それとも、本を読みながら一人で身につけたのだろうか。
「……あ。」
ふと、何か違和感を覚えたのか、彼の手が止まった。
「仮面のせいで、見間違えた。」
そう言って、彼は自ら仮面を外し、横に置いた。
視界が狭くなっていたのが、どうにもやりづらかったらしい。
そして再び、針と糸に意識を戻す。
クラリスは、彼が何かに没頭しているときの表情を、ほとんど初めて目にした。
――ほとんど瞬きもしない。
その真剣さに、思わず視線が額のあたりに引き寄せられた。
「ずいぶん力が入ってるみたい」
いつの間にかクラリスは針仕事の手を止め、彼をぼんやりと見つめていた。
けれど当の本人は、その視線に気づくこともなく、ただ縫い目に集中しているだけだ。
やがて彼は、細い針の先をふと口にくわえる。
糸を替えようとして、手が足りなくなったのだろう。
――危ないじゃない。
そう言いかけて、クラリスは言葉を飲み込んだ。
その瞬間、彼の唇を見つめた拍子に、少し前にユジェニが残していった、あの無責任な一言が脳裏をよぎったのだ。
『キスするところを想像してみなさい』
「……っ、わ、私、何を考えてるの、クラリス!?」
クラリスは慌てて自分を叱りつけた。
ユジェニが「応用してみろ」と言ったのは確かだけれど、まさか本当にそんなことをする気など、これっぽっちもない。
――それも、相手が目の前にいる状態でだなんて。
彼女はそう言い聞かせるように、ぎゅっと目を伏せたまま、再び針を手に取った。
――これ、ノアが知ったら、きっと不快に思う。
だから、早く別の、まっとうなことを考えなければならなかった。
キスや口づけなんてものとは、できるだけ縁のない、健全な考えを。
「……お嬢さん?」
「あ、ち、違うの!」
何を考えればいいのか見つからないままノアに呼ばれ、クラリスは思わず、反射的に否定の言葉を口にしてしまった。
「やっぱり、どこかおかしいな。」
そう言うと、ノアは再び刺繍に視線を落とし、じっと観察し始める。
「ああ、刺繍の話か……。」
「ほかに、何か気になるところはある?」
「ううん。大丈夫。うん、悪くない。すごく上手だよ。」
クラリスは、彼が縫い終えた刺繍を素早く褒め、なんとか微笑みを作った。
「……どこか、気に入らない形だったりする?」
けれど、ノアを誤魔化すことはできなかった。
彼は、じっとクラリスの方を見つめていた。
――クラリスのことを、本当にここまで理解している人なのだろうか。
「いや、本当に素敵だと思う。私がやったら、こんなふうに自然な色合いには絶対ならないもの」
「私だって、そんなに自然ってわけじゃありませんよ。もし何か引っかかることがあったら、ちゃんと話してくださいね」
「うん。あ……そうだ。ちょっと、窓でも開けようかな。埃が多いのか、喉がいがらっぽくて」
「すぐ開けます」
ノアは道具を机の上に置き、椅子から立ち上がった。
「ち、違う、違う!」
クラリスも慌てて針仕事を置き、彼を制した。
喉が本当にいがらっぽかったわけではない。
ただ、窓を開けるふりをして、少し気分を切り替えたかっただけなのだ。
そのことを悟られるのが、なぜかひどく恥ずかしかった。
クラリスは足元がおぼつかないまま、よろよろと窓の前へ向かう。
そして、まだベッドのそばに立っていたノアが、どこか不思議そうな表情でこちらを見ていることに気づいた。
――見られている。
そう、はっきりと感じた。
「あ……はは。」
喉が詰まったような、ひきつった笑いを漏らしながら、クラリスは慌てて両腕に力を入れ、窓を開けようとした。
ドン、ドン!
しかし、窓は半分ほど開いたところで止まってしまう。
「あ……」
少ししてから、クラリスは自分の部屋の窓が歪んでいることを思い出した。
――最初から、傾いた方向に押しながら、慎重に開けなきゃいけなかったのに。
普段なら無意識にやっていることだったが、今は動揺して、完全に頭から抜け落ちていた。
こういうときは、いったん閉めてから、もう一度開け直すしかない。
クラリスは、今度は窓を下へ押し下げてみた。
けれど、窓は反対方向にも、ぴくりとも動かなかった。
――うん、完全に固まってる。
これほど力を入れてもびくともしないなんて、初めてだった。
――だからといって、窓に張り付いて悪戦苦闘している姿を見せるのは嫌だ。
こうなってしまった以上、できるだけ自然に振る舞うしかない。
最初から半分だけ開けるつもりだった、という顔をするしかなかった。
ちょうどいい言い訳も思い浮かぶ。
冬だし、あまり大きく開けたら寒い――そう言えばいい。
「それに、この窓は管理室に連絡して直してもらわないといけないって、ヌヌも言ってたし……」
そう言い終えるより早く、いつの間にか背後へ回り込んだノアの腕が、クラリスの腰のあたりをかすめるように伸び、彼女の手ごと窓枠を掴んだ。
彼がぐっと力を込めて引いても、窓はぴくりとも動かない。
「本当に固着してるな。バレンタインが見たら、“お前、力持ちの少女か”ってからかい始めそうだ」
その声は冗談めいていたが、窓と同じくらい、クラリスの身体も動かなくなっていた。
ノアがやわらかく笑いながらかけてきた言葉に、クラリスは少しむっとしてしまった。
そもそも、誰のせいでこんなことになっているのかも分からないというのに。
「……ノアのばか。」
理由のない苛立ちが胸に広がり、クラリスは不満そうに彼を振り返った。
だが当の本人は、クラリスが少し不機嫌になっていることにも気づかず、相変わらず窓を閉めるのに悪戦苦闘していた。
――なんだか、ずるい。
そう思いながらも、化粧をしていないノアの素顔から、どうしても目を離せなかった。
見ているうちに、驚くほど気分が良くなっていく。
――これが、「顔に惚れる」というやつなのだろうか。
ノアは、そうでなくとも整った目鼻立ちをしているうえ、落ち着いた雰囲気まで纏っている。
そんな彼と、これほど近い距離で向き合っていれば、否応なく幸福な気持ちになってしまうのも無理はなかった。
きっと、どんな宮廷の美の達人であっても、ノアを前にしたら――
『じゃあ、私がノアを見るたびに、なんだか変な気分になるのって……ゴーレムマスターだから?』
クラリスはノアの顔をじっと見つめたまま、さらに考え込んだ。
――でも、それだけだと断言するには……。
実際、ノアの顔が好きだと思うことと、キスを想像したときに胸が妙に高鳴ることは、まったく別の話だった。
なにせ、ノアの唇には“石”がないのだから。
「とりあえず、なんとか閉まったけど……また同じことが起きる前に、管理室に連絡して窓を新しいのに替えてもらわないとな。……それで、少女。何か問題でもあるか?」
カタン、と音を立てて窓を閉めたあと、彼はようやく彼女の表情に気づいたのか、目を細めた。
クラリスははっとして、慌てて首を横に振る。
「ち、違う、キスが……じゃなくて!」
……あまりに慌てて答えようとしたせいで、頭の中いっぱいに浮かんだその言葉を、うまく外に出せないまま、口にしてはいけない失言をしてしまったのだと、クラリスは悟った。
「……?」
ノアが、きょとんと目を見開く。
それも無理はない反応だった。
「あ、えっと……その……」
クラリスは、答えにならない言葉を口にしながら、落ち着きなく両手を動かした。
だが、どう取り繕っても、まともな言い訳は思い浮かばない。
それどころか、こちらをまっすぐ見つめるノアの視線が、次第に重く感じられてくる。
何があっても、この言い間違いの理由だけは、きちんと説明しなければならなかった。
「ご、ごめん。ほら……あれ。全然、変な意味じゃなくて……」
クラリスは中途半端な弁明を諦め、代わりに、先ほどまでユジェニアと一緒に話していたことを、できるだけ無難に説明することにした。
もちろん、すべてをそのまま話すわけにはいかず、少しだけ色を付け足しながら。
「ユジェニアと、人の心理について……その……話していて……だから……学術会?みたいなことをやってたの」
「学術会、ですか?」
「そう。どこまで理論的に掘り下げられるか、っていう試み!どうすれば“好き”って気持ちを……自覚できるのか、ってテーマでね」
「……テーマが?」
「変でしょ?」
クラリスは、ノアの考えを理解していながらも、思わず呆れたように言った。
「ぜんぜん変じゃない!すごく大事なテーマだよ!人類共通の課題みたいなものだし。試験に出てくる哲学者だって、愛についてどれだけ研究してきたと思ってるの!」
勢いのある主張は、だんだんと熱を帯びていく。
「……まあ、そう言われると」
「でね、ユジェニが意見を出したの。相手とキ、キスするところを想像してみたら、自然と分かるんじゃないか、って」
「……自然に?」
「たとえば、こういう感じ」
話が途切れずに進むにつれ、クラリスは少しずつ肩の力が抜け、思わずくすっと笑ってしまった。
「ノア、私とキスするところ、想像できる?」
この問いに、彼はきっと「うわっ」と言って、頭をかくに違いない。
クラリスはそう思っていた。
――そしたら、「ほら、これよ」と、ユジェニアが話していた“身体の反応”を説明するつもりだったのだ。
……そのはずだった。
ところが、向かい合ったノアの顔が、みるみるうちに熟れた果実のように赤く染まっていく。
しかもなぜか、瞬きもせず、じっとクラリスを見つめたままだ。
「……え?」
驚いたのは、クラリスのほうも同じだった。
想像していた反応とは、まるで違う。
「ど、どうして……私の心臓、急にこんなに速く……?」
呼吸まで浅くなってきた。
息は次第に上ずるのに、ノアとの距離が近すぎて、それだけが気になってしまい、思うように息を整えることすらできなかった。
いや、そういう問題じゃない。
まるで魔法にかかったみたいに、ノアの紫がかった瞳から、どうしても視線を逸らすことができなかった。
『どうしよう……私……』
こんな気持ちを認めてはいけないはずなのに、なぜか今ならノアとキスできてしまいそうな気がした。
『……違う、そうじゃないって……思いたいのに……』
生まれて初めて感じる思考と感情は、彼女が受け止めるにはあまりにも重すぎた。
思わず、無意識のうちにぎゅっと目を閉じてしまうほどに。
けれど視界を閉ざしたことで、逆にほかの感覚が研ぎ澄まされていく。
クラリスは、ノアが身を屈めて、自分にさらに近づいてきているのが分かった。
「え……ど、どうするの?本気……?」
なぜか両足が小刻みに震えそうになるのを、必死で堪えなければならなかった。
いつの間にか、スカートの裾を握りしめる手にも力が入り、布がしっとりと湿っているのがはっきりわかるほどだった。
「クラリス。」
彼が彼女を名前で呼ぶことは、めったにない。
それなのに今は、こんなにも近い距離で、囁くように名を呼ばれるのが、どうしようもなく心地よかった。
溶けてしまいそうな感覚に、思わず小さく喉を鳴らした、その瞬間――クラリスの唇の上に、ひどく冷たくて、大きなものが触れた。
……ノアの手のひらだった。
驚いて、細く目を開けると、ノアは笑っているのか怒っているのか判然としない表情で、荒い呼吸を繰り返していた。
「……っ、これは……本当に、まずい。」
そう呟くと、彼は氷のように冷えた手でクラリスの口を塞いだまま、大きく息を吐いた。
――まずい、だなんて。
それは、どう考えても、あまり良くない事態を指す言葉だった。
クラリスは、なぜだか胸の奥がちくりと痛んだ。ほんのわずかでも期待してしまっていた、その分だけ。
「……そ、そんな目で見ないでください。わ、私……その……勘違いしてしまいそうで……」
どんな勘違いなのか。
本当はそう問いかけたかったのに、ノアの手がまだ彼女の唇をそっと塞いでいて、言葉にすることができなかった。
「……知らなくていい」
けれどノアは、聞かずとも彼女の気持ちを正確に理解しているようだった。いつものことだ。
「少女は、まだ幼い」
そう口にするノアも、クラリスより二つ年上なだけに過ぎないのに。
「だから、その手の話題……についての議論は、もう少し大人になってからの方がいいな。せめて、十八を越えてからじゃない?」
『……でも、その頃の私は……ノアとキスなんて、できない』
クラリスはそう思いながら、言葉にはできず、ただ胸の奥でその想いを抱きしめるしかなかった。
そう考えた途端、クラリスはなぜか悔しさがこみ上げてきた。
少しだけ……悲しい気も。
彼女の胸の痛みに気づくこともなく、ノアの諭すような言葉は続く。
「他の人の前では、絶対にああいう大人びた真似はしないでください。いいですね?」
返事を待つつもりだったのか、彼はクラリスの口を塞いでいた手を離した。
「……」
クラリスは、どうしてだか彼が少し憎らしく思えて、何も答えなかった。
「……あれ、拗ねました?え……どうして?」
――知らないわよ、ばか。
そう叫びたい気持ちを必死にこらえて、クラリスはただ、彼の胸元をこぶしで一度、軽く叩いただけだった。
ノア・シネットは、本当にずるい。
……それでも、だからといって、ノアとキスをしたくなくなったわけではない気がした。
ノアの手助けもあって、お守りはほどなく完成した。
そして彼は、わざわざ管理室まで足を運び、窓の修理が終わるまで面倒を見ると約束してくれた。
クラリスは、妙に一歩ほど距離を空けたまま、彼の後をついて歩いた。
自分の胸に芽生えた違和感――その正体を測りかねながら。
そんな中、洗面室の前でユジェニと鉢合わせした瞬間、クラリスは慌ててノアに一言断りを入れ、彼女のもとへ駆け寄った。
「ユジェニ!」
「クラリス」
ユジェニは、きちんと立ったままこちらを振り返っていたノアに軽く会釈をしてから、クラリスの前へと歩み寄る。
「どうしました?」
「え、えっと……今、少し時間ある?」
「三分ほどでしたら。どうぞ、お話しください」
「それそれ!」
勢いづいたクラリスは、思わず口を開きかけて――『ノアとキスを想像してしまって――』……そこまで言いかけて、はっと言葉を飲み込んだ。
「……したい。」
そんな言葉を、修道院の回廊で、思わず叫びそうになってしまった。
だがクラリスはすぐに我に返り、ユジェニアの腕を引いて中央庭園のほうへ連れて行った。
周囲をきょろきょろと見回し、聞き耳を立てる人も、近くに誰もいないことを確かめてから、ユジェニアにそっと距離を詰める。
「ね、あの……」
それを見て、ユジェニアの目がきらりと光った。
「なるほど。応用しましたね。」
核心を突かれたクラリスは、自分でも驚くほど反射的に「ち、違います!」と否定してしまった。
「わ、私がノアを相手に、そ、そんなこと考えるわけ……」
顔が熱くなっていくのも、声が震えているのもはっきり自覚して、クラリスは慌てて口を閉ざした。
これでは、誰が見ても嘘だと分かってしまう。
「……つまり、そういうことですね。」
クラリスは、なおももじもじしながら、改めて言葉を紡いだ。
「……ノアの顔に、惹かれちゃったんです。それだけは、本当にどうしようもなくて……」
「猫の仮面に惚れた、という意味ではなさそうですね」
「そ、そうなんです。私はノアの仮面も可愛いと思ってます。でも……」
クラリスは耐えきれず、両手で顔を覆った。
ほんの少し前、間近で見たあの顔を思い出すと、胸の奥がざわついて、どうにも落ち着かない。
「ずるいです。あんな顔をしてたら、誰だって変なこと考えちゃいますよ!」
「…………」
しばらく言葉を失っていたクラリスだったが、ユジェニの時間をこれ以上奪うわけにはいかないと我に返り、慌てて顔を上げた。
「だから、これは無効ってことですよね?ね、ユジェニ。あの方法論が必ず通用するわけじゃないって話ですよね? 相手の外見があまりにも魅力的な場合は、考慮外……つまり例外、ですよね?」
必死に言い募るその様子は、まるで自分自身を説得しているかのようだった。
「……」
ユジェニは、細めた優しい目でクラリスを見つめ、やがてゆっくりとうなずいた。
「ひとまず、そうだと受け取っておきましょう。」
その言葉に、クラリスの表情がぱっと明るくなる。
「そうしたほうが、クラリスの心が楽になるなら。」
「ああ、ほんと、ユジェニって最高!」
思わず声を上げると、ユジェニは面白そうに喉を鳴らして笑った。
「頭を撫でてもいいですか?」
「……どうぞ。好きにしてください。」
もじもじと答えたクラリスの髪を、ユジェニは遠慮なく、けれどやさしく撫でた。
いたずらっぽく、少し意地の悪そうな笑みを浮かべながら。
――こんなときは、本当にバレンタイン王子と兄妹のように似ている。
ふと浮かんだその考えに、クラリスははっとして我に返った。
王族という特別な家は、普通の家族とは違う。
彼らはそれぞれ異なる常識を持っていたが、その中には、かつて王室に身を置いていたクラリスだからこそ知っている事情も含まれていた。
――王の血筋は、決して「双子」として存在してはならない。
王の血は常に唯一無二であるべきものであり、他の存在と誕生や運命を分かち合う双子など、あり得ない――それが、彼らの揺るぎない信条だった。
そうした背景を思えば、バレンタインとユジェニが「双子のように似ている」と考えること自体が、極めて無礼な行為となる。
それはすなわち、バレンタインの血統そのものを疑うに等しい言葉だったのだから。