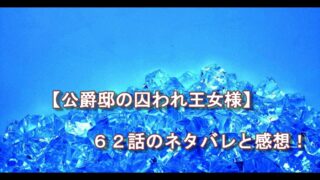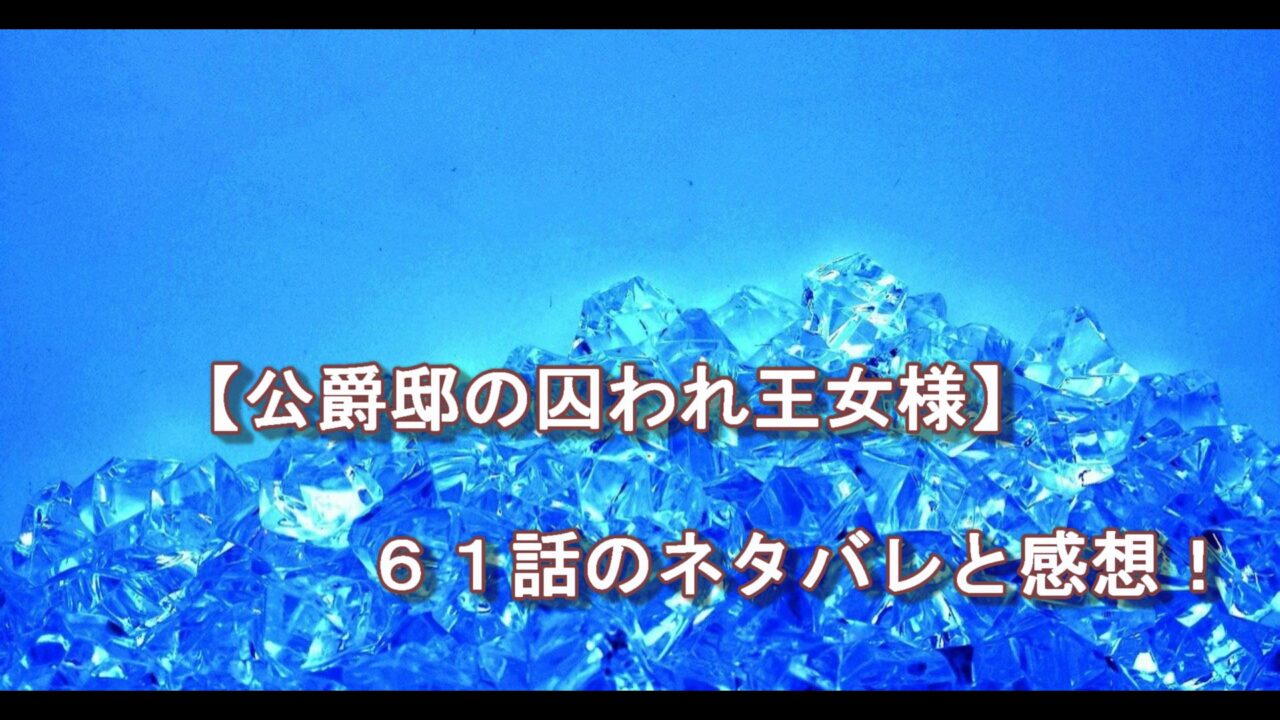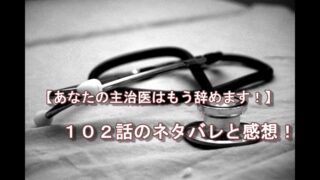こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
今回は61話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

61話 ネタバレ
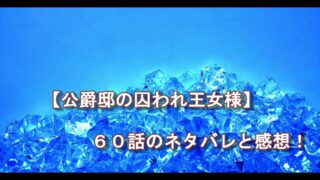
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 目覚め
北の城壁。
「大変だな」
マクシミリアンは雨が気持ち悪いほど降る北の城壁で、全身をびしょ濡れにしたまま、最も高いところに立っていた。
その前の焙火では3つの炎が燃え上がり、真っ白な煙を空の上に上げている。
しかし、絶え間なく降る雨のせいか、湧き上がるのはただ細い煙だけ。
「どうやら霧まで濃く立ち込めていて、焙火が見えないようです。遅くとも明日の午前中までにはシェリデン邸に消息があれば援軍が適時に出発するはずですが、どうしましょう?」
彼のそばを守る騎士が、遠く暗い北を心配そうに振り返った。
そこから吹いてくる風の音が、なぜか魔物の嗚き声のように聞こえる。
定期的に北側の城壁の向こうを訪れる探索隊は、城壁とさほど遠くない森で魔物とその卵を発見した。
これは数十年に一度あるかないかのことで、シェリデンにとっては「災害」に近い発見だ。
暖かい夏に生まれたばかりの子供の魔物の食性は実に酷い。
卵の殻はもちろん、時には自分の母の肉までかじって食べたりもしたから。
そのため、母親たちは子供たちがお腹が空かないように必死に餌を供給しなければならなかった。
遠い北でこのような場合、魔物同士の戦争が起こるものだが、このように北の城壁に近いところで子が生まれる場合・・・。
母の魔物は人間を餌に選ぶものだった。
マクシミリアンはすでに近くの村に避難命令を出し、北側の兵士たちをすべて城壁に連れてきた。
だが、子魔物の数が思ったより多く、万がーに備えた支援軍が必要な状況だ。
「公爵様」
ノア・シネットが彼のそばにやってきた。
後を追う他の魔法使いはいない。
「なんで一人でここにいるの?」
公爵が眉をひそめて尋ねると、ノアは軽く肩をすくめた。
「私が残ると言いました」
「他の魔法使いたちは・・・いいや、なんでもない」
公爵はあえてこれ以上言わなかった。
たぶん彼らは村人たちと一緒に逃げたらしいから。
「彼らを責めないでほしい。魔法使い団が従う基準では、私がより目上の人になり、彼らを保護する義務があります」
とはいえ、こんなに幼い少年を置いて大人たちが逃げるなんて。
恥ずかしいことだった。
「消息は伝わっていますか?」
マクシミリアンは首を横に振つ。
「天気の影響で城壁の近くの可視性が良くないね」
このような状況に備えて、シェリデン邸に人を送っておいた。
しかし、悪天候のため、適時に到着するのは難しそうだ。
「城壁にいる兵士たちでも十分に戦うことはできるが・・・」
マクシミリアンはできるだけ犠牲が少ないことを願った。
戦争で負った傷がまだ癒えることもないだろうから。
「焙火と人づてのほかに消息を伝える方法はありませんか?」
ノアの問いにマクシミリアンはすぐにシェリデンの鐘を思い出す。
北側の魔物の勢いがおかしい度に、あらかじめ鐘を鳴らして知らせてくれたという伝説の主人公の言葉だ。
「もし・・・屋敷の鐘が4回鳴ったら」
シェリデンで長い間働いてきた年配の騎士たちが、その意味を知り、直ちにここまで支援軍を派遣してくれるだろう。
「兵士たちが駄目になったと不平を言うあの鐘のことか」
マクシミリアンは苦笑いする。
確かに鐘は長い歳月が過ぎ、その神妙な力をほとんど失ってしまった。
おそらく今も鐘は鳴っていないはず。
その時だった。
北側から吹いてきた風に積まれた「クェェェェェ!」という気持ち悪い音が城壁をいっぱいに埋めた。
それは卵が孵化するという合図。
一方、シェリデン邸周辺は洪水に近い雨が毎日降っていた。
公爵が席を外した今、ブリエルが責任を負って邸宅に近い村人たちを保護した。
家や道が水に浸からないようにするのはもちろん、突然の事態で食糧を調逹できない家庭を助けるのも彼女の役目だ。
彼女は太陽が山の向こうに落ちてこれ以上外に出歩けない時になってようやく邸宅に戻ったが、一番最初に向かったのはクラリスの部屋だった。
「熱は下がりましたか?」
ノックもせずに入った部屋には女中1人がクラリスの額に新しいタオルを置いていた。
「はい、少しずつ落ちましたが、まだ夜ですから」
「解熱剤は?」
「2時間前に食べました」
ブリエルはベッドに近づき、クラリスの額に注意深く手を乗せる。
熱が下がったその上、子供の額はまだシェリデンの冬を溶かすほど熱かった。
「・・・私のせいです」
ブリエルはため息をついた。
どんなに一人でも大丈夫だとしても、担当する女中一人もいないわけではなかった。
急に落ちた気温と雨による被害を解決するために邸宅の皆が血眼になっていた間、クラリスはこの部屋の中で放置された。
それも開け放たれた窓に体を半分ぐらいかけたまま気絶した状態で。
「夏といっても雨の日にはむやみに窓を開けてはいけないと教えなければならなかったのに」
「奥様のせいではありません。クラリスもそれは知っていたはずです」
メイドが慰めて渡した言葉にもブリエルはそっと首を横に振る。
もしかしたら、子供は村のことを心配して、開いた窓の向こうを眺めていたのかもしれない。
優しい子だから。
そうでなければ、あまりにも忙しい大人たちの間で邪魔にならないように一人寂しさを抑えていたのかもしれない。
どうしてもう少し気を使わなかったのだろうか。
あまりにも後悔した。
「ふぅ・・・」
乾いたクラリスの唇が少し開き、弱音が聞こえた。
「・・・だめです」
もしかして、何か悪い夢を見ているのだろうか。
ブリエルは汗まみれの子供の髪をそっと撫でた。
何度かもっと切実な言葉を寝言のように話していたクラリスは、すぐにまた深い眠りに落ちた。
マクシミリアンがピンチです。
鐘を鳴らそうにも外壁卿は返事をせず、クラリスも病床に伏せています。