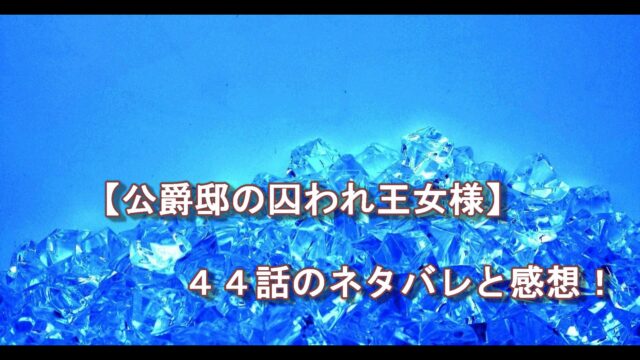こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

133話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 皇族の役目
マクシミリアンは、ライサンダーに呼び出され、第二城壁へと向かった。
その城壁は、身分によって出入りが厳しく制限されている高い壁であり、その下には、罪を犯した者たちを収容する牢獄が広がっている。
ライサンダーが彼を呼んだ場所は、まさにその一角だった。
当然のことながら、マクシミリアンの胸には、言いようのない不安が芽生えていた。
彼が馬を降りると、待ち構えていた侍従が、城壁の下――地下へと続く道へ案内した。
階段は次第に狭まり、光も薄れていく。
湿り気を帯びた、むっとする空気の中に、鼻を突くような腐臭が混じりはじめた。
――もし「最悪の臭い」というものがあるとしたら、きっとこんな匂いなのだろう。
マクシミリアンは、反射的に眉間にしわを寄せそうになるのを、必死で堪えた。
少なくとも、慈悲深き王の目前で浮かべるべき表情ではない。
重装の騎士たちが守る分厚い鉄扉を抜け、マクシミリアンはついに地下牢の奥へと足を踏み入れた。
細長い通路の両脇には、重々しい鉄格子に閉ざされた牢が並んでいる。
だが、その大半は空だった。
かつて囚われていた罪人が残していった、藁屑や、打ち捨てられた器だけが、ここに人の気配があったことを物語っている。
「兄上、思ったより早かったな」
最奥から聞こえてきた声に導かれ、さらに進むと、ライサンダーが古びた木の椅子に、堂々と腰掛けているのが見えた。
その前には、地面に膝をつかされ、項垂れる罪人が五人。
鎖の擦れる音と、荒い呼吸だけが、重苦しい沈黙を破っていた。
地下牢の空気は冷たく、そして重い。
ここは、嘘も言い訳も通用しない場所――真実だけが、否応なく引きずり出される場所だった。
……いや、正確には、床に額をこすりつけるように身を折り、声を殺して苦痛に耐えていた。
マクシミリアンは、そこにいる者たちを順に見渡した。
その多くは見覚えのある顔だった。
王宮の侍従や、没落した下級貴族たち――。
マクシミリアンは囚人の話に入る前に、ライサンダーの背後に立つバレンタインへと視線を向ける。
焦点の定まらない蒼い瞳は、行き場を失ったまま小刻みに震えている。
「……殿下。」
マクシミリアンは、何よりも先に彼のもとへ歩み寄り、両肩に手を置いた。
彼の胸元にすら届かなかった幼い頃を思えば、信じられないほどの成長だった。
今や騎士と見間違うほどの体格を備え、「少年」という呼び名は、もはや似つかわしくない。
それでも――マクシミリアンは忘れていなかった。
彼が、まだ十五にも満たない年齢であるという事実を。
クラリスと同じ、まだ十五の年頃だ。
こんな陰鬱な場所に連れてくるには、あまりにも早すぎる――ライサンダーの言葉には、そんな含みがあった。
「兄上は、何が起きたのかを聞く前に……あの子のことが気がかりなんじゃないか?」
ライサンダーは、後頭部に手を回して首を大きく伸ばし、軽く肩を鳴らした。
「ここは、王太子殿下にお見せするには相応しい景色ではありません」
「……」
「俺が初めて人を殺したのは、十五の時だった。たぶん、兄上も似たようなものだろう?」
思い出したくもない、最初の殺しの記憶が、否応なく蘇る。
何度剣を振るい、何人もの命を奪ってきた今でも――初めて、掌に伝わったあの感触だけは、異様なほど鮮明だった。
顔に跳ねた、生温かい血。
喉を突く鉄の匂い。
相手は、王家の威光に刃向かった反逆者だった。
「たった一人の、こんな下劣な罪人を自分の手で裁けないようでは、王にはなれん」
そう言って、先王は容赦なく息子を突き放した。
王になるということは、守るために、躊躇なく奪う覚悟を持つこと。
その重みを、誰よりも早く叩き込まれたのが、王家の子どもたちだった。
地下牢に漂う腐臭の中で、マクシミリアンは静かに拳を握り締めた。
――あの日から、ここへ至るまで、決して楽な道ではなかったのだと、改めて思い知らされながら。
彼は、息子の手に自ら剣を握らせた。
平凡な家庭であれば残酷な教えと受け取られただろうが、王家においては、それは「愛情」と呼ばれていた。
殺せなければ、殺される。
その原始的な自然の摂理に、誰よりも強く縛られているのが、王族という存在ではないだろうか。
ライサンダーの場合、最初の殺しを命じたのは、ほかならぬ彼の母だった。
おそらく、それもまた愛から生まれた行為だったのだろう。
我が子が、王になることを誰よりも強く願っていたのだから。
マクシミリアンは、初めて罪人を斬り、血にまみれた手を洗おうと神殿を訪れた、かつてのライサンダーの姿を覚えていた。
何度も何度も手を洗い、それでも落ちない血の感触に耐えきれず、ついには冷たい水槽に身を沈め、頭まで水に浸したまま泣き崩れた、気弱な少年――。
マクシミリアンは、その少年を、夜明けまで黙って抱き続けたのだった。
「だからこそ、だ。」
ライサンダーは、口元を歪めながら、言葉を続けた。
幼い頃、「処刑」という言葉が話題に上るたび、周囲に浮かんでいたあの怯えた表情は、もはやどこにも見当たらなかった。
「そろそろ……末の王子にも、人を殺める覚悟が求められる頃合いだと思ってね」
「陛下、王子殿下は……我々とは、違うのではありませんか」
「違う、だと?――いいや、兄上。違わないさ」
ライサンダーは腰を上げると、そのまま床へと一歩踏み出した。
ぬかるんだ血溜まりを踏みしめる、嫌な音が地下牢に響く。
視線を落とすと、彼の靴底の下には、まだ温もりの残る小さな肉片が、無惨に潰されていた。
その瞬間、マクシミリアンは悟った。
彼らの罪――いや、“やらかしたこと”の正体を。
おそらく王家に関する、決して公にしてはならぬ噂話を、軽々しく口にしたのだろう。
だからこそ、捕らえられ、ここへ連れてこられた。
ライサンダーが彼らに施したのは、拷問ではない。
それは「裁き」ですらなかった。
――舌を切り落とす刑。
死してなお、魂が冥府で言葉を紡ぐことすら許さぬ、徹底した沈黙の儀式。
真実を“語れなくする”ための、王家特有の残酷な知恵。
地下牢に満ちる腐臭の中で、マクシミリアンは静かに息を吐いた。
恐怖は、とうに置き去りにしてきた。
残っているのは、王であるために背負うべき現実だけだ。
――そして、その現実を、次に突きつけられるのは。
間違いなく、あの幼い王子なのだろう。
「私たちとは違う。あの子は――兄上だからな。」
「…………」
マクシミリアンは答えなかった。
この場には、聞き耳を立てている者が多すぎる。
「ちょうど、彼らがバレンタインについて面白い話をしていてね。だからこの機会に、罪人を裁くというのがどういうことか、教えておこうと思って急ぎ呼び出したんだ。」
「……陛下。」
「これは、私一人の判断じゃない。最初に“それがよい”と言い出したのは、叔父上だ。」
レノクス侯爵――彼は大王妃アメルダの双子の兄である。
若くして侯爵位に就いた彼が、最初に行ったのは、特に功績もないまま王位に就いていた王に対し、自分の妹を後宮に迎えるよう進言したことだった。
双子という存在を警戒する王家の立場からすれば、拒むことも十分に可能だった。
だが、後ろ盾も財も持たない王を支える役目を担わされ、日々不満を募らせていた家臣たちの声に―ー王は、高貴なるレノックス家の令嬢を、喜んで妃として迎え入れた。
その結婚に異を唱える声が、まったくなかったわけではない。
だが、そもそも王家の血は、直系の子を多く残すことに執着しない。
双子を設けなかったところで、何が問題になるのか――その問いに、誰一人として明確な反論を用意できなかった。
先王が崩御してのち、彼は弟の権威を後ろ盾に、ときには王の前ですら「大人」の役を買って出るようになった。
「陛下は、バレンタイン殿下をたいそう可愛がっておられる。王家の一員なのに、あまりにも手厚く守りすぎではないかと、案じておられましたよ」
「…………」
「ああ、そうだ。彼らが何を囁いていたのか――兄上も、ご存じでなければなりませんよね?」
そう言うと彼は、かかとを持ち上げ、マクシミリアンの耳元へと顔を寄せ、唇を近づけた。
ライサンダーは、罪人たちが広めた噂の中身を、静かに囁く。
そして、意味深な笑みを浮かべると、何事もなかったかのように一歩引いた。
地下牢に残されたのは、言葉を奪われた者たちと、そして――真実を知る者だけが背負う、重く冷たい沈黙だった。
マクシミリアンは視線を伏せる。
王として、兄として。
そのどちらの立場も、もはや彼を楽にはしてくれない。
――王冠とは、選ばれた者に与えられる栄光であると同時に、決して逃れられぬ「責任」そのものなのだから。
「わかっているだろう、兄上。こういうことを口にする者たちをきちんと統制しなければ、尊厳などあっという間に地に落ちる。尊厳を失った王家が、どうなるかは――理解しているはずだ。」
尊厳とは、王族を守る鎧だ。
それを失えば、民衆に引きずり出され、無残に殺される。
だからこそ、殺しを教えるという王家の教育方針を、単純に「残酷だ」と切り捨てることはできなかった。
生き延びるために何をするか――それは人の本能なのだから。
「……だが。」
マクシミリアンは、バレンタインにそうした教えを与えることに、どうしても耐えられなかった。
王家の兄弟の中に、せめて一人くらいは――忌まわしい“初めての殺し”を経験せずに済む者がいても、よいのではないか。
マクシミリアンは、冷や汗を浮かべ、震えが止まらないバレンタインの肩を、さらに強く引き寄せて抱きしめた。
どれほど大きな衝撃を受けたのか、いつもとは違い、彼はマクシミリアンに完全に体を預けていた。
「私が、王子殿下を別宮へお連れします」
「それは困る」
「陛下……!」
「もしあの子が処刑を執行しなければ、この件をどう収めるつもりだ?外戚の顔を立てねばならなくなるのは、我らの母が誰よりも理解していただろう?」
その言葉は、いずれライサンダー自身が苦しむことになる――そう告げているに等しかった。
「処刑には、私が執行人を手配いたします」
「いや、ダメだ」
ライサンダーは、きっぱりと言い切った。
「ただの罪人ならともかく、こいつらは――俺の弟の尊厳に手を伸ばした連中だ。それを自分の手で裁けないようでは、王太子の面目が立たないだろう?」
静かな声だったが、そこに揺らぎはない。
逃げ道を、一つずつ塞ぐ言葉だった。
その瞬間、マクシミリアンは悟った。
彼が求めている答えを。
「……私が、やります」
そう告げた自分の声が、地下牢に重く落ちる。
それは決意であり、同時に、王家に生まれた者としての避けがたい役割の受諾でもあった。
ライサンダーは、その言葉を聞いて、ようやく満足そうに口角を上げた。
――王になるとは、選び続けることだ。
守るために、奪うことを。
そして、その責を、誰にも預けず、自らの手で背負うことを。
地下牢の冷たい空気の中で、マクシミリアンは静かに息を吸った。
もう、後戻りはできない。
それを聞いて、ライサンダーはわざとらしく目を見開いてみせた。
「本当か?」
「……はい。」
「まあ、少しずつ慣らしていくのも悪くはないだろう。最近は女色に夢中で、剣なんてほとんど握っていないと聞いたしな。」
ライサンダーは、軽い足取りでマクシミリアンのそばへと歩み寄った。
「いずれ、私の可愛い愛犬もここへ連れてくるつもりだからな。今のうちに練習しておいた方がいいだろう?」