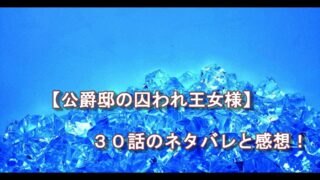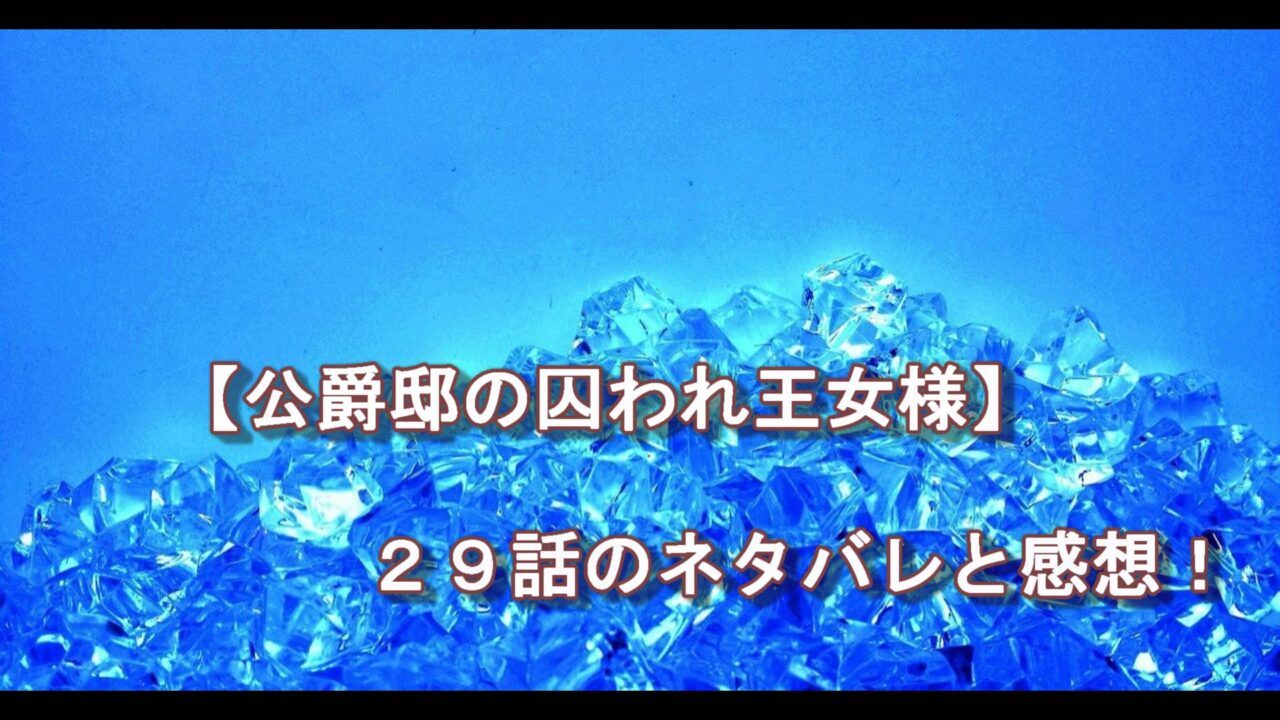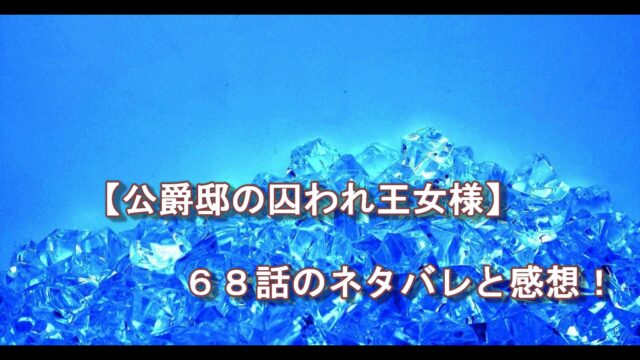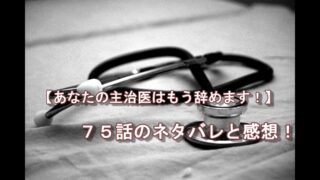こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
今回は29話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

29話 ネタバレ
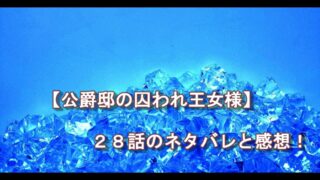
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- side マクシミリアン
マクシミリアンは先王の長子だった。
自然に彼はいつか王になる者として教育を受けてきた。
だが、彼の母親が急死し、王の2番目の夫人だった「アメルダ」が王妃になり、版図はあっという間に変わる。
その上、まもなく先王の死まで続くと、アメルダは裕頑な実家の影響力を利用して息子「ライサンダー」が王位を継ぐようにした。
一方、マクシミリアンは母方と呼ぶほどの家門自体がない状況で、そのまま後継者の席から押し出されることになった。
そして、マクシミリアンの婚約者がライサンダーとの婚姻を発表し、彼は本当にすべてを失うことになる。
伝統ある家門出身の婚約者は、彼に残っていた最後の救いだったはずだから。
しかし、マクシミリアンは一方的に婚約者を恨んだり、弟を憎悪したりする態度を見せなかった。
かえって二人の結婚式に自ら出席し、お祝いの言葉をかけたほどだ。
その余裕のある姿に、人々はマクシミリアンに何か他の希望があるのではないかと疑ってきた。
そのような噂は、大王妃のアメルダの不安を増大させた。
せっかく王になった息子が席を奪われるようなことがあってはならないから。
彼女はマクシミリアンをさらに墜落させる方法を思いつく。
北の不毛なシェリデンの領主に任命したのがその最初だった。
また、アメルダは息子を煽り、マクシミリアンを財産も力もないダーリントン伯爵家と婚姻させた。
この結婚にはマクシミリアンが何の対応もする暇もなかった。
王命で行われた婚姻だったのだから。
強制的に婚姻することになった夫婦は、シェリデンの初対面で、さっそくささやかな挙式を行うことに。
この席には驚くべきことにマクシミリアンの弟であるライサンダーが参加した。
彼は大王妃が止められることをあえて意地を張ってシェリデンまで訪ねてきたのだ。
「面白いね。貴族たちは王命がゲームにでもなると思っているようだね?」
ライサンダーは一目で花嫁が変わったことを知って、結婚式後にマクシミリアンの執務室に訪ねてきて怒りを吐き出した。
以前、側近を通じてアセラ・ダーリントンの肖像を探して調べたことがあるから可能なことだった。
「どこかで結構似たような女にうまく変えてきたみたいだ」
「似ていますか?」
「伯爵がどこか外で生んできた雑種だろう。あんな優雅な銀髪が平民の間では珍しいんだから」
ライサンダーは伸びをしながら長いソファに両足を乗せて横になる。
「王命はかなり馬鹿げているようだ。これは、ちゃんとお返しを用意しないと困るね」
あえて王家を騒そうとしたのだから、本来なら伯爵の名誉を捨てなけれはならないのはもちろん、死刑に処することもできた。
「お兄さんはどうしたいの?」
彼の質問にマクシミリアンはしばらく悩んでいた。
いつも正しさを追求する彼に来た「偽の花嫁」とは。
実際、答えは決まっていた。
しかし、マクシミリアンはどうしても伯爵を罰しようとは言えなかった。
最初からこの婚姻自体があまり望ましいものではなかったのだから。
さらに、「マクシミリアンの立場を狭める」というアメルダ大王妃の目的を考えれば、ニセ花嫁の存在はむしろ役に立つほどだった。
マクシミリアンはこれ以上、大王妃の境界に入ることを望まなかった。
「殿下の許可があれば、このままでも構いません」
「え?」
彼の答えが意外だったのだろうか、ライサンダーは立ち上がって尋ねる。
「お兄さんみたいな王子様が・・・雑種と結婚するって!?」
「厳密に言えば、すでに結婚式は行われています」
「はっ!」
ライサンダーは理解できないという目でマシミリアンを見た。
「私の兄さんは怒り方を忘れたりしたの!?それとも、高貴な純血王子は雑種たちに特に寛大な趣味でもあるのか!?」
「・・・」
マクシミリアンは沈黙を守った。
幸い、ライサンダーは彼をこれ以上追及しなかった。
「・・・勝手にして」
「ありがとうございます」
そしてライサンダーは、シェリデンに留まらず、すぐに去ってしまった。
マクシミリアンの中途半端な態度に嫌気がさしたように。
そのように始まった結婚生活で、マクシミリアンは自分の花嫁である「偽アセラ」にあまり関心を持たないことにした。
ここの生活が彼女には監獄に他ならないはずなのに、あえて彼が苦痛を加える必要はないのではないか。
彼の無関心な態度にもかかわらず、彼女はこの寒い土地でなんとか根を下ろしているように見えた。
すぐに使用人をよく統率し、騎士の間でも良い評判を維持した。
マクシミリアンは身分は偽物だが、彼女はいい人に違いないと思った。
だからいつかは必ず彼女を自由にしてあげると決心した。
一緒に夜を過ごさないのも、その思いのためだ。
お互いに体を交えていないことを証言すれば、この婚姻は存在すらしていないことにできる。
そうなれば、いつか彼女もいい男と新しく始められるはずだから。
この考えは今まで変わりがなかった。
・・・そのはずだったのに。
マクシミリアンは自分の前に座って絵を描いていたクラリスを思い出した。
子供は白い紙の左側に彼の顔を描いて「終わりました」と差し出す。
彼は絵でぎっしり詰まった左側と比較的暇な右側を交互に眺めていて、一つ心配になった。
視力に困難がある子供の場合、このように片方に絵が偏るようになるという話を思い出したのだ。
彼は慎重に疑問を呈した。
「絵が片方だけ満たされたのはどういう意図なんだ?」
「分かってもらえて嬉しいです」
クラリスが満面の笑みで答えるのを見ると、意図された構図のようでマクシミリアンは安堵する。
「ここはですね」
子供は真っ白な右側を手のひらでこすりながら恥ずかしそうに笑った。
「公爵夫人の席です」
「・・・」
「公爵様と公爵夫人はお互いにお好きですよね?」
マクシミリアンはしばらく悩んだが、すぐにうなずいた。
先日の晩餐会の時に交わした話を思い出してみると、他に言うこともできなかった。
「だから並んで描いてあげたかったんです。公爵様の隣は奥様の席ですから」
「そうかな」
「もちろんです!奥様の隣の席は一生公爵様です!」
いや、そうではないだろう。
マクシミリアンは反射的にそう思いながらも、なぜかクラリスの話が不便ではなかった。
いや、むしろ・・・。
聞き心地がよかった。
彼女が自分のそばに一生存在するだろうという・・・小説のような言葉が。
実におかしなことではないだろうか。
見送るべき人を相手にこんな・・・こんな酷い所有欲を抱くのは。
「所有・・・欲」
マクシミリアンは自分の感情の名前を不快に繰り返した。
彼はやっと一つの事実に気づく。
彼女がどうして彼をそれほど難しがり、不便に思うのか。
賢明な彼女は自分の心にこのような悪いものがあると気づいたのだろう。
敢えて人間を所有しようとする汚い欲求に微笑んでくれる相手はいないだろうから。
だからマクシミリアンはなんとか自分の不細工な気持ちを彼女に表に出してはいけないと思った。
・・・本当にそうするつもりだったのに。
「これでもお前の偽母が命でも持ち堪えることができると思う?私が父に連絡して、すぐに殺してしまえと言うよ!」
「お前は女中の娘・・・いや、それでも実の娘でもないじゃないか?森に捨てられたくせに!この事実を知っていながらも公爵があなたをこの場に置くと思う?」
ただでさえ怪しい招かざる客が、その本音を底までさらけ出す瞬間。
彼は紳士の礼儀も忘れて彼女の髪をつかみそうになった。
そうしなかったのは、このような瞬間にもその無礼な人を残念な覗線で眺める妻の視線のためだ。
あんな人がどこがかわいそうで、そんなに残念そうに眺めるのか。
幸い、招かれざる客を処断することはそれほど難しくなかった。
そもそもこの婚姻は王が許可したものだから、相手が何と言おうと憚ることは少しもない。
むしろ彼の困難は事件後に発生した。
「それとも・・・誰でもいいのですか?」
こう尋ねるブリエルの言葉に、彼は何と答えたらいいか分からなかったから。
率直に言えば彼女の言うとおりだ。
誰でも構わなかった。
偉大な王妃アメルダはマクシミリアンの疑いを捨て、それ以上は甘やかされていない
しかし・・・。
しかし自分を見つめる美しいお嬢さんにどうしてもそのように答えたくはなかった。
何よりも彼女ががっかりして涙を流す姿を見たくなかった。
「誰でもよかったのは・・・決してありませんでした」
すぐに飛び出した言葉は完璧な嘘。
彼は自分がこんなに嘘がうまいとは知らなかった。
これでは詐欺師は自分の方ではないか。
いや、実際にそうだった。
彼女が身分を隠していることを知っていながら、長い間口をつぐんでいなかったのか。
「そもそも騙されたたことはないから。むしろ私があなたを騙したことに対して許しを請いたいです」
彼はすぐにこれについて謝罪を求めた。
するとすぐに彼女が泣き出した。
なぜか深い「安堵」が混ざっているような泣き声なので、マクシミリアンは思わずある期待感を抱いてしまう。
「もしかすると・・・彼女もシェリデンで過ごすのがそこまで嫌ではなかったのか?」と。
そのような考えが浮かぶと、長い間大事にしていた疑問が自然に出てきた。
「あなたの名前を聞きたかったです」
一人でも十分に調べられると同時に今までそうしなかったのは、きっと彼女の口から聞きたかったからかもしれない。
しばらくハンカチに顔をつけていたブリエルは顔を上げた。
少し赤くなった目元がどうして可愛く見えるのか、彼が涙で汚れた顔から視線を離すことができない時。
ついに彼女が答えを聞かせてくれた。
「ブリエルです」
「・・・」
「ブリエル・・・ウッズ。平凡でしょう?お嬢さんが私の名前をつける時は、本当に驚きました」
「いいえ」
マクシミリアンは首を横に振る。
「ブリエル・ウッズではありません」
「はい・・・?」
ブリエルはすすり泣きながら頭を上げた。
「ブリエル・・・シェリデン」
マクシミリアンは一瞬の欲望で、彼女の名前に冷たい冬の城の名前を足かせのようにつけた。
純粋な彼女は、これがどれほど恐ろしい所有欲から生まれた言葉なのかも知らないようだった。
そうでなければ・・・。
「私の名前がそう呼ばれると不思議です」
こんなにも日差しのように笑うことはできないはずだから。
マクシミリアンの人生が壮絶でした・・・。
ライサンダーとの関係はそれほど悪くない?
ブリエルが自分の本当の名前を告げることができて良かったです!
これも全て、クラリスの頑張りのおかげですね。