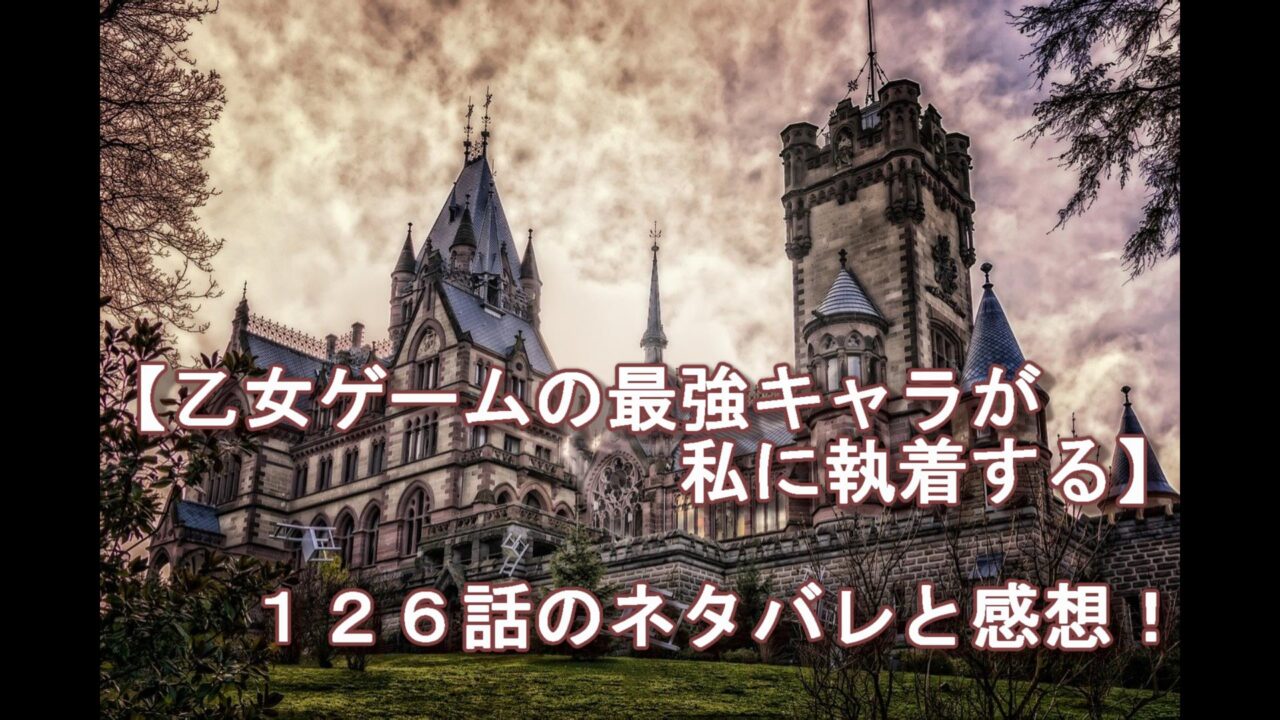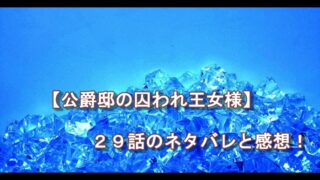こんにちは、ちゃむです。
「乙女ゲームの最強キャラたちが私に執着する」を紹介させていただきます。
今回は126話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

126話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- side アセラス
アセラスはいつもこの帝国が燃える姿を見たかった。.
「いつからそうだったのか」という質問は意味がない。
生まれた時から彼には母親がいなかった。
旅館の主人の話では、馬小屋で彼を産み、すぐに死んだという。
いつも嘘ばかり並べ立てる者だったので、信じることはできなかった。
彼は自分がどこで生まれたのか分からず、どこから来たのかも知らなかった。
超越者であることも10歳の時、早い開花を屋根裏部屋の隅で一人でうずくまってから知った。
彼は時々、まだ自分はあの屋根裏部屋にいて、この世は全て10歳の彼が見る夢であり、自分は永遠に終わらない開花の中に留まっているのかもしれないと考える。
力を使えば、苦痛とともに幻聴が訪れる。
その声は10歳の時に彼に言ったのと同じことを言い続けた。
一つの命令だった。
くフレドリックを燃やせ!>
そうだ。
彼はことごとく燃やすだろう。
彼はそれがいつも自分が生まれた意味でもあるように感じた。
誰かに認められるため、誰かを得るためというのは、すべて付随的な理由に過ぎない。
ダリア・ペステローズを望む理由も単純だった。
自分が狂う前に魂を浄化して計画を成功に導くこと。
しかし、実に奇妙なことが起こる。
通りで偶然ダリア・ペステローズに会ってから、彼は何度も混乱し、ためらいがちになった。
すべてのものが混ざっていく。
あってはならない人がその場にいるようで、この場にいなかった人ができた気分。
変だ、すべてが初めて経験することなのに、前とは違うという違和感がしきりに感じられる。
しかし、それで彼は彼女にもう一度会いたかった。
彼女をもう一度見て確認したかった。
本当に何かずれているのか。
それを確認したとしても、何も変わることはないだろうが。
「ケルシオンが裏切ったね」
ケルシオンとアルゲルはとりわけ親しかったのだから、アルゲルはケルシオンに騙されたのだろう。
彼が隠していた1つの計画が再び水の泡となった。
しかし、アセラスは驚きも慌てもしなかった。
これもまた無数の可能性の一つに過ぎない。
皇后を洗脳することに失敗した時から、アセラスはこの結末を予想した。
そのため、ケルシオンが素直に思い通りに行動してくれたのは、むしろ自分の計画に予測しやすい変数一つを加えたことに過ぎない。
しかし、アセラスは危険を冒してペステローズ邸に向かう自分だけは本当に理解できなかった。
「あはは・・・」
邸宅警備の厳しい見回りを避けて入ったペステローズ邸後苑で、アセラスは笑い声を聞く。
ダリアの声だった。
彼女は本当に幸せそうに嬉しそうに笑い出していた。
アセラスは思わず頭を上げてその声を追う。
窓を開けて外に身を乗り出したダリアは、本当に明るい笑みを浮かべていた。
そして、その向かい側には窓枠をつかんで宙に浮いたまま話しているセドリック・ベルシェローナ・ミケリオがいた。
彼は自然にダリアの手を握って何か言い、彼女は振り切る代わりにいたずらにくすくす笑っている。
誰が見ても恋人になったばかりの、あるいはその直前の姿だった。
「そうか。二人が恋人という話は聞いてないんだけど」
アセラスは胸の中が熱くなるのを感じた。
そしてしばらくして、その感覚が嫉妬心から始まったということに気づく。
「私がどうしてあの女のせいでこんな感情を?」
彼は胸をなでおろした。
おかしかった。
感情とかはもう完全に失くしたと思ったのに。
自分を見ながらにっこり笑っていたダリアの笑顔がまだ消えず、頭のどこかにくっついているのが明らかだ。
「・・・彼女は特別なのか、調べる価値がある」
ますます狂気に流されるこの魂を浄化するためにも、彼はダリア・ペステローズをこの手に入れる義務があった。
それならセドリック・ベルシェローナ・ミケリオ、ダリアの恋人はここでこの上ない妨害要素になるだろう。
「どうせ、薬をまた使うには、彼がいなくならないといけないんだ」
これは絶対に嫉妬心のためではない。
ただ理性的な決定にすぎない。
そう合理化し、アセラスは自分の次の道を決めた。
そして、ペステローズ邸の後苑を静かに離れる。
フレデリック帝国に再び春が訪れた。
その年の秋と冬は本当にいろいろなことがあった。
その中で最も不思議なことは、4大公爵家の一つであるアルトス公爵家の世代交代。
一時、代々途絶えていた私生児出身の超越者が現れ、公爵位を継いだのだ。
先代のアルトス公爵は、彼が爵位を継ぐやいなや、突然持病が悪化して死んでしまった。
人々は、私生児が公爵位を占めたのがお腹が痛くて火病で死んだのではないかとひそひそと話す。
私生児を粗末に扱っていた公爵家の一員たちは皆入れ替えられた。
たった一人、メリダ・アルトス以外。
しばらくの間、アルトス家の勢いが尋常ではなかった。
しかし、新しい公爵は超越者らしく非常にハンサムな青年であり、私生児というには信じられないほど立派な話術と能力を備えている。
おかげでアルトス家は一度試練を乗り越えて再び立派に根を下ろしていた。
こうなって一番得をしたのはメリダ・アルトスだ。
最初は彼女がコウモリのようだと非難するしていた人々も、現アルトス公爵が家門の勢力を育てるのを見ると、彼女がやはり卓越した政治的感覚があると褒め称えた。
今春にはフレデリック帝国と神聖帝国の間のダービー・ガトラン条約が更新される。
ダービー・ガトラン条約は神聖帝国とフレデリック帝国との間の条約で、神聖力に弱いモンスターがよく出没するガトラン山を神聖帝国が管理する代わりに、毎年巨大クラーケンが出没するダービー海域をフレデリック帝国が独自の音波技術で保護する条約だ。
もし今回の条約が破られれば、ダーピー山脈のモンスターウェーブを防ぐために少なくとも一つの超越者をそこに派遣しなければならない。
そこのモンスターウェーブは、一般的な剣と銃で防げるレベルではなかったから。
しかし、この条約の更新があまり残っていないことを知っている人はごくまれだった。
あまりにも古い条約だったし、普通条件調整なしに更新し続けてきた条約だから。
しかし、今度は違うだろう。
ブルーポート領地の屋敷の噴水で目をつぶって水を浴びながら修練しているダン・ルウェイン・ブルーポートは考えた。
彼は原作の最後の男性主人公。
一番トウルーエンディングに近いルート保有者であり、3人の男性主人公の中で最も純粋な恋をした人でもあった。
ファンも最も多かった。
執着と疲弊を基盤にした話で、唯一騎士らしい騎士、紳士、多情、そのようなキーワードがついていた人物だったためだ。
金髪の青い目、童話の中の王子様のような外見のおかげでもある。
しかし、彼は今噴水の水を浴びていた。
先代ブルーポート公爵、メアリー・ブルーポートがその姿を見るやいなや邸宅から飛び出した。
「ルウェイン!お願いだから中に入るなって言ったじゃない!」
すると、ルウェインはゆっくりと目を開ける。
そして、濡れた髪を越えて、水に濡れてくっついて中が透けて見えるワイシャツとズボン姿で母親の方を振り返った。
彼の目にしばらく異彩が浮かんだ。
「・・・ああ、お母さん。生きていらっしゃったんですね」
「・・・じゃあ、死ぬことでも望んだということなの?いったいあなたという子は・・・私がダリアちゃんに半分だけ似ろとそのように口がすり減るほど・・・」
優雅で優しいメアリー・ブルーポート公爵だったが、この息子の奇行には限りなく小言が増えざるを得なかった。
ルウェインがまだ首都に一度も行ったことがないのが、人々は皆領地で海を守るのに忙しいからだと信じた。
しかし、現実は違う。
メアリー・ブルーポートが息子をこの状態で到底どこかに行かせたくなかったためだった。
むしろ仕事でもできなければ、他の人に公爵位でも渡したいほどだ。
預言者のように「できないことは、ちょうどだめだ」とし、「うまくいくことは、ちょうどうまくいくだろう」と指摘し、領地の発展を先鋒で導いた。
しかし、彼が繰り広げる奇妙な行動は深刻だ。
誰よりも正しい礼法を駆使しながら、一方では食事中の食卓に平然と魔手の死体を乗せて手入れする。
話の最中にいきなり今年度と月を間いたり、病気になったこともなく元気に生きている人に「まだ生きていたのか」と言って喧嘩を起こしたり。
そんな彼を首都に行かせるのが怖くてずっと先延ばしにすると憎かったが、永遠に先送りすることはできない。
今回のダービー・ガトラン条約に問題が生じ、関連技術を保有したブルーポート公爵家も交渉に参加しなければならなかった。
おかげでメアリー・ブルーポートの小言がさらに増えた。
「もうすぐ首都に行くのに、どうするの!」
「ああ、あの条約」
ルウェインは水が入り、曇った目をこすりながら一歩ずつ噴水から出てきた。
彼の後ろに水がぽたぽたと落ちる。
「その条約は破棄されるでしょう。アセラスはこの帝国をすべて壊すことを望んでいるんです」
メアリーは息子が不明なことを言うたびに少し呆然とした。
彼の目つきにその度に微細な狂気が宿るためだ。
そしてあの断定的な態度。
「・・・まるで未来でも見通したように言うね。それは傲慢だよ」
「傲慢ではありません。実際に見たから」
メアリー・ブルーポートは口をつぐんだ。
メルデン・アルトスの現在のアルトス公爵が租父と同じ特性を持っているように、家ごとによく遺伝する超越定規の特性ないしは形質がある。
ブルーポート公爵家の場合は、時間を操る力だった。
息子があんなことを言うたびに、メアリーはその力が本当に初代の伝説に出てくる話ではなく、実在するかもしれないという考えをした。
彼女は息子が通った跡ごとにぽたぽたと残った水の跡を見てため息をつく。
たぶんあのまま邸宅の室内に堂々と入るだろう。
そうすれば、下女たちが目の保養としてモップの袋を持って競争するように、息子の後について行きながら水を拭いてあげるだろう。
「・・・首都に上がったらダリアさんに会って挨拶しなさい」
「お母さまがおっしゃらなくても、そうするでしょう」
ルウェイン・ブルーポートは堂々と空を見上げた。
「ダリア・ペステローズ」
彼は本気で、本気で彼女に早く会いたかった。
アセラスの行動が不穏ですね。
そして、いよいよ登場したルウェイン。
彼はかなり癖のある人物のようです。