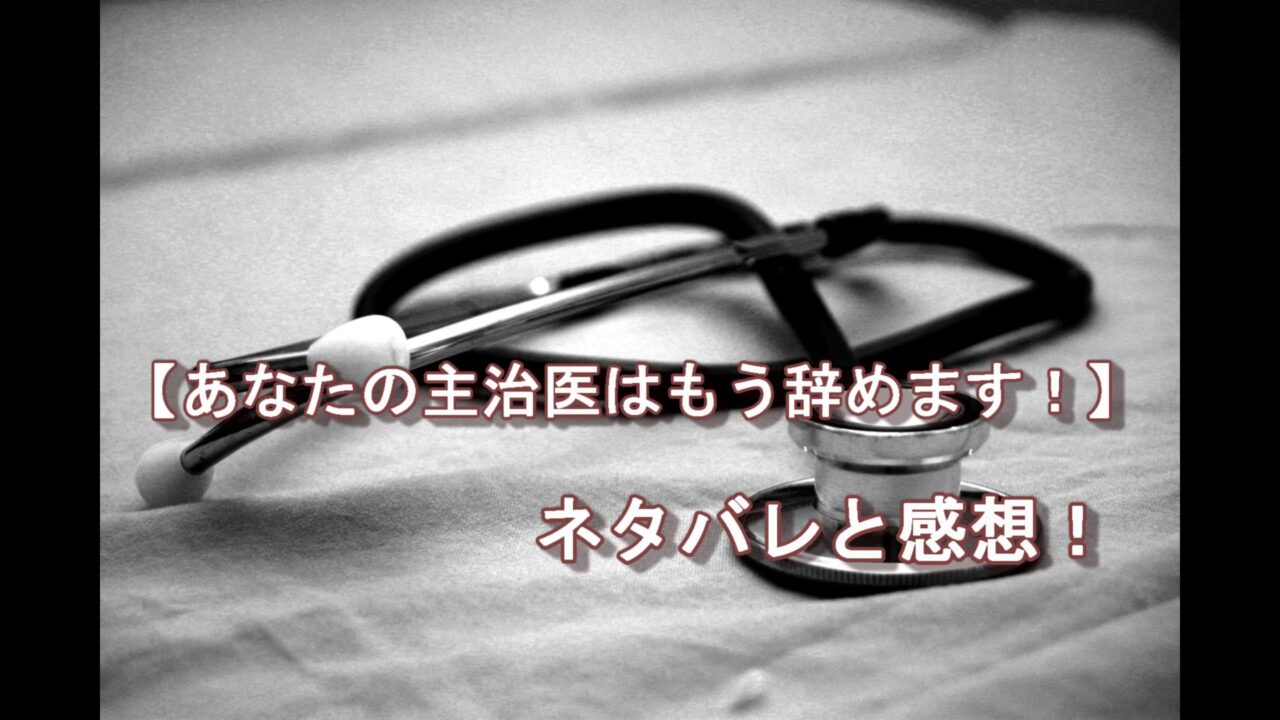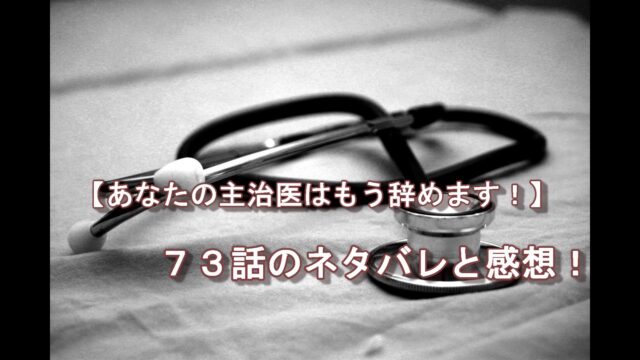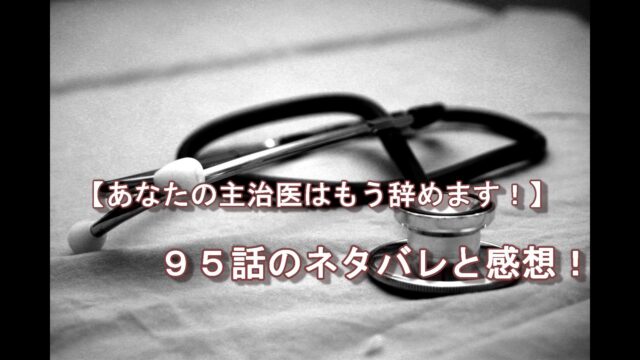こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
今回は116話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

116話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 家族として
慎重に馬車から降りると、私を待っているフェリクス卿が目に入った。
「リチェ・・・」
老人の声が震えながら響いた。
「・・・気づかずにいて、本当に申し訳ない。」
予想外の最初の言葉に私は驚いた。
申し訳なさそうに涙を拭っている彼の顔には、どこかしら寂しげな表情が浮かんでいる。
彼の脚は震え、バランスを崩しそうになっていた。
私は急いでフェリクス卿を支えた。
「最初に君がここに来たとき、疑いを持ってしまって申し訳ない。」
「何もない平民の女の子が珍しい魔法アイテムを持っているなんて、疑われても当然ですよ。」
私は軽く笑いながらそう答えたが、知らず知らずのうちにため息が混じってしまった。
彼がそんなことを思っていたなんて一度も想像していなかった。
それを聞いた瞬間、心が少し痛んだ。
同時に、私自身も独りよがりな考えに浸っていたのではないかと思い知らされる。
お互いが大切すぎて、自分にはその価値がないと勝手に思い込んでいたようだ。
何もかもがうまくいかないように思えることが悪いだけでなく、それ以上に、漠然とした不安感が胸に渦巻いていた。
目の前の表情はきっと、私が抱いていた疑問や混乱そのものを映し出していたに違いない。
「アルガが言っていたよ。君はとても遠慮深い性格だって。」
「え?」
「ぎこちなくて、自分を避けようとしているようだってね。『お父さん』と呼んでほしいだけなのに、いつも『伯爵様』と呼ぶからって。」
「あ、それは・・・」
私は居心地悪そうにしながら、髪を耳の後ろにかき上げる。
自分の口で説明するのはとても難しく、言葉を選びながらも結局正直に話すしかなかった。
余計な誤解を生まないように、思い切って事情を説明するしかないと心に決めた。
申し訳なさそうなフェリックス長老の様子。
「私のせいでシオニー様がうまくいかないように思えて・・・。本当に多くの人々に愛されている方なのに、私が生まれてきたばかりに・・・」
そう思っただけで涙が出そうになり、私は必死に目に力を入れて涙をこらえる。
「皆、私を疎ましく思っているのではないかと・・・」
「なんということだ、子供よ。」
フェリックス長老は私の手を取って、深い声で語りかけた。
まるで想像すらしていなかったというような表情で、深いため息をつきながら彼は私の肩を軽く叩いた。
「どうしてそんなことを考えられるのか。」
私は一度も「子供」と呼ばれたことがなかった。
招待状を受け取った時、すでに予感はしていた。
それでも胸がドキリと鳴り、緊張してしまった。
「私たちは皆、君をとても長い間待っていたのだよ。」
その一言で、それまで心の中に積み上げられていた不安が、氷が溶けるように消えていくのを感じた。
フェリックス長老の目にも、私の目にも、自然と涙が滲んでいた。
「長老、大理石の道は膝にはよくないのでは・・・。」
「いや。」
彼は毅然とした口調で言った。
「一緒に歩きたいのだ。」
邸宅へと続く一直線の大理石の道を、二人で並んで歩き始める。
その道を歩む私の足元も、震え始めていた。
私が生まれる前からずっと私を待っていたというこの道を歩く感覚は、とても不思議な気持ちだった。
そしてその道を囲む真っ白なラベリ島の観賞用樹木もまた、新たな意味を持って私に迫ってきた。
「リチェ!」
大理石の道をすべて歩き終えたとき、邸宅の扉が開き、セイリンの光景が広がった。
「シオニが一番好きだった花なのよ。黄色い花が好きだったんだ。」
彼女は私に黄色のフリージアの花束を手渡した。
「本当にごめんなさい・・・。気づけなくて、最初に伝えるべきだったのに。」
胸を刺すような濃い花の香りに包まれると、またしても涙があふれてきた。
「本当にごめんなさい。あなたが気づいてこの家に来てくれたのに。」
「常識的に考えて気づけるわけがないじゃないですか。私のせいで・・・そのせいでシオニー様が亡くなったような気がして・・・」
「シオニー様だなんて、リチェ。」
セイリンが私の頬をそっと触れながら、悲しげに言った。
「お母さんだよ。」
その言葉に、私の頬を涙がぽろぽろと流れ始める。
申し訳なくて、馬車の中でも「お母さん」と呼ぶことができなかった。
私は顔をまともに見ることができず、バスケットに緑のリボンで飾られた整った顔立ちの女性の緑色の瞳が、明らかに私に似ていることに気づいた。
小柄で丸みを帯びた顔立ちまで、私は彼女に似ていた。
「それに私は・・・私は叔母だよ。」
「あ・・・。」
「叔母って呼んでくれないかい? まだ許してくれない? アルガのような奴にだって、堂々とお父さんと呼べるのに。」
「許しますよ。最初はそんなことを考えもしなかったんです。」
私たちの会話に割り込むように、横に立っていたフェリクス老人が静かに言った。
「さっき、私のことも老人って呼んでたよね・・・。」
私は深呼吸をして、はっきりと言った。
「おじいさま、叔母さま。迎えてくださってありがとうございます。」
一度も呼ばれたことのない呼び名で、少し照れくさかったが、お互いにそれを望んでいた瞬間だった。
「遅れてごめんなさい。」
その言葉が終わるや否や、私たち三人は黙って抱き合い、涙を流した。
初めてこの屋敷に足を踏み入れた時から、自分の部屋ができるまで、一連の出来事があっという間に過ぎ去った。
私たちの周りをうろうろしていた屋敷の使用人たちも、次々と離れて席を空けてくれた。
「アルガは・・・あの様子を見るのが怖いらしく、シオニー様の墓に行っている。」
それでも姿が見えずに気を遣っていたところだった。
「君がまた視線を逸らしてぎこちなく接するんじゃないか、自分を見失って絶望してしまうんじゃないかと怖かったんだ。あんなに長い間探して、迷いながらも切実に求めていたというのに・・・」
「私と似てますね。」
私は目頭が熱くなりながらも、少し微笑んだ。
「私も同じように怯えてどうしたらいいのかわからなかったんです。」
たぶん似たような行動をしていたのは、きっと彼から受け継いだものだろう。
「・・・お母さんのお墓に行きたいです。」
一度も行ったことのなかった、名前も知らずに森の中で発見された遺体が埋められているお母さんの墓。