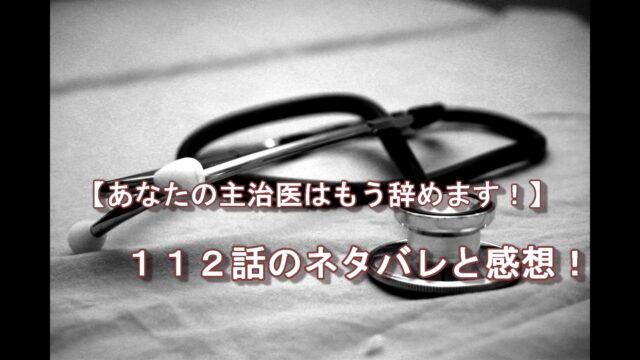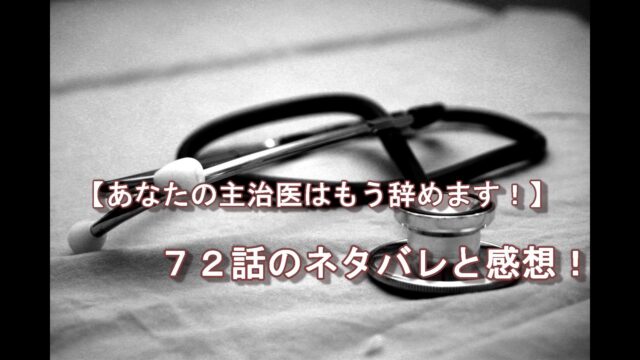こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

135話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 皇室裁判⑥
「やたらと静かで狂った人間じゃなかった……。」
セイリンが何を言っていようと、アルガがどんなに強い言葉を投げかけていようと、周囲がどれだけ騒然としていようと、動揺するエレナの同行者は冷静にリチェに向かって動いていた。
「家族と大切な時間を過ごしてね、リチェ。」
この血を注入すれば、彼は別の意味でしばらく混乱し、正気を保てなくなるだろう。
毒性は強いが、1級毒物とは性質が異なるため、最初から最後まで研究して解毒しなければならないからだ。
「長い間、見守ってきたんじゃないか。」
当然のことだが、エルアンはアルガのためではなく、リチェのために救助を行ったのだった。
家族の中で困惑した表情を浮かべるリチェを見たエルアンは、躊躇なく自分をリチェの優先順位の後ろに置いた。
アルガを攻撃しようとするハエルドンの動きを察知した瞬間、自分が錯乱状態に陥り正気を保てなくなることがアルガの死よりもリチェにとって負担になると判断したのだった。
「君が望むことなら、何でもしてあげたい。」
エルアンが穏やかに微笑みながら話す間、リチェは彼の腕に注射器を刺し、アルガのE型の血液を注入する。
そして彼女はその短い瞬間に多くの考えがよぎった。
彼に家族と時間をしっかり過ごしてほしいと言いながらも、彼のデートの誘いにはまったく応じなかった。
彼が近づいてくるのはいつも自然なことであり、彼女はただそれに応えればいいと考えていた。
かつて彼が幼くて病気がちだった頃には、安定した呼吸音すら愛おしく思ったものだが、いつの間にか健康な彼を当たり前の存在と感じるようになっていた。
ディエルと彼が交わした会話を耳にしたとき、もっと上手く付き合えればよかったと思った。
彼女は考えるよりも心配ばかりしているような気がして、本当にもう少し注意を向けようと考えたのだ。
何があっても、リチェにとっては家族が自分よりも大切だと語ったあの力強い声が思い出され、彼女の目には涙が浮かんだ。
そのため、彼女の優先順位が当然ながら下であることを自覚し、危険を顧みずに駆け寄ったのだった。
(また同じ間違いを犯したのかもしれない、今回も……。)
以前、牢に閉じ込められ死にかけた時、家族がどれほど必要かさえ考えもしなかった。
今回はエルアンが本当に自分にとって大切な存在だということを、きちんと認識していなかった。
いつもそばにいるものだと思い込んでいた。
彼女の腕の中で、彼が再び無事でいられるように祈りながら、彼が幼かった頃、彼を看病しながら過ごした多くの夜のことを思い出した。
あの夜たちが走馬灯のように流れていった。
リチェは注射器の針を抜き、アルコールを布でしっかり押さえつけ、自分の感情まで押し殺して静かに言った。
「信じてください、エルアン様。私がどうにかして必ず目を覚まさせますから。私の言葉を聞いてください。」
幼い頃、彼が苦しんでいた時に見守っていたその記憶が鮮明に蘇った。
エルアンはかすかに笑いながら、アルガの手をそっと握り、その手を優しくさすった。
「うん、リチェが言うなら信じるよ。」
リチェは周囲のざわめきには構わず、幼い頃に眠る彼を見守っていた頃のように、エルアンの手を握りしめ、その閉じかけた瞳の動きをじっと見守り続けた。
エルアンの目はゆっくりと閉じられた。
体調の異変を感じた時から、アルガに長時間説明を聞いていた彼女は、今回、エルアンが再び目を開けない可能性があることを理解していた。
「大丈夫だよ。」
しかし、幼い頃のようにもう目を開けられなくなるかもしれないその長い闇が、彼にとっては怖いものではなかった。
「目を閉じていても、君が見えるから。」
リチェのエメラルド色の瞳に静かに涙が溜まった。
「だから、いつからか暗闇が怖くなくなったんだよ。」
アルガはエルアンのもう片方の手を握りしめ、必死に彼の生命の鼓動を確認していた。
失神し意識を失ったエルアンの姿を見て、リチェは静かに泣き始めた。
原因さえ分かればきっと治せると分かっているのに、目の前で無防備に横たわるエルアンの姿が彼女の心を締め付けた。
そして、その表情を見つめながらアルガは深い決意を抱いた。
リチェのそばで、エルアンは決して許せないと思っていたが、それでもリチェがあのような表情を見せるのはもっと許せなかった。
ついさっき冷たくなった娘の顔を見た瞬間、彼はようやく娘が望むならエルアンのような者も受け入れるしかないと悟った。
「泣くな。」
アルガはエルアンの呼吸を確認しながら、リチェにそう告げた。
「この人間をあの忌まわしい毒から救ったんだ。E型の血液がもう一つ増えたからといって、それを解毒できないはずがない。」
「その通りです……。」
リチェは声を上げて泣くこともなく、ただ涙をぽろぽろと流しながら、自分自身に言い聞かせるように答えた。
「私がどうにかして助けますよ。もっと難しい解毒もやってみせます。」
アルガは苛立ち気味にエルアンの顔を見つめて息をついた。
「結局、俺にこんな言葉を言わせるのか。やはり執念深いセルイヤーズだ。本当にしつこい性格だよな。俺が子どもの頃から嫌いだった理由がこれだ。」
ケイロンもイサベルも、結局自分の望むものを手に入れるためには何でもするタイプの人間だった。
満足できる結果を得ることができない自分が、いつまでもその家門の意のままに動く存在であったのだろうか。
彼は歯を食いしばりながら一言吐き捨てた。
「本当に嫌でたまらないが、一度だけデートくらいしてやるから起きろ。お前が俺を助けてもらったからといって、こんなことをするつもりはない。」
久しぶりに開かれた王宮の裁判は、なぜ裁判が開かれたのかも忘れられるほど、多くの話題を残して幕を閉じた。
首都のすべての貴族たちは、反乱軍の背後関係について知ることとなった。
フェレルマン家がその娘の健康を理由にセルイヤーズ公爵を説得し、彼の体を犠牲にしてフェレルマン家の娘を助け、その後放り出したという話が長い間語られた。
当然ながら、ジェイドの脳の健康については公式の場で一切触れられなかった。