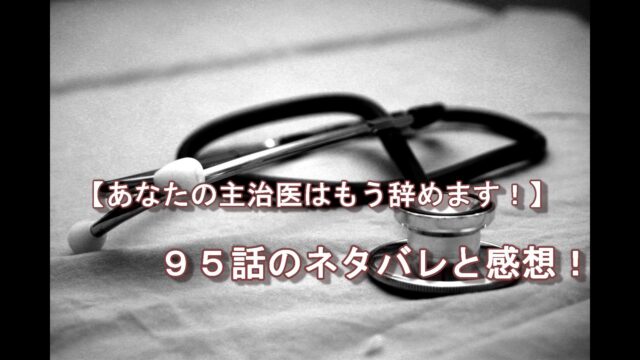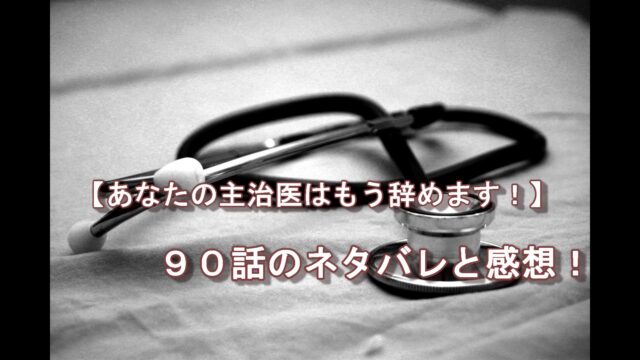こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

136話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 皇室裁判⑦
すべての出来事は私が計画した通りに無事に終わったものの…意識を失ったエルアンを見つめていると、全く喜びが湧いてこなかった。
患者を移送するには、できるだけ負担をかけない方が良いと判断し、父はその場で首都に小さな住宅を購入した。
「首都に家が一つあれば便利だろうし、公爵の治療にはかなりの時間がかかりそうだからな。これが良い機会だ。」
こうして私と叔母、父、そしてディエルは、意識を失ったエルアンと共に、しばらくの間首都で生活することに決めた。
父のE型血液を最速で投与したおかげで、エルアンが永遠に昏睡状態から目覚めないという最悪の事態には至らなかった。
脳への深刻な損傷も免れたため、現在のように段階的に治療を進めていけば、いずれ回復できる見込みがあった。
しかし、発病から応急処置に至るまで、すべてが初めての試みだったため、治療は一から十まで新しい挑戦だった。
私はイザベル様に状況を説明しながら、患者を移送するのはできるだけ負担を減らす方が良いので、しばらく首都で彼を世話したいと手紙をディエルに託した。
自分が天才だというのは否定しようのない事実だ。
エルアンの体で暴れていた魔力は徐々に安定し始めた。
このまま辛抱強く寄り添いながら治療を続ければ、確実に彼は立ち直れるだろうと確信していた。
気温の変化によって一度大きく倒れたことで、一度かかった病気に対する免疫力が高まるように、これからはさらに頑丈な身体を手に入れるはずだ。
既知の症状に対して既知の毒ならば治療は可能だという確信があったが、エルアンが倒れた時は胸が締め付けられる思いだった。
大切な人を失いそうな感覚を知ったからこそ、これからはより一層慎重に医学に取り組めるだろうと思った。
首都と公爵領は遠くなかったため、手紙を送ってからすぐにイザベル様のお部屋へ通されることになった。
「お嬢様、セルイヤーズ公爵領からお客様がお越しです。イザベル様です。」
エルアンに輸液を投与しているところに、侍女が入ってきて告げた。
「はい、準備いたします。」
当然ながら、イザベル様は息子であるエルアンの様子を見たがっているはずなので、応接室で父と少し話をした後、すぐにこちらに案内するよう指示を出した。
わずかな解毒作用とE型血液が反応したことで、エルアンの身体がそのまま静止してしまう現象が起こっていた。
彼は目を閉じたまま、ちょうどその瞬間に止まったかのようだった。
すべての動きが止まり、完全には静止していなくてもさらに悪化することはなかった。
輸液を全て投与し、彼の髪を撫でていると、ノックの音が聞こえた。
父と挨拶を交わしているイザベル様がまだ来ていない中、扉を小さく叩いて入ってきたのはディエルだった。
イザベル様を連れて公爵邸から一緒に来たようだった。
「セルイヤーズ公爵邸の書類を少し持ってきましたが……」
私は彼の肩を軽く叩き、微笑みながら答えた。
「じゃあ、その書類を私の部屋に全部持っていってくれる? まだ研究室が整っていないからね。それに、後で自宅にも私の研究室と温室を作る予定だから、その予算も考えておいて。」
私の言葉にディエルは嬉しそうに目を輝かせた。
「公爵邸の研究室のインテリアはすでに流行が過ぎたけど、今度は最近流行りのパステルトーンで飾るのが……あ、それですね。」
ディエルは私の箱の中から何かを取り出して渡してきた。
「必ず持ってくるように言われたものも持ってきました……」
私はディエルから小さな箱を受け取った。
しばし気を散らすような会話を交わした後、ディエルが研究室にふさわしいと感じる色とりどりのものを並べて出て行った後に、次に入ってきたのはイザベル様だった。
簡単に私と挨拶を交わした後、イザベル様は横たわっているエルアンを見つめ、しばらくの間ため息をついた。
「本当に……。」
彼女はエルアンの腕をそっと撫でながら言葉を詰まらせた。
「子どもがこんな風に苦しんでいる姿を見るのは、私の歳になってもやっぱり辛いわ。どれだけ強い心を持っていてもね。」
「きっとすぐに良くなりますよ。」
私は彼女を安心させるためにすぐさまそう言った。
「魔力の流れも早く正常に戻りつつありますし、身体の他の異常も良くなっています。もう少しで意識が戻るはずです。」
「リチェ、あなたが見ているからこそ、大変なことだろうな。それは信じているよ。」
「私が必ずどうにかします。それに、父を助けるために尽力しただけで……イザベル様のお顔を見る資格なんてありません。」
「ならば、当然その心の重荷を背負わなければならないね。」
イザベル様はゆっくりと私に視線を向けた。
その目は、まるでエルアンを見るように私をじっと見据えているようだった。
「この子を一生面倒を見るのよ……」
「……え?」
「これからは私のことを『お母様』と呼べばいい。」
彼女が力を振り絞って話すので、私も知らず知らずのうちに彼女を励ました。
どうやら父がセルイヤーズ城に残る理由があったようだ。
父の話を聞く限り、この家から簡単に抜け出すのは難しいことは間違いないだろう。
「当面は結婚なんて無理だと思います。父の許しも必要ですし、私も家族ともっと時間を過ごしたいんです。」
「永遠に待っていればいいさ。ただし、今から『お母様』と呼んでくれるなら、それで問題ないよ?」
「あ……はい、お母様。」
私は躊躇わず、即座に返事をした。
エルアンがあのような状態では、イザベル様の望むことをすべて叶えてあげたいと思う。
しかし、だからといって人生を全部犠牲にするつもりはなかったので、私は少し戸惑いながら話した。
「ですが私は……仮に結婚しても、お母様のように公爵家の内政を担いたくはありません。それでは経済的な負担が重すぎると思います。」
「もちろんだよ。エルアンは能力がずば抜けているから、ひとりで全部やれるさ。君がやりたいことは何でもやればいい。そして、もともと君の内政をエルアンがやるべきだろう? あと、君は今、自分の口で『結婚』すると言ったんだ。それを絶対に忘れちゃいけないよ。」
イザベル様はまるで脅すように断言しながら、息子の腕を掴んで優しく微笑んだ。
私はしばらく呆然としていたが、この際、すべてを覚悟しなければならないと決意し、うなずいた。
「そして、公爵様が何事もなくご無事でいらっしゃれば、私や父のような後見人は必要ないと思います。理由もなくいつも体調を崩していた以前とは状況が異なり、これからはもっとお元気になられるでしょうし、私がついているからといって特にすることもないでしょう。」
「うん、それでいいよ。でも、後見人以上にもっと強固な絆で私たち親子が結ばれることになるんじゃないか? 家族のようなものだ。そうだろう?」
イザベル様の静かな視線を見つめながら、私はまるでエルアンと話しているような感覚になった。
「え……まあ。」
私がフェレルマン領で一生を過ごしたいと言ったとしても、イザベル様がエルアンと一緒に住むために領地を移すと言い出しそうな気配を感じ、私は震える思いで微笑みながらご機嫌を取るしかない。
「さっき遺書の話をしたんだけど、シオニーはリチェが自分に似ると思ってそんな契約書を書いたらしい。私たち夫婦に似た息子だったらきっと受け継ぐにふさわしいと考えたんだろうね。冗談だとしても契約書を書いたという話さ。」
「あ。」
「もちろん外見は私たち夫婦の極めて優れた調和があるけれど、彼女もまた、二人の慎重な混ざり合いにより、絶対に結婚のようなことはさせないという覚悟をしていたらしい。それでも契約書の話を持ち出してきたところを見ると、一生反対するつもりではないみたいだね。」
余裕たっぷりな様子のイザベル様の表情を見て、私はどう見てもセルイヤーズがフェレルマンよりも一枚上手だと考えざるを得なかった。
こうして息子を完全に託すことにしたイザベル様が公爵邸に戻ってからも、エルアンは起き上がることができなかった。
以前は、彼が私を待っているということをあまり考えたことがなかったが、今では私が彼を切実に待っていると感じていた。
誰かを待つというのは思った以上に孤独なことで、私は何も言わずに彼の顔をそっと撫でた。