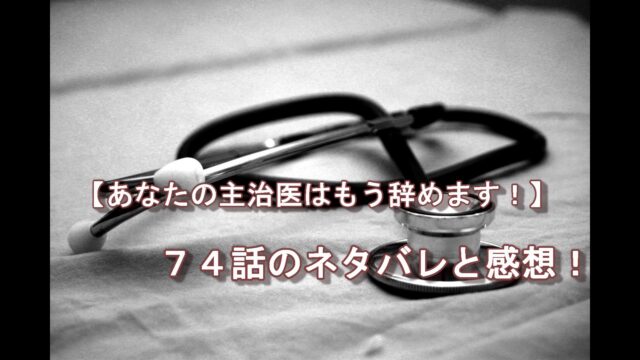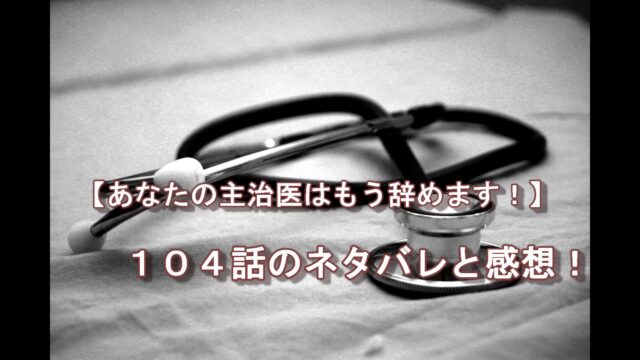こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

143話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- エピローグ
「ダメだ。」
エルアンはキャンバスを見て、ため息をついた。
「これしか描けないのか?リチェはこれよりずっと可愛い。次。」
ディエルが即座に答えた。
「次はレイビル・オーストラムという画家で、メロフォン公爵家と専属契約を結んでおり、イースト国王の肖像画で有名です。」
「見せてみろ。」
私はエルアンが投げ捨てたキャンバスを見て、ため息をついた。
もう12枚目。
すべて、私が家族の肖像画を描きたいと言った一言のせいだ。
祖父の遺言リストを一つずつ消していきたかったから、それが私の最優先事項だった。
どうにかして良い画家を雇おうと、叔母と祖父の前で大げさに語った彼は、最も単純で無神経な方法を選んだ。
報酬を支払い、有名な画家をすべて招待し、まず私を描かせた後、彼が気に入るまで交換すること。
その仕事のために、彼は目覚めてから今まで公爵領にも行かず、首都で画家の面接をしている最中だった。
もちろん、母は「公爵領の仕事はすべて終わらせているので、無条件で最善を尽くしなさい」との書信を送ってきた。
「……こんなにまでしなくてもいいんじゃないですか?」
私は熱中している彼に、慎重に尋ねた。
「私が見る限り、全部うまく描けているようですが。」
「何を言ってるんだ。ディテールの違いがすごいんだよ。ほら見て。君のアイラインはこの角度よりもっと上がらなきゃいけないし、耳のカーブはもう少し寄せるべきだ。」
「あ……私も初めて知った事実ですね。」
「俺は一目見れば分かる。信じて任せな。」
エルアンは微笑みながら、私の髪を優しく撫でた。
「一生懸命やって、フェレルマン家にどうにか良い印象を与えなきゃな。そうしないと、次の肖像画を描いてもらえない。必要な時は私も入るよ。」
「お母様とエルアンもこの機会に……。」
私はもう彼を「エルアン」と呼んでいた。
エルアンは、私が名前を呼ぶたびに嬉しそうな表情を隠せなかった。
「ああ、俺たちはすでにセルイヤーズの肖像画の件について合意してるよ。」
「どういうことですか?」
「君と一緒に描かないなら意味がないってことさ。」
エルアンと母の関係は極端に良くなり、最近は雰囲気がとても柔らかくなった。
問題は、二人の話題がいつも同じだという点だ。
どうすれば、フェレルマン家の地位にふさわしくなれるのか――。
私を急かして一日でも早く結婚させようとすること以外は、二人はほとんど長い会話をしなかった。
「お母様がご自分が亡くなる前までに描いてもらえればいいと言っているから、負担に思わないでね。」
「えっ、そうなんですか?」
「でも、私の体調がちょっと良くなくて、長生きしそうにないってことも伝えてって。」
結局、負担を感じさせるつもりだったのだ。
エルアンは、以前に聞いた両親の恋愛話を時々聞かせてくれた。
お母様が義父を獲得した話を聞くと、私の未来はすでに決まっているように思えた。
まあ、常識的に考えて、辺境の貴族の庶子の恋愛が、全く接点のなかった大貴族セルイヤーズ公爵家との結婚へとつながるのは、普通の恋愛話ではなかった。
もちろん、父がエルアンを警戒するのは、恋愛話をすべて知っているわけではないからだろう。
「次の肖像画を描くときには、子供も一緒にいるといいな。」
ディエルが次の画家を呼びに行った隙に、エルアンは私の隣に寄ってきて、目を細めながら微笑んだ。
「娘ひとり、息子ひとり。君が話していた通りに。」
「それ、覚えてるの?」
「君ほど天才じゃないけど、君の言葉は全部覚えてるよ。」
彼は私の手を取り、そっと囁いた。
その瞬間、ノックもなしに扉が勢いよく開いた。
「離れろ!離れろって言ってるだろう!離れろ!」
父の怒鳴り声に、私たちはそのまま顔を見合わせた。
エルアンは手を離した。
「俺が何度も大目に見て、しばらくの滞在は許したが、ずっと居座るのは絶対に認めない!」
「お義父様、私たちはお互いの命を救い合った深い絆の……。」
「お義父様と呼ぶな!伯爵閣下と呼べ!公家の品格を守れ!」
父は、公家の威厳を保ちながら、エルアンに対して怒鳴るように言った。
もちろん、公爵であるエルアンが父を伯爵と呼ぶ必要はなかったが、私たちの関係が問題視されるのは当然だった。
母の話によると、父はどうせ認めるしかないのだから、せめて最大限の圧力をかけて、自分の気が済むようにしたいのだろう。
どうしてそんなことが分かるのかと尋ねたら、「私とケイルンの恋愛模様をこの目で見てきたからよ」という答えが返ってきた。
案の定、父は時折こう言っていた。
「ケイルンの時は、横で見てる分には面白かったが……。まさか自分の娘が当事者になるとは思わなかった。」と、ため息混じりに目を細めていた。
「ええと……。」
その時、扉が開き、ディエルが静かに頭を下げた。
「次の画家が参りました。」
「入れなさい。」
父はまだ不機嫌な声でそう言いながら、脇に置かれたキャンバスを眺め、顔をしかめた。
「これは何だ?どうしてうちのリチェをこんなにひどく描くんだ?」
私にはどれも上手に描かれているように見えたが、父はどうしても納得がいかない様子だった。
「まつげの角度と耳の形が不自然です。私が確認しました。」
「そうか、言われてみればその通りだな。よくやった。」
「次の絵は、最善を尽くして検討いたします。」
「……ふむ。」
父は腕を組み、エルアンと私の間に腰を下ろした。
そして、次の画家候補として呼ばれたレイビル・オストラムは、緊張のあまり震えながら筆を取るしかなかった。
エルアンには洗練された審美眼があり、彼が選んだ画家は見事にその期待に応えた。
幸い、大陸をひっくり返すような騒動を起こす前に、レイビル・オストラムがエルアナの厳しい目を満足させる仕上がりを完成させたのだった。
私は、父や叔母、祖父に囲まれて静かに座っていた。
家族の肖像画を描くにあたり、母は私たち四人にぴったりの衣装を用意してくれた。
白と緑が混ざり合った、シンプルながらも気品のあるデザインで、家族の統一感を表す装いだ。
叔母と父は、このような贈り物をもらうといつも「自分で選びたい」と言いながら、わざわざ別の服を買ってきた。
しかし最終的に、私に最も似合うのは母が選んだものだという点では一致せざるを得なかった。