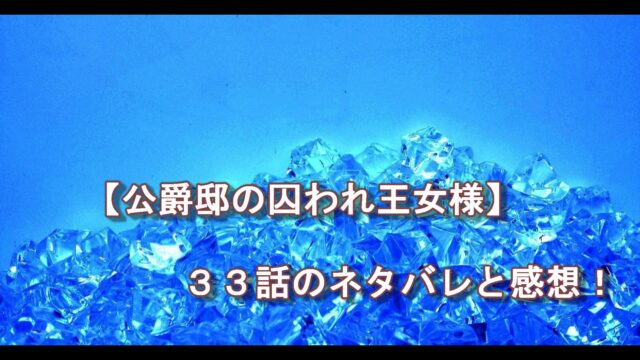こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

124話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 結婚の祝福②
結婚式は美しかった。
クラリスは一番前の席に座り、結婚式のすべての過程を目に焼き付けた。
穏やかな音楽に包まれ、お互いの指に指輪をはめる様子とか。
皆の祝福の中で熱烈にキスを交わす場面まで。
これまで彼女が本で見てきたあの結婚式と、実際の結婚式を比べてみると、ひどくリアルに感じられた。
火がつきそうだった。
そしてすべての日程が終わり、最後に新郎新婦と挨拶を交わすことになったとき。
クラリスは思わず興奮して大きな声を出してしまった。
「本当におめでとうございます!ああ、本当に美しい結婚式でした。」
目を輝かせるクラリスの姿が面白かったのだろうか。
しばらく見つめ合った新婚夫婦は、同時にくすくすと笑った。
「気が合えば、二人もいずれはここで結婚してもいいですよ。うーん……少し順番は遅れるかもしれませんが。」
「……え?」
「その時は、私も必ず呼んでくださいね。ああ、名刺どこに置いたかしら。」
彼女は友人に預けていた小さなハンドバッグから名刺を取り出し、クラリスに手渡した。
「必ず連絡してくださいね。待っています。」
クラリスは名刺を受け取って、しばらく考え込んだ。
今からでも事実を話すべきだろうか?
しかし、こんなに大切な行事の一部が「嘘」で満たされていたと知ったら……今日結婚した夫婦が失望するのはもちろん、首都の名誉にまで傷がつくのではと心配になった。
クラリスが困っているのを察したのか、そばにいたノアが代わりに答えた。
彼はいつの間にか白いローブを着ていた。
「もちろん連絡しますよ。大切な瞬間にお役に立てて光栄でした。」
「私たちの方こそ感謝しています。」
クラリスとノアは彼らと礼儀正しく挨拶を交わして別れた。
「クラリス!」
ちょうど遠くで彼女を見つけたクエンティンがうれしそうに両手を大きく振った。
「それじゃあ、私は部屋に戻って荷物を片付けます。」
「先に行くの?」
「彼とゆっくり話をしてください。」
ノアはクエンティンに軽くお辞儀して挨拶を交わし、先に戻っていった。
『もう少し一緒にいてくれたらよかったのに。』
クラリスはまた名残惜しさを感じた。
どうしてこんな気持ちばかり湧いてくるのだろう?
ノアが特に冷たく接しているわけでもないのに。
「ここにいたんだな。探したぞ?」
「すみません、おじさま。」
「公爵様が必ず君の様子を確認してこいとおっしゃってね。」
「もちろん、とてもお元気そうだとお伝えしてくださいね?」
「そうだな。君が結婚式でこんなに大きな役割を果たすと知っていれば、お二人も来られただろうに。」
「えっ?!」
クラリスは驚いて思わず扇子を落とした。
「だめです、今日の結婚式の主役はどこまでいっても――しかも新郎新婦なんですよ。」
ところが、まもなく公爵夫妻が現れると、皆の視線がそちらに集まってしまった。
「それでも、きっと寂しく感じるはずだよ。」
どうやら最近は「寂しさ」が流行語のようだ。
けれど、それはあまり良い感情ではないと思ったクラリスは、静かに顔を伏せた。
「私は……お二人が私に対して良い感情を抱いていてくれたら嬉しいです。寂しさじゃなくて。」
「うーん、そうか?でもね、僕の考えでは、それって別に悪い感情じゃないと思うんだ。」
「悪くはないですよ。でも、あなたは寂しさを感じる時、なんだか切ない気持ちになりませんか?」
「それはね、ただもっと一緒にいたいって気持ちの表れだよ。」
クエンティンはクラリスの頭をそっと撫でた。
まるで子供の頃からそうしてきたかのように。
「もちろん私も、君と別れるたびに寂しさを感じるよ。」
「私もです。」
クラリスは少し乱れた髪をそのままにして、彼に向かってにっこりと笑った。
「私もおじさまともっと長くお話ししたいです。」
「もちろんできるだろう。ただ、たとえ長く話したとしても、別れるときにはまた寂しさを感じるものさ。」
「そうですね。そもそも、この寂しさってどうすればなくなるんでしょう?」
「なくならない方が良いんじゃないか。」
「それは……そうかもしれません。」
クラリスは彼の結論に自分でも納得しながらうなずいた。
誰かに対する寂しさがなくなるというのは、結局その相手を思う気持ちすらなくなったということと同じだから。
「それなら、寂しさを感じる方がいいですね。そうでしょう?」
「親しい関係では、寂しさを感じるのが当然です。」
「はぁ、本当に。おじさまってどうしてそんなに分からないんですか?」
クラリスはいつも自分を悩ませていた疑問に、あまりにもあっさりと答えが出たことに嬉しくなった。
そう考えてみると、彼女がノアに寂しさを感じるのは、あまりにも自然なことだった。
「君もすぐにナチャのようになれるよ。一生懸命勉強すればね。」
彼はそう言って、懐から財布を取り出した。
「それと、これはたまにお菓子でも買って食べなさい。わかった?公爵様には絶対に言っちゃダメだよ。」
彼は財布から紙幣を取り出して、クラリスの手に無理やり握らせた。
「こ、これは私有財産じゃ……!」
「いやいや、財産じゃないよ。糖分が落ちたときに備えての非常用資金ってやつさ。」
だとしても、彼が差し出した金額はあまりにも多すぎた。
「全部受け取ってくれなきゃ、僕が“さみしい”気持ちになるよ。」
「うん、わかりました。」
クラリスは、彼が差し出したお金をすべてポケットに入れた。
「次に会ったときには、そのお金で……じゃなくて、おやつに何を食べたかをお話ししますね。」
「ふぅ、そうだな。楽しみにしてるよ。しっかり食べるんだよ、わかった?足りなかったらいつでも言ってくれ。とにかく君の年頃には、しっかり食べ続けなきゃ。それが義務なんだから。」
彼は再びクラリスの頭を撫でた。
「そういえば、さっきエビントン・ベルビルっていう受験生に会ったよ。」
「あ……。」
クラリスは、エビントンがクエンティンに失礼なことをしなかったかと心配になった。
「何度か助けを求める手紙を送ってきたことは知っていたけど、とてもいいアイデアだね。」
「えっ?」
「立派な心構えだったよ。今日、君が他の受験生たちのために時間を犠牲にしたという話も聞いたよ。普段はあの子と問題なくやってるんだって?」
毎日のように騒ぎがあるとはいえ、誇張ではなかったが、クラリスは無理やり顔を背けた。
くだらないことでクエンティンを心配させたくなかったのだ。
「実は私は首都院では友情なんて芽生えるはずがないと信じていた人間なんだ。」
彼は自分のひざをなでながら、再び視線をそらした。
「年を取ると少しは考え方も変わるようだな。君は彼と健全な競争をする“親友”として過ごしなさい。いいね?」
「えっ?!」
「もちろん、彼にもそう言っておいたよ。」
クラリスは、もしかして…という気持ちから彼に質問を投げかけた。
「な、何ておっしゃったんですか?」
「うちのクラリスと親しい友情を育んでほしいってね。」
彼は「おじさん、うまくやったでしょ?」というような目つきをした。
その後ろではエビントン・ベルビルがクラリスに向かって手を振っているのが見えた。
今回はためらいなく悪態をこらえる表情だった。
クラリスはクエンティンと別れ、首都の寄宿舎に戻るとすぐにノアの部屋へ向かった。
少し前は結婚式のことで頭がいっぱいで話せなかったが、彼に聞きたいことがあった。
少し開いたドアの隙間から、ノアがそっと扇子を閉じるのが見えた。
「お嬢さん、もう来たの?」
「おじさまが急いで行かなきゃって。挨拶の途中でも何だか忙しそうでした。残念です。」
「優秀な方だから、会いたがる人も多いでしょうね。」
「うん……そうだね。式場でもみんな彼と話したがってたよ。」
彼と親しくなりたいのはエイビントだけではなかった。
式場にいた誰もが「彼だ」と言わんばかりにクエンティンを羨望のまなざしで見つめていた。
クラリスは、そんな多くの人々から称賛を受けているクエンティンが、それでも自分をさりげなく気にかけてくれていることに、少しだけ切なさを覚えた。
「ノア、荷物の整理は終わった?」
「全部終わりました。」
「じゃあ、いいじゃない。」
クラリスはドアの隙間からさらに一歩近づき、にっこりと笑った。
「ちょっと中に入ってもいい? 魔法使いの城へ行ってきた話を聞きたくて。」
「そ、それなら……」
「もちろん部屋の中が狭ければ、外で話しても大丈夫よ。」
クラリスは前回の教訓を活かし、ポケットに家族用の手袋まで入れてきていた。
「それはダメです!」
しかしノアはあわてて反対し、険しい表情でドアをバンと開けた。
「お嬢さんはどんなに寒くても“セリデンの誇り”を胸に耐えるに決まってる。」
「実際、セリデンの人はこのくらいの寒さではびくともしませんから。」
それでもノアの部屋でゆっくり話すほうがよいのは確かだったため、クラリスはすぐに彼の部屋にさっと入った。
「本当にきちんと整理されてますね。」
ノアの部屋は長らく人が住んでいるとは思えないほど、すべてがきちんと片付いていた。
首都に来るたびに小さなトランクがいつも床に転がっているクラリスとはまったく対照的だった。
「カバンの中の物を元の場所に戻すくらいのことは、さほど難しくありませんよ。」
「私には難しいですけど。」
外出から戻ると、すぐにベッドに倒れ込んでグダグダしながら、あれこれと会話を交わしているうちに、いつの間にか荷物整理のことは忘れてしまった。
「座ってください。」
ノアがたった一脚の椅子をクラリスに差し出した。
彼自身は座る場所がなかったので、机の上にちょうどよく腰かけた。
「魔法使いアストはお元気ですか?」
「特に変わりありません。僕が戻ってきたら、また一緒に難解なゴーレムの研究でもしようって、しつこく誘ってきましたけど。」
ノアは「ちょっと面倒でして」と顔をしかめた。
「そんなふうに嫌がっちゃダメ。魔法使いアストにとって、ノアと過ごす時間は『名残惜しい』ものなんだよ。」
「『名残惜しい』って言葉に、そんなに大きな意味があるんですか?」
「『名残惜しい』というのは、つまり相手が大切だという気持ちの表れだよ。魔法使いアストは、ノアのことを本当に大切に思っているんだ。」
「うーん……」
ノアは返事の代わりに片方の腕を枕にして身を横たえた。
「魔法使いの宝石はどう?少しは団長を示す気配が見える?」
「そんなの誰にもわかりませんよ。」
「でも団長がいない時間が長すぎるよ。」
「それは人間の私たちには長く感じても、宝石は鉱物です。彼らの霊魂と比べたら、数十年なんてほんの数秒程度でしょう。」
「じゃあ、誰にすべきかまだ決められてないのかな?」
「もしかしたら、宝石が待っている相手がまだ十七にも満たないのかもしれません。」
「じゅう……しち?」
ノアは扇子をくるくると回した。
「少なくともその時までに、土台になる素養があってこそ、団長の座を引き継げるのではないですか?」
「それなら……」
クラリスは向かいに座るノアの膝に手を置いた。
そして目をぱちぱちと瞬かせた。
「本当にノアじゃないのかな?」
「またその話ですか。」
「でも、どの鉱石もノアのことが好きなんだよ。魔法使いの宝石までノアが好きなんて、絶対に何かあると思う。」
「鉱石の人気順に並べられたら、私よりあの子の方が……あ、うん。なんでもないです。」
彼は話題を変えようとすぐに続けた。
「いずれにせよ、今回の血族検査については、魔法士団も相当恥ずかしく思っているようです。費用をかけて血を採ったのに、まともに管理できていなかったとは。」
「内部的にもいろいろあったんですね。でも、後継者や公爵家で問題にされなかったなら、解決されたということですよね?」
「他の魔法使いたちはそう思っているようですが、私は……そうは思っていません。」
「まだ問題が残ってるの?」
「少なくとも、私には。」
彼が深刻な表情でしばらく壁を見つめると、クラリスは黙って待った。
「……彼が消えました。」
「彼が?」
「以前、君が足で蹴ろうとした灰色ローブの魔法使いのことだ。」
「ああ……」
不快な記憶だったその人物のことを思い出し、クラリスは自然と眉をひそめた。
「その人が消えたってことは、何も言わずに魔法使いの城を出たってこと?」
「そうだ。誰も彼が出て行く姿を見た者はいないと言っていた。魔法使いアストンは、彼の失踪と今回の件には関係がないと言っていたが、私はなぜかそう思えない。」
「どうして?」
「それは……」
ノアは、以前に都でその魔法使いと交わした出来事を話してくれた。
「実は、その出来事がずっと心に引っかかっていて城に行こうとしていたんです。どう考えてもおかしかったんですよ。めったに魔法使いたちがローブを自ら持ち出すなんてこと、ありませんから。」
「その魔法使いが、公爵夫人に手紙を渡そうとしていたのでは?」
「いえ、夫人の結果は郵便機関を通じて届けられました。記録も残っていますので、確かです。」
「じゃあノアは、魔法使いが持っていた手紙が別の人に渡されたと考えているの?」
「その手紙が怪しいと見ています。だから私が立てた仮説は、彼がある貴族家門の依頼でこうしたことをして逃亡したのではないかということです。」
「うーん……」
「魔法使いと貴族が協力して互いに欲しいものを手に入れた例は、歴史上いくらでもあります。別に新しい話ではありません。魔法の力で爵位を得た者、財産を築いた者もいました。」
彼の説明にもかかわらず、クラリスは簡単には扇子を止められなかった。
「なんだか……変だわ。」
「何がですか?」
「私、あの魔法使いが貴族たちに協力するとは思えない。」
クラリスは、彼が貴族に見せたあの露骨な態度を思い出した。
『ふん、貴族なんてこんな子どもの助けも借りられない、どうしようもない連中じゃないか。』
それはほんの数か月前のことだった。
それなのに突然態度を変えて彼らに協力するなんて、考えにくかった。
何より、彼は魔法使いアストを深く尊敬しているように見えたからだ。
クラリスの説明を聞いたノアは、ゆっくりと扇子を閉じた。
「そう……いうこともあるかもしれないな。だとすると、一体何があったのか。」
ノアがしっかりと立てかけていた飾り布が風に揺れ、少し元気がなくなっているように見えた。
カーテンの隙間から深いため息が漏れた。
「魔法士団で独自に追跡はしないの?」
「追跡隊は編成しましたよ。すべての魔法使いは魔法士団の指示を受けなければならないですから。」
「それならすぐに見つかるかもしれないね。ノアのように魔力を感知できる人が含まれていればの話だけど。」
「そうなることを願います。彼が戻ってくれば、私も今回の件を“単なる過ち”として受け入れられる気がします。」
「待とう。魔法使いアスト様がきっと解決してくださるはず。」
「もちろんそうですが、今のところは追跡をどこから始めればいいのか手がかりがない状況です。」
「うーん……僕が行けば何かわかるかもしれないのに。」
クラリスはノアの膝の上に置いた手をぽんぽんと叩きながら、ある仮説を思いついた。
「魔法使いの塔には話ができる石がたくさんありますよね。事情を知っている友人がいるかもしれません。それは絶対にノアです。」
ノアはきっぱりと言い切ったが、クラリスはまだ未練が残っていた。
石たちは常に魔法使いたちを見守っているため、もしかしたら血が混じってしまった事件の答えが得られるかもしれない。
「聞いてみたら……うぅ、ほんとに!聞いてみないと。」
「どうして試さないんですか、少女が危険の中に行くと言ってるのに!」
「それじゃなければ、ノアが言ってた石を持って行けば……うん、そうだ。ノアは見分けがつかないって言ってた。」
正確にどの石が特別なのかを見分けられるのは、ただ一人、ゴーレムマスターだけだった。
魔法使いたちは、その周囲に誰かの魔力が込められていることはかろうじて感じ取れるかもしれないが、どの石なのかを正確に選び出すことはできなかった。
『じゃあ次はモチをノアの手に持たせて送ればいいかな?』
モチが石たちの話を聞いて、クラリスに伝えてくれるかもしれない。
もちろん、モチがこんな作戦を好むとは思えないけど。
『……あれ?』
そのときクラリスは、ふとある考えが頭をよぎった。
『そういえば、今回魔法使いの城から戻ってきた特別な石……あったよね?』
クラリスは顎をゆっくりと上げて、ノアの顔をじっと見つめた。
「ノア、仮面をちょっと外してくれない?」