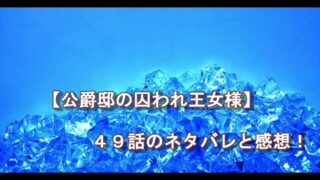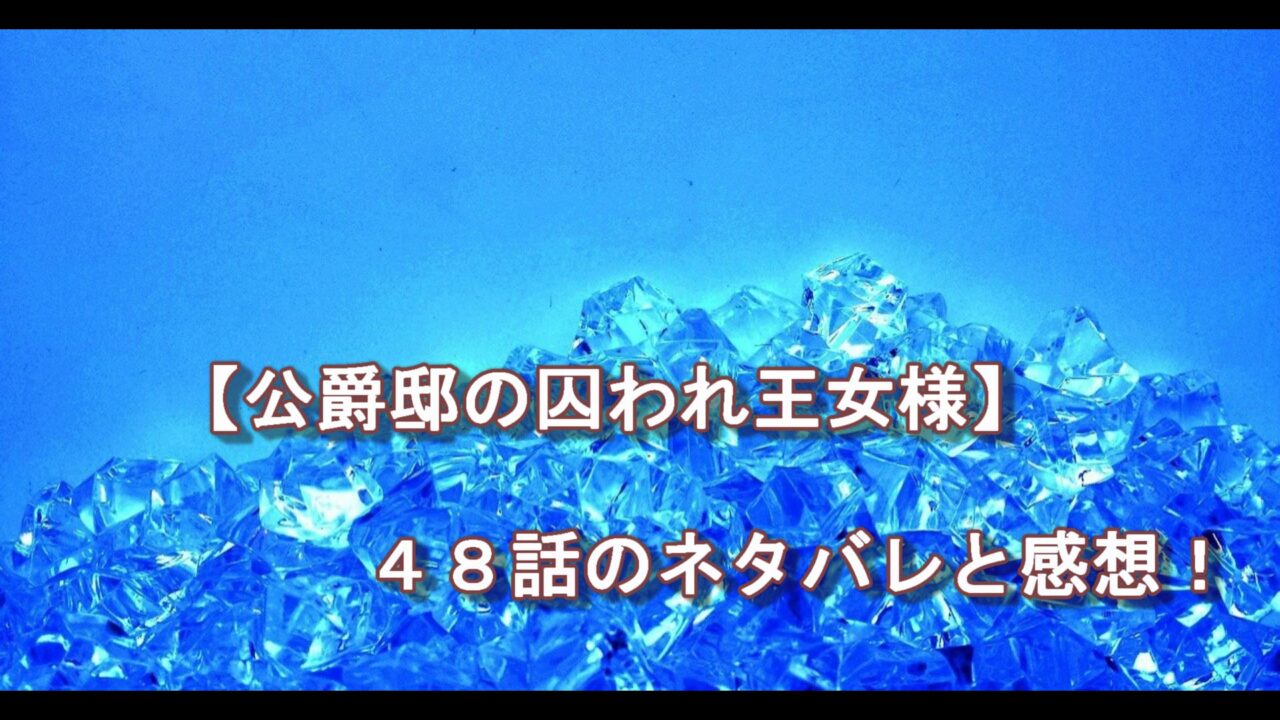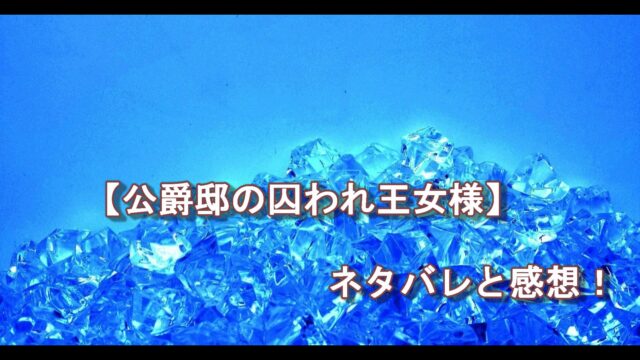こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
今回は48話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

48話 ネタバレ
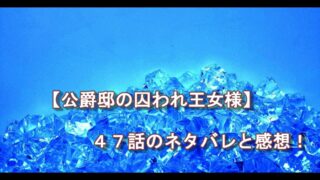
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- ロザリーの後悔
その夜、クラリスは王妃が出席した晩餐に共にする光栄を享受した。
その席が終わった後は部屋に戻り夜の外出を準備する。
今日は空が晴れた夏の夜に、ノアと一緒に騎士団の宿舎に遊びに行って星を見物することにしていたのだ。
クラリスは寒さに備えて薄いショールをかけ、首の下についた小さな覆いのボタンをかけた。
いつの間にかロザリーが鏡の前に椅子を置いて立って待っていた。
「私はこれから一人でブラッシングができます」
「ああ、どうかこのお婆さんの楽しみを奪わないでほしい」
クラリスはロザリーの楽しみを大切にしていたので、すぐに椅子に座り両足をバタバタさせた。
口ザリーは髪を梳かす達人だ。
ひどくもつれた髪の毛も痛くないようにとかしてくれたりした。
たまにはサラサラとかれる気持ちが良くて、しきりに目が閉じようとするほどだ。
「本当に気持ちいいです。ロザリーはブラッシング王です」
「そう言ってもらえて嬉しいわ」」
「ロザリーはいいことばかり言います」
「悪いことを言う機会がまだなかったからだろう」
「ありますよ」
クラリスはしばらく自分のつま先で視線を落とした。
なんだか鏡をまともに眺める自信がないのだ。
「私に悪いことを言いたい人もきっといるはずです。そうでしょう?」
「なんてこった」
髪の毛をとかしていた手がしばらく止まった。
「私がそのすべての話を聞かなければならない義務があるということは知っています。しかし、口ザリー、私は・・・とても弱いです」
「クラリス、おいで」
口ザリーは子供の前に戻って座り、うつむいた顔をじっと見る。
心配に満ちた顔で。
「あなたにそんな義務はないんだ。あなたはただの子供だったし、今もそうだよ」
クラリスは静かに首を横に振った。
「私がシェリデン邸に住み、殿下の後援を受けるようになったのは、『ただの子供』ではないからだということを知っています」
クラリスは何度も考えたことをゆっくりと説明していった。
「私は罪深い王家の最後の血筋です。その事実を忘れてはいけません」
口ザリーはクラリスの手をしっかりと握る。
「その名の下に苦しんだ人たちがいたということも」
「それはまだ若いあなたが抱え込むにはあまりにも重い責任よ」
クラリスは首を横に振った。
「私がすることは覚えていることだけです。それでも・・・少しは怖いです」
「・・・」
「私が立派な18歳になりたいと言うのは、利己的なのでしょうか?」
クラリスは「謝りたいのなら不幸になれ」と言ったロックハート先生の言葉がただ間違っているわけではないと考えている。
「クラリス、あなたが何を言っているのか分かっているよ」
しばらく悩んでいたロザリーが落ち着いた声で答えた。
「仕方がなかったという言葉ですべてのことを忘れることはできないだろうから、幸せになることが罪悪のように感じられる時もある」
「ロザリーも・・・そんなことがあるんですか?」
注意深く尋ねた質問に、ロザリーはしばらく悩んだ後、ゆっくりとうなずいた。
「もう20年近く経ったね。私にとっては昨日と同じことだが・・・私が面倒を見ていた貴重なお嬢さんがある日、屋敷で拉致されたの」
「え・・・?屋敷で?」
「そうだよ。影のように動く人たちが、こっそりとお嬢さんだけを拉致して消えたんだ。邸宅を守る騎士たちもこれに気づかなかったという」
「恐ろしいことです。お嬢さんは何歳でしたか?」
「まだ4歳なんだ。私はその日のことを今でも許せない。お嬢さんをあまりにも深く寝かせたのではないか。私が徹夜をしてでもそばを守らなければならなかったのではないかと思って」
「とんでもない。騎士さんも知らないほど静かに行ってきたんですって。そして、ロザリーがそばを守ったとしても、その恐ろしい人たちにやられていたかもしれません」
「分かるよ。でもね・・・」
口ザリーはクラリスの手の甲を優しく磨いた。
「それでも、あんなにむなしくお嬢さんを見送ったという事実がつらくて仕方がない。無事に育っていたら・・・今ごろは侯爵家の誇りになっていたでしょうに」
「私もとても心が痛いです。ロザリーは小さなお嬢さんを深く愛していたんですよね?」
「そう、とても愛しているよ。そのふさふさした銀髪もくりくりした目鼻立ちも・・・」
「銀髪のお嬢さんだったんですね?まるで公爵夫人のように!」
「あ、ああ・・・」
クラリスの話にロザリーは困ったような笑みを浮かべたまま、しばらく何とも答えられなかった。
「ええと・・・しかし、私がそう思うのは、おそらく公爵夫人に迷惑をかけることだろう」
「そうなんですか?」
「誰がそんな悲しい目にあった子に似てるという言葉を・・・喜ぶかな?」
「それは・・・」
クラリスはロザリーがおそらくそのような考えを無理やり何度か折っておいたのではないか、と密かに推測した。
「私はただその可愛いお嬢さんを・・・忘れないだけだよ。それが私にできるすべてだろう」
「ロザリー・・・」
「だから記憶だけでは十分ではないと言うあなたの気持ちが少しは分かるような気もするね」
クラリスは両手を高く上げてロザリーの首筋をぎゅっと抱きしめた。
似た心が近いところで出会い、少しでもお互いを撫でることができるように。
その間にクラリスはある答えを得た。
まさに自分が利己的なのかと思ったことだ。
そうではなかった。
それはロザリーを見れば分かる。
痛みを抱いていながらも、今を誠実に生きる口ザリーが利己的な人であるはずがない。
「ロザリーはいい先生です」
「私のようなおばあさんに何を学ぶと思う?これからもっと賢くていい方に会えるんだよ」
「それでも今日はロザリーが私には最高の先生です」
クラリスはロザリーをぎゅっと抱きしめた。
ノックの音が聞こえたのはその時だった。
クラリスを訪ねてきたのはマクシミリアンだ。
彼はクラリスに何か不便なことがないか尋ねる。
改めてこのような質問をするのを見ると、ロックハート先生のことが気になったようだった。
「先生を素直に送ってくれるのは、見向きもせずに邸宅に人をかけた私の無知を一番叱責しているからだ」
彼がホールでそう言ったとき、クラリスはとても驚いた。
同時に、とても申し訳ない気持ちもあった。
彼に罪悪感を感じてほしかったことはなかったから。
「感謝しています。公爵が私の意見を受け入れてくれたじゃないですか。苦労してよこした先生なのに」
「彼を送り出す決定には君の意見だけがあったのではないから、あまり気にしなくてもいい」
「また、誰が何と言いましたか?」
「邸宅が広いだけに、見る目も多いものだ」
彼が曖昧に話を進める頃には、ちょうどクラリスを迎えに来たノアもドアの前に到着した。
「魔法使いシーネット」
公爵は近づいてきたノアの姿をずっと見て開いたローブをきれいに手入れしてくれた。
「夏でも夜は気温が下がるものだ。暖かく着なさい」
ノアはその優しい手に少し当惑したに違いない。
びくびくしながら公爵を見上げたまま何も答えられないのを見ると。
「じゃあ行ってきなさい、クラリス」
公爵はクラリスとノアが一歩後退するのを許した。
「行ってきます」
クラリスはにこやかに挨拶し、ノアはぎこちなくうなずいた。
(もしかして、開いていたローブに触れたのが不快だったのだろうか)
マクシミリアンがそんな心配をするのもつかの間。
廊下を通る子供たちの背後にくすくす笑う声が広がり始めた。
もう何か楽しくなったらしい。
「楽しそうですね」
彼らの姿を見守ったまた別の誰かが彼の後ろから話をかけてきた。
マクシミリアンはあえて振り向かなくても、その相手が誰なのか分かったので、小さくため息をつく。
ロザリーの思い出のお嬢様。
銀髪なのは公爵夫人もですが、まさか・・・?
最後にマクシミリアンに声をかけてきた人物とは?