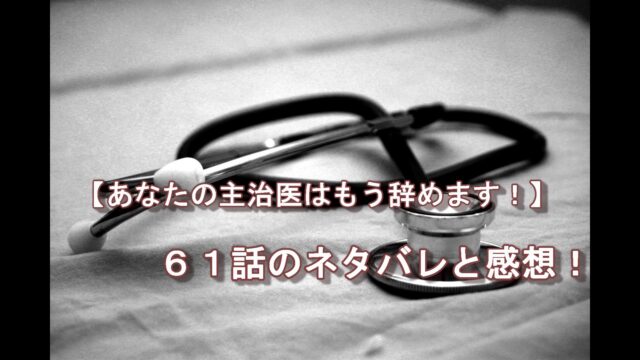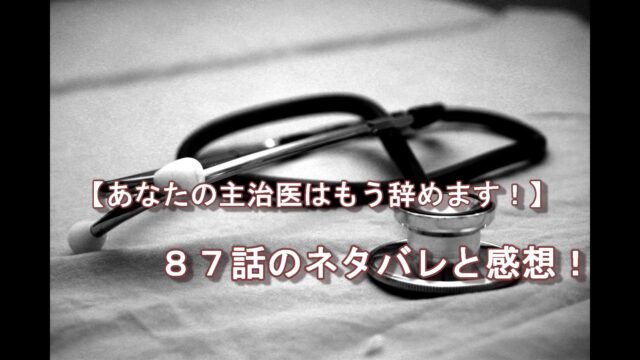こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

138話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 皇室裁判⑨
皇宮は依然として物々しい雰囲気だった。
アルガは平然と宮殿に入ると、やはり都は噂が早いと考えた。
皇室調査団が反乱軍勢力を次々と突き止めて摘発しているという話が、毎日のように聞こえてきたからだ。
セルイヤーズ公爵領を巧みに利用して、イシドール南部を手中に収めたハエルデン皇子は、ほとんど全てを手にしたも同然だった。
既存の体制が崩れると利益を得る家門たちは、まるで亡霊のように永遠に現れるようだった。
当然、本格的な反乱が起きる前に、こうした家門の多くが音もなく静かに消えていくことは明白だ。
果てしなく軍勢を動員している領主は、ジェイドが自ら出陣すれば数時間内に殺されると知っていたため、全員が無条件に身を潜めている。
ジェイドはいつも目をぎらつかせながら「どうせ私が勝つのに、反乱なんてなぜ起きる?」と、冷笑するような態度をとっていた。
『だが、その混乱の中で必ず死者や負傷者が出るのだろう。』
いずれにせよ、ハエルデン皇子が長い間準備してきた反乱は、このように収束に向かっているようだった。
アルガは調査官の前で、それまでその場にいた。
事実をすべて明かしながら、もう一度怒りがこみ上げてくるのを感じた。
感情を抑えられず、すべてを語り終えたとき、調査官は深いため息をついて彼に言った。
「本当に大変なご経験をされましたね。それでも娘様を見つけられて本当に幸運でした。再び裁判が開かれるのは間違いないでしょう。」
「とても辛い経験でした。苦しみました。私は今回の件の最も直接的な被害者です。皇太子様は特に損害を受けたわけではないでしょう?」
「おっしゃる通りです……」
調査官は真剣な顔つきで続けた。
「ハエルデン皇子の処遇をフェレルマン子爵に委ねるのはいかがでしょうか。恐らく、子爵様が要請されれば、皇太子様もそれを受け入れると思います。ああ、自ら寛容に振る舞われるのもいいかもしれません。」
「許すだなんて。これまでの出来事を耳にされましたか? 私がそんな奴を許せると思いますか?」
「いいえ。」
たった一言の「許す」という言葉に激しく反応し、アルガの顔に現れた怒りを見て、調査官は即座に答えた。
「一目見て、許しとはほど遠いお顔をされていますね。」
「人を見る目があるようですね。」
「いずれにしても、処分権を要請されますか?」
「はい、もちろんです。」
アルガは歯を食いしばりながら、相手を説得し続けた。
調査官はその場で侍従を呼び出し、何かを言い聞かせた。
侍従は一時的に姿を消したが、ほどなく戻ってきた。
侍従が持ってきた公文書を開いた調査官は、特に難しそうでもなく、再びペンを手に取った。
「皇太子殿下が全ての処分権を任せるとおっしゃっています。どのようにされますか?」
「えっ?こんなにすぐに?」
「元々、処理が迅速な方ですから。」
アルガは、迅速というよりも単に事務的に済ませたいのではないかと疑ったが、精神衛生のため口には出さなかった。
代わりに、別の疑問を口にした。
「……その処分を私に任せるとおっしゃったのは、一体どなたですか?」
「ケインズ卿です。」
「私の娘を家族として狙った件についての主導者に関係があるのですね。」
アルガは苦笑し、調査官に自分が望む処分内容を伝え始めた。
調査官は一言一句記録しながらも、時折見せるため息に近い様子を隠せず、アルガは居心地の悪さを感じつつ焦りを隠せなかった。
「私ではなく、セルイヤーズ公爵が考えたことです。」
「そうですか、その公爵様も随分とそういった考えを巡らせる余裕が出てきたようですね。今では少し落ち着かれましたか?」
「まあ、娘が見ているので大丈夫だと思います。」
アルガは考えるだけで心がかき乱されるような思いを抱きつつも、深いため息をつく。
だが、その表情には既に疲労感が漂っていた。
「それでは……面会は今行いますか?」
「はい。」
アルガは決心を固めた後、調査官の後について皇宮の監獄へと足を踏み入れた。
以前、一度セルイヤーズ公爵邸の地下監獄を訪れたことがあった。
その時も不気味な場所だと思ったが、皇宮の監獄はさらに陰鬱だった。
当然ながら、光が差し込むことは一切なく、暗く生命感のない空間が広がり、心を追い詰めるような圧迫感が満ちていた。
湿気を帯びた道をしばらく歩き、アルガはやがて遠くの先にいるハエルデンを目にすることができた。
若い頃、常にリーダーとして振る舞い、傲慢なほど自信に満ちていたハエルデンが、今では狂気じみた人間のように監獄の隅で縮こまり、薄笑いを浮かべているのを見て驚かされた。
「どうしてこんなことをしたのか、なんて聞くつもりはない。」
皇子に対してぞんざいな口調でアルガは冷淡に言い放った。
「お前のように劣等感に囚われた者は、それだけの理由だ。誰かが上手くいくのを見るのが嫌で、何とかして妨害したくて、自分の行動で相手を苦しめてやりたいと思う。そしてその様子を見て喜びを感じ、ただ相手を痛めつけるためだけに行動する。」
調査官に感情を吐露していた時とは対照的に、アルガは無表情を保ちながらさらに言葉を続けた。
「それは病気だ。非常に厄介な病気だ。正常じゃない。」
「もし嘲笑しに来たなら、さっさと消えろ。お前には十分、長い苦痛の時間を贈ったと思っている。どうせ私は死を迎えるだけで、もう何の未練もない。」
「まあ、それならまずは私が君の処遇権を得たという知らせを伝えに来た。」
「だから祝福の言葉でも投げかけてやろうか?」
ハエルデンが自分の残された人生に何の未練も抱いていないというのは明らかだったが、アルガは腕を組み、ただじっと彼を見つめていた。
「まあ、私は人情味あふれる慈悲深い人間だからね、心が弱くなったんだ。」
「戯言を言うなら消えろ。」
「皇妃が懐妊した。」
しもべのように笑っていたハエルデンの表情が、ピリッと引き締まった。
「私の娘、リチェが天才だって知っているだろう?リチェの処方を受けたんだから、ある意味当然のことだ。」
「嘘だ……。私がずっと研究しても解決できなかった問題だ。」
「リチェの実力はお前のほうがよく知っているだろう。」
揺れるハエルデンの瞳を見て、アルガは彼が完全に心を揺さぶられていることを感じ取った。
「私は妻を失い、19年間娘を探した。私の娘は養育院で枯れ果てるように育った。」
「……子どもには罪はない。むしろ私を殺してくれ。私を解放してくれ。」
「そうだ、子どもには罪がない。だから殺されることはないだろう。」
ハエルデンがこれほどまでに望んだのは、アルガがあまりにも気高い存在だったため、それを逆手に取って彼をさらに深く傷つけようとしたからだ。
そして、その象徴となる存在が子どもだった。
「子どもが生まれたら、皇后を処刑し、その子どもは遠く離れた養育院に預けるつもりだ。その子ども自身の人生だ。理解してもらうしかない。」
「……私をどうしようと構わない。ただ、穏やかな養育院に……。」
ハエルデンは無様に鉄の手すりを握りしめ、強く懇願した。
それは耐え難い屈辱の中での頼みだったが、アルガは具体的に指摘はしなかった。
「お前も19年を耐えて自殺せずによく生き延びたな。その報いとして、私はその子どもをお前に見せるつもりだ。一度も顔を見られなかった子どもがどれだけ切実だったか、理解させてやる。そうだ、その気持ちは私がよく知っている。ただ、その間、私の苦しみを感じてみろ。」
アルガはその「苦しみ」が何であるのか具体的には言わなかった。
しかしハエルデンはその言葉を聞いたので、どんな苦しみでも耐えざるを得なかった。
アルガの言葉を半信半疑ながらも、どこかで信じざるを得ない気持ちが湧いていた。
それは19年間、アルガがそうやって生きてきたからだ。
エルアンが再審の傍聴席でセイリンに話したという内容が、まさにこれだった。
『リチェの実力だ。彼らがそれをよく知っているなら、反抗しながらも信じざるを得ないだろう。牢獄に閉じ込められたまま、一生涯の苦痛に耐えながら、自殺せずにこれを乗り越えたら子どもに会わせてあげるとおっしゃいましたね。期限はフェレルマン公爵がリチェを探し回った19年程度でいいでしょう。』
もちろん、イザエラは妊娠していない。
リチェも処罰されながら特に大きな効果はないだろうとさえ予測されていたから。
「そして19年後、あなたがその苦痛に耐えきれずに死んだとしましょう。ちょうどエルデンがリチェに罪をなすりつけようとした濡れ衣のように、リチェのせいで公爵夫人が亡くなったのだと。」
長い時間苦痛を与えた末に、最後にその時間が無意味であったことを知らせる。
それがアルガが受けたことと同じように報いる方法であった。
苦痛は宮廷の牢獄で実現されるもので、ジェイドにそれを要求するつもりだった。
受けた分だけ返すということであれば、その19年間がどれほど辛いものだったか知ることによって、アルガがどれほど落胆するか。
そして後になって、その子供が実際には存在しなかったと知ったら、どれだけ絶望するだろうか。
あるいは、永遠に知らせないという選択肢もあった。
「私は1年ごとに一度訪ねるつもりです。娘は成長しました。大きくなりました。勉強もよくできます。このように想像上の子供についての情報を与え続けることで、存在しないことにさらに執着させ、苦痛を深めるつもりです。」
アルガはエルアンがセイリンに言った言葉を思い浮かべながら、ゆっくりと足を進めた。
「もちろん結婚は絶対にだめだが。」
彼は苛立ちながら続けた。
「リチェをこれ以上苦しめずに起き上がれ。」
エルアンのそばで幼い頃のように寄り添いながら心配そうなリチェを見て、彼はため息をついた。
「1年に1度訪れるなら、とにかく立ち上がらなければ話にならない、この愚か者め。」
エルアンがまたリチェの隣に遠慮なくくっついているのは本当に嫌だったが、リチェが心配そうな顔をしているのを見るのはさらに嫌だった。
消耗していくセルイヤーズもまた然りだった。
一度深く絡み合ったものを振り払うことは不可能だった。
彼は、「最初からケイルランと親しくならなければよかった」と30年前のことを悔やんでいた。