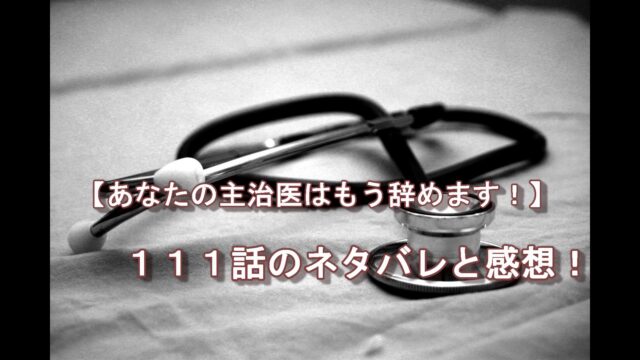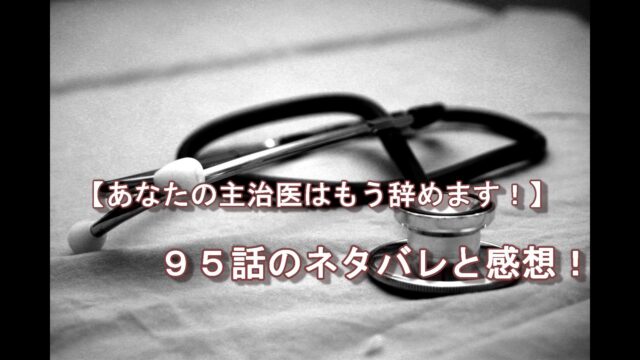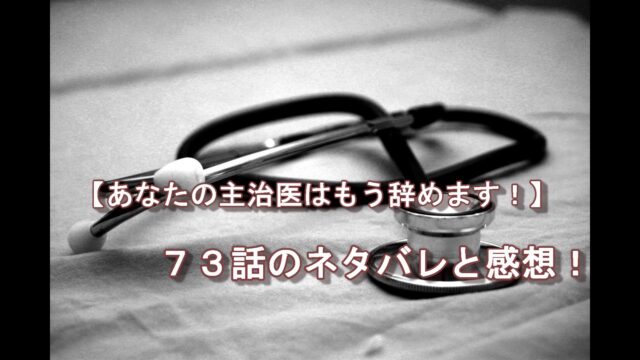こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

140話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 目覚め
首都にあるフェレルマン邸宅の主は、急な客を迎えることとなった。
ジェイド皇太子が親しげに言葉をかけながらやってきたのだ。
父親が先に出発して客人を迎える準備をすると言っていたが、結局二人は同時に到着してしまった。
馬車の速さが競争を決定づけたのである。
父親が服を整えて戻ってくるまで、ジェイド皇太子は一人で私を相手にしなければならなかった。
「ああ、すまない。馬を急がせたら速度を調整できなくなってね。でも、私は気にしないよ。どうにか準備すればいいさ。」
「ええ。どうせ急ごしらえの邸宅ですから、大した準備は必要ありません。」
ジェイド皇太子は私を見るなり、世界が終わるかのようなため息をついた。
「私が5歳の時、侍女の一人が子供用の遊び道具を持ち出してきて、私をからかい、その後も追いかけ回しながら魔法アイテムを一つ持ち出したことがあった。それ以来、すっかり忘れて暮らしていたんだけど……。」
「ええ。」
「ごめん……本当にごめん、リチェちゃん。それとフェレルマン氏にも何度も謝ったよ。これからはおもちゃなんて二度と手を出させないようにするよ。それに惑わされて、絶対に魔法アイテムを持ち出したりしませんから。」
「はい、当然です。そのつもりでお願いします。ぜひ心に刻んでください。」
私は席を譲りながら、軽く礼をした。
もちろんジェイド皇太子のせいで私が不快な思いをしたのは事実だが、彼が意図的にこれを仕組んだわけでもなく、5歳の子供に悪意があるとも思えないため、それほど大きな恨みは感じなかった。
代わりに、もし当時の手紙に書かれていたように彼が嘘を言っているのではないかと冷たく問いかけた。
「それでも、私も申し訳ありません。皇太子殿下のお気持ちにはお応えできません。私はセルイヤーズ公爵様が好きで、互いに気持ちを通わせている間柄ですから……。」
「そうだね、リチェさん。もちろん理解しているよ。」
ジェイド皇太子は困惑した表情を浮かべながら、軽くため息をついた。
「僕も、フェレルマン夫人の死に何らかの形で関わった。そしてセルイヤーズ公爵もフェレルマン家を守るためにあんな無茶をした。だから……リチェさんの選択を尊重するよ。」
『何かがおかしい……。』
「僕だって、状況をうまくまとめるくらいの力量はあるつもりなんだ、リチェさん。」
「ええ、でも実は私は一度も皇太子様を男性として好意を抱いたことはありません。」
「そうだね。セルイヤーズ公爵がこんなふうに伏せているのに、僕への気持ちが当然揺らぐことがないなんてこと、リチェさんはどう感じる?僕もリチェさんが僕を選んでくれることを望んでいたよ。救ったときにすべてが無意味になることを悟ったんだ。理解できるだろう。」
「……」
ただ、私たちの縁をここで終わらせ、これ以上深追いしないほうが良いと感じた。
送り出せないなら、どうしてできないのかと泣きわめき騒ぐよりもましだ。
結局、私はこれ以上真実を伝えることを諦めることにした。
本当にハエルドン皇子が飲んだ毒の副作用なのか、それとも生まれつき何かが少し足りなかったのか、知る術はないだろう。
二度と回復することがなく、ジェイド皇太子を救えない以上、生涯その真相を知ることはできないだろう。
最も能力のある賢者たちが集まっただろうに、なぜ皇太子の知的能力がこの程度なのかも分からない。
「遅れて申し訳ありません、殿下。」
その時、父が慌ただしく服を着直しながら応接室に入ってきた。
普段身につけているはずの外套もなく、眼鏡もしておらず、ネクタイが少し乱れているのを見て、私とジェイド皇太子が二人でいることに気まずさを感じたようだった。
「いや、私が早く来ただけだ。それで、リチェに対して誠心誠意謝罪をした。」
ジェイド皇太子は私を見つめ直し、もう一度だけ軽く頭を下げた。
「もし足りないと思われたら……。」
「いえ、足りないことはありません。充分に真心のこもった謝罪を受け入れました。」
私はこれ以上同じ会話を繰り返したくなかったので、慌てて答えた。
父もまた、私とジェイド皇太子の会話を止めたいと思ったのか、真剣な表情で割って入った。
「殿下、いずれにしても私にも一言申し上げたいことがありまして……。」
「ああ、うん。」
ジェイド皇太子はため息をつきながら答えた。
「今回のことで、本当にたくさんのことを悟ったよ。」
応接室に慎重に入ってきて、父の眼鏡をそっと渡してくれたディエルが少し驚いていた。
「その間、私は全てを乗り越えればそれで終わりだと思っていた。それは事実だが、その過程で傷つく人々が出ることもあった。」
「そう、正しいですね。」
私は感嘆しながら答えた。
「実際、反乱が起きたといっても、皇太子殿下がすべてを抑え込んだとしても、その過程で本当に多くの人々が傷ついたことでしょう。平和に生きていた人たちが突然巻き込まれ、処刑を宣告された被害者も確かにいたはずです。」
それが私の率直な意見だった。
「その通りだ。だからこそ心から後悔している。セルイヤーズ公爵が中心となって反乱を知らせてくれたとき、その忠告を無視すべきではなかった。」
「はい、よくなさいました。」
「それで、私は今決断した。」
私と父も同じく、不安な気持ちで彼の次の言葉を待っていた。
「以前、毒を使う際に少し軽率だったことを認め、賢明な人々の意見を積極的に聞くことにする。各分野の優れた専門家に任せるつもりだ。当然、忠誠が保証された者たちに限る。そして、崇高な人々の教えを取り入れて、改めて学ぶつもりだ。」
私は深いため息をついた。
自らの過ちを認めるというのは、どのような状況であれ最悪の事態を回避する第一歩だからだ。
「はい、帝国の未来が幸いにもこれほど暗いものにはならないようですね。」
「それでだ。」
ジェイド皇太子は父をじっと見つめた。
「皇室の医療研究チームを解散しようと思う。ケインズ卿がそう言っていたが、実際にはハエルデン皇帝の個人的なグループと変わらなかったそうだ。」
「ええ、そうですね。昔から少し聞き及んでいましたが、なんとなく納得がいきます。」
父は少し困ったような顔をしてうなずいた。
「しかし、医療は国家福祉において非常に重要だ。だから、あなたがその責任者を引き継いでくれるといいのだが。」
「責任者ですか?」
「19年前の研究員たちが言うには、フェレルマン子爵の実力はハエルデン皇帝を上回っていたそうだ。」
「そうですね。」
「フェレルマン子爵の才能が反乱軍の実力を掌握し、忠誠心も保証され、実力については言うまでもありません。」
ジェイド皇太子の言葉に、父の顔には少し戸惑いが見えた。
若い頃、父は公爵という地位を持ちながらも、多くの人々に貢献したいという情熱と能力を示したいという野心から研究員に志願したのだろう。
自分が同じような気持ちを持っているため、父の胸中がどれほど揺れているか想像がついた。
だから私はすかさず口を挟んだ。
「うーん……一度解散して新たに作り直すのであれば、条件が必要です。」
「ん?何だい、リチェ?」
「皇室の医療研究所ではなく、国立医療研究所になればいいのですが。皇室のためだけではなく、この国のためにあるものですから。」
「それは同じことじゃないのか?」
「少し違います。後で勉強すればわかるでしょう。とにかく、より良い方法だと思います。」
「私を助けてくれたリチェさんがそう言うなら、それが正しいのでしょうね。わかりました。」
「それから、身分よりも実力を重視した編成にしてください。平民でも貴族より賢いことがありますから。」
私はかつて平民の身分で射撃大会に参加したときに無視された記憶を思い出しながら、はっきりと言葉を続けた。
「父さんが直接選べばいいと思いますよ。父さんはセルイヤーズ公爵領でたくさんの人を選んできましたから。天才だとひと目でわかるでしょう。」
「お。」
父は息をついて、しみじみとした様子で言った。
「誰の娘だからこんなに賢く、抜け目がないんだろう。ああ、この事実をもうみんなが知っていて、これ以上言葉にすることができないのが悲しい。」
ジェイド皇太子は「専門家の意見に従いましょう。」という言葉で私の話に同意し、皆に頭を下げた後、さらに続けた。
「リチェさんも当然、永住の対象ですよね?」
「もちろんです。」
父の声には明らかな喜びがこもっていた。
「出勤して一日中一緒にいるんだ。娘と一緒に医学研究の議論ができるなんて、なんて楽しいことだろう。」
私もまた、自分の能力が万人の役に立つという点で、本当に良い提案だと思った。
初めて何も知らなかった昔でさえ、皇室医療研究所に入りたかったのだから。
ましてや父と一緒に研究するという話に、本当に心が惹かれた。
しかし、私は微笑みながら首を横に振った。
「今は遠慮します。公爵様が無事に回復されるまでは見守って差し上げたいんです。」
「うん、それは分かった。そうするように。あ、それからリチェさんの頼みがあるんだけど……母上がぜひリチェさんを迎え入れたいと仰っていてね。」
「伯爵の地位ですか?」
「そう。おそらく研究所の総責任者に任命される際に、伯爵の地位まで一緒に授与される予定だと知っている。」
「ああ……リチェ、こんなことまで気にかけてくれるとは。もう十分だ。」
父は深く感動したようで、ため息をつきながら話した。
「私も、公爵の栄誉よりは伯爵の栄誉が適していると思うよ。そして……」
私は静かに答えた。
「私を探すことを諦めていたその伯爵の地位を、父にお譲りできることがとても嬉しいです。」
ジェイド皇太子と父は、新しい国立医療研究所の構成や計画について話し始めた。
父が出勤することを考えると、いずれにせよ公爵職を辞任する決断は結果的に良い判断だ。
私は途中までその話を聞いていたが、エルアンの状態を確認するために使用人が声をかけに来た。
ディエルがそっと近づいてきて、心の内を静かに打ち明けた。
「どう見ても、かなりのハッピーエンドになったみたいだね……。」
彼は相変わらず言葉を濁しながら、微妙な表情でためらいがちに話を続けた。
「公爵も、君の友人があの方(=貴族女性)だと知ってから、これからは善良で穏やかに生きようと決心したみたいだよ……。魔法師様もそれが効果的だと言っていたし……。ああ、それと、ジケル卿が、過去の教育の未熟さについて君に感謝の意を伝えてくれとお願いしてきた。彼曰く、『今まで気づかなかった礼儀や人間性について学んだ』と言っていたよ。」
正確に言えば、それは私が教えたわけではなく、私を取り巻く状況が彼に反省を促したという話だけど……。
「皇太子殿下も、ついに自分の実力だけでは何もできないことに気づかれたようだ。自分に足りない部分を補うために、他人の知恵を借りるべきだと思い直したようだね……まあ、兄上には散々苦労させられて、それでやっと気づいたというのも、ある意味良い結果なのかもしれない。あの女性に振られることまで考えたら……。」
「そうさ、全部私のおかげだよ。」
私は無感動に肩をすくめて言った。
「知能と人間性がそれぞれ欠けていた二人の男たちが、どうにか私のおかげで足りない部分を補おうと決意したんだってさ。」