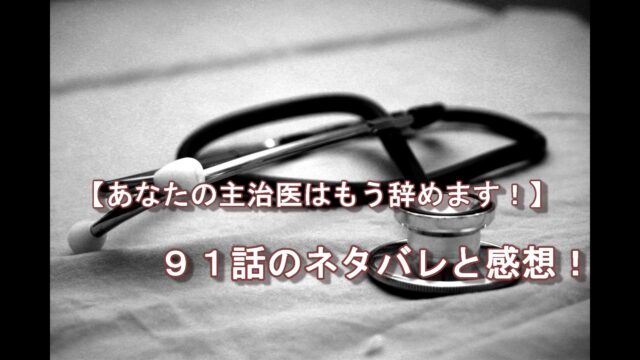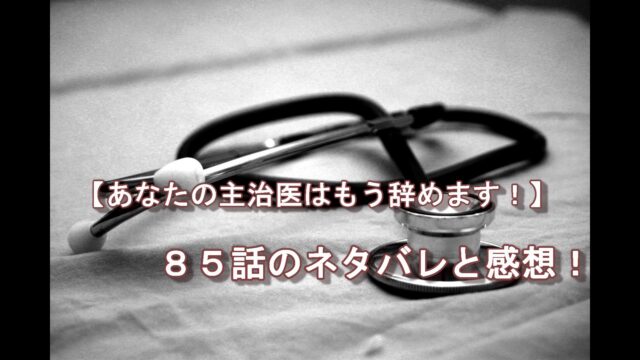「エルアン?」
私が執務室のドアをノックして、そっと顔をのぞかせると、書類に没頭していたエルアンがぱっと笑顔になり、声を上げた。
「リチェ!」
「おやつを持ってきましたよ。一緒に食べながらどうぞ。」
長期研究プロジェクトを無事に終えた私は、久しぶりにとても長い休暇をもらい、公爵城で家族と過ごす日々を送っていた。
私が持ってきた巨大なチョコレートケーキを見て、エルアンは一瞬不思議そうな表情を浮かべたが、すぐにぱっと笑った。
「ケーキだね?」
「はい!チョコレートも砂糖もたっぷり入れました。体には良くないかもしれませんけど……でも、甘ければ甘いほど美味しいでしょう?」
もちろん台所の皆は、私に料理の才能はないと言った。
料理はただ甘ければいいというものではないと、何度も強調された。
甘ければ甘いほど好きだという私の味覚は、偏っているし適度に甘くなければならないとも言われたけれど……それでもエルアンは、私が作ったものは全部美味しそうに食べてくれた。
ただ私が作ったから無理して食べているのだと言うには、他の人には一口も分けなかった。
だから、私たちの味覚は似ているのかもしれないと思いたかった。
「セドリアンとユリアも一緒に作ったんですよ。かなり疲れたのか、作り終えた途端に食べもしないでそのまま昼寝すると言って寝てしまいました。」
不思議なことに、セドリアンとユリアは私が何かを作るときは楽しそうに一緒にいてくれるのに、いざ食べるときになると、そっと席を外すことが多かった。
まぁ、あえて二人きりで過ごさせようという深い配慮だったのだろう。
特にセドリアンは幼い年齢にもかかわらず、本当に大人びていたから。
すぐにでも立ち上がって駆け寄ってくると思っていたエルアンは、誘惑するようにただにやりと笑みを浮かべるだけだった。
ほんのひとときティータイムを楽しむなら、テーブルに向かい合って座るべきなのに。
お茶を持ってきていないから、侍女に持ってこさせなければならないし……。
けれど彼は、甘い言葉を囁く代わりに、疲れたように軽く目を閉じた。
私はふと疑わしく思い、結局彼のそばへと歩み寄った。
「エルアン、どこか具合が悪いのですか?」
エルアンは答えることなくただ目を細めただけで、私はもしかして本当に体調が悪いのではと気になり、机の上にケーキを置いてから、そっと彼の頬に手を当てた。
私が近づいた瞬間、エルアンは私の腰を抱き上げ、そのまま膝の上に座らせた。
「えっ!」
あっという間に書斎の椅子に座る彼にまるで子どものように抱かれてしまった私は、少し目をしばたたきながら尋ねた。
「な、何をしているんですか?」
するとエルアンは率直に答えた。
「わがまま。」
近くで見た彼の体は、どこも悪いところがなく、むしろ驚くほど健康そのものだった。
私のそばに寄り添っているときの彼の顔は、いつになく生き生きとして血色も良かった。
「ティータイムをするなら離れて座らないといけないだろう。でも僕はこうしていたいんだ。」
もっとも、こんな姿を侍女に見せるわけにはいかなかった。
いくら私たちが仲睦まじいのをセレイアス公爵城の誰もが知っているとはいえ、恥ずかしいものは恥ずかしいのだから。
私は小さく息を吐き、彼の体に身を寄せた。
その体は思った以上に引き締まっていて、とても逞しかった。
「じゃあ、仕方ないですね。」
「ありがとう、リチェ。」
エルアンは私の頬や首、肩などに熱い口づけを落としながら、低くつぶやいた。
「ケーキ……僕も一緒に作れたら良かったのに。」
家族との時間を何よりも大切に考えるエルアンにとって、一緒にケーキ作りに参加できなかったことは、とても悲しいことだった。
「でも、予算案が少し急で……」
けれどもエルアンは非常に優秀な参謀であり、それはつまり仕事が山ほどあるということでもあった。
私は彼の力強い腕の中に抱かれ、降り注ぐ口づけを受けながら、切なげに答えた。
「もちろん仕事が優先です。普段だってちゃんと一緒に過ごしているんですから……」
「お母さまが少しでも手伝ってくださればいいのに、書類の一文字さえ見ようとされないんですから。」
「良心があるなら、お母さまに助けを求めるわけにはいきませんよ。」
「……それもそうだね。」
エルアンが公爵位を継いでから、お母さまは本格的な社交と享楽の日々を送っていた。
それまで几帳面に領地を管理していた姿とはまるで別人のようだ。
私が幼かった頃、公爵城に日替わりで使者たちが出入りしていたことを思うと、なおさら信じがたい変化だった。
「そんなに働くのがお嫌いだったのなら、私が公爵位を継いだ後も仕事をされていたのはなぜかしら……。」
――私を必ず嫁に迎え入れなければならない、とエルアンをフェレルマン邸に送り出し、またエルアンが病で意識を失っていたときにも、母上はずっと公爵家の仕事を代わりに取り仕切ってくださった。
だが、エルアンが回復するとすぐに、母上は完全な引退を宣言された。
数日前、ティタインで私が「急に仕事を放り出してしまってよろしいのですか?」と尋ねたとき、母上は宝石のカタログをめくりながら、あっさりと答えられた。
「私が働くためにセレイオス公爵と結婚したと思う?あの美しい顔をじっくり眺めて、この莫大な財産を湯水のように使おうと思っただけよ。」
「……は?」
「この程度の図々しさがなければ、あの頑固な公爵が私にこの座を譲ることなど決してなかったでしょうね。」
「お父さまを……愛していらしたんですよね?」
「もちろん愛していたわ。その人がこの世を去ったあとも、この美貌とこの魅力で一人の男性にもなびかなかったのを見ればわかるでしょう?でも、その人を愛していたからといって、その人の背景まですべて好きになる理由はないじゃない?」
「まぁ……確かに、かなり独立心の強い方ではありましたけど……。」
「そうよ。良い人間が良いものを持っていれば、それに越したことはないのよ。」
――言われてみれば確かに一理あると思い、私は思わず口をつぐむしかなかった。
どんな言い方をされても、お母さまがお父さまを心から愛していたことだけは間違いなかったのだ。
私が初めて母上をお見かけしたときも、すでにかなり高貴で美しい方だったが、それ以上に管理を徹底されていたので、今もなお驚くほどの美貌を保っていらした。
その美しさに加えてその才覚であれば、多くの男性が言い寄ったはずなのに、どの男性とも噂になったことはなかった。
息子であるエルアンが幼いころ長く領地に下っていたため、心置きなく他の男性と出会うこともできた環境だったのに、結局一切なかったというのだ。
エルアンの話によると、母上の机の書棚には常に父上の小さな肖像画が置かれていたともいう。
私は思わず胸が詰まった。
父が母を亡くし私を探して大陸を駆け回ったように、母上もまた父を失ったあと、領地をしっかり治めるために並々ならぬ努力をなさったのだ。
大切な愛を失っても、なお残されたものを守るために――。
二人が人生をかけて尽くしてくれたおかげで、私たちはこうして生きていけるのだろう……。
私がひとり胸を熱くして感動していると、お母さまは目をぱちりと開けて言い放った。
「だからあなたも公爵家の仕事を引き受けようなんて思わないことね。あれは骨折り損よ。全部エルアンに任せなさい。最初から関わらないのが一番よ。」
「ええ、まぁ……今のところそうしていますけど……。」
「うちの息子だけど、顔はいいんだから、それでも眺めてお金でも使って暮らしなさいよ。それって最高の立場じゃない?」
とにかく母上はそのようにして公爵家の仕事から完全に手を引かれた。
私も研究で忙しく、公爵家の仕事を手伝うことはほとんどできなかったので、エルアンは一人ですべてをこなさなければならなかった。
さらには、通常なら公爵夫人が担うような雑務まで、エルアンがすべて引き受けていた。
「仕事が多いですよね?私が少しでも助けになれたらいいのに……」
「君は存在そのものが助けなんだ。こうして時々会いに来てくれるだけで、すべての疲れが溶けていく気がする。」
エルアンは私をぎゅっと抱き寄せ、私の首筋に深く口づけをした。
押し寄せる熱に息が詰まり、思わず体が震えたけれど、私は懸命に気を保ちながら会話を続けた。
「私が研究室に行くとき、あなたは必ず帰り道にまで迎えに来てくれるでしょう。疲れているはずなのに……。」
「何を言ってるんだ。お前の顔を見るだけで疲れなんて吹き飛ぶんだよ。少しでも一緒にいたいから迎えに行ってるのに、それがどうして疲れるんだ。」
「でも、それは……理論的に言えばエネルギーを使ってるわけですから、疲れてることには違いないでしょう。」
「そうか。」
エルアンは淡々と答えながらも、にっこり笑って私の目をまっすぐ見つめた。
「だったら次の研究テーマにしてみたらどうだ?なぜエルアン・セレイアスはリチェに関することなら、エネルギーを使っても逆に疲れが取れるのか。」
「な、何を……。」
「俺は生体実験だって歓迎するぞ。お前が直接やるならな。」
彼が整った顔を上げてにっこり笑った瞬間、それまで必死に抑えていた理性が少しずつ解けて、心がふわりと揺らぐような気がした。
そうだ、母上のお言葉は正しかった。
いずれにせよ、セレイオスの血筋は見事で、この美しい顔を見られるだけでも、公爵夫人の座は十分に価値あるものだった。
「僕はこうしているだけでも疲れが取れるんだ……」
エルアンは私の腰を優しく撫でながら、微笑を浮かべた。
「研究してみない?」
ゆっくりと彼の唇が近づいてくる。
抗えないことをわかっていながらも、私は不満げに小さくつぶやいた。
「……今こうしようとして研究を口実にしたんですか?」
「違う。」
エルアンは柔らかく息を混ぜながら、私の唇に触れて囁いた。
「今だなんて、とんでもない。最初からずっと、そうしたくて仕方なかった。」
まあ、誰もいない執務室に入った時点で、エルアンが私を大人しくさせておくつもりなんてないことくらい、わかっていた。
分かっていても彼の思うままにされてしまったのだから、今さらじたばたする理由もなかった。もちろん拒む気持ちもなかった。
私は彼の膝の上に座ったまま、静かに目を閉じてその想いを受け入れた。
私が作ったチョコレートケーキよりも、はるかに甘美な口づけだった。
私にとっては、いつだって与えてくれるのはエルアンだったけれど――
こんな状況では、私が抵抗しても結局は抱きしめられるように包まれてしまうので、ついには涙がにじむほど切なくなってしまった。