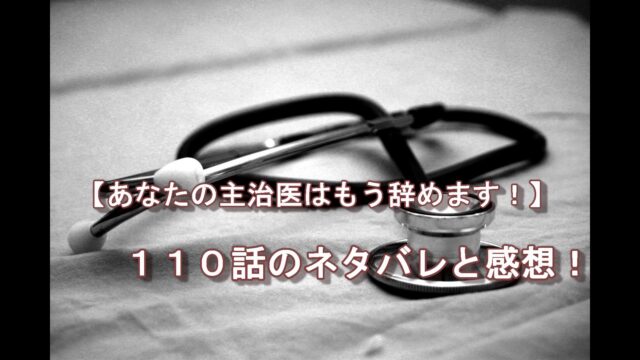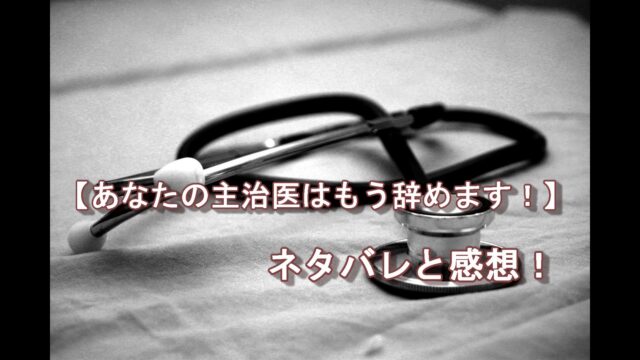こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

165話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- カンシアと子供たち②
しばらく後。
「まったく、最近の人たちは情けがないねぇ。」
よれよれの服を着た一人の乞食が、くたびれた布の袋を背負い、公爵城の前にたどり着いた。
「それにしても、最近の子どもたちはどうして野遊びをしないんだ?」
深い皺が刻まれた顔に、長く垂れ下がった白髪。
そしてその奥で鋭く光る眼差しを宿した老人――カンシアだった。
エルアンとリチェは、公爵家に変数など存在しないと考えていた。
だがカンシアという人は、誰の予想をも裏切る存在だった。
彼女はぶつぶつ言いながらつぶやいた。
「昔は、私に言い寄る若いのが絶えなかったのに。」
もちろん、その自信は紙のように薄っぺらく、いつでもひっくり返るものだった。
もともと彼女はお金が足りなくなるたびに自由都市へ行って、若者を餌食にして金を巻き上げていたが、最近ではそんな風に彼女に付きまとう追従者もめっきり減っていた。
「本当に、信じられない。若者たち、前みたいじゃない。」
カンシアは悲しげにつぶやいた。
「一文銭も遊ばずに、真面目に倹約しながら暮らしてるっていうのに。まったく、この国はどこへ行こうとして、みんなこんな有様なんだ?」
最近の若者たちは、誰も一文銭を無駄にするような真似をしないと言われ、いくら嘆いてみても意味がなかった。
少し前、帝国にとても有能な皇太子妃が迎えられてからというもの、帝国の若者たちは様々な制度を受け入れ、それぞれ夢と希望を持って誠実に自己管理に努めるようになっていたのだ。
仕方なく哀れな老婆のふりをして物乞いをしてみても、最近は乞食さえも誠実に振る舞うようになっていたため、ただ年老いているだけでは人々の財布の紐を緩めさせることはできなかった。
「おばあさん、せめて目の見えないふりでもしないと。今どきは生きるのがどれほど大変か……。それに、おばあさんは着ているものもきちんとしていて、みすぼらしくなんて全然見えませんよ。」
隣の区域の浮浪少年にノウハウを伝授され、年配者のふりをしてみたものの、一日も経たずにただ目を閉じているのが鬱陶しくなって叩き起こしてしまった。
「それなら顔だけでもサービス精神を発揮してみてください。にこやかに微笑んで、『あなたの小さな気遣いが一人の人を正しく導くことができます』って言ってみるんです。特に子供たちには、優しいおばあさんのように笑いかけてください。」
自分を正しく導けるという言葉だった。
嘘をつくくらいならまだしも、笑顔を見せるなんて到底できることではなかった。
とりわけ彼女は子どもが大嫌いだったので、子どもたちに愛想よく笑いかけるなんて、なおさら身の毛がよだつ思いだった。
「それじゃあ花でも売ってみたらどうだい、おばあさん。あそこの花市場の横のゴミ箱をよく漁ってみれば、案外いいものが見つかるよ?一日経っただけだって嘘をついて、安くしてやるって言えば、意外と売れるもんさ。」
カンシアはその言葉を聞いて、もうこれ以上は物乞いとして食いつなぐこともできないだろうと考えた。
その浮浪児の言葉の中で唯一おもしろそうに思えたのは、「一日経ったものを新品だと偽って売りつける」という発想だけだった。
残りはすべて労働しなければならないのが嫌だった。
「勤勉な労働の価値」を強調する神殿の教えに反する彼女としては、到底受け入れられるものではなかった。
そして数日後、その浮浪少年は国が実施するという「貧民救済労働事業」に応募して、まじめに製菓製パン教育を受けるために出ていった。
もちろんカンシアは役所で「あなたも誠実に生きられます」という決まり文句を聞いて人々が押し寄せるや否やすぐ逃げ出してしまったが。
「ちぇっ、だんだん生産性のない浮浪者にまで堅苦しい世の中になってきたな。街の浮浪者が希望を見つけて職を持ち、誠実に生きるだと……?国がどうしてこんな風に生きることを好むようになったんだ?うんざりする。」
とはいえ食べて生きるにはどうにかしなければならず、結局彼女は「パンは焼かない」という信念を一気に捨ててセレイアス公爵邸へ向かった。
数年前、彼女がセレイアス公爵城にやって来たときのことだった。
まず無表情な門番が、ぶっきらぼうに声をかけてきた。
「あなた、ここで何をぶつぶつ言っているんですか?」
カンシアは、今にも自分を追い払おうとするような門番の顔を見ながら、澄ました声で答えた。
「リチェ・エステルに会いに来たのよ。」
彼女が門を通ることを許したのはリチェだった。
いずれにせよ、彼女の助けを借りて父親を見つけ出したのだから。
もちろん、カンシアが善意でリチェを助けたわけではなく、仕方なくそうせざるを得なかっただけなのだが……。
いや、むしろだからこそ訪ねてくるのが気楽だった。
リチェがカンシアを恩人のようにもてなしていたなら、カンシアの性格上、さっさと荷物をまとめて逃げ出していたはずだから。
カンシアはいつでも気楽に食いものにできる相手を好んだ。
腹を満たすことと同じくらい、楽しみを満たすことも重要だったが、たいてい彼女の楽しみは他人を食い物にすることで生まれたのだから。
「リチェ・エステル?」
門番が怪しむように顎を上げると、カンシアは堂々と答えた。
「そうよ!リチェ・エステルに伝えて! カンシア・ローズエターが来たって!」
以前「リチェ・エステル」という名を出してから公爵邸に入った記憶があったのかもしれない。
カンシアは考える間もなく声を張り上げた。
だが若い門番は眉をひそめ、ただ長い間考え込んでいるだけだった。
リチェという名は奥方の名ではあるが、リチェ・ペレルマンでもなく、リチェ・セレイアスでもないとなると、少し怪しく思えたからだ。
門番が曖昧な表情を浮かべているのを見て、カンシアはついに怒り出した。
「ほら!あの茶色い髪に緑の瞳、賢そうに見えてとんでもなく頭の回転が早い子がいるでしょ!」
門番はますます困惑した。
確かに似ている人物がいたような気はしたが、かといってすぐに同意できるほど確信のある話ではなかったからだ。
しかも、公爵夫人であるリチェは今は不在中だった。
だが、不在だからといって門前払いしてしまうのも難しい状況だった。
本当にこの人物を通してもいいのだろうか?
「前にも来たって言ったじゃない!あんたみたいな青二才じゃなくて、ちゃんと経験があるのよ!」
「ふむ……“前”とは、いつ頃を指しておっしゃっているのですか?」
カンシアは指を折って大まかな数字を数えてみせたあと、あいまいな口調でしどろもどろになった。
「えっと……その……7年前だったか、8年前か?いや違うか?9年前かな?」
答えは煮え切らなかったが、結論は明白だった。
もちろん当時勤めていた門番たちは全員昇進し、公爵邸の内部管理者になっていたのだ。
結局、門番はこの怪しげな訪問者について上に報告するという、ごく安全な選択を取ることにした。
「少々お待ちください。すぐに上官に報告してまいります。」
「そう? じゃあその前に、ちょっとこちらに来てみて。これを見せれば、話が早くなるはずだから。」
カンシアはカバンをまさぐり始め、門番も何か証明書でもあるのではないかと思い、彼女のそばにぎこちなく近づいていった。
その時だった。
「何をしている!」
鋭く響く声と同時に、固い剣の鞘がカンシアの手首を打ち払った。
「きゃあっ!」
カンシアの悲鳴とともに、彼女が手にしていた銀の腕輪が床にカランと落ちた。
門番は驚き、その腕輪を拾い上げた。
慌てて腕輪を見てみると、銀の腕輪が一瞬のうちに消えていた。
「なんと、この婆さんがいつの間に私の腕輪を!」
「いつもそうよ。近づいてくるとすぐに仕事を始めるんだから。」
そして、カンシアのスリ行為をその場で見破ったユリアが堂々と告げた。
「地下牢へ連れて行きなさい。卑しいスリなんだから。」
門番は再び銀の腕輪を手に取り、カンシアを見つめた。
怒るというより、むしろ呆れ果てた表情だった。
「お婆さん、本当に何もご存じないようですね……。ここはどこでもない、セレイオス公爵城内ですよ。その中で犯罪を働くつもりですか?まさか、他のスリ仲間たちに恩を売ってもらえなかったのですか?」
門番は手で喉をなでる仕草をしながら、困惑したように言った。
「イザベル・セレイオス様の時代から、この公爵領はもちろん、公爵家の中でも犯罪はすっかり根絶されたんですよ。ご存じなかったんですか?」
「私の領地でもないのに、どうしてそんなことを知っていなきゃならないの?」
カンシアは透き通るように澄ました声で、不機嫌そうに吐き捨てた。
「セレイオスが小さな犯罪にもどう対応しているのか、噂程度でも聞いたことがあれば、地下牢のような残酷な結末は避けられたでしょうに……」
「地下牢?そこで食事をするの? 実を言うと、私は牢獄には慣れているの。」
悠然と耳を掻くカンシアを見て、門番が声を荒らげた。
「そんなことがあるものか! 水一滴たりともやらんぞ。」
「おや、この豊かな領地でそんなにケチなのかい?まったく、持ってる者は欲深いね。なら行かない!絶対に行かないよ!」
堂々としたカンシアの言葉に、ユリアが冷ややかな顔で鋭く言い放った。
「それを決めるのはお前じゃない。犯罪者のくせにどこでそんな大声を張り上げるんだ?」
「なんだい、ちょっと盗んだくらいで、まるで大罪人を軽蔑するような顔をして!え?そんなことしてたら、この子がすごくお堅くて堅苦しい大人に育つじゃないか!」
「馬鹿げたことを言うな、さっさと連れて行け。私の目の前から!」
ユリアはそばにいた騎士たちに冷たく命じ、カンシアはとうとう彼らの手に引きずられ、公爵城の中へとずるずる連れて行かれた。
結論から言えば、カンシアは地下牢へは送られなかった。
「リチェを呼んで!リチェを呼んできなさい!それが無理なら、あのつまらない公爵でもいいから連れてきて!あなたたちが私をこんなふうに扱っていいはずがないでしょう!」
カンシアはすぐさま公爵城の前庭で地団駄を踏み、大騒ぎをした。
そのとき、ちょうどセドリアンと散歩をしていたイザベルが彼女を見つけゆっくりと近づいてきたのだった。
「え…… そ、その……」
イザベルは目を細めて大きく見開き、驚愕していた。
カンシアの名前までは思い出せなかったが、それでも水晶の口寄せで真実を教えてくれた、あの不気味な集会については覚えていた。
明確に水晶を差し出したわけではなかったが、それでもリチェやシオニーに真実を知らせてくれた人物である。
だから軽々しく否定することはできなかった。
「……そう、だからあなたは……」
その場で犯罪者を地下牢へ連れて行けと厳しく命じていたユリアも、思いのほか柔らかなイザベルの態度に驚き、ぱちぱちと目を瞬いた。
「えっ、おばあさま?」
そしてその顔を見て、カンシアがユリアに顎をぐいと突き出した。
「小娘、分かってる?世の中はお前が予想もできないようなことで満ち溢れているんだよ。」
カンシアの呼称をどうすべきか迷っていたイザベルが、自信なさげな声で尋ねた。
「あなたは……物乞いのジプシー?」
イザベルはセドリアンとユリアの前に立ち、言葉選びに気を遣おうとしたが、頭に浮かんだのはそれしかなかった。
「そうよ!ようやく話が通じる相手に出会ったじゃない!」
カンシアはさっと立ち上がった。
もちろん、彼女はイザベルのことをまったく覚えていなかったが、それなど関係なく、まるで当然の権利であるかのように堂々と問い詰めた。
「リチェはどこ?」
かなり無礼ではあったが、イザベルは咎めなかった。
何にせよ、リチェの伴侶を探し出してくれた恩人であることに変わりはなかったからだ。
「リチェは今、公爵城にはいないけれど……何の用なの?」
「ふん。」
リチェがいないと聞いた瞬間、カンシアの表情がわずかに歪んだ。
それなら、せめて顔なじみで、リチェに執着していたあの男でも会わなければ……。
以前、どこか貴族の邸宅で出会ったこともあったのだから。
標的を即座に切り替えたカンシアは、仕方ないといった様子で続けて尋ねた。
「じゃあ、あの家庭教育も受けてない目つきの悪い公爵の小僧は?」
もちろんイザベルはその問いにも素直に答えるしかなかった。
「彼もいないの……。」
カンシアの顔に本格的な失望の色が浮かび始めた。
そうなると、ここでこれ以上探す相手がいない。
面識もない人間に「私がリチェと知り合いだから金を出せ」と言ったところで、どうにかなるはずもない。
結局カンシアは半ば諦めたように、苛立ちを混ぜて尋ねた。
「まったく……で、あんたは誰なんだい?」
イサベルはとても忍耐強く答えた。
「家庭教育が行き届いていなかった公爵の息子を産み、育てた人です。」
カンシアは「あら」と小さな感嘆を漏らした。
よく見ると、顔立ちがとてもきつい印象なのが、どことなく目元が彼とよく似ていた。
「ほう、目元を見ると似ているような気もするな……。ただ者じゃない息子をお産みになったようで。ご苦労なさったでしょうな。ふふふ。」
どれほど強気なカンシアであっても、この状況でイサベルに金を差し出そうとは思わなかった。
敗北を素早く悟ったカンシアは、自分をじっと見つめているセドリアンとユリアには目もくれず、苦笑いを浮かべた。
「おほほ。」
彼女は「もう駄目だ」と思ったように身を揺らし、すっかり立ち上がった。
そして肩をすくめて言った。
「まあ、リチェがいないなら私はこれで。じゃあ元気でね。」
しかし、そのまま立ち去ろうとしたカンシアは、しっかりとした子供用の木剣に行く手を阻まれた。
ユリアが目を大きく見開き、きっぱりと言った。
「怪しい人を放っておくわけにはいきません。それに母と知り合いだなんてあり得ませんから!」
「お前は何だ?その鋭い目つきをして。」
「……その鋭い目をした公爵の娘です。」
「あ。」
カンシアは額に手を当て、こめかみが痛むような表情をした。
「そういえば、あの忌まわしい奴に本当にそっくりだったわね。」
イサベルとエルアン、ユリアの目元は三代にわたってよく似ていたため、イサベルはまたしても胸の奥で深いため息をつかずにはいられなかった。
――あの食い詰めた者を救ったのはリチェの恩人。その者のおかげで、すべての出来事の真相を知ることができたのだ……。
彼女がこれほどまでに忍耐を示すのは、本当に久しぶりのことだった。
事情を知らないセドリアンは、にやりと笑いながら口を挟んだ。
「一体誰なんだ?このくらいの状況なのに、俺たちの祖母が黙って見過ごすとは……確かにただ者じゃないな。」
「じゃあお前はリチェの息子か?利口ぶって実際は全然大したことないところは母親そっくりだな。」
カンシアは子供に対して少しも愛着を持たないので、特に関心を示すことはなかった。
だが時間を無駄にするのが惜しくなり、ユリアの木剣を軽くはたきながらぶっきらぼうに言った。
「もういいだろ。私を放してくれなかったらどうするつもりだ?」
「泥棒の見せしめに城門に吊るしてやるんです!」
ユリアは朗々とした声で叫んだ。
その気迫に、思わずイサベルが感嘆の眼差しで手を口元に当てた。
「まあ……私の孫娘が、まるで私に瓜二つだわ……。」
セドリアンが深刻そうに口を開いた。
「ともかく、公爵が使用人に危害を加えようとしたのだから、ユリアの意見通り調べるのが妥当だと思う。父さんと母さんがいない分、僕たちがしっかり城を守らなきゃいけないってことだよ。」
二人とも子供とは思えないほど、しっかりした物言いだった。
それに、リチェ・エステルも一度たりともカンシアに屈したことはなかった。
「それに、あの人は僕たちの父さんと母さんを侮辱したんだ。」
ユリアも同意するように、力強く言った。
「うちの母さんはあんなに軽率じゃないし、父さんだってあんなに卑しくない!うちの父さんと母さんは完璧なんだから!」
「なんだって?」
カンシアが鼻で笑った。
「おチビちゃん、それはなんてでたらめだ?いくら子供でも、そんなふざけたことを言っちゃいけないよ。」
「パパは優しくて朗らかな人なんだ!誰にとっても太陽みたいな大人なんだから!それを『まともじゃないやつ』だなんて、そんな侮辱は許せない!」
「……太陽?太陽だって?ははっ、太陽はもう全部凍りついて死んでるわ。」
ユリアの言葉を聞いたカンシアは、地面を叩きそうなほど大笑いした。
そして呆れたようにイサベルを見やった。
「これは一体どういうことだ?太陽だと?最近の太陽どもは頭がおかしくなったのか?」
「ごほん、ごほん。」
イサベルはカンシアの目を避けながら、戸惑ったように黙り込んだ。
彼女が考えても「太陽のようなエルアン」なんて言葉は到底受け入れられるものではなかったからだ。
「まあ、家庭教育がうまくいって、エルアンも今は温かく真っ直ぐに生きているようね。」
「なにを……。そんなの演技に決まってる!人がそんな簡単に変わるわけないだろ!」
カンシアがまたケラケラ笑い出すと、セドリアンも耐えきれず隣で拳を握りしめて叫んだ。
「父さんだけじゃない!母さんまで侮辱するのか?うちの母さんは、どんな状況でも知識をひけらかしたり、人に怒りをぶつけたりするような人じゃない!」
「アハハハハハハ!これは面白いわ。笑えるじゃない。死にそうだ、ほんとに。」
カンシアは真剣なセドリアンの顔を見て、またもや腹を抱えて笑い出した。
そして、ある瞬間に笑いをぴたりと止め、目を細めながら言った。
「お前たち、じゃあ私が面白いものを見せてやるから、それを見てから失せるんだな。」
どんなに落ち着いたふりをしていても、子供は子供だった。
「面白いもの」という言葉に、子供たちはすぐに反応した。
「……面白いもの?」
カンシアはカバンをごそごそと探り、水晶玉を取り出した。
「あ……」
数年前、その水晶玉を使って皆の前でカンシアがシオニーの死を見せたことに衝撃を受け、見守っていたイサベルは息を呑んだ。
祖母の反応を見たユリアとセドリアンもますます動揺し、喉の渇きを覚えた。
カンシアは仕方ないといった様子で再び公爵邸の前庭に立ち、ぶつぶつとつぶやいた。
「見たい過去があるなら言ってみな。一つだけ見せてやる。」
「え?」
「早く言いな。何が見たい?これは魔法だ。誰にでもできることじゃないんだよ。」
その瞬間、セドリアンとユリアの目が見開かれた。
二人にとって、まともな「魔法」を目の当たりにするのは初めてだったからだ。
何かおかしいのでは、と二人の子供がイザベルの表情をうかがったが、イザベルもまた完全に真剣な顔をしていた。
イザベルは深刻な目で慎重に尋ねた。
「本当に……また見せてくれるの?」
「また」という言葉に、セドリアンとユリアは一瞬で固まった。
それならおばあさんは、すでにこの人の魔法を見たことがあるの?
子供たちが少しパニックに陥る中、カンシアがぶつぶつ言った。
「その代わり、さっき小物を盗んだのは見逃してちょうだいな。本当は金の指輪もあったのに、正直に銀の腕輪だけにしたんだから。」
「金だろうと銀だろうと、それはきちんと罰を受けなきゃいけない。」
そのとき、セドリアンがようやく我に返り、理屈っぽく反論した。
「そんな才能があるなら、どうしてそんな暮らしをしてるんだ?そのくらい魔法を使えるなら、大金だって稼げるはずだろ!」
「この世間知らずのガキは何も分かっちゃいないな。」
カンシアは鼻で笑いながら答えた。
「そんな風に金を稼いだところで、何が楽しい?私は労力や能力を金に換えたいわけじゃない。そんな金に価値なんてないんだよ。」
「……そ、そうなのか?」
十七年生きてきて積み上げてきた価値観を揺さぶられたセドリアンに向かって、カンシアは面倒くさそうに言い放った。
「他人をちょっと脅して、金を巻き上げるのが好きなのさ。」
そしてまるで自分が会話の主導権を握っているかのように、カンシアが鋭く言い放った。
「それで、いつ見たいの?一度だけよ。魔力がかなり必要なことだから。」
「え、えっと、それは……」
イザベルは困惑した目で足をもじもじさせ始めた。
この機会を逃すわけにはいかない気がするのに、あまりにも唐突で動揺していたのだ。
再び見たい過去の出来事なんてあるだろうか……これ?それともあれ?一度だけしか見られないというのに……。
イザベルが迷っている間、カンシアは苛立ちを抑えられずに怒鳴った。
「もういい!私が勝手に見るわ!」
「そんなのありえないでしょ……!」
イザベルが抗おうとしたその時、水晶球に映像が映り始めた。
初めて目にする光景に、ユリアとセドリアンは驚いて呆然と水晶球を見つめた。
「リチェ、気をつけて。歩かないで。行きたいところがある? 私が抱いていってあげる。赤ちゃん、何か食べたいものはないかい?」
今より少し若く見えるエルアンがいた。
彼の顔には喜びが満ち溢れていた。
イザベルは衝撃のあまり目を大きく見開いた。
水晶球に映った姿は、まさにセドリアンが胎内にいた頃の映像だった。