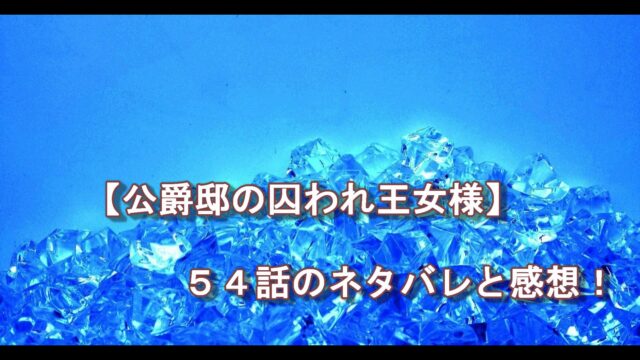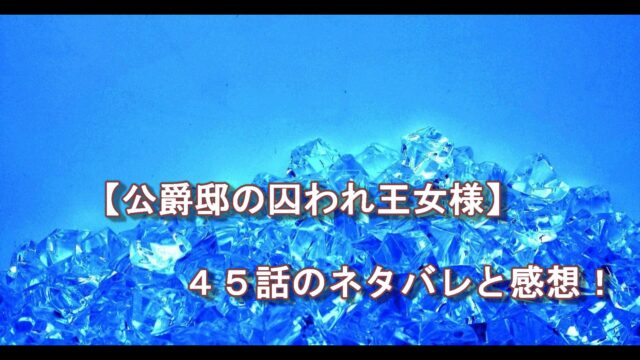こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

134話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 脆い感情
「すぐ戻る」と言っていたはずのバレンタインは、日が暮れても修道院へ戻ってこなかった。
最初は、――何か大事な用事が長引いているのだろう。そう思っていた。
だが、日が沈み、夜が更けても姿を見せないことに、シャルロッテとクラリスの胸に、じわじわと不安が広がり始めた。
彼が特別に危険な場所へ向かったわけでもない。
それなのに――こんなにも胸騒ぎが消えないのは、きっと――あの日の会話のせいだ。
『私が戻るまで、勉学にだけ集中していなさい』
あの言葉は、なぜわざわざ口にされたのだろう。
――もしかして、王子殿下にとって好ましくない何かが起きているのでは?
そんな不安に駆られ、クラリスは司祭から新聞を借りて目を通した。
だが、王城や王族に関する異変を示す記事は、どこにも見当たらない。
それでも胸のざわめきは消えなかった。
――もし、少し前に起きたあの事件と関係があるのだとしたら……?
レノクス侯爵家と魔法師団が密かに結託していたという噂。
もしそれが真実なら、決して穏やかでは済まない出来事が起きている可能性もある。
そう考えた途端、クラリスは落ち着かなくなり、ただひたすら、ヴァレンタインが戻るのを待つようになった。
勉強に身を入れようとしても、集中は長く続かない。
時折、理由もなく体がうずくと、修道院の門の近くまで歩いては、遠くの道を見つめた。
午後の陽が傾きはじめた頃――遠くから、誰かが近づいてくる気配がした。
胸の奥が、きゅっと締めつけられる。
――来たのだろうか。
そう願いながらも、同時に、胸の奥で嫌な予感が静かに息を潜めていた。
馬車の姿が見えた。
王室の紋章を掲げたものではなかったが、クラリスは――もしかするとバレンタインが別の馬車に同乗して戻ってくるかもしれない、そう思い、近づいてくるのを待った。
やがて、正門のすぐ前で馬車が止まり、扉が開く。
修道院で定められた灰色の僧衣が、わずかに覗いた気がしたが……。
馬車から降りてきたのは、エイヴェン・ベルヴィだった。
彼はクラリスを見つけるなり、言葉も交わさず、まるで吐き気をこらえるように一瞬だけ眉をひそめた。
「……っ。」
クラリスも、同じように顔をしかめる。
「……っ。」
互いに“できることなら見たくなかった相手”を前に、数秒ほど睨み合ったのち、エイヴェンはようやくクラリスの前まで歩み寄った。
「ともあれ、私と友情を保とうとする最低限の努力は評価しますよ。ですから――挨拶くらいは交わしておきましょう。」
彼はそう言って、わざとらしく一礼した。
「……ただいま戻りました。」
「どういう意味ですか?」
「わざわざ迎えに出てきてくれたことへの感謝、という意味ですよ」
そう言うと彼は、有無を言わせずクラリスの手を取って握り、取り出したハンカチで掌を丁寧に拭った。
「私があなたと親しくしているのは、サンクレア様の慈悲深いお心を引き出すためです。……お分かりですか?どうか、私がどれほど高潔な人格を備えているか、きちんとお伝えください」
その様子を見る限り、彼は余裕を失った衝撃から、完全に立ち直ったようだった。
いつもの――いや、むしろ平常以上に自信に満ちた態度だ。
クラリスは無用な言い争いを避けたいと思い、ひとまず小さく頷いた。
だが、クエンティンと再会し、アビントンについて語り合う――そんな展開を期待する余地は、残念ながら微塵もない。
「結構です。では中へ入りながら、どこへ行っていたのか説明していただきましょう」
「……はい?」
「それを聞きたくて、わざわざ迎えに来たわけではありませんよ?もっとも、試験生代表として王城に招かれた以上、多少の説明責任はあるでしょうが」
彼の声は終始穏やかだったが、その奥には有無を言わせぬ圧が滲んでいた。
クラリスは胸の奥に、言い知れぬ重さを覚える。
――やはり、ただの迎えではなかった。
そう確信しながら、彼女は黙って修道院の扉へと足を向けた。
静かな石畳の上で、二人の影だけが、ゆっくりと並んで伸びていった。
「――それは、誰にとっても羨ましい話でしょうね。」
エイヴェンは、内心では皮肉の一つも言ってやりたい気分だったが、城壁の向こうで“然るべき人間たち”と会ってきた直後なのか、戻ってきた彼の肩はどこか誇らしげに持ち上がっていた。
「今回の奨学生選抜に、関わってこられたのですか?」
「ええ。陛下が直々に遣わされた侍従とお会いして、意見を述べてきました。」
どうやら、王妃が進めていた奨学事業は、一時的に王の管轄へ移されたらしい。
「その侍従の方も、かつてこの修道院で学ばれた経験がおありで。私に、司祭方の近況を尋ねる程度には、親しみを見せていました。」
「……そうでしたか。」
クラリスは、王城へ行ってきたというエイヴェンに、何か異変を感じ取れなかったか、探るように問いを重ねることにした。
「何かありましたか?」
「第三城壁の内側で、何か“特別な出来事”はありませんでしたか?」
クラリスの言葉に、エイヴェンは一瞬だけ間を置き、ゆっくりと頷いた。
「ええ。だから今、その“特別な用件”について話している最中では?私の業務の一環ですから」
「いえ、それは……」
クラリスはこれ以上の説明を諦め、小さく首を振った。
どうせ、ヴァレンタインが戻れば、何が起きていたのかはいずれ明らかになる。
「本当に何でもありません。王都まで足を運んでいただいて、お疲れさまでした」
彼は眼鏡の位置を直し、片手で顎を軽く撫でた。
「試験生代表として、当然の務めですよ」
気がつけば二人は並んで回廊を抜け、寮の玄関前へと辿り着いていた。
「それでは」
クラリスは勉強に戻る旨を告げ、別れの挨拶をしようとした。
だが彼は、何かを思い出したように足を止める。
「ああ、そうだ」
何気ない口調のまま、彼は言葉を続けた。
「私があちらで、誰と会ったか……ご存じですか?」
その問いに、クラリスの胸が微かに波打つ。
――やはり。
穏やかな声音とは裏腹に、その視線は逃げ道を与えない。
見えない糸で絡め取られるような感覚に、クラリスは言葉を失った。
彼の周囲には、いつの間にか“然るべき人脈”が、巧妙に張り巡らされている。
それを誇示するかのように、彼は薄く微笑んだ。
沈黙の中、夕暮れの風が二人の間をすり抜けていった。
「勉強しに行ってきたんです。」
エイヴェンが誇らしげに語り始める気配を察して、クラリスは話が長くなる前に、さりげなく相槌を挟んだ。
「驚かないでください。セリデン公爵様にお会いしましたよ。」
「え?本当ですか?」
「新聞に時々載る肖像画よりも、実物のほうがずっと迫力があって……正直、驚きました。」
「でしょう!」
思いがけない方向の話題に、クラリスはそれ以上追及するのをやめ、軽く肩をすくめながらエイヴェンの隣へ並んだ。
「肖像画と実物を比べたら、肖像画が気の毒になるくらいです。」
「まさにそれです。あまりに立派で、きちんと礼を失していなかったか、あとから心配になるほどでした。」
エイヴェンは感極まったような表情で、両手を胸の前でぎゅっと合わせた。
「それでも、公爵様は私にとても丁寧に接してくださいました」
そう口にしながら、クラリスは自分でも驚くほど、わずかに誇らしい気持ちになっているのを自覚した。
公爵の慈愛は、彼女が特別に望んで得たものではない。
それでも――。
「修道院の調度は不便ではないか、食事は口に合うか……そんな細かなことまで、気にかけてくださいました」
彼が静かに頷きながら話を聞く姿が、自然と脳裏に浮かぶ。
真剣で、どこか慎重で、相手の言葉を決して軽く扱わない表情。
そして、少しだけ自意識過剰かもしれないと思いながらも、クラリスは考えてしまう。
あれほど修道院の環境を気にするのは――自分が、ここにいるからではないのだろうか、と。
『公爵様は、私のことを……気にかけてくださっている』
以前は、それを単なる監督官と被監督者の関係だと思い込もうとしていた。
立場の違いがそうさせているのだ、と。
けれど、共に過ごす時間が重なるにつれ、クラリスは公爵の眼差しに宿る“熱”を、見過ごせなくなっていった。
冷静さの奥に、確かに存在するもの。
それが何であるかを、はっきり言葉にする勇気は、まだない。
たとえ彼が直接、愛情を口にしたことは一度もなかったとしてもクラリスは分かっていた。
「本当に、良い方ですよね。」
気づけば二人は、自習室も階段も通り過ぎ部屋の前まで並んで歩いてきていた。
「はい。できることなら、もう少しお話ししてみたかったです。」
――せめて、処刑の話題でなければ。
そんな言葉を、彼は胸の内で飲み込んだ。
「え?しょ……処刑、ですか?」
クラリスは耳を疑い、はっとして周囲を見回したあと、慌てて彼の唇に指を当て、小声で囁いた。
「静かにしてください。誰かに聞かれたらどうするんですか!」
エイビントは一瞬むっとしたものの、すぐにまた、どこか楽しげな、悪戯っぽい笑顔に戻った。
「受験生の代表みたいな立場ですから。こういう話を知っていても不思議じゃないでしょう?それに……私もいずれは、あの城壁の内側で重要な役割を担う人間になるわけですし。」
クラリスは、とりあえず小さく頷いた。
少し前に「処刑」という言葉を耳にしたせいだろう。
胸の奥に、重たいものが沈んだまま離れなかった。
「私と一緒に向かわれた司祭様は、王室に挑んだ愚かな罪人たちに、最後の祈りを捧げるために行かれました」
だから今日は、エイヴィントが一人で戻ってきたのだ。
「本日、王城では公爵様が直々に主宰される非公開の処刑が行われます。ああ、残念です。卑劣な反逆者どもを斬り伏せるお姿を、この目で拝見できないとは。公爵様なら、きっとこう――」
彼は口で「チャッ!」と音を立て、手刀で誰かの首を落とす仕草をしてみせた。
その瞬間、クラリスは氷水を浴びせられたような感覚に襲われ、無意識に肩をすくめた。
――おかしな気分だった。
クラリスは、マクシミリアンが処刑を執行したという事実に、思いのほか深く傷ついている自分に気づいてしまった。
胸の奥が、ひりつくように痛む。
それが嫉妬なのか、恐れなのか、それとも――彼を知ってしまったがゆえの痛みなのか。
答えは、まだ見つからないままだ。
――それは……私が心を痛めることじゃない。
公爵様は、公爵様として「やるべきこと」をなさっているだけ。
そう何度も言い聞かせ、胸の奥に湧く感情を押し戻そうとしたが、気持ちは少しも軽くならなかった。
――どうして?
いつかは、クラリス自身も“マクシミリアンが担う立場”になるはずなのに。
……その事実は、最初から分かっていた。
この地に来ると決め、約束を交わし、今日まで生きてこられた幸運に、彼女はずっと感謝してきた。
その想いを――忘れていない、つもりだった。
けれどクラリスは、いつの間にか自分が「処刑」というものを、どこか抽象的な概念としてしか捉えていなかったことに気づく。
そうでなければ。
マクシミリアンが自らの手で、誰かの首を刎ねる存在になるという現実を、これほど生々しく、胸を締めつけるように感じるはずがなかった。
……恩恵の意味すら分からぬまま。
彼女はいつの間にか、自分がまるで公爵家の一員にでもなったかのように、無自覚に振る舞っていたことに気づいてしまった。
公爵を称える言葉に、思わず肩をすくめてしまうことも。
公爵夫人が身ごもったと聞けば、生まれてくる子どもたちを「弟や妹」のように思い、心のどこかで待ちわびていることも。
――どれも、彼女の立場にはまるでふさわしくない。
たとえ公爵夫妻が情深く、そのような距離感を許してくれていたとしても、クラリスは自分を戒めるべきだったのだ。
彼女はふらつく足取りで、自室へと向かった。
いつの間にか、自習室に置き忘れてきた本やノートのことなど、完全に頭から抜け落ちていた。
今はそれよりも――自分が何者であるのか、その境界線を、はっきりと胸に刻みつけることの方が重要だった。
(私は……)
心の中で、強く言い聞かせる。
――私は、グレジェカイア王国の王女、クラリス・レノ・グレジェカイア。
――そして、戦争捕虜。
――王家に預けられた存在。
それ以上でも、それ以下でもない。
その事実を忘れた瞬間、きっと――取り返しのつかない一歩を踏み出してしまうのだと、彼女は直感していた。
その恩恵で、かろうじて生き延び、十八歳を迎えたとき――。
そこまで考えた瞬間、彼女は自室まであと数歩という場所で、ぴたりと足を止めた。
――それじゃあ、私は……十八になったら……。
「お嬢様?大丈夫ですか?」
そのとき、クラリスの部屋の前で待っていたノアが、心配そうに歩み寄ってきた。
そういえば今日は、管理室の窓を直すと言っていた。
きちんと修理できるか不安だから、ノアも一緒に見に来る、と話していたのだ。
クラリスははっとして、慌てて顔を上げた。
今は、なぜだかノアに会いたくない――そう思った。
……いや、違う。
本当は、とても会いたかった。
こんなふうに心がぐらぐら揺れる日には、ノアが、クラリスを抱きしめてくれなければならなかった。
けれど、その衝動もまた……罪人という立場にふさわしいものでは、決してなかった。
――分かっている。そんなことは。
クラリスは顔を上げることもできないまま、傍らに立つ彼の腕を、そっと掴んだ。
逃がさないように、けれど壊さぬように――ほんのわずかな力で。
「……ノア」
涙を含んだ声で名を呼ぶと、彼は驚いたように身をかがめ、彼女の表情を確かめようとした。
その仕草があまりに優しくて、胸の奥に、感謝と同時に新たな自己嫌悪が押し寄せる。
――いけない。
――こんなこと、してはいけないのに。
そう思うのとは裏腹に、掴んだ手は、無意識のうちに少しだけ力を増していた。
やがて、ゆっくりと顔を上げ、彼と視線が重なる。
その瞬間、クラリスは自分を縛りつけていた理性を、すべて置き去りにしてしまった。
抑え込んできた思いも、理屈も、立場も。
全部、振り切って――ただ一人の少女として、素直な願いを口にする。
「私……一度だけでいいの。抱きしめて、くれない……?」
言葉を終えた途端、堰を切ったように涙が頬を伝い落ちていく。
止め方など、もう分からなかった。
それでも彼女は、逃げなかった。
その場に立ち尽くしたまま、答えを待っていた。
少しのあいだ、もじもじしていたノアは、クラリスに何か話しかけようとしていたようだった。
けれど、彼女の頬を伝う涙を見つけた瞬間、彼はほとんどためらうこともなく、クラリスの腕を取って彼女の部屋へと連れて行った。
カーテンが陽光を遮り、視界がほの暗くなった部屋に入ると、窓を閉め、回された腕がそのままクラリスを包み込んだ。
その腕は、まるで最初から彼女を抱くために存在していたかのように、しっかりと、けれど優しく彼女を抱き寄せていた。
導かれるままに進んだ先で、クラリスは自分のために用意されたかのような場所に、顔をうずめることができた。
同時に、喉の奥でかろうじて堪えていた嗚咽が、ついにこぼれ落ちた。
まるで幼い子どもに戻ったかのように声を上げて泣くことを、不思議に思うべきなのかもしれない。
それでもノアは、ただ黙ってそこにいてくれた。何一つ、言葉を発することなく。
なぜだか、クラリスが先に彼を押しのけ、顔を上げるその時が来るまで――彼は、いつまでもこうしていてくれるような気がした。
「……いつまでも」
そうであるなら、クラリスはこの時間が、ほんの少しでも長く続けばいいと願ってしまった。
なぜなら――
「私……ノアを、好きになってしまったから」
身の程もわきまえず。
才ある魔法使いと、死刑囚など、釣り合うはずがない。
未来の約束ひとつできない人間が、こんな感情を抱いていいはずがあるのだろうか。
クラリスは、答えは否だと思っていた。
「ごめん……なさい」
涙がようやく収まったように感じられて、クラリスはおそるおそる彼に言葉を向けた。
「そんなふうに言わないでください」
ノアは、クラリスの背をゆっくりと撫でてくれる。
「……それでも」
静かな声が、すぐ耳元で響いた。
「俺が、君の役に立てるなら。それだけで嬉しい」
ああ、本当に。
その実直すぎるほどの優しさが、嬉しくて、そして少し憎らしくて――クラリスは思わず両腕を伸ばし、ノアの腰にぎゅっと抱きついた。
「うぐっ」
それほど強く抱いたつもりはなかったのに、なぜか苦しそうな声が返ってくる。
からかわれているのだと思ったクラリスは、相変わらず彼の胸に顔を埋めたまま、ちらりと顔を上げた。
「そんなに強く抱きしめてないのに……」
もう涙は止まったはずだと思っていたのに、まだ目元には湿り気が残っていて、頬をかすめるたびにくすぐったく、また涙が滲んでくる。
「…………」
やがて、少し冷たい指先がクラリスの顎に触れ、そっとなぞるようにして涙を拭った。
伏せた視界の向こうで、彼が目を細めているのが見える。
「……あまり、泣かないでください」
「…………」
静かな声が、すぐ近くで落ちる。
「少女が泣いていると……俺の決心も、どうにも揺らいでしまう」
そう呟きながら、彼はまた零れ落ちる涙を指先で拭い、そのままクラリスを強く抱きしめた。
クラリスは何度か小さく鼻をすする音を立て、それから無理やり喉の奥に嗚咽を押し込み、ようやく彼に声をかける。
「もう……全部、泣いたと思う……」
「嘘だ」
まるでそれを否定する証拠を突きつけるように、彼は彼女の背をゆっくり撫で、堪え込まれた涙をさらに引き出した。
「……できなかった」
泣きながらこぼしたその言葉に、ノアは少しだけ笑ったようだった。
彼女の胸に顔を埋めているせいで、その音ははっきりとは聞こえなかったけれど。
「それ、外したら……だめ?」
クラリスが抱きしめていた腕をほどきながらそう言うと、彼はぎょっとした様子で首を横に振る。
「あ、だめです。それがないと困るんです!」
「何が?」
小さな問いが、二人の間に落ちた。
「……あ、それ」
彼はしばらく呆然と宙を見つめ、それから諦めたように小さく首を振った。
「がっかりした。とにかくダメです。それ。そ、そんなに露骨に失望した顔をしても無駄ですよ」
「それはがっかりするよ。だって私は、ノアの顔がとても好きで、いつも見ていたいって思ってるんだもの」
「お願いですから、そういうこと言わないでください……」
彼はひどく困った様子で、顔をそっぽに向けてしまった。
――ノアは心が優しいから。
一番の親友であるクラリスが、彼の顔を見たがっているという事実を、きちんと気にかけてくれているのは間違いなかった。
「ねえ、あるでしょう?ノア」
クラリスはつま先立ちになり、彼の仮面へと、そっと手を伸ばした。
顔を見ることが叶わないのなら、せめて――あの美しい紫色の瞳と、向き合っていたかったのだから。
「……少女!」
けれどノアは、クラリスの手が伸びてきた理由を、まったく別のものだと勘違いしたらしい。
彼女の指先を避けるように、とっさに身をひねり、完全に体を背けてしまった。
「あ……」
つま先立ちのまま手を伸ばしていたクラリスは、その瞬間、均衡を失って横へと傾ぐ。
「……っ!」
息をのむ間も束の間。
彼女は、すぐにノアに腕を取られ、どうにか転ばずに済んだ。
「はあ……本当に」
さすがに驚いたのだろう。
ノアは壁に背を預けるようにして、そのままずるりと床へ腰を落とした。
彼の腕に体重を預けていたクラリスも、自然と一緒に座り込む形になり、気づけば冷たい床の上で、完全に彼の胸に収まっていた。
「お願いですから、あまり驚かせないでください。泣いたり、急に仮面を外そうとしたり……そんなふうにされたら……」
言葉の途中で、彼は小さく息を吸う。
「……心臓に悪いんですから」
そう言って、困ったように、けれどどこか安堵した声で、ノアは呟いた。
「本当に……手が付けられませんね」
彼のついた溜息が、クラリスの髪の合間をすり抜けていった。
そのはっきりとした呼吸を感じたとき、クラリスはようやく、自分の手に何かが握られていることに気づく。
それは――ノアの仮面だった。
どうやら体勢が崩れた拍子に、本人も気づかないまま掴んでしまったらしい。
(外そうとしたわけじゃ、なかったのに……)
そんな彼女の本心など知る由もなく、ノアはまるで事件の証拠でも見つけたかのように、その仮面をじっと見つめている。
困ったように、けれどどこか可笑しそうに。
クラリスはその様子に、ついもう一度ノアの顔を見て、思わず小さく笑ってしまった。
「……ああ、本当に」
「ごめんなさい」
「まあ……とりあえず、泣き止んだみたいで何よりです」
そう言いながら、彼が優しく髪を撫でる。
その仕草に、クラリスはますます熱心にノアの顔を見つめていた。
滅多に見ることのできないその表情を――逃すまいとするかのように。
陽の当たらないせいで、ひときわ白く見える肌。
その奥で、意志の強さを宿した鮮烈な紫の瞳が輝き、長い睫毛が落とす影が、静かに揺れている。
「……きれい」
胸の奥が、きゅっと音を立てて締めつけられた気がした。
まったく、分をわきまえないにもほどがある。
「どうして、またそんな顔をしているんですか」
「それは……」
クラリスはノアと向き合ったまま、少し言葉に詰まり、それから意を決したように、そっと口を開いた。
「たぶん、私……自分の立場を忘れてたんだと思う。私は罪人で……死刑囚、でしょう?」
「…………」
「変だよね。そんなこと、忘れたことなんて一度もなかったはずなのに」
「変じゃありませんよ」
ノアは即座に、きっぱりと言い切った。
「まったく、おかしくない」
そして、穏やかだけれど揺るぎない声音で、続ける。
「公爵夫妻は、あなたを“ただの罪人”として育てたりはしなかった」
「それは……二人が、あまりにも優しすぎたから――」
言い終わる前に、彼は首を横に振った。
「違います」
紫の瞳が、まっすぐにクラリスを射抜く。
「それは、あなたが“そういう人”だったからです。罪を背負っていようと、それだけで人の価値が決まるわけじゃない」
静かで、しかし強い言葉だった。
「あなたが忘れてしまったわけじゃない。ただ……ここにいる間だけ、少し安心してしまった。それだけでしょう」
ノアはそう締めくくり、ほんのわずか、照れたように視線を逸らす。
「それは……悪いことじゃありません」
その一言が、胸の奥に、ゆっくりと染み込んでいった。
「……ええ。あのご恩を思えば、なおさら……私が、こんなことを望んだら……いけないんだよね」
そう呟きながら、彼女が胸の奥で抱えている“願い”は、ひとつやふたつではなかった。
公爵夫妻のそばに、いつまでもいたい。
二人の間に生まれるであろう、愛らしい子どもたちを慈しみ、守り続けたい。
セリデンの人々に囲まれて、同じ場所で、同じ時間を笑って過ごしたい。
そして――
クラリスは、ノアを見つめた。
視線が重なった瞬間、どうしてか、また涙がこみ上げてきそうになる。
「手に入れることもできないのに……願ってはいけないのに……」
彼女は、仮面を落としてしまった手を胸の前でぎゅっと握りしめた。
「……それでも」
静かに、しかし迷いのない声が返ってくる。
「少女は、何を願ってもいい」
「ノアは……それがどういう意味かも、分かっていないでしょう?」
「そう言うのは、卑怯だって……前にも言ってましたよね」
軽く笑うような響きを含みながら、彼はそう返した。
「でも――」
紫の瞳が、まっすぐにクラリスを映す。
「願うことまで、罪になるわけじゃない。叶うかどうかと、願っていいかどうかは……別の話です」
穏やかで、けれど確かな言葉だった。
「あなたが望んだものは、どれも間違っていない。ただ……それがあまりにも、真っ直ぐで、優しすぎただけです」
その言葉に、胸の奥で何かが、静かにほどけていくのを感じた。
「……それは……」
クラリスは、言葉を失った。
そんな言葉を交わした瞬間を、忘れたことなど一度もなかった。
ノアが、初めて仮面を外し、彼女にその素顔を見せてくれたときのことだ。
あのときも、クラリスの胸の奥には、なぜか小さな痛みが残っていた。
何が理由だったのかは、もう思い出せない。
ただ、ノアの顔を初めて目にした衝撃があまりに大きくて、他の感情をすべて押し流してしまったのだろう。
「……それでも、私は学ばなきゃいけなかった」
「罪人として、ですか?」
クラリスは、静かにうなずいた。
「それなのに……望んでしまった。だから……泣いたの」
彼女自身もはっきりとは説明できない、曖昧な言葉だった。
それでもノアは、その奥にある感情を、きちんと受け取ったように見えた。
「少女」
そう呼んで、彼は手を差し出す。
そこにあったのは、形だけの仕草でも、借り物の温もりでもない。
――本物の、ノアの手だった。
だからこそ、クラリスは反射的に、その手を強く握り返していた。
ただ向かい合って、手を取り合っているだけなのに――それだけで胸がいっぱいになり、思わず笑みがこぼれそうになる。
「……私も、少し前に似たようなことで、セリデン公爵と話したことがあるの」
「ノア……が?」
「どうしても手放してはいけない想いを、どうやって処理すればいいのか分からなくて。そんなふうに悩んでいた私に、公爵様はこう言ってくれた」
ノアが握る手に、ほんのわずか力がこもった。
「――『おめでとう』って」
「……手放してはいけない想いを、抱いていたのに?」
「ええ。それは、私が成長した証なのだと」
彼は、ゆっくりと言葉を選ぶように続ける。
「どんな状況になっても、その想いそのものが持つ価値は、誰にも奪えない。だから……」
そこで一度、言葉が途切れた。
驚くほど優しい眼差しを、クラリスに向けたまま。
「だから、少女。あなたが今抱いている気持ちを、恥じる必要はありません」
その言葉は、そっと差し出された手の温もりとともに、静かに、確かに――クラリスの胸に届いた。
「少女は、尊い心を抱いた」
「…………」
「その祝福されて然るべき想いを、私は誰よりも強く祝福し、応援します」
「……壊れてしまいそうな心なのに?」
脆い感情は、堅牢な現実の前では容易く押し潰される。
何ひとつ変えられないまま、最初から無かったものと同じように。
それでもノアは、はっきりとうなずいた。
――今は、その心が“在ってもいい”のだと、そう言っている。
「……変だよね。私は、この想いを一人で押し殺さなきゃいけないって、ずっと思ってた」
「少女が、ひとりで堪える理由はありません。私がいます」
「…………」
「いつでも、あなたが頼れるように」
“頼る”という言葉に、クラリスは一瞬だけ息を詰まらせた。
どこかずるい響きで、反論したくなる言い方だった。
けれど――少し前の、自分の行動を思い返してみれば、この言葉は、決して誇張でも綺麗事でもないのだと分かってしまう。
だからクラリスは、言い返す代わりに、そっと、その手を握り直した。
強くもなく、離れない程度に。
まるで――「ここにいる」と伝えるみたいに。
「……ごめんね」
「大丈夫。責めてるわけじゃない。ただ……そうしてほしいって、お願いしただけ」
「ノアは……どうして、こんなにも」
どうして、私にこんなに優しいの――その問いを、クラリスは飲み込んだ。
『私たちは仲のいい友達だろう?』
もし、そんな言葉を向けられたら。
なぜだか、それだけで胸がひりりと痛みそうだったから。
――おかしいな。ノアと友達でいられることは、いつだって誇らしかったのに。
それなのに今は、その言葉に傷ついてしまうなんて。
「え?何か言った?」
「……ううん、何でもない」
「どうして、また黙っちゃうんです?」
「黙ってるわけじゃないよ。ただ……」
クラリスは、彼の手をそっと離し、今度はノアの肩に、ことりと体を預けた。
「壊れたわけじゃないの。ただ……」
小さく息を吸ってから、囁くように告げる。
「ノアのこと……すごく、大切だから」
そして、ほんの少しだけ言葉を足した。
「……好きすぎて、困ってるだけ」
その重みを、肩越しに伝えるように。
そして、囁くように告げたその言葉は――実のところ、これまで彼女が口にしてきた「好き」とは、まったく別の意味を持っていた。
「……?」
次の瞬間、ノアの腕がクラリスの腰を引き寄せる。
驚いて、預けていた頭をわずかに上げた、その刹那。
クラリスの額に、ノアの唇が触れた。
彼の唇から伝わるひんやりとした感触は、次第に、彼女の温もりに溶けるように、柔らかく額全体へと広がっていく。
――これは……慰め、なのだろうか。
クラリスはそっと目を閉じ、これまでずっと慣れ親しんできたこの“冷たさ”に、意識を集中させた。
やがて、彼は彼女の名を呼ぶ。
まだ額に唇を寄せたまま。
「……クラリス」
その一音一音が、くすぐったいほどに胸を揺らす。
触れたのは、ただ唇だけのはずなのに――まるで、声そのものまでが、彼女に触れているみたいだった。
「……う、うん」
かろうじて返した声は、思った以上に頼りなく震えていた。
すると、彼の手が、クラリスの片頬を包み込んだ。
その指先が、わずかに震えているのが分かって、彼女はノアが緊張しているのだと気づく。
理由までは、分からなかったけれど。
そして、彼に導かれるように顔を上げ、視線が重なった、その瞬間――
――トントン。
「…………」
「…………」
背後から、控えめなノックの音が響いた。
どうやら管理室からのようだ。
「……あ、助かりました」
なぜだか分からないまま、ノアはクラリスの頬から慌てて手を離し、そう口にした。
どうして、そんな言い方をするのだろう。
胸の奥が、ちくりとする。
――私は……少し、名残惜しいのに。
「……残念です」
ノアは、まるで何か悪いことでも起きたかのように視線を伏せ、管理人の来訪を受け入れた。
慌ただしく立ち上がり、クラリスの方を振り返ると、
「すぐ戻りますから。少しだけ……待っていてください」
そう言って、彼は、そっと手を差し出した。
「少女、立てますか?」
少しだけ気恥ずかしそうで、どこかくすぐったい気持ちになりながらも、クラリスは一瞬、その手を取るのをためらった。
――今日が終わってしまえば、また白い手袋越しの手しか、差し出されなくなるかもしれない。
そう思うと、今この手を取らなかったことを、あとで後悔してしまいそうだった。
クラリスは、目にはまだ涙を浮かべたまま、それでも唇には小さな笑みをのせて、ノアの手を握った。
すぐに伝わってくる、彼の引き寄せる力に身を任せると、クラリスは軽く床を叩くようにして、すっと立ち上がることができた。
不思議と、気分も少しだけ晴れている。
「……私、ノアの手、好きかも」
感謝の気持ちから出た言葉にしては、少しだけ素直すぎただろうか。
ノアは何も言わず、クラリスの手を離すと、床に置かれていた仮面を慌てて拾い上げた。
――トントン。
再びノックの音がして、ノアははっと顔を上げる。
そして急いだ様子でノアは扉を引き開けた。
待たせてしまったことが気にかかっていたのか、その動きはひどく慌ただしい。
歪んでいた窓は、あっという間に直された。
専門家が少し手を加えただけで、開閉は驚くほど滑らかになる。
これでもう、慎重に窓を扱わなくていいのだと、クラリスは何度も自分に言い聞かせた。
そのときになって、ようやく気づく。
開いた隙間から吹き込んでくる風が、ひどく柔らかい。
――どうやら、春が……近づいているらしい。