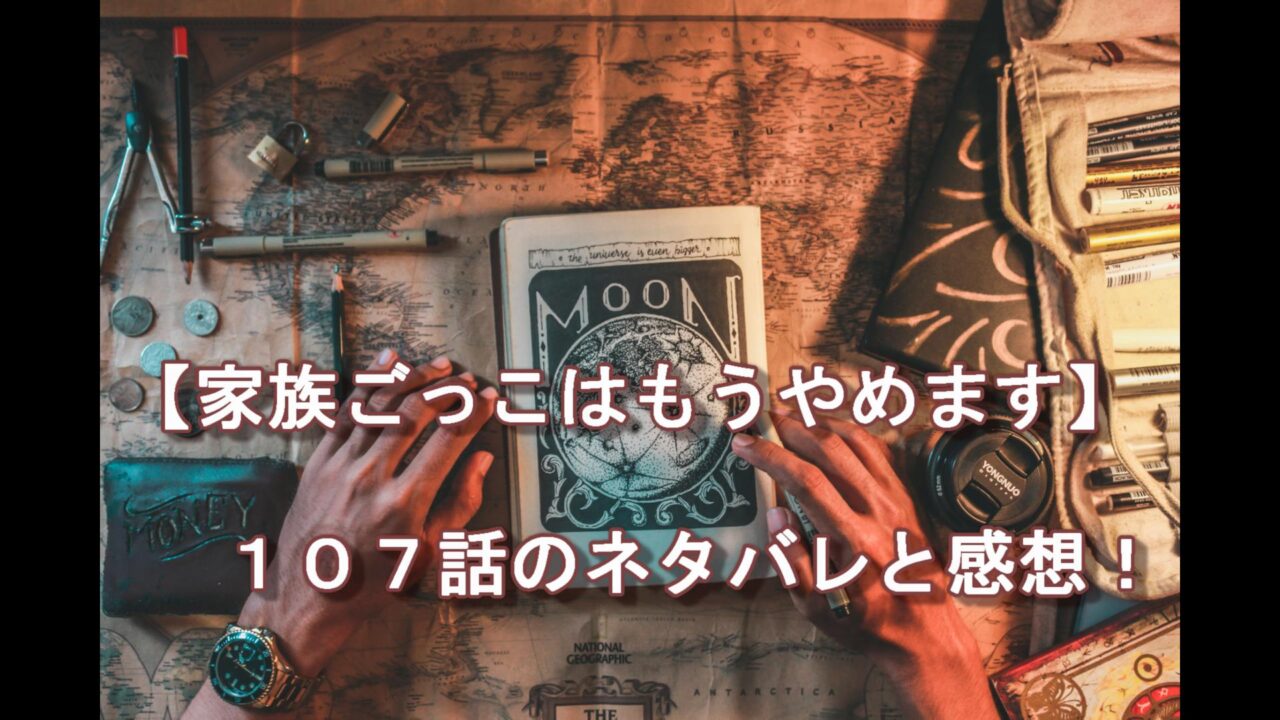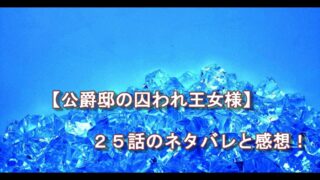こんにちは、ちゃむです。
「家族ごっこはもうやめます」を紹介させていただきます。
今回は107話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

107話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 第二皇子②
ユリッヒをはじめとする彼らはすぐに城内に、場所を移した。
「これまでの間、何があったのか?一体どこにいて今になって戻ってきたんだ?」
皇帝が単刀直入に尋ねると、ダイアナの表情がさらに冷たくなる。
あの子の返事によって、直ちに魔法使いの殺傷魔法が稼動する予定だった。
クリードの唇が落ちる。
「実は、私にはこの2年間の記憶を除いた以前の記憶がありません」
クリードはこの日のためにナビアと数百回も繰り返して彼らを騙す練習をしておいた。
真実を混ぜた嘘は、まるで油を塗ったかのように滑らかに流れ出る。
「私が気を失って目を覚ました場所は、エセルレッド公爵家でした」
「エセルレッドだって!?」
クリードは周囲が混乱していることを気にせず、話し続けた。
「そこで話すことと書くこと、そして魔法を学びました。私の魔法の能力は、エセルレッド公爵に教えられたものです」
ユリッヒは思わずため息をつく。
(ただでさえエセルレッドをどのように懐柔するか頭が痛かったが、これがこのように解けるとは)
その時、クリードが心の分からない表情で話題を転換する。
「優勝者には爵位を授けるとおっしゃいましたね?」
「そうだ。君は皇子ではあるが、厳然として大会の優勝者だから爵位を授けるだろう。もともとは子爵位を下すつもりだったが、皇子が得る爵位なら話は違う」
クリードはしばらく黙っていた。
(皇子なんてなりたくない。そしてこんな汚い所と関わりたくもないし)
ここは母親を殺し、自分を苦しめ、ナビアを苦しめた場所だから。
だから接点を望まなかった。
「私はアイルツの城が欲しいです、陛下。」
クリードは自分の体に流れる半分の血、アイルツ公爵家の血だけを望んだ。
ダフマンの姓なんて絶対使いたくなかった。
その時ダイアナが鋭く反応する。
「アイルツは反逆家門の城だという。あなたがどうやってその姓を使おうとしているのか分からないわ」
「代わりに皇位継承権を放棄します」
「・・・」
ダイアナは黙った。
(アイルツの姓を使う代わりに継承権を放棄する?)
これは彼女にとって最高の取引だった。
クリードは親孝行な息子のように話し続ける。
「今になって私という存在が、訳もなく皇室の秩序を乱すのではないかと心配です。陛下、どうか私の意思を受け入れてください」
ダイアナは内心では訴えながらも、表向きは心配していた。
(だけどアイルツ公爵家は反逆家・・・)
アイルツって、あの公爵家を訳もなく再建させて、ルチアの足を引っ張ったら困るから。
すると、ユリッヒが言った。
「クリードからダフマンの城をおさめ、アイルツ大公に任命する。いいことではないのか?」
ダイアナはびっくりしてしまった。
「それは死滅した爵位じゃないですか!」
(大公だなんて!公爵より高い爵位なんて許せない!)
ユリッヒは少しいらいらして言った。
「皇位継承権を放棄したとしても、クリードは兄の息子だ。ところで、大公が過分だと
言っているのですか?」
「・・・そんなことはありません」
「それでいい。すぐにクリードをアイルツ大公にし、それにふさわしい権限を合わせる
ようにしなさい!」
補佐陣が頭を下げた。
「お命を賜ります」
クリードはあっという間にアイルツ大公になる。
ダイアナは大公位になったクリードにもう言葉を下げることができなかった。
「爵位の冊封おめでとうございます、アイルツ大公」
「ありがとうございます、皇后陛下」
クリードは少しも感動せず、淡々とした表情で最後の要求を口にする。
「神聖帝国アカデミーに入学して勉強したいです」
「しかし、すでにさまざまなことをエセルレッド公爵から学んでいると言っていたではないか?」
「実は・・・公爵様は私が皇子だということを知ってこれ以上私を教えないとおっしゃいました。エセルレッド公爵家はしばらくすべての対外活動を止め、蟄居する予定だそうです」
「また引きこもりだなんて」
ユリッヒはエセルレッドの歩みを少しも予測できないと思ってため息をつき、クリードに向かって微笑んだ。
「あなたが使える部屋を用意しておくように言っておいた。後で一緒に食事しながらアカデミーについて話そう」
「父君のお言葉に従います」
クリードはそのままヘレン侍女長についていく前、ふと思い出したという表情で話した。
「あ、そういえば、バミロ・スタンレーが試合開始前に私を脅していましたよ?」
「え?脅迫だって?」
「皇后陛下が自分を優勝させてあげようとする席だとし、私に死にたくなければ適当にしろと言いました」
ダイアナはまさかクリードがこんな風に出ると知らなかったので顔色が青ざめた。
「それはどういう意味ですか?」
「そうですね。とにかく彼の提案を断ると、試合開始から私を殺そうと話していました。どうやら真相究明が必要だと思います、陛下」
「・・・そう、分かった」
クリードは爆弾を投げつけ、何も知らないという表情で頭を下げ、ヘレン女将の後を追う。
角を回っていたヘレン侍女長が突然足を止めた。
「皇女殿下はここまでどうしたのですか?」
皇女殿下とは、ソフィア皇妃の娘、モニカを意味する言葉。
「私の勝手よ」
幼いが手強い性格であることが分かる声だ。
クリードの無心な視線が壁にひょろひょろした姿勢で背中をもたせたまま、挑戦的な目つきを送るモニカに届く。
モニカは視線がぶつかるやいなや目を輝かせた。
まるでライオンと虎が同じ領域で出会い、お互いを探索するような気配が広がる。
「お前が第二皇子だって?」
クリードは少しうなずいて、また行こうとした。
しかし、モニカは彼を放っておかず、強い手でつかんだ。
クリードは片方の眉をさっと上げる。
自分にしがみついた力は、決して子供のレベルではなかった。
(力が異常に強いんだけど)
魔法使いの中で魔カコントロールに相当な才能がある者たちは、その力で身体を強化することもできる。
実際、それに完全に特化したタイプがまさにネロだ。
ネロは遠距離魔法はもちろん、魔力で人間を遥かに超越した身体能力を発揮することができた。
それはクリードも同じ。
ところが、目の前のこの子は魔法使いでもないのに、まるでそのような能力を使ったように力が強い。
この程度なら成人男性に少し及はない水準だったはずだ。
(魔力に感応する生まれつきの身体条件の人間が時々いると聞いた)
モニカは言った。
「話をしてくれ。うちの姉弟だからちゃんと挨拶はできないの?」
クリードはきっばりと答えた。
「嫌だ」
「なんで?」
「面倒だから」
モニカは不満そうな顔をして、すぐにくすくす笑う。
いろいろな面で、その年代の少女らしくない姿だった。
「正直なのは気に入ったよ。アレスは遠回しに言うからイライラするんだ」
すると、優しい口調だが冷ややかな声が舞い込んだ。
「それは残念だね?」
相変わらず派手な儀典用の服装できれいな姿をしたアレスがここに歩いてきていた。
「モニカ、君のことを気にかけてあげたかったんだ」
モニカは吐き気を催す。
「うえ、いい子ぶって」
するとヘレン侍女長が言った。
「アレス皇子殿下に礼を尽くしてください、皇女殿下」
モニカは口元をひねって笑いながら皮肉を言った。
「ふん、私は習えないからそんなこと知らないよ」
皇居ではわがままなモニカを置いて「やはり外で育てた子なので学んで食べられなかった」、「果たしてあんな水準の低い皇妃の子なので浅薄だ」等、あらゆる言葉を吐き出した。
モニカが幼くても耳があるから、宮廷人たちがひそひそと話す声を間けないはずがない。
もちろんモニカは我慢せずに彼らを殴り、頭をかきむしって徹底的に罰したが。
「気をつけてください、皇女殿下」
ヘレン侍女長は高位貴族であり、皇后の最側近であり、完璧な仕事処理でユリッヒの信任も得た人。
そんな侍女長の警告に逆らうと、とにかくモニカの損だった。
クリードは腹黒い異母姉に舌打ちをし、アレスに話しかけた。
「はじめまして、皇子殿下」
すると、クリードが意図した通り、視線が彼に注がれる。
アレスは蛇のようにずる賢い笑みを浮かべた。
「お会いできて嬉しいよ、クリード。こんな風に弟ができるなんて、本当に嬉しいね!私はいつも一人だから寂しかったんだ」
クリードは嘲笑する。
「そうなんですか」
「気楽に話して。私たちは兄弟じゃないか」
アレスはいいお兄さんになったかのように、慈愛に満ちた笑みでクリードに握手を求めた。
不満そうな表情で状況を見守っていたモニカは、食欲が落ちるという表情で、あっという間に席を離れてしまう。
アレスと付き合うのも嫌だという赤裸々な態度だった。
モニカの敵意にもかかわらず、アレスは少しも気にしなかった。
彼女は自分の相手になれない虫のようなものだから、彼が気にする対象は、突然彗星のように現れ、自分の心を強く逆なでするクリードだった。
「これから仲良くしよう、クリード」
クリードはその手をじっと見つめながら、ラルクの言葉を思い出す。
・
・
・
『ああ、あいつは気をつけろ。ナビアに執着する姿を見ると、絶対に素直に退くやつではなかった』
『お姉さんは何も言わないんですか?』
「坊や、回帰者っていうのはね、本当に飴みたいなもんだよ。大したことをあまりにも繰り返しているので、これ以上そんなことが大したことではなくなるのだ』
『・・・』
『私は娘の『別事』がもうあの子には何事もなくなったのが、一番・・・ゾッとする』
そう言って、ラルクは笑った。
・
・
・
あの時、ラルクが作った微笑は世の中に未熟なクリードが見てもとても複雑な悲しみで絡まっていて、まだ昨日のことのように鮮明に浮び上がった。
クリードはゆっくりとアレスの手を取り合う。
「・・・」
手を圧迫する強い力にかろうじて呻いたアレスの表情が硬くなった時だった。
「そうだね、兄さん」
アレスはナビアにとっては別物だった。
だからクリードにとっても別のことになった。
「くれぐれも仲良くしよう」
(果たしてそんなことがあるかは分からないけど)
クリードの瞳の上にちょっと不気味な眼光が宿って消えた。
クリードが大公の地位を得ました。
皇女モニカの存在も不気味ですね・・・。