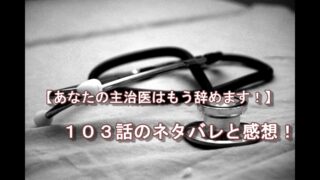こんにちは、ちゃむです。
「夫の言うとおりに愛人を作った」を紹介させていただきます。
今回は62話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

62話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 幼馴染との出会い
北部の社交界は南部とは雰囲気が違った。
北部の人々は治政関係が社交界の中心である南部とは違い、絶対に他の貴族あるいは平民との浮気を許さない。
概して静的で、それさえも南部のように頻繁に集まらず、各領地が閉鎖的な雰囲気だ。
ただ、コルチザンの需要は活発な方だった。
大半が平民だったが、たまに優れた容姿と能力を持った奴隷が貴族のコルチザンに選ばれる。
王族や貴族、金持ちのような上流層にコルチザンはあるがない存在、人だが人よりは布団の中に隠しておいたアクセサリーに近い人たちだった。
マクシオンは北部の大貴族カリオドの次期家主が抱いて暮らしていたコルチザンの子だった。
彼の母親はマクシオンを妊娠していることに気づくとすぐに静かに姿を消した。
カリオドの次期家主が他の貴族女性との結婚を控えた時点だったので、彼女の妊娠のニュースが知らされれば、家主の子供も彼女も無事でなくなるだろうと思ったからだ。
マクシオンは、カリオドの領地とリンデマンの領地の間に位置するある男爵家の小さな領地で、母親の世話の下で育った。
逃亡は賢明な判断だった。
「海に近い北部に伝染病が広がったそうです。2〜3年程度病んだ後は死んだり、大きな後遺症証を残したまま辛うじて生き返ると言いますね」
「ちぇっ、病気で死んだ者たちの死体が山を作ったそうだが」
彼が5歳になった頃、北部に広がった伝染病でカリオドで多くの人が死んだ。
その中には彼の叔父と父親の情婦、そして先代カリオド伯爵もいた。
カリオド伯爵になったマクシオンの父親も伝染病を避けることはできなかった。
彼は2年ぶりに病床から起き、やっと生き残ったが跡継ぎのいない身となった。
まだ情婦関係者とその間に子供がいなかった時点だった。
アヨンブヨン伯爵の上に上がった若いカリオド伯爵はパニックに陥る。
傭兵を主に相手にする飲み屋で働いていたマクシオンの母親は、彼を店に預けて一人でカリオドに向かった。
純粋に子供の実父が心配な気持ちで決めた旅程だった。
「なぜ帰ってきたのか。あなたも私が本当に不具になったのか気になるのか?」
彼女がカリオドの領地に到着した時は、性機能を失った伯爵の自責の念が絶頂に逹した時期だった。
彼女はかつてないほど衰弱した伯爵の姿に一瞬同情する。
それで、自分が去った理由を告白してしまった。
彼の息子を密かに産んで育てていると。
彼は自分の子供を盗んだことに怒り、マクシオンの母親を地下牢に閉じ込めてマクシオンの居場所を話すように脅したした。
伯爵の狂気が怖かった彼女は、最後まで口外しなかったが、結局刑務所で伝染病にかかって生を終えた。
「・・・今日も帰って来なかった」
その時まで母親がどのように死んだのか知らなかったマクシオンは、約束した期間が過ぎても母親が帰ってこないと、自分が捨てられたと思った。
彼は旅館で生まれ育ち、あらゆる旅館を転々としただけに、旅館の生態についてよく知り、また早くから明敏に振る舞うと思った。
母親が残した保証金がすべて削られる前に、彼は幼い頃に店の仕事を手伝い始める。
他人の子供を預かることになったのが面倒だったが、旅館の主人は保証金が全部なくなってもマクシオンを追い出すことはなかった。
だが、子供が助けることができることはきわめて少なく、彼もまた子供ができて時間が経つほど頭が痛い状況になった。
「生活が苦しい親が子どもを捨てて逃げるのは、私たちにとっては珍しいことではない。幼い頃から頭もよく使うし、骨格もいいから、もう少し大きくなったら使える戦士になる」
母親が彼を置いて去った後、店の悩みの種になって半年、マキシオンが8歳になった年だ。
店によく立ち寄っていたある傭兵団が事情を知ってマキシオンをおさめた。
彼はその時から傭兵団に付きまとい、雑用をした。
傭兵団は伝染病が広がった北部を避けて仕事を探して南部に向かった。
そうして1年が過ぎた。
引き続き南部に向かった傭兵団は、ペリルスに到着した。
ある大富豪の暴れん坊の息子が冒険に出ると言って家を出たが、行方不明になった事件の依頼を引き受けたためだ。
依頼はその息子の遺体を訪ねる内容。
森の入り口で彼と似た身なりの男性が倒れていたのを目撃したという情報提供を土台に傭兵団は森の端に向かった。
彼らは運が悪かった。
「あああっ!」
「助けてくれ」
「逃げろ!」
一番安全だと知られている時間帯に、森の端に気をつけて入ってきたにもかかわらず、危険な動物に出くわしたからだ。
森は入り口から真昼も夜のように暗かった。
暗間の中で彼らを襲ったのは、ペリルスにいる動物がよくいるように奇怪な形だった。
体は一般的な熊よりも大きかったが、それより速く、魔法も通じなかった。
マクシオンは初めて自分に死が近づいたことを直感した。
あまりにも淡々とした方だったので、幼い打ち方で死の前でも淡々とできると思ったが、いざ目の前に近づくと、淡々とした姿は何か、狂ったように体が震えて怖かった。
「助けてください。どうか助けてください」
マクシオンは一団員の遺体の下で息を殺したまま身を隠す。
素早く逃げた少数を除いて森に残った団員の大部分が瀕死状態に陥った。
獣が鼻息を吐きながら生きたものの匂いを探した。
それは徐々にマクシオンに近づいてきた。
鋭く巨大な鉤状の爪が目の前に到逹した時、マキシオンは両目を閉じて耳を塞いだ。
そして、この森にどんな妖精や神のようなものがあれば、どうか彼の命を助けてほしいと切実に祈った。
彼にできることは祈りしかなかったから。
閉じた目から熱い涙が絶えず流れた。
黒い爪が彼を突き破るために高く間こえた。
ぎゅっ。
その瞬間、鋭いものが何かを切り裂く音と同時に彼の頭の上にとろどろと浮く熱い液体がばたばたと落ちた。
最初、マクシオンは彼を発見してよだれを垂らす獣の唾液だと思ったが、続いて巨大な気配が速い速度で彼らから遠ざかった。
厚く敷かれた暗雲を連想させる灰色のまつげが聞こえ、黒い瞳が彼の前に立った歯を発見した。
白髪に近い銀髪は、暗い森でも神の恵みのようにきらびやかに輝いた。
どんなに遠くからでも光が当たっていても、彼女の姿を明らかにするのに十分だった。
黒い血のついた剣をざっくりとはたいて、さやに入れた女の子が振り向いてマクシオンを見つめた。
彼女の神秘的な紫色の瞳が彼の心臓に突き剌さった。
彼の祈りが天に届いたのは明らかだった。
心臓がドキドキする。
森の妖精か、神の使徒か、神の現神そのものかもしれない。
彼はこれまでこんなに神秘的に輝く人を見たことがなかった。
女の子が彼に近づいた。
「生きているんだ。よかった。怪我したところある?」
子供が手を差し出して明るく笑う。
彼女は貴族的な発音と平民のように軽い口調で話した。
それさえも立派に見えた。
マクシオンは気の抜けた顔で彼女の手を取り、死体から抜け出して席に立った。
「いいえ」
「よかった。じゃあ、私をおんぶして」
まばたきするたびに純真無垢な光の瞳がむき出しになった。
「今、あなたを求めて足首をくじいたんだ」
それがマクシオンとルイーゼの初めての出会い。
「・・・はい?」
「今、あの子を追い出して足首を捻挫したって。痛い。もうむくみ始めてるね。早く、うちのお母さんを呼んでこないと。そうしてこそ他の人も生かすことができる。涙だらけだけど、ちょっと拭いて。泣き虫」
「あ、はい」
手の甲で涙の跡を拭いたマクシオンが急いでルイーゼをおんぶした。
二人とも身長は似ていたが、傭兵団がよく食べさせ、よく転がしていたので、彼の体格は幼い頃から大きい方だった。
彼は彼女をおんぶしてルイーゼの指示通りに走った。
「ハア、ハア・・・」
マクシオンが疲れ果てて倒れそうになると、小屋が彼らの前に現れた。
その前で眼鏡をかけたまま本を読んでいたある男性と、ルイーゼのような銀色の髪の毛を持った女性が同時に彼らを発見して近づいてきた。
アレンとレンシアだった。
レンシアが先に口を開いた。
「ルイーゼ、また何も言わずに森に入ったの?」
「さっき丘で野いちごを摘んでいて、森に人が入るのを見たんですよ。カマンが最近、あそこによく出て、そのままにすることができませんでした」
マクシオンは汗まみれの顔で荒い息を選びながら「カマン」が何なのか考えた。
まさかあの熊に似た巨大怪物のことを「カマン」と呼ぶのか。
マクシオンが混乱している間、アレンは心配そうな顔でルイーゼを見た。
「うちの娘、そんなことしたら大変なことになるぞ。怪我はないの?」
「足首をくじきました」
「ごほん、あら、えーと。アイヤ。ルイーゼをここに降ろしてくれる?ところで、この男の子は誰?」
男の口調は、ここで過ごす人とは信じられないほど貴族的だった。
彼はひよこのように黄色い金髪に慈眼を持ったが、目の色がルイーゼと呼ばれた女の子と同じだ。
顔を覆う丸い眼鏡のフレームが美貌を殺しそうだったが、彼は眼鏡をかけた状態でもかなりきれいな顔だった。
その恐ろしい悲劇について平然と語り合う父娘の前で、マキシオンは慎重に彼女を手放した。
ルイーゼは平気な顔で答えた。
「倒れた人たちの間で拾いました」
「そうだったんだ」
「拾った・・・」
マクシオンはルイーゼの言ったことをかみしめた。
アレンは彼女の足首を見に行き、ルイーゼは森を指差す。
「怪我をした人が多いです。フロン村方向の入り口です。熊の領域側のねじれたギンナラシ群落にあります」
「久しぶりに用事ができたね。あなた、退屈していたじゃないか」
「面倒くさい」
アレンは咳払いをして笑った。そんな彼を固い顔で眺めていたレンシアは深いため息をついて森に向かう。
マクシオンとルイーゼの出会いが語られます。
マクシオンの過去も相当悲惨でしたね・・・。