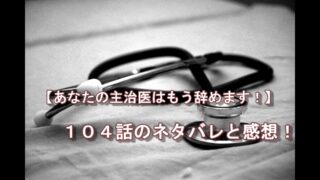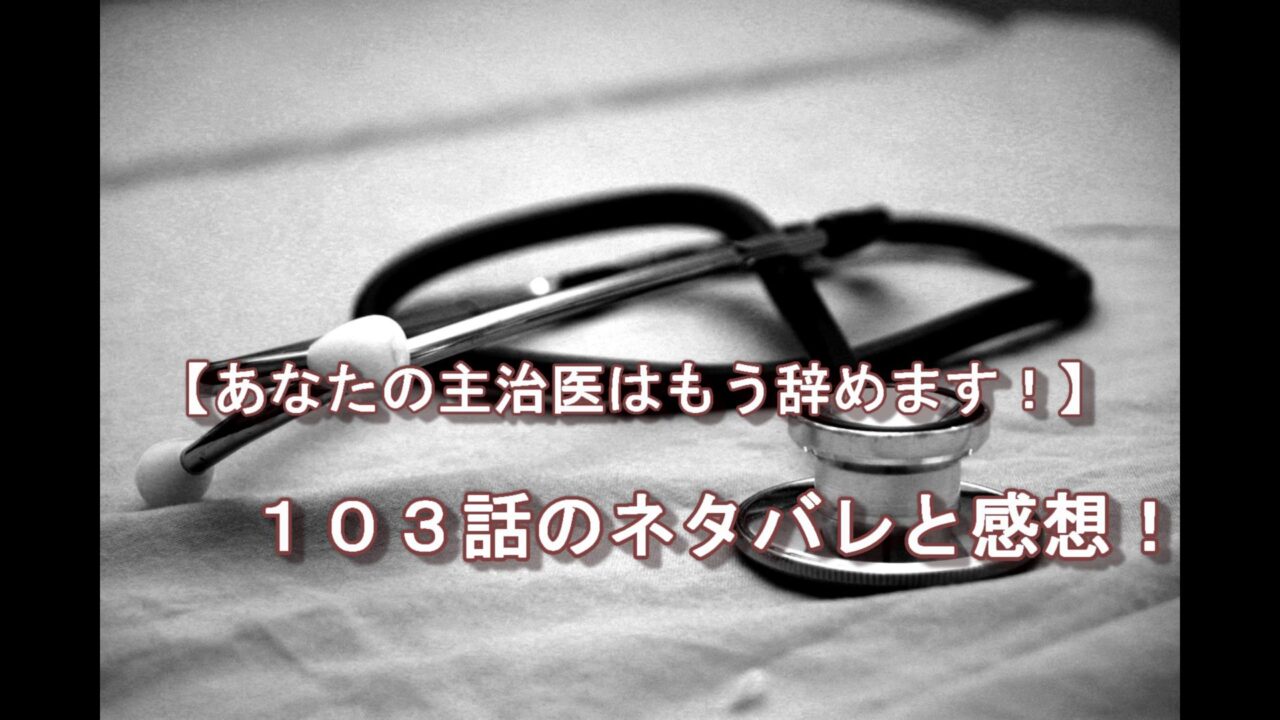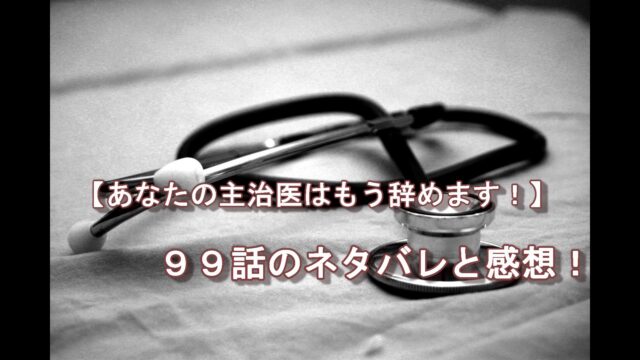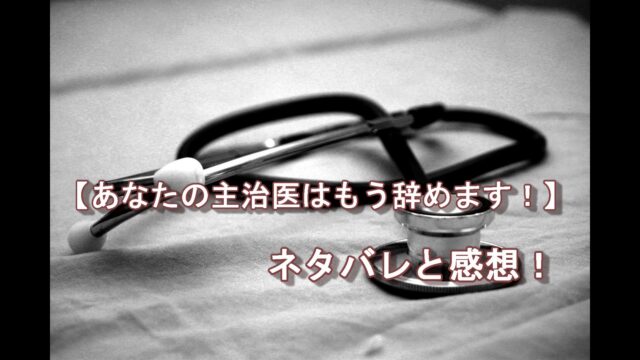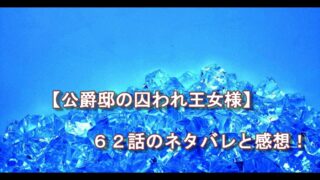こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
今回は103話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

103話 ネタバレ
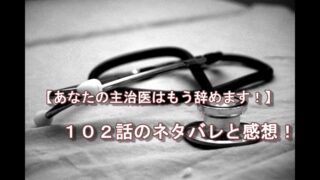
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 真実
研究室に座っているとあっけにとられた。
最後の段階は試薬検査で、また退屈な時間をかなり待たなければならない。
ディエルが準備しておいた試薬であれこれ検査を行い、フェレルマン子爵と私の間には微妙な沈黙が流れた。
いくら他の人々の前では「違うかもしれないという可能性」を開いておくと言ったが、互いに似た考えをすることは仕方がなかった。
「ディエル」
「はい!」
試薬を整理していたディエルが固く凍って答えた。
「月給の500%ボーナスだ」
淡々としたフェレルマン子爵の言葉にディエルの目が丸く大きくなる。
「いや、子爵様・・・私がそんな代価を望んでしたことではないのですが・・・」
「嫌ならいい」
「それでもそれだけの代価をもらうことではありました」
一瞬にして態度を変えたディエルがにやりと笑う。
私は彼の肩をたたいて謝った。
「ごめん、そんな事情も知らずに私は君が事故を起こしたと思ったよ」
「もういいよ」
資本の力なのか、ディエルはとても寛大な顔で話した。
「それくらいは大目に見てもいいよ。友逹同士で」
彼は平気で吐き出して、ぎょっと驚いて、フェレルマン子爵の顔色をうかがった。
「いや、私の話は・・・まだ私たちが友逹だということだよ。君がフェレルマン人になれば、その時は話が当然変わるだろう!」
そうなれば私の身分は貴族になるわけで、ディエルがなぜ急に付け加えたのか分かるような気がした。
私が貴族の身分を得るという意味は、もうこれ以上誰かの養女に入らなくてもエルアンと結婚が可能だという意味だから。
しっかりと敷かれているフェレルマン子爵邸の大理石の道を思い浮かべながら、私はフェリックス老人がくれたハンカチをいじった。
老人の真心が入った物を持っていれば良いことが来るそうだが。
(本当に私が血肉を見つけたのか)
あの大理石の道が私のためのものであり、私がフェリックス老人の孫娘になって、セイリン卿の姪になって、フェレルマン子爵の娘になるのか。
(それならお母さん・・・私のお母さんシオニーは・・・)
まともな産婆や医者なしに私を産んで、魔力が混じって死んだのだろうか。
そんな考えをすると訳もなく鬱積した。
最後に建国祭のブースで見たイシドール男爵の顔でも、思いっきり殴りたいと思った。
「ところで、子爵様の娘さんが反乱軍と絡んでいると言ったじゃないですか」
私は注意深く言い出した。
「いったいどういうことなんでしょうか」
「分からない」
フェレルマン子爵はため息をつきながら言った。
「反乱軍なんて、私はそんな政治的問題とは絡んだこともない。興味もないしね。唯一、皇家と近かったことは、皇室医療研究チームに入ったことだ。それさえもそこに行っては研究ばかりしていたし」
「研究ばかりされていて問題でした」
ディエルがすぐに割り込んできた。
「そういうところでは社会生活というものをするべきでしたね。特にハエルドン皇子様がいらっしゃるんですから」
「君はその時、幼いのに詳しいことも知らないくせに、どうしてしきりに知っているふりをするんだ?」
「耳にたこができるほど聞いてきましたから」
私は腕を組んで物思いにふけった。
反乱軍と絡まっているというフェレルマン子爵の娘が私である可能性が高くなった今、どうしても真実を知りたかった。
フェレルマン子爵がどこでも歓迎されない人だということは知っているが、今だからといって反乱軍の標的になるほどあちこちに威張る性格でもない。
問題は、反乱軍の片割れに過ぎないイシドール男爵を捕まえるとしても、これといった答えを出すことができないということだ。
私は深呼吸をした後、注意深く尋ねる。
「反乱軍の後ろにハエルドン皇子様がいらっしゃるのではないでしょうか?」
フェレルルマン子爵とディエルを信じているからこそ言える言葉だった。
証拠もなく皇族をする者と疑うことは冒涜罪に該当する。
私は雨後の筍のように立ち上がった反乱軍の最終背後が明らかにならなかった時に回帰した。
「皇太子様が怪我をしたら、すぐ次の皇位継承者ですから」
「どうなんだろう」
フェレルマン子爵は物思いにふけった目で答えた。
「事実かどうかは別として、今の皇帝陛下は老衰と持病が深刻で、反乱軍を踏む余力がない。そして皇太子様は・・・ご存知のように・・・」
「実力だけ信じて何の考えもないでしょう・・・。しかし、今度は命が本当に危険にさらされましたが、相変わらず何も考えていませんか?」
「大多数の人がそうであるように、事故だと信じていらっしゃる」
私もやはり、エシオンの一言で気づいたので、何とも言うことがなかった。
だからといって、決心して私を助けてくれたエシオンを困らせるわけにもいかなかったから。
事実、ただじっとしていてもジェイド皇太子がすべて殴って壊すのは事実だったので、あえて乗り出す必要はなかった。
しかし、真実がとても気になってしまう。
「それに対外的に、ハエルドン皇子は皇室医療研究陣を率いる自分の位置に本当に満足している。政治よりは研究の方が適性に合うという言葉を広めているから」
「アルガ様の考えはどうですか?直接一緒に研究されたじゃないですか」
「ふむ・・・」
フェレルマン子爵は下唇をかみしめて答えた。
「真の医療関係者なら、常に患者の回復が優先されなければならない。しかし、皇子は表向きの研究実績にこだわる人だ」
私は狩猟大会でのハエルドン皇子を思い浮かべながらうなずいた。
すぐに輪血が急がれる患者なのに、ゆっくりと人前でナタリーが来るまで待ったこと、2人の人が怪我をしたことを「興味深い対決」と表現したことからすでに気づいていた。
「とにかく私たちだけでこう言ったところで、何の成果もないということはご存じでしょう?」
ディエルは試薬を丁寧に整理しながら言った。
肝が小さい彼はこのような話題が不便そうだ。
「こんなことは皇室を勝手に疑っても、それに対抗する権力が十分な公爵様に任せましょう」
そうでなくてもエルアンはウェデリックをもっと「締めなければならない」として地下監獄に消えたままだった。
すでに出てくるものはすべて出てきたようだが、一言でも多く覚えれば手がかりになるのではないかという話だ。
もちろん、アーロンも熱心に尋問したようだが、彼はスパイであるため、ウェデリックほど知っていることはなかった。
私がそこまでしなくてもいいと言ったが、彼は「あなたに関することじゃないか、リチェ。絶対に手伝わないと」と言いながら不気味に目を輝かせた。
反乱軍とフェレルマン子爵の娘が関係があるようだと言い放った人がウェデリックだったため、追加尋問を何とかやり遂げるということだ。
「今は私たちが特にすることがありません。そのまま待ってください。どうせ証拠もないじゃないですか」
ディエルは研究室をもっと忙しく整理したが、それはやめてほしいと言わんばかりに言った。
間違ってはいなかったので、私は黙っていたが、ディエルが何かを片付けようとしているのを見て、ばっと立ち上がった。
「だめ、ディエル。それはまだ始まってもいないんだ。そこにほっといてくれ」
「うん?ずいぶん前からあったよ?」
「まだ分かっていないからだよ。でも、すぐに明らかにできるから」
その言葉に好奇心を示したのはフェレルマン子爵だった。
「何だ?」
彼はゆっくりと立ち上がり、ディエルが持っている実験器具をのぞき込んだ。
それはウェデリックが以前エルアンに与えたお菓子であり、もう成長したサルロイ草を投入して成分を調べることだけが残っていた。
「何だよ、お前が分からないのか?」
「ああ・・・ウェデリック様が幼い頃、公爵様に変なお菓子をこっそり食べさせたんですよ」
「え?私に内緒で?」
「はい。イルビアにお帰りになって、体のほうがずっとよくなったじゃないですか。それでお菓子に何の成分があるのかとずっと研究していました」
私は思い出したついでに、慎重に成長した肉芽を入れて、お菓子の成分を分離しながら言った。
「実はほぼ6年近く握ってたんですが、到底調べることができないんです。いくらお菓子で作って成分を類推するのが大変だとしてもここまで分からないのがとてもプライドが傷ついて・・・。それでも、いよいよ成分を分離できるようになりました」
「ウェデリックがそんな知識を持っているはずがないし、少しでも医学的知識を持っているのはイシドール男爵なのに・・・彼が作ったお菓子の成分をお前が今まで明らかにできなかったと?」
「だから気が狂いそうでした」
私は眉間にしわを寄せながら不機嫌そうに答えた。
私の実力にそんなはずがないのに。
「どれ」
フェレルマン子爵はあごを上げて私が分理している試験官たちを一つ一つ調べ始めた。
私は「やってみろ」という表情でそっと後ろに下がった。
悔しいが、私の実力に匹敵するのはフェレルマン子爵だけだ。
それなら、これらの成分を一度に突き止めることもできる。
まあ、皇室医療研究陣は名声はすごかったが、狩猟大会の時に見ると、私たちの実力の比ではなかった。
彼が成分を分析している間、私は顎を突いてしばらく身を引いた。
どうせ成分をすべて分離した以上、私もゆっくり覗いて見れは毒の原理は分かるはずだ。
しばらく羊皮紙に何かを書いていたフェレルマン子爵は、ため息をつきながら額をついた。
「ディエル」
「え?」
「証拠が出たのだから、もう少しこのことについて話してもいいだろう」
「証拠ですか?」
「うん」
フェレルマン子爵は真剣な顔で片眼鏡を持ち上げた。
「リチェがこのお菓子の成分を突き止めることができなかったのは当然だ」
「・・・どうしてですか?」
フェレルマン子爵が「証拠」と言及したということは、この菓子が皇室と関連したという意味だ。
せいぜい皇室の医療研究陣が作った案を私が長い間発見できなかったというそれを受け入れることは容易ではなかった。
「私は天才です。一体どうして分からなかったのでしょうか?」
「もう一人の天オが作り出したのだから、見分けがつかない」
フェレルマン子爵がくすくす笑いながら答えた。
「皇室医療研究陣に所属していた時、私が作った配合だから」
リチェが孫だと知ったときのフェレルマン子爵の反応が気になります。
アルガが作った配合だから、リチェもなかなか解き明かせなかったのですね。