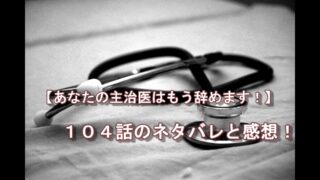こんにちは、ちゃむです。
「夫の言うとおりに愛人を作った」を紹介させていただきます。
今回は63話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

63話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 幼馴染との出会い②
その間にルイーゼの足首は治療が終わった。
包帯で巻いた足首を見たルイーゼの唇が飛び出す。
薬箱を閉めたアレンがマクシオンを見ながら尋ねた。
「それで、あなたの名前は?」
「マクシオンです」
「子供がひどい惨状を見ても淡々としている方だね。小便をするに値するはずだったのに、死に慣れている方みたいだ」
マクシオンはうなずいた。
最初は彼も小便をしたり震えが消えず眠れない日を過ごしたりした。
しかし、それも何度かあった。
使い道がなければ死ぬか捨てられる。
それが傭兵の生だ。
マクシオンは自分の役に立つように環境に適応した。
「見た目や言葉遣いからすると、北部出身のようだね。一行がやられたにもかかわらず、不安な様子が少ないのを見ると、親と一緒に来たのではないようだ」
「偏兵団で雑用をしていました」
「保護者は?」
「・・・たった今死にました」
マクシオンは目を伏せて答える。
「帰るところはあるのか?」
「いいえ」
どうせ彼を一番大事にしてくれた人は死んだ。
彼を収めた団長は真っ先に首が飛んだ。
帰っても団員の相当数を失った傭兵団で、彼は再び捨てられるだろう。
マクシオンはやっと彼がその惨状の中で生き延びたことを実感した。
緊張が解けると、再び全身がぶるぶる震えてくる。
傭兵団について回りながら、初めて見た死ではないにもかかわらず、恐怖が簡単には消えない。
恐ろしいのは死だけではなかった。
9歳の子供が知人や保護者なしに生き残らなければならない冷たい現実が、彼には残りの人生の大きさほど漠然としていたのだ。
ルイーゼは怪我をした足を空中でぐるぐると動かし、マクシオンに向かって首をかしげる。
「お父さん、またしばらく家の外に出てはいけないんですか?」
「当然だよ。足首が回復するまではだめです」
「もどかしくて嫌なんだけど」
床に視線を置いたまま、2人の会話を聞いていたマクシオンが素早く頭を上げた。
「私が乗り物になります」
そんな彼を驚いた顔で眺めていたルイーゼとアレンが、お互いにそっくりな紫色の瞳を瞬かせ、すぐに爆笑した。
「ああ、ごほん、ははは。面白い友逹が入ってきたんだね、ルイーゼ」
「ふふ。はい」
森に消えていたレンシアは夕方頃になってようやく小屋に戻った。
アレンが彼女にルイーゼの乗り物で志願した人がいると言って、マクシオンを紹介する。
「おいくつ?」
「9歳です」
「私の家には部屋が多くない。二人で一部屋を使わなければならない。でたらめなことをしたらルイーゼが誤って殺すかもしれないから気をつけたほうがいいだろう」
「はい」
レンシアの脅迫と本音が混じった言葉にマクシオンが直ちに答えた。
「ルイーゼ、大丈夫?」
「はい」
ルイーゼは初めてここに泊まるようになった同年代の友人が気に入った様子だ。
レンシアがくすくす笑って答える。
「そうだね。じゃあ過ごしている間、ルイーゼの面倒をよく見てくれ」
幸い、しばらく滞在できる空間ができたことにマクシオンは安堵のため息をつく。
マクシオンはルイーゼの家族に急速に溶け込んだ。
アレンとレンシア、ルイーゼは新しく入ってきたマクシオンにまるで以前から一緒にいた隣人の子供のように気楽に接した。
マクシオンもまた、外国人傭兵団で過ごした様子で、すぐに自分の居場所を取り戻した。
彼は小さな手でワラビのように優しくルイーゼの世話をした。
同時に、彼は初恋を患い始めた。
「・・・美しいです」
「何が?」
「瞳です」
ルイーゼに救われて以来、彼は卵を割って生まれて初めて会った人を親として慕うようにルイーゼの後をちょろちょろついて回った。
彼にとってルイーゼ家族が住む小屋は暗い森の中の神殿のようで、彼ら家族は人間界にしばらく遊戯を楽しみに降りてきた神のように見えたのだ。
マクシオンの初恋は愛よりも崇拝に近い気持ちで始まる。
彼は速いスピードで黒歴史を作り出していった。
「何よ、気持ち悪い」
「手も、髪の毛も、息も全部」
「どうしたの」
そんな彼をレンシアとアレンが面白いという顔で見た。
彼はルイーゼの前に泥水が現れると、「私を踏んで通ってください」と喜んでうつぶせになり、ルイーゼが彼の食事でソーセージを貪欲な目で見ると、「卑賤な人間の真心です」と、ルイーゼの器に自分のソーセージを喜んで譲った。
見るに見かねたアレンが彼に何か錯誤があるようだと教えようとしたが、面白いからもう少し見物してみようというレンシアの引き止めに素直に口を閉じることに。
結局、レンシアは1ヵ月が過ぎてからマクシオンに真実を知らせた。
「森の妖精や神様じゃないんですって?」
「そうだよ。普通の人だよ」
レンシアは肩をすくめた。
「とんでもない」
「あはは!」
彼女は腹を抱えて笑った。
マクシオンは不審そうな顔をしていた。
彼らが人だなんて。
人がどうしてこんなところでこんなに平和に過ごせるのか。
彼らの小屋はペリルスの森の中なら中、外なら外と言える曖昧な位置にあった。
正確には、ペリルスのすぐそばの平凡で小さな木立の境界になる場所だ。
ペリルスを重点的に考えると気が変わり、他の人が見るにはペリルスと呼ぶに値する位置だった。
森と森の間だったが、境界は明らか。
ペリルスの森は木が奇怪に大きくてねじれた形をしたうえ、枝と葉が茂り、昼も夜のように暗かった。
それに対し、すぐそばに広がる木の森はそこが完全に別の空間ということを確実視するように、平凡な木々がまばらに育つ明るい森だった。
森の近くにいくつかの村があったが、頻繁に行き来することはないようだ。
マクシオンは人がこんな危険な区域に家を建てて暮らすことができるとは想像もできなかった。
その上、これらの家族はどこか非凡なところがある。
珍しい美しい外見もそうだったが、アレンは治療師として能力が優れているようで、村に行くたびにかなりのお金を稼いできたし、ルイーゼとレンシアは信じられないほど剣術の実力がすごかった。
「・・・そうだったんだ。人だったんだ」
「今はちょっと気がつくようだね。それで、そんな神秘的な存在じゃないのに、まだルイーゼが好き?あなた、ルイーゼが好きじゃん」
マクシオンの顔は真っ赤に輝いていた。
生まれつきの肌の色が濃い方なのに、変化が目立つほどだ。
「・・・はい」
人とはむしろもっと良かった。
ルイーゼが自分のような人間だということは、妖精や神のようにいつ消えるか分からない未知の存在ではないという意味だったからだ。
レンシアは嬉しそうな顔で笑う。
「私とルイーゼに剣を習って。ここで過ごすなら、君の体くらいは守れないと。そして、その崇拝する神を祀るような言い方はやめた方がいいだろう。実はもっと見物したかったんだけど、そのままにしておいてはルイーゼとあなたの仲が永遠に近づけないと思って教えてあげたんだよ」
「それなら・・・」
「楽に接した方がいいんじゃない?同年代のように声をかけてみて。どうせ同い年じゃない」
レンシアに助言を聞いたマクシオンは、おずおずと家の前で剣を振り回していたルイーゼに近づく。
彼女はびくっとして後ずさりした。
「また変なことを言おうとしているんだ」
「・・・いいえ」
「本当に?」
「気楽にしてもいいですか?」
マクシオンの言葉にルイーゼは疑いの目でゆっくりうなずいた。
「うん。その変な言い方はやめてほしい。敬称を除いてそのまま名前で呼んで。気楽に話して」
「・・・はい、いや、わかった。ルイーゼ」
ルイーゼの表情が明るくなる。
その日以来、マクシオンは母と娘から剣を習い始めた。
基礎はレンシアに教わったが、細かい技や組手はルイーゼと一緒に。
森の一部でもあるかのように飛び回るルイーゼは、強くて自由だった。
とても幼い時から血と負傷者、死体を見てきたためか、遠慮なく近づいて死んだ人には祈りを捧げ、生きている者たちは力の及ぶ限り助けてくれた。
「マクシオン、こっちにおいで。ポポを紹介してあげる」
彼女は森でよく出没する獣に名前をつけた。
大半が凶暴だったが、信じられないことに、中には彼女に親しげにふるまう個体もいる。
獣たちは小屋に住む彼らを害さなかったが、時々ルイーゼが森で腐った匂いがひどいという日には小屋まで這い出て攻撃的に振る舞う場合もあった。
彼女の両親はルイーゼに注意するように忠告したが、彼女を強く制止しなかった。
他の安全な地域に引っ越そうという気持ちもなさそうだ。
「10歳になったら記念にカバンで開かれる祭りに連れて行ってあげる。ペリルスから近い都市の中で一番大きくて面白い祭りをするところだよ」
レンシアの言葉にルイーゼは大喜びした。
彼らが神や妖精のような特別な存在ではないという事実を知った後、マクシオンは彼らの家族がなぜここに住んでいるのか理解できなかった。
平凡な人があえてなぜこのような危険なところで隠遁したまま暮らし、外の世界に定着しようとしないのか。
「お母さんは帝国の英雄だ。人々の覗線に私が不幸になるかと思って、ここで静かに暮らしてほしいとおっしゃった」
「・・・そうなんだ。銀のレンシア。外で過ごす時、先生の名前を聞いたことがある」
「本当?」
「うん」
「ほら、だからお母さんは私のためにここにいるのよ」
ルイーゼが小さく笑うと、マクシオンは顔を赤らめた。
理解できないことはないし、楽しい顔で笑うルイーゼを見ると心臓に産毛でも生えてきたようにサラサラになる気がするというのは相変わらずだった。
「お二人が私に害になるようなことをされるわけがない。私をとても愛しているんだから」
「私もそう思う」
「だから私はここで私の家族同士で一生いつまでも幸せに過ごすつもりだ」
ルイーゼの言葉にマクシオンは自分もその家族の中に入っているのか疑問に思った。
彼は自分がその中に入ってほしいと思いながらも、一つの単語が引っかかって気分が悪かった。
一生。
ここで生まれ育ったルイーゼならともかく、外で暮らしていたマクシオンは到底このようなところで一生を生きていく覚悟ができなかった。
「マクシオン。最初は君が変な子だと思ったが、あなたと過ごせばこれからも楽しいと思うよ」
「・・・うん」
マクシオンがきらめく目つきで彼を見つめるルイーゼを見て、しぶしぶうなずいた。
どうせ彼はすぐにここを離れるつもりがなかったので、別れはしばらく後のことだろう。
マクシオンの初恋は黒歴史のようです。