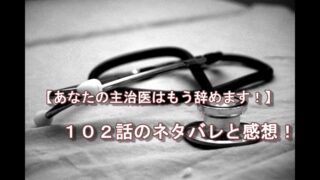こんにちは、ちゃむです。
「夫の言うとおりに愛人を作った」を紹介させていただきます。
今回は61話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

61話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 目覚めのリンゴパイ③
「おはよう、マクシオン。いい夢見たかな?」
「・・・はい」
「目覚めた姿を見ると気持ちいいね」
長い足で大股で歩いてくるエドワードを見ていたルイーゼが慌てて手のひらで自分の顔を隠した。
わんわん泣いて顔がむちゃくちゃだ。
「ごめんなさい。気が気でなくて呼ぶのをうっかりしていました」
「そうだったんですか?」
「マクシオンも目覚めたし、エドワードも確認したので、それでは私はこれで自分の部屋に戻ります」
ルイーゼが立ち上がろうとした瞬間、マクシオンは彼女の腕をつかんだ。
「行かないで」
「・・・うん?」
「まだ、いてくれ」
深淵のように黒い瞳がルイーゼに執拗に追いついた。
ルイーゼは左の指をV字に開いて、マクシオンの顔を見る。
彼は声のように頑強な表情だった。
ルイーゼはこっそりとまた座る。
「顔がめちゃくちゃなのに・・・」
そんな彼女の前に、突然きれいに折り畳まれた白いハンカチが一つ現れた。
ハンカチの縁には空を飛ぶ銀色の鷹が刺繍されている。
「必要ですか?」
近くから聞こえてきた聞きやすい丁寧な声に、ルイーゼがそっと顔を赤らめ、慎重にハンカチをひったくった。
「・・・ありがとうございます」
彼女は残った涙の跡をぬぐい、エドワードの顔色をうかがった。
幸い彼は彼女ではなくマクシオンを見ていた。
少しでも隠れるかと思って、訳もなくハンカチで目をぎゅっと押さえる。
押したからといって腫れが中にすっぽり入るはずはなかったが。
逆に、さらに激しく上がってくる腫れによって、ルイーゼは一人だけの戦いをあきらめ、静かに諦めた。
なぜかエドワードにだけはソーセージのようにむくんだ目を見せたくなかった。
しかし、だからといってすぐにここで一人で冷湿布と温湿布を交互にすることはできないのだから。
「はあ」
エドワードはそのような行動をマクシオンを見つめるふりをしてこっそりと横目で見ていた。
彼が我慢できず、手であごを触るふりをしながら、口元を隠して小さく笑う。
「・・・」
2人の姿を見守っていたマクシオンが無表情な顔で呆気に取られた。
自分の前では好き嫌いもなく泣いていた子がエドワードが登場するやいなや顔を気にすることで、そんな彼女を見ないふりをしてそれとなく気にするエドワードはまた何をしようとしているのか。
2人とも消えたらと思いながらも、3人が集まっているのが悪くはなかった。
「エドワード様はどのくらい起きていらっしゃいましたか?」
「まあ、君がぐっすり眠っている間はずっと」
「ルイーゼ。私よりひどい患者があそこにいる」
マクシオンが来ると、ルイーゼは驚いた顔でエドワードの顔色を見た。
そうするうちに2人の覗線が自然に向き合う。
「ちょっと待って。じゃあ、三日間一睡もしなかったんですか?どうりでいくら早く起きてもエドワードはいつも先に起きていておかしいと思ったが。それじゃ大変なことになりますよ!」
「よくあることです。あまり心配しなくてもいいです」
「それがありふれているんですって?それならもっと大変ですね。顔色が良すぎて知りませんでした。おかしい、3日も徹夜した人の顔じゃないのに」
「顔色を変えてくれる薬を飲んだのですか」
「・・・それでも」
「どれどれ」
ルイーゼはすぐに席から立ち上がり、エドワードの顔を間近で見る。
ぐっと近づいた顔にエドワードの表情が当惑で固まった。
ルイーゼはむくんだ目を丸くして、彼の顔を注意深く見た。
右手を上げて目の下をそっと押して目の状態も点検し、熱はないのか額に手を当ててみたりもした。
「見た目は本当にまんまと一杯ですね。それによる副作用も特に見られないようで。それでも心理的な要因なら、眠れなかった時にかえって悪化することがあります」
短い問診を終えた彼女がそっと視線を上げて彼と目を合わせた。
目の前で出会った赤い目は、人を魅了するために作られた魔導具のように魅惑的な光を帯びている。
「・・・」
「・・・」
二人が黙ってお互いを見つめ合った。
人がどうしてこんなに非人間的に美しいのだろうか。
ルイーゼがそう思った時だった。
「一人で休憩する時間が必要なようです。そのまま両方出て行ってください」
マクシオンは真剣な表情で口を開いた。
その時やっと近すぎたことに気づいた彼女は慌てて一歩後退する。
ルイーゼの顔が真っ赤になった。
エドワードは驚いた顔をして、視線をそらし、咳払いをした。
彼の顔には淡いピンク色が浮かんでいた。
「それでは使用人に君の健康状態を確認するセラピストを呼んで来いと指示する」
「はい」
「わ、私は顔の調子が悪いので、これで自分の部屋に帰った方がいいと思う。マクシオン、また明日ね。また目が覚めないと、あなた、本当に怒られるよ」
「・・・そうだね。また明日」
二人が急いで部屋を出ると、マクシオンはがっかりしたように笑う。
率直に言って、ルイーゼとエドワードは誰が見てもよく似合っていた。
そのような2人が親しく過ごす姿が悪くはないが、彼らのむずむずした場面を両目で直接鑑賞するのは妙に不便なところがあった。
大切にしている妹の恋愛シーンを偶然目撃した気分と似ているのだろうか。
いや、それよりもルイーゼは彼にとってはるかに複雑な存在だった。
それより近い、遠くて遠い、もっと近い。
「あの時とはすべてが変わった」
師匠も、小屋で彼だけを待っていた田舎の少女も、もうこの世にいない。
先にルイーゼをそこに置いて去ったのは彼だったが、彼女に再び会ってから気づいた。
あの時間に留まっていたのはルイーゼではなく自分だったと。
彼女が去った後、マクシオンの記憶はまだそこに残っていた。
ルイーゼの世に数多くの人が入ったが、やはりどう考えても彼にはルイーゼしかなかった。
家族と名付けられるような人も、幼なじみも、そして・・・。
「始まりは初恋だったのか」
愛と呼ぶ人も。
マクシオンの口元が薄い弧線を描く。
やっぱりマクシオンもルイーゼが好きなのですね。
二人の過去が気になります。