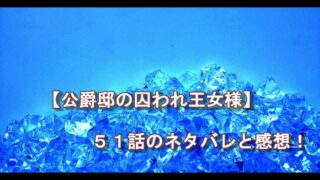こんにちは、ちゃむです。
「夫の言うとおりに愛人を作った」を紹介させていただきます。
今回は50話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

50話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- かくれんぼ③
「まったくごもっともなことです。とても燃えています。背中がめちゃくちゃになることも知らずに良い時間を過ごしたようですね?」
ロビンはつぶやきながらエドワードの背中を見る。
背中の腰に指三節の長さほど破れた傷痕が残っていた。
幸い傷は深くはなかったが、血がかなり出ている。
「ロビン、そういう言い方は慎むように」
マクシオンはエドワードの顔色をうかがいながら言った。
エドワードは平然とした表情で表情を変えなかった。
「枝が騎士団服を破って食い込みました。感染しないように気をつけなければなりません。制服は魔法で直せばいいそうですが、人の体は不可能です。いくら魔法で適当に止血しても、この状態で人を持ち上げることさえしたのですから、血がどくどく流れ出なくてはなりませんか?」
「ルイーゼさんは知らないことだから、口止めしてね」
「え?人がこんなに怪我をしたのに気づかなかったんですか?練習試合の時に見たら血の匂いに敏感な方のようですが」
「他の匂いに隠れていたようだ」
「他の匂いですか?」
ロビンが不思議そうな顔をして尋ねると、エドワードは知らんぷりをする。
「そうだ。それにしても他の薬草はないのか?治療する前より今の方がもっと痛いようだが」
「大げさな話もない方が話を変えるには。もう麻酔薬の感覚がないと思いますが。縫う時は何も言わなかったくせに」
ロビンはぎくしゃくして傷口を圧迫するように包帯を巻き始めた。
「・・・それでその姿勢でいらっしゃったんですか。ルイーゼに見られないようにしようと思って」
そんな彼らを見守っていたマクシオンが口を開く。
「さあ?」
無表情だったエドワードの顔に笑みが浮かんだ。
「恋人じゃないか。抱いてみたくてそうしたのに」
「ああ!私は悲しくて生きていけない!治療も終わったので、これ以上頼むことがなければ私はもう行きます!」
「・・・」
「ロビン、いい夜を過ごせるように」
「はい!」
治療を終えたロビンが耐えられないという顔で首を横に振り、逃げるように兵舎の外に出た。
エドワードは平気な顔で上着を着て、マクシオンに尋ねる。
「ルイーゼさんが私のマナの匂いを嗅ぐことができるようだ。もともとそういう能力があった?」
「私の知る限りではありませんでした。もともと匂いをよく嗅ぐ方ではありましたが、普通の範囲内でした。ちょっと変わったところがあったんですけれども」
「変わったところ?」
「ルイーゼは、天気や森の変化に簡単に気づきます。天気は空や空気の状態から分かるそうですが、森の動物が特に不安定に見える日には間違いなく悪臭が感じられるそうですね」
「悪臭か」
エドワードは上着を着て着飾った。
「君もその悪臭を感じたことがあるか?」
「ありません」
「そうなんだ。それでは点検を始めてみようか」
彼が席を立ち、マクシオンを同行させて採幕舎の外に向かう。
「もっと調べなくてもよろしいですか?」
「ルイーゼちゃんは匂いの正体を知らない様子だった。関連内容が分かる人はエイブンだけなのに、彼は黒魔法の専門家だから大きな期待をかけることは難しいし。だからといって関連書籍を探せる状況でもないじゃないか」
「それはそうですが」
「これから気をつけなければならない」
エドワードは団員たちと挨拶を交わし、兵舎を一つ一つ確認した。
食事は組を分けて行ったため、団員の大半は兵舎を守っていたり、歩哨に立っていたりしていた。
「あの、エドワード様」
「なんだ?」
「ルイーゼは私たちと最後まで一緒にいるわけではないと聞いています」
「そうだよ。そうじゃなくても、昼間にルイーゼさんにアカデミーの剣術教師の席を提案したんだ。君の言うとおり、とても気に入っていたよ。時間が少し残っているからゆっくり説得するつもりだ」
「なるほど」
「首都が安定したら、その時にルイーゼさんを再び首都の邸宅に招待しようかと思うんだけど。どう思う?」
「いい考えですね」
マクシオンの返事が終わるやいなや遠くない距離でルイーゼが叫んだ。
「エドワード!食事をしないんですか?」
片方の手には湯気の立つマッシュルームスープ、もう片方の手にはベーコン、チーズ、ほうれん草入りのバゲットを持っていた彼女は彼らに近づいた。
「念のためエドワードの分を取ってきました。今日捜索練習で苦労したじゃないですか」
「ありがとうございます」
エドワードは笑顔でスープの入ったボウルとサンドイッチを受け取る。
「食事は普通上官からしませんか?本で読む時はそうだったのに」
「エドワード様は特別なことがなければ一番最後に食事してもらっている。そうしてこそ団員たちも後ろの順番の配給分まで考えて、最初から適当に食べるのが習慣になるのですから。主君を飢えさせるわけにはいかないから」
「そういうことだったんだ」
ルイーゼはうなずいた。
「そして・・・」
「うん?」
「・・・何でもない」
マクシオンは特有の無言の表情で彼女を見た。
彼の黒い瞳に怪謗な顔をしたルイーゼが映る。
(私もまだ食事の前なのに)
不満や寂しさだけはあまり顔に出さない方でよかった。
そうでなかったら、最近何度も残念な様子を見せていたはずだから。
もうルイーゼのそばには自分一人だけではなかった。
最近、彼女は自分よりエドワードと近く見え、ヘンドリックやロビン、他の団員たちもルイーゼを大切にしていることが露骨に感じられるほどだった。
奇妙な喪失感が彼を沼のように徐々に引き寄せていく。
「ねえ、ルイー___」
「ルイーゼちゃん!こっちに来てみてください!」
焚き火の近くでマシュマロを焼いていたヘンドリックがルイーゼを呼んだ。
「はい、行きましょう!マクシオン、何か言いたいことがあるの?」
「・・・ないよ」
「うん」
ルイーゼは彼に微笑み、ヘンドリックの元に向かった。
マクシオンの視線が遠くなるルイーゼの後ろ姿が長くなる。
そのせいで彼はエドワードが後になって足を運ぶまで彼を見ていたという事実に
気づかなかった。
ルイーゼが気になる匂いの正体は魔力?
マクシオンの喪失感にエドワードも気づいているようですね。