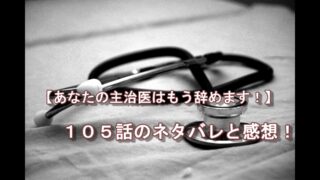こんにちは、ちゃむです。
「夫の言うとおりに愛人を作った」を紹介させていただきます。
今回は64話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

64話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 幼馴染との出会い③
アレンの咳が頻繁になった。
彼はしばしば薬の製造と販売をやめ、本格的にルイーゼに治療法を教え始めた。
ルイーゼはセラピストとしての技術を伝授されるのに忙しい時期を過ごす。
表向きはアレンの仕事を手伝うという趣旨だったが不思議なことに、マクシオンの目にはアレンが自分の最後を準備する姿のように見えた。
二人は十歳になる。
レンシアは10歳になったら祭りに連れて行ってあげるという約束を守るために、マクシオンとルイーゼを連れてカバンに向かった。
隣接した村から再び村の一つを過ぎて到着したカバンは、人出が多いかなり大きな村だ。
特にここで開かれる冬祭りはとても有名で人々が多く訪れる。
冬なので何重にも重ね着した服で全身を武装したおかげで、南部では珍しいマクシオンの外見も、ルイーゼとレンシアの銀色の髪の毛も帽子と服の中にほとんど隠されていた。
「もし一行を失ったら、中央広場で集まるんだ。通りすがりの人に中央広場はどこかと間けば教えてくれるからすぐ市場に来て。マクシオンは言うことをよく聞く方なので心配ないが、特にルイーゼ」
近くの屋台に置かれているイチゴキャンディーを眺めていたルイーゼの肩が震えた。
「はい!」
「見失ったら人々に聞いて中央広場で集まると言った。そんなことがないように気を引き締めて」
「はい」
ルイーゼは熱心にうなずく。
祭りは規模が大きかった。
食べ物、見どころなどがいつにも増して豊かだ。
真冬にも上着を脱いだ身で力公演をする北部人とさすらいの魔法使い、吟遊詩人など多様な人々が一堂に会し、不思議な見どころを提供した。
いつの間にか薄暗くなろうとする時間帯だった。
「そろそろ見るものも全部見たけど、これでメインショーを観覧しに中央広場に行ってみようか」
「・・・はい」
街の語り手の話が終わると、レンシアが足を運んだ。
マクシオンは彼女の隣から立ち上がって横の席を確認する。
ルイーゼが消えた。
「そうだと思った」
レンシアが頭痛がするように手のひらで額を触りながら眉間を集めた。
「どうせ中央広場に行こうとしたところだったから、そこで待とう、マキシオン」
「はい」
マキシオンが当惑した顔でレンシアにぴったりとくっついて行く。
ルイーゼとあんなに一緒にいたのに、彼女がいなくなることさえ気づかなかった。
すごい騎士であるレンシアマザーも、ルイーゼが決心して気配を隠せば、捕まえるのが大変だった。
広場の中央には巨大な氷の彫刻が展示されている。
巨大なドラゴンに対抗して剣を持った女性の彫刻像だ。
火が像を囲んでいたが、不思議なことに氷は溶けなかった。
「・・・先生みたいですね」
「そうだよ。ドラゴンを倒す前にここに立ち寄ったんだ。それを記念するお祭りだよ」
「あ」
「まあ、打ち破ったという言葉には語弊があるが」
レンシアが付け加えた。
「先生が倒したのではないですか?」
「う一ん、ちょっと違うけど、似ている。それよりルイーゼが遅いね。きっと何かに気を取られているのだろう」
「光る物でも見つけたようですね。ルイーゼはキラキラするのが好きじゃないですか」
「そうかもしれない。私が真っ白なカラスを産んだみたい。早く来ないし、何をしているのかしら」
レンシアは不満そうな声で言った。
口ではああ言ってもルイーゼが心配なのか、引き続き周辺を見回している。
ペリルスと普通の小さな森の間の小屋にはあまり明かりがつかなかった。
そのためだろうか、ルイーゼは特に光が好きだ。
彼女は天気の良い日には必ず丘に来ると、きらびやかな光の中の世界をじっと見つめた。
ルイーゼは光が毎日変わると言ったが、マクシオンは何が違うのか感じられなかった。
それで彼は彼女と一緒に世の中を眺める代わりに、そのような世の中を眺めるルイーゼを凝視した。
世の中を眺めるルイーゼの顔はほとんどが楽しかったり幸せそうに見えたが、時々寂しい気配が浮び上がったりもした。
ある時は残念な気持ちと憧れがにじみ出たりもした。
『あの光を盗んで私の家に持って行けたらいいな』
彼女はしばしばそのように呟いていた。
祭りが盛んに熟した。
村の人たちが中央広場に集まって紙で作った模型のようなものを持ってきて、10から数を逆に数えている
人々の叫びと同時に紙の模型に火がついた。
暖かい光の入った紙の模型が空に浮かび上がる。
数百個の風灯が一度に空に舞い上がる場面は絶景だ。
今どこかを歩き回っているルイーゼもこの瞬間だけは夜空に彩られた光の饗宴を眺めているだろうとマクシオンは思った。
その姿は彼さえ視線を奪われるほど美しかった。
光が夜空の中に遠くなる頃だった。
「お母さん!マクシオン!」
ルイーゼは人込みをくぐって彼らのところにやってきた。
せっせと歩き回ったのか、頬に赤みが残っている。
「どこを歩き回っていたの?」
レンシアが沈んだ声で尋ねると、ルイーゼが急いで答えた。
「人を助けてきました」
「誰」
「知らない人です。変な人たちに連れて行かれていて助けてあげました。お返しにこれもいただきました。綺麗ですよね」
ルイーゼは小さなボタンを差し出す。
「そんなおせっかいは私に似ているようだね」
レンシアが止められないかのようにため息をついては、ルイーゼが出したボタンを確認した。
彼女の顔はあっという間にこわばる。
ルイーゼはレンシアにしがみついて、さっき見た人のことを話し続けた。
「目がきらきらと輝いていました。とてもきれいで、最初は宝石かと思いました。光が当たると地平線から昇る太陽のような光を放ちました」
「・・・人の目がどうしたの。宿に行こう。20年は老けた気分だよ。早く休まないと」
「マクシオン、マクシオン。本当だよ。本当にきれいだった!」
翌日、小屋に戻った一行は、約束通り元気なアレンと挨拶を交わした。
マクシオンはその日以来1か月間その輝く目のことを聞かなければならなかった。
子供の言葉が普通のように、彼女が見た輝く目に対する修飾は次第に誇張され、ぴかぴかと光が出て周囲を真昼のように照らすようだったという表現もついて。
その間、「後光がやたらに噴き出した」という言葉まで生まれた。
「頭の中で鐘が鳴って真冬なのに、世界中に赤いバラの花が咲き乱れているような気がしたんだ」
ますます神格化していく水準に発展する彼女の話をおとなしく聞いていたマクシオンが、ふとルイーゼと彼の初めての出会いを思い出す。
彼の表情が暗くなった。
「・・・ルイーゼ」
「うん?」
「あなた、その人に惚れたの?」
ルイーゼが口を開けて食べたパンを通りに逃した。
爆発しそうに赤く燃え上がったルイーゼの顔が彼の問いに代わりに答えている。
マクシオンはルイーゼに初めて機嫌を悪くした。
「いいよ。もうその話はやめなさい」
「なんで?」
「興味ない。聞きたくないし」
ルイーゼはショックを受けた表情で静かにうなずいた。
その答えが死刑宣告のように感じられ、マクシオンは固い顔で食事を終えて一人で外に出る。
ルイーゼは後になって彼の後をついて行った。
彼女は注意深くマクシオンに話しかけたが、彼は堂々と彼女を避けている様子が歴然としていた。
「あなた、ずっとそうするの?私が何をそんなに間違ったと言うの」
ルイーゼは怒りをぶちまけて、すぐに振り向く。
二人の初めての喧嘩だった。
ルイーゼが助けた相手とは誰のことでしょうか?
マクシオンとルイーゼの喧嘩は、どのように終結する?