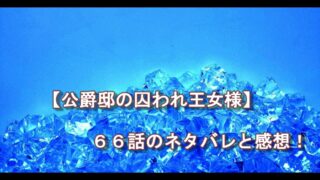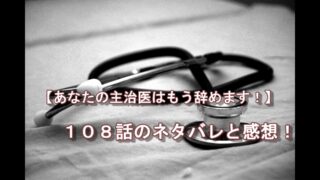こんにちは、ちゃむです。
「夫の言うとおりに愛人を作った」を紹介させていただきます。
今回は65話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

65話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 幼馴染との喧嘩
喧嘩してからまた1か月が過ぎた。
マクシオンはその1か月の間に彼女の馬鹿げた話をもっと聞いてあげればよかったと思った。
2人は互いに対話も交わさず、必ず一緒にいなければならない時を除いては、各自の時間を過ごすことに。
彼女の徹底した無視に、マクシオンは時々密かに涙まで拭った。
告白したこともないのに、徹底的に振られた気分だ。
その間に冷たい空気が消え、暖かい風が吹き始めた。
やせこけた枝に新芽が育ち、小さくそびえていた蕾がすぐにでも花を咲かせるようにぽっちゃりに。
他の日よりとりわけルイーゼの気持ちがよさそうな日だった。
マクシオンは勇気を出してルイーゼに話しかける。
「今日は丘に一緒に行ってもいい?」
「心から謝るなら」
「あなたに敏感になってごめんね。次からは何でもないことで理由もなく怒らないよ」
「そうだね。私もごめん。あなたは聞き飽きただろうに」
「大丈夫だよ。君の話は全部聞きやすいから」
「そうなの?」
「・・・」
ルイーゼは明るく笑う。
一度声をかけてみると、その後は簡単だった。
「今日はどうしてそんなに気分がいいの?」
「明日が私の誕生日だから」
「・・・」
ルイーゼは鼻歌を歌いながら丘を登っていく。
誕生日。
母親が消えた後、一度も面倒を見たことのない日だ。
その夜、マクシオンは居間のソファで一人で夜を明かした。
そして翌朝、彼は目を細めてルイーゼに何かを渡す。
「これは何?」
「誕生日プレゼント」
木を粗削りにした品物は変な形をしていた。
四方に大きな角が生えていて、斜めに小さな角がそびえている平たい形の木片をルイーゼはしばらく眺める。
「これは何?」
「光」
ルイーゼは木片とマクシオンを交互に見た。
マクシオンは照れくさそうな顔で横を掻いた。
「家に盗んで来たいと言ったじゃないか。盗むことはできないから作ったの」
「きれい」
彼女は世界で一番幸せな子供のように笑う。
ルイーゼはその後1か月間、彼がプレゼントした光のかけらについて話した。
彼はそれですっかり気分がほぐれた。
1ヵ月後、彼がプレゼントした光のかけらは、彼女の話の中で世の中のどの光より明るく輝く何かに変わっていた。
「時間があまり残っていないようだ」
彼らが12歳になった年にアレンはそのように自分の口から宣言する。
むしろ最近は咳をほとんどしなかった。
それでルイーゼとマクシオンは彼の病気がましだと思っていた。
レンシアは先に話を聞いたのか、淡々とした表情だ。
「今日からは当分の間、剣術の訓練を休んでみんなであれこれしながら過ごすことにしよう」
沈んだ声から、その言葉が冗談ではないことが感じられた。
かなり大きくなった2人の子供は違った反応を見せる。
マクシオンは面食らった顔でアレンを眺めているだけで、ルイーゼは驚いた表情で固まったが「それではこれからお父さんに会えないのですか?」と言って鶏の糞のような涙をぽたぽたと流す。
ペリルスの近くに住んでいて、森に出入りしているので彼らの家族は死者を見ることが多かった。
死んだ姿を見ることに慣れているからといって、身近な人の死まで慣れているというわけではない。
「君たちに私たちの家に伝わる秘術を教えてあげる」
アレンはこれまでマクシオンに応急処置の方法と軽い病気を治療する方法を教えてくれた。
しかし、正式に後継者の授業を受けたのはルイーゼ一人だけ。
そんな彼がいきなり家門の秘術を教えてくれると言うと、マクシオンが緊張した表情で乾いた唾を飲んだ。
「私が知ってもいいのですか?」
「大したことないよ。みんなに通じるわけでもないんだから。親しい人や他人にこっそり教えてあげたりもしたから大丈夫。人にも教えることなのに、しかもあなたは家族じゃないか」
尻尾のようについてきた言葉に彼は胸の中で何か熱いものがうごめくようだった。
「秘術名は『旅立った者の声を聞く方法』だ。名前だけ大げさだよ」
アレンは静かに彼を見つめるルイーゼの頭を撫でる。
「セラピストは必然的に数多くの死と向き合うことになる。誰かの最後を家族の代わりに守ったり、すでに去った姿に出くわしたりする。代々数多くの治療士が多くの人々の終わりを
見た」
彼は目をそらしてマクシオンを見た。
「これは残された人々のためのものだ。治療術は死者のためには使えないから」
「・・・」
「内容は簡単だ。愛した人を送った後、会いたい人と一番幸せだった時間に戻って彼と対話を交わすんだ。必要なら似たような状況を再現するのもいい」
「・・・それで終わりですか?」
ルイーゼは目を瞬かせながら尋ねる。
「終わりだよ」
「どうやってその時間に戻りますか?人がいないのに話し声はどうやって聞くんですか。それが何の治療術なのですか」
「想像しているんだ」
「なんでそんなことをするんですか?」
「残された人に愛する人の死が怖いのは、二度と会えなくなるからだ」
アレンの言葉にルイーゼは悲しそうな顔で頭を下げた。
そうだ。
彼女の恐ろしさも彼との永遠な別れが近づいたことから始まったから。
「どうして幸せな思い出なんですか?もっと見たくて悲しいと思うけど」
「それが一番大事だよ、ルイーゼ。死の前に立った人たちは、ほとんどやったことよりできなかったことを残念に思うんだ。愛する人を残していく人たちはもっと愛せなかったことを残念がって。だから彼らが言いたかったことは、お互いを責めたり不幸だった時より幸せだった時間帯にある」
アレンはルイーゼを見て優しく笑う。
「君を誇りに思っているよ。病気にならないで。心配だ。ミスしても大丈夫だから、心から幸せになれ。そのすべてをもっとよく表現する方法が分からなくて申し訳なかった。それでも君を愛してかるよ」
アレンの話を聞きながら、マクシオンは突然彼のもとを去った母親を思い出した。
自分を捨てた彼女も、自分にそんな気持ちを持ったのだろうか。
自分を愛したのだろうか。
自分が幸せになってほしかったのだろうか。
疑問符のようについてきた数多くの質問の最後には、何の確信もなかった。
マクシオンはアレンの言葉の意味を理解し、「みんなに通じるものではない」と言った。
「多くのセラピストが他人の世話をして人生を終えた。セラピストの最後には家族が一緒にできないことが多い。必然的に危険に近い職業だから。それで残された人たちのために残した先代セルベニアの息子の知恵ではないかと思う」
「うちの家には治療師が多かったようです」
「そういう方だよ」
「ところで、こんなのが秘術なんですか。人にそれとなく教えたりもしたそうですね」
「秘術を持った家柄なんて、立派に見えるじゃないか。その事実一つだけでもすごい家門のように見えるそうじゃない?」
ルイーゼはアレンに細い目で答えた。
「・・・見栄っ張りだね」
「それでよかった。もしこれが本当に重要な治療術だったら、うちの家門が独占して多くの生命がそのまま死ぬことになったかもしれないんだ。私たちだけの秘密なら意味がないという。治療術は人を生かすために存在するものだから」
ルイーゼはゆっくりうなずいた。
「ルイーゼ。お前はこれからも新しい人にたくさん会うことになるだろう。愛する人ができるかもしれないし、彼らと幸せな思い出をたくさん作って。いつか別れが訪れた後も振り返る思い出がいっぱい残るように。過去は道を作り、未来は方向を描く。私たちは記憶の上を歩きながら、明日に向かって生きていくんだ」
「難しい話は分からないけど、他の人に会わなくてもいいから、一生私と一緒に生きてください」
ルイーゼの目にまた涙があふれる。
アレンは返事の代わりに子供の顔を平手でそっと撫でるだけだった。
その夜、泣いて疲れたルイーゼは早く寝た。
居間にいたアレンがそわそわして夜遅くまで起きていたマクシオンを呼んでソファーに座らせた。
「レンシアはあなたが一生ルイーゼのそばに留まってくれるかもしれないと思うが、私は違う。マクシオン、あなたは外の世界を経験したので、きっとまたそこに戻ることになるだろう」
「・・・」
マクシオンは答えられなかった。
彼の言うことが正しいと納得するには恩知らず一人になったような気がしたからだ。
ただ、彼の言ったことは事実だ。
マクシオンは時間が経つにつれ、ここで一生生きていく自信がなくなった。
彼はもっと広くて大きい世界が懐かしかった。
「ルイーゼはここを離れてはいけない。少なくとも大人になるまでは。もしかしたら、その後もしばらくはここに留まらなければならないかもしれない。そもそも、ここを離れないほうがいいだろう。だから、あなたがいつかここを離れることになっても、必ず一人で離れてほしい」
「ルイーゼも離れたいと思うでしょう」
マクシオンは外の光に憧れるルイーゼの本心を知った。
そんな彼女をここに一人にして離れたくなかった。
「少なくとも二十歳まではルイーゼをここに置いて。いや、多めに23から5までがいいと思う。もしルイーゼがここを離れ、体の具合が悪くなったら、また戻ってこなければならない。そうすれば治るよ」
「理由をお伺いしてもよろしいでしょうか」
「ルイーゼがここを離れられる年になった時、裏庭にある大きな岩の下を掘ってみなさい」
「・・・はい」
アレンは笑いながら彼の髪をかきわけた。
「子どもに頼もしいところがある。心強い息子ができた気分だから安心するんだよ。うちの女たちをよろしく頼む。一生じゃなくて、滞在する間だけ優しくしてくれ」
「はい」
数日後、アレンは彼が言ったように世を去った。
彼はぐっすり眠っているかのように安らかな姿で彼ら家族に永遠の別れを告げた。
ルイーゼは堂々と泣き、レンシアは密かに涙を拭った。
マクシオンは涙を流す代わりに、ルイーゼを抱いて慰める。
本来も体が大きい方だが、ここに滞在している間にその間にルイーゼより背が高くなったので、今は彼女が彼の胸にしっかりと抱かれた。
「ルイーゼ、もっとうまくやるよ」
12歳、初めて心を与えた親しい人の死以後、マクシオンはルイーゼに顔を赤くしなくなった。
くすぐったい気持ちよりは責任感が、守れない以上よりは守ることができる約束が彼の中に位置した瞬間だった。
父親が亡くなったルイーゼ。
この瞬間からマクシオンはルイーゼの保護者として生きることを決心したのですね。