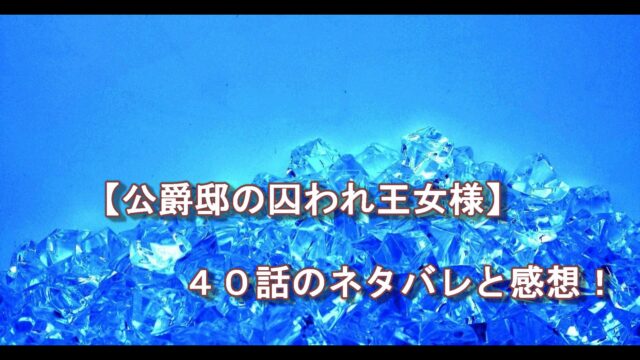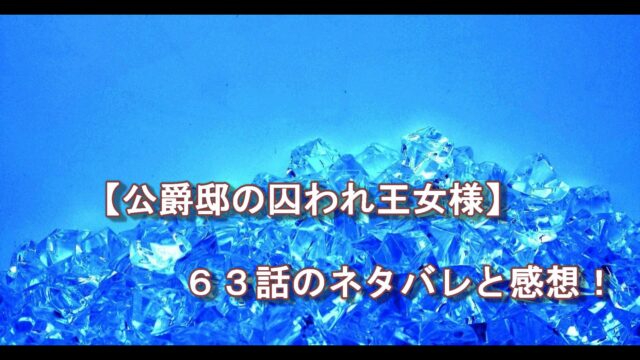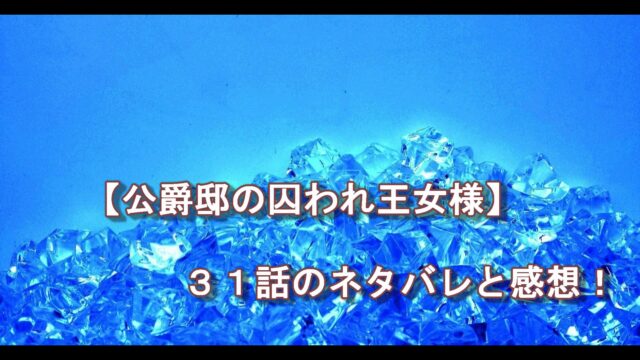こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

137話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 愛らしい子ども
処刑の手続きがすべて終わり、罪人の“死”が正式に確認された、その直後――マクシミリアンは、しばらくその場から動けずにいた。
春の夕陽が、磨き上げられた床に長い影を落とす。
その光は穏やかで、あまりにも平穏で――まるで今日という一日が、ただの「いつも通り」だったかのように世界を包んでいた。
「……春、か」
誰に聞かせるでもなく、低く呟く。
嫌いな言葉だった。
命を芽吹かせ、始まりを告げる季節。
それは同時に、終わりを遠ざける残酷な猶予でもある。
時間は、確実に流れている。
止まらない。
待ってはくれない。
クラリスの“終わり”に向かって、容赦なく。
マクシミリアンは、ゆっくりと右手を見下ろした。
微かに震える指先。
それは初めて、人を殺した夜と、まったく同じだった。
正義の名の下であろうと。
秩序を守るためであろうと。
――殺しは、殺しだ。
「……正しくなんて、あるわけがない」
吐き捨てるように言い、彼は拳を強く握り締めた。
それでも彼は、剣を置けなかった。
剣を持つしかなかった。
この世界がそういう形でしか成り立たない以上、王子として、彼は“選ぶ側”であり続けなければならない。
だが――
「……一歩、近づいたな」
クラリスの死に。
その事実が、胸の奥で鈍く痛んだ。
春の光は、変わらず優しい。
何も知らない顔で、すべてを照らしている。
マクシミリアンは目を閉じる。
――まだだ。
まだ、終わらせない。
終わらせるわけには、いかない。
彼の中で、かすかな決意が、静かに、しかし確かに形を成し始めていた。
それでも、父の命令を忠実に実行したのは、彼が愛する家族を守るためだった。
父と母、そして……可愛い妹。
彼は、脇に置いてあった酒杯を手に取った。
魅惑的な香りに一瞬心が揺れたが、彼はそれを口にしなかった。
――いや、できなかった。
時に酒は、時間を早く流してくれる。
だが今は、それに頼ることは許されなかった。
時間。
それは幼い頃のクラリスが切望していたものであり、そして今は……マクシミリアンが望んでいるものだった。
杯を置いたとき、彼は自分の袖に残る黒ずんだ痕に気づいた。
「……あ」
彼はすぐに侍従が用意した水盆に袖を浸した。
澄んでいた水に、赤い色がゆっくりと溶けていく。
……その血の色を、彼は見慣れていた。
あまりにも、何度も。
水に滲む赤を見下ろしながら、マクシミリアンは静かに息を吐いた。
胸の奥が、ひどく冷えていく。
――家族のため。
そう言い聞かせてきた。
父の命令に逆らわなかったのも、剣を握り続けているのも、すべてはそのためだった。
父と母。そして、まだ何も知らない――幼い妹。
彼女の無邪気な笑顔が、脳裏をよぎる。
この血の匂いなど、一生知らずにいてほしい存在。
彼は何も言わなかった。
ただ、濡れた袖を押さえ、水を絞る。
赤い色は、なかなか消えない。
まるで染みついた罪のように。
侍従は頭を垂れたまま、沈黙を守っていた。
言葉が不要だと、理解していたからだ。
時間は流れる。
酒も、血も、感情も――すべてを少しずつ洗い流しながら。
それは、幼い日のクラリスが熱望していたものであり、今は……マクシミリアンが望んでいるものでもあった。
彼は濡れた袖を整え、再び杯を置いた。
今回も、酒は飲まなかった。
飲んではならない。
酔ってはならない。
正気を失う余裕はなかった。
なぜなら――彼は知っていたからだ。
クラリスの時間は、彼がどれほど目を背けようと、どれほど手を汚そうと――止まらないということを。
「……待っていろ」
誰にも聞こえない声で、そう呟いた。
それがクラリスに向けた言葉なのか、それとも自分自身を縛るための言葉なのか、彼自身にも分からないまま。
水盆の中で、赤い波紋がゆっくりと揺れ、やがて沈んでいった。
その赤い痣が、彼の指先に触れた瞬間、人を斬る感触が生々しく蘇った。
処刑場の空気は、冬の寒気がそのまま居座っているかのように、ひどく冷え切っていた。
膝をついた罪人たちの中央で、目隠しをしたまま、ライサンダー、バレンタイン、王妃アメルダ、そして彼女の双子の兄――オラヴィン・レノクス侯爵が、処刑の証人として列席していた。
王室の尊厳に触れたこと。
それが、彼らの罪だった。
バレンタイン王子に隠された双子の姉がいる――などという、口にするのも馬鹿げた流言を広めたこと。
「王の血は、決して双子として存在しない」
王室に伝わるその言い伝えを思えば、彼らが囁いた言葉が許され難いものであったのは確かだった。
朗読者が判決文を読み上げ、司祭たちが罪人のために祈りを捧げる。
そして――マクシミリアンの番が来た。
ライサンダーが、わずかに顎を引く。
それが、合図だった。
マクシミリアンは、無意識のうちに罪人たちを見回し――そして、ふと視線が絡んだ。
必死に救いを求めるその眼差しを……彼は、ぎゅっと瞼を閉じて耐えた。
ためらってはならない。
この処刑場に、バレンタインが顔色を失い、ほとんど引きずられるようにして連れて来られている意味を考えれば、なおさらだ。
もしマクシミリアンが、ほんの一瞬でも躊躇すれば。その残酷さは、幼い弟――ライサンダーの肩にのしかかることになる。
この凄惨な光景を見せるのも耐え難いが、押し付けるなど、なおさら望まなかった。
だから、彼は――。
「――公爵様!」
切迫した呼び声に、はっとして意識が引き戻される。
いつの間にか、両袖は血に濡れ、無残な有様になっていた。
「……公爵様」
背後から聞こえてくる、ブリエルの抑えた声と、背に触れるぬくもりに、彼は苦しさを覚えた。
なぜ慰めというものは、こうもすぐ傍にあるのだろう。
――もっと、自分の罪悪を、骨の髄まで味わうべきだというのに。
「私に……」
彼は、自分の腰に回された小さな手を、振り払うこともできないまま、慎重に言葉を選んだ。
「来てはいけません」
彼には罪が貼りついている。
この穢れを、妻や子に触れさせるわけにはいかなかった。
「嫌です」
だがブリエルは、逆に彼の正面へと回り込み、両手で彼の頬を包んだ。
「……私は、汚れています」
「それなら、その汚れを私に分けてください」
マクシミリアンは、彼女が“強い”のだという事実を、あらためて思い知らされた。
「私がめちゃくちゃになっても、かまいませんから」
ブリエルは背伸びするように持ち上げた両腕で、彼の首元にしがみついた。
大柄な男は、抵抗することもなく、彼女の腕に引かれるまま、狭い肩に縋るように顔を埋める。
その場で、マクシミリアンは重く、荒い呼吸を繰り返していた。
必死に平静を取り戻そうとしているのが、ありありと伝わってくる。
「人を……殺しました、ブリエル」
ブリエルは小さく頷き、彼の長く黒い髪をそっと撫でた。
「私が、処刑しました」
「…………」
「……ブリエル。私は、きっと……」
言い淀んだ末に、彼はそれ以上言葉を続けることができなかった。
ブリエルは、その“最後まで言えなかった言葉”の意味を、完全に理解していた。
それが、もう三年も残されていない――クラリスの十八回目の誕生日を指していることも。
震える手で、マクシミリアンはブリエルの腰と背を、切実に抱き寄せた。
想像の果てにある未来から、目を逸らすかのように。
結局のところ、恐れていた事態は避けられなかった。
彼の血に濡れた衣の裾から滴り落ちた赤い水は、ブリエルの衣装や髪にまで無残に染みついていく。
「……私は、分かっていました」
そう呟きながら、彼女は夫をいっそう強く抱きしめた。
「あなたが、あの子を……とても深く愛していること」
マクシミリアンは、ブリエルの肩に額を預けたまま、静かに首を横に振る。
「私には……そんな資格はありません」
過去の自分が脳裏に蘇り、胸の奥が締め付けられるように痛んだ。
あの小さな子に、彼は何度「罪人」という言葉を向けただろうか。
当時のクラリスは、せいぜい人形に心を預けることしかできない、か弱い幼子だったというのに。
「過去に戻れるのなら……そうできたら、どれほど良かったか。できるのなら……」
冷たい処刑場の床に座り込んでいた、あの小さな少女を――彼は今度こそ、高く抱き上げ、温もりのある場所へ連れて行きたかった。
――そうしていれば、きっと違っていたはずだ。
セリデンへ連れて来たその日から、思う存分に走り回らせてやってもよかった。
多少わがままを言わせても、誕生日には盛大な祝いの席を設けると、そう約束してやればよかった。
罪人の部屋ではなく、セリデンのお嬢様として、屋敷で一番いい部屋を与えていたはずだ。
夜会の晩だって、決して一人きりで部屋に残したりはしなかっただろう。
何より――あんなにも早く、大人の理不尽を突きつけることはなかった。
そして、まだまだ……幼いクラリスにしてやりたかったことは、数え切れないほど残っていた。
けれど今となっては、もう二度とあの時間へ戻る術はない。
「……時間を巻き戻すことはできません、公爵様」
「分かっている。私も……それは承知しているが……」
「それでも、必要ありません」
彼女は、項垂れる男の頬にそっと手を添え、顔を上げさせた。
真正面から、きちんと目を合わせるために。
「クラリスは――まだ、私たちの傍にいますから」
その言葉は、静かで、しかし確かな温もりを帯びて、彼の胸の奥へと届いた。
彼女はマクシミリアンの頬をそっと撫で、静かに言葉を重ねた。
「まだ、何も遅くありません。今からでも、いくらでも愛してあげられます」
「…………」
「私は……あなたにはお伝えできていませんでしたけれど、実は……」
彼女は、強い意志を宿した瞳で彼を真っ直ぐに見つめた。
「ずっと前から、クラリスを守ると決めていました」
「ブリエル……」
「でも……やはり、私一人では力不足です。よろしければ、誓っていただけませんか?」
マクシミリアンは、ゆっくりと背筋を伸ばした。
長いあいだ胸を縛りつけていた痛みが、この瞬間、わずかに和らいでいくのを感じる。
――最も愛する人が、同じ未来を見据え、同じ願いを語ってくれる。
それが、これほどまでに深い救いとなるとは。
彼は初めて、ほんのかすかに、息がしやすくなった気がしていた。
「クラリスを……いいえ」
彼女は軽く首を振り、そっと片方の手を差し出した。
「私たちの子を守ってください、マックス」
――私たちの子。
クラリスの許しもなく、こんなふうに呼んでしまっていいのだろうか。
それでも今は、その温かな言葉が胸に心地よく響いた。
彼はゆっくりとブリエルの手の甲に唇を寄せ、誓う。
「……守ります。必ず」
そして視線を上げ、ブリエルをまっすぐに見つめた。
「私たちの、大切な子を」
もはや、迷う理由はどこにもなかった。