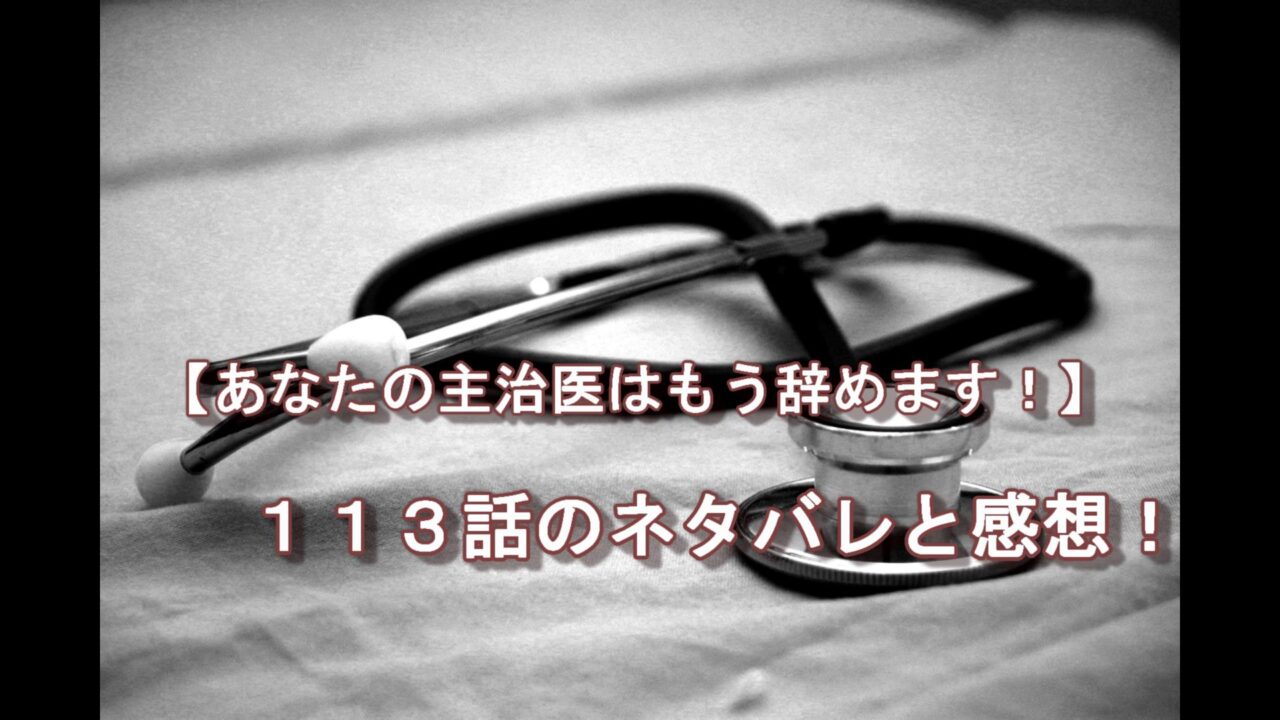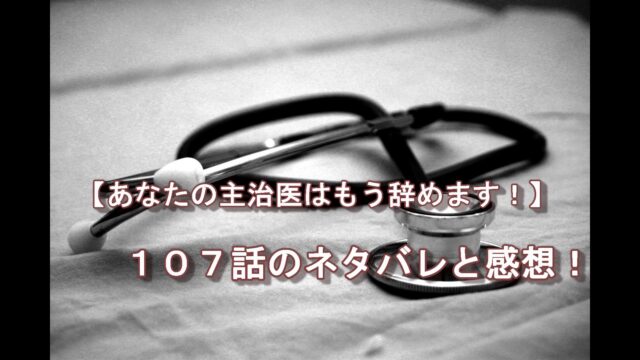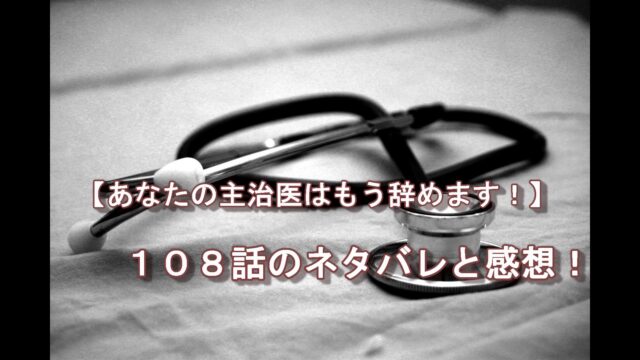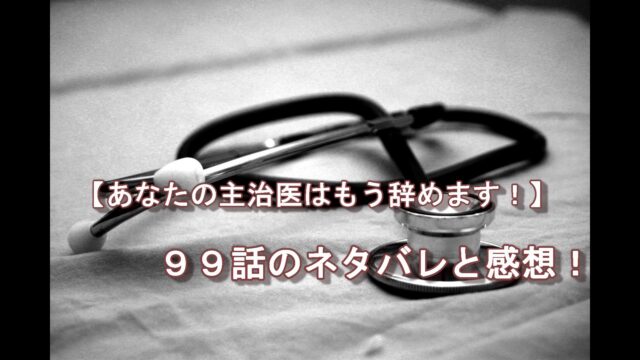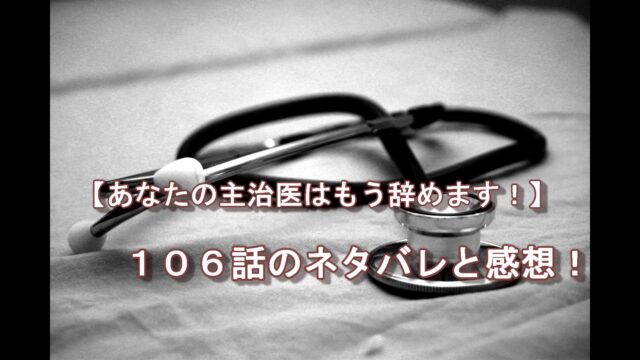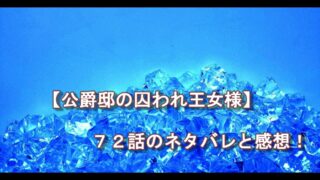こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
今回は113話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

113話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 戸惑い③
アルガはフェレルマン公爵邸へ行き、フェリックスと話をすることにした。
彼はセイリンに対して、すべての事実を打ち明けることに。
ハエルドン皇子がどんな神託を受けたのか、シオニーがどのようにして命を落としたのか、そして行方不明になった娘が誰なのか。
話す者も聞く者も、その内容に怒りと涙を抑えきれないほどの重い話だ。
リチェが自分を「父」と呼んだという話に至っては、フェリックスとセイリンが同時に声を上げた。
二人の表情には、歓喜と感激が入り混じった様子が浮かび、それを見つめるアルガの顔には微妙な表情が浮かんだ。
「しかし、それ以来リチェは非常に控えめになってしまいました。」
アルガは重い表情で付け加えた。
「『父』と・・・もう呼ぶこともなく、ただぎこちなく『公爵様』と呼んでいます。」
「いや、一体どうして・・・」
セイリンは指先をもじもじと動かしながら話した。
「ただここに連れてきたら良かったんじゃない? 今やリチェの家はここなんだし。」
「もちろん一緒に行こうとは言ったよ。」
アルガは無表情な口調で答えた。
「でも・・・断られたんだ。ああ、セイリン卿とフェリックス殿によろしく伝えて欲しいって、それだけ言ってた。」
「え?」
セイリンもまた深刻な表情で口を開いた。
「セイリン卿? フェリックス殿? なんでそんな呼び方するの?」
「・・・はあ」
アルガが小さくため息をついた。
「最初は明らかに泣きながら喜んでいるようだったけど・・・考えてみると、引っかかることが多すぎるんだよな・・・。」
アルガのその言葉に、フェリックスとセイリンも肩をすくめた。
「気になることが多すぎる?」
アルガはリチェのぎこちない表情を見つめながら、頭が痛くなるような考えを一気に吐き出した。
「最初に会ったとき、いきなりうるさい小娘って言ったし、親切に検査を手伝うって言ったのに疑ってきて、ジェニーに監視までさせたんだ。初対面で、当然俺にがっかりしたのが分からないか?」
彼は考えれば考えるほど、なんて無情なんだろうと頭を振った。
「リチェは・・・狩猟大会で私のためにハエルデン皇帝に直接謝罪までしてくれたのに・・・」
その言葉にフェリックスも、何か大変なことが起きたような表情を浮かべた。
「それならここに来ないのも、私たちに失望したからなのかもしれないね。」
老いた者の額に刻まれたしわがさらに深くなり、震える手でそれをなでた。
「そうだな・・・あの子が個人用熱追跡機をつけてくれって言ったとき、どれだけ私がそれを拒否しようとしたか・・・どうやって信じるんだと怒りもしたよ・・・。」
フェリックスは初めてリチェに出会った時のことを思い返す。
彼はため息をつきながら言った。
「あの子はこれまでずっと私のためにエナベの関節炎薬を送り続けてきた・・・そうだ、祖父に失望したに違いない。」
青ざめた顔になったのは、セイリンも同じだ。
「私はひどいことに、あの子がアルガの娘でフェレルマンの血族ではないと言ってしまったのよ。初対面があんな形で終わったのだから、私を叔母だなんて呼びたくないはず・・・。」
結局、初対面でリチェに冷たく当たったのは、3人全員同じだった。
狂ったように探し求めていた家族を目の前にしても、疑念の目でしか見ようとしなかったのだ。
「リチェは自分から私たちを探しに来たのに、私たちがそれに気づかなかっただけなんだ。」
アルガはそれを思うだけで、後悔の念に駆られるようだった。
彼は歯をぎゅっと噛み締める。
親しい娘を見つけてとても嬉しいけれど、それが他の誰でもないリチェだから、まるで夢のようだ。
しかし、どうにも申し訳なくて言葉にできない。
思わず冷たく見えるのではないかと心配して、理由も尋ねられずに、アルガは自分の不器用な性格にただ苛立っていた。
「それで?」
セイリンはアーガの鋭い目線を見つめ、困惑した様子で言った。
「ただここに逃げてきたってこと?」
「・・・君と父親に知らせるべきなのか?」
アルガは頭を掻きながら答えた。
「明日の朝にまた出発するよ。皇室調査団が来てイシドール男爵の自白を聞く予定だから、その場には当然出席しないといけない。軽率に逃すわけにはいかない。」
「そいつ、私が殺してもいい?」
「ダメだ。」
セイリンの殺気を帯びた質問に、アルガは即座に首を振る。
「死ぬなんて、その男爵にはあまりにも簡単な罰だ。」
「え?」
「延々と苦痛に身震いさせることが、本当の復讐だとセルイヤーズの狂った公爵が言ってたんだ。まぁ、その通りかもしれないけど・・・。」
アルガはさらに何か、心に引っかかるものがあるような表情を見せた。
「あの男がリチェを利用して結婚を口実に全体の教団を牛耳ろうとしているんだ。当然許せない。でも公爵城全体をひっくり返したい気持ちを抑えられないのに、リチェがあまりにも疑心暗鬼で動けなかった。」
「ダメだ!」
セイリンは勢いよく立ち上がった。
「リチェはシオニーに似てるわ。顔色を失ってでも生きる意思が強いのよ。セルイヤーズ公爵なんか、間違いなく顔しか見てないわ!」
彼女は震える手でナイフを握りしめながら言葉を続けた。
「もともと危険だと思っていたけど・・・私が近づけばもっと危なくなる。あの人間、どう見ても普通じゃないもの。」
「確かにそうだ。全然似ていなかった。ただ命を助けてやっただけなのに、腹の中が真っ黒な奴だったとはね。」
アルガが同意するようにナイフを握りしめる。
「やっと見つけたのに、結婚だなんて話にもならない。それもそんなとんでもない相手と。」
そのとき、フェリックスが杖を床に三度叩きつけた。
「カン!」という音が響き渡り、アルガとセイリンは一瞬にして口を閉ざした。
「今、こんなことで争っている場合ではないだろう?」
老人の目はどの時よりも鋭く光っていた。
「みんなでリチェに会いに行くのがいいだろう。」
「え?」
「もし何か悪かったなら謝って、失望させたなら、これからはその分ちゃんとすればいいじゃないか。アルガ、このダメな奴がリチェを疑ってばかりで涙ぐんでる間に、あの子はどうしてここまで逃げて来たんだ?」
「逃げたわけじゃなくて・・・」
「どうせセルイヤーズ公爵邸に戻ったんだろう? セイリンと私も一緒に行く。孫娘を直接見届けたい。」
「お父さん。」
「それと当然、連れ戻して来るんだ。リチェがそこに居続ける理由なんてないだろう。」
アルガは困惑した表情で答えた。
「私だってそうしたいですが、リチェはあそこの主治医・・・。」
「お前一人いれば十分だろう?お前はそこにいろ。リチェだけ送れ。」
「え?私も娘と一緒にいたいんですが?」
「じゃあ二人とも辞表を書け。その公爵はそんなに弱いのか?」
その言葉に冷静に答えたのはセイリンだった。
「いいえ、非常に強健です。我々の中で最も必要とされない人間です。」
「では話は終わりだね。」
フェリックスは決然とした表情で言った。
「行こう。あの狂った公爵から私たちの孫娘を連れ戻さなければならない。」
「ちょっと待ってください。」
アルガが素早く言った。
「難しいと思います。あのセルイヤーズ公爵は決してリチェを手放さないでしょう。」
同じような執念を持つイザベルやエルアンを思い出しているセイリンは熱心に眉をしかめた。
深刻な表情を浮かべたフェリックスを見てアルガが言葉を続けた。
「特に公爵が体調を崩している場合、彼はドレノールすら要求してくるかもしれません。その場合、すでに主治医の契約書にサインしているほどの責任感の強いリチェを連れてくるのはほぼ不可能です。実際には、季節の変わり目の診察なども見守る必要があります。」
「それでは・・・」
「むしろここに呼び出して会うのがいいでしょう。」
アルガは、宮殿調査官に直接会うために、セルイヤーズ公爵領に向かう時間を調整しようとしていた。
しかし、リチェとイザベルがいる以上、自分自身が必ずしも必要ではないと判断を下した。
進行が早すぎることに負担を感じているリチェを残し、イザベルとエルアンが婚姻のために動いていた過去を振り返ると、今は過去よりも未来が重要だと考えた。
どれほどフェレルマンの領主が強大であったとしても、その戦力はほぼ全てが弱体化している状態。
イザベルとエルアンが強情に粘り、リチェを手放さずに時間を稼ぐならば、セルイヤーズ公爵と戦闘をしてでもリチェを連れ出すこともあり得る状況だった。
「いずれにせよ、私はハエルドン皇子の審問に呼ばれるほかありません。その時でも証拠は十分です。まずはリチェを連れてくるのが良いでしょう。」
アルガは息をつき、ゆっくりと語りかけた。
「もちろん・・・私たちを許せないなら、そして再びセルイヤーズに行くというのなら、どうしようもありませんが・・・。」
リチェが12歳で公爵城に入り、成人する今に至るまで、リチェと最も多くの時間を過ごしたのはイザベルだ。
もしリチェが自分を認めず、初めての日を迎えたフェレルマンを嫌だと言い、セルイヤーズに留まると決めた場合、その時は送り出さなければならないだろうが・・・。
そう考えると、その思いに沈む暗闇がさらに深まるようだった。
アルガの顔を見ながらセイリンは毅然とした口調で言った。
「回り道をしなくちゃいけないわ。」
セイリンは決意を込めて顎を引いた。
「公爵城から抜け出すのが容易ではないことには同意するわ。私の人生で最もお兄様が頼りになる瞬間ね。」
「そうだな、招待状は私が書く。」
フェリックスもすぐに筆を手に取った。