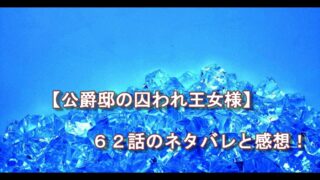こんにちは、ちゃむです。
「できるメイド様」を紹介させていただきます。
今回は193話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

193話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- モリナ王女
簡単な後始末の後、マリはクローヤンの首都であるコモン城に戻った。
残りの問題はエトナ島を管轄する行政官が解決するだろう。
誰がわざと広めたのか、彼女が成し遂げたことはすでにコモン城全体に広がっていた。
「さすが総督閣下」
「今回もまたすごいことをやり遂げたという」
人々は彼女の行列を見ながら騒いだ。
誰かが嘆息するように話す。
「いくら待っても、モリナ王女は帰ってこないね。私はもうモリナ王女ではなくても、あのヒルデルン子爵なら私たちが仕えるのに十分な方ではないかと思う」
「確かに・・・」
他の人たちがその言葉に同意した。
誰が彼女が足りないと言えるだろうか。
モリナ王女が懐かしいが、あの少女なら彼らを治めるのに一抹の不足もなかった。
「私はこんな気もする。モリナ王女はすでに亡くなっており、ヒルデルン子爵の身を借りて私たちの元に戻ってきたのではないかという」
「どういう意味だ?」
「ただ。あの方の行跡が過去の王女殿下の行跡があまりにも似ているのではないかと思って」
その言葉に人々の表情が妙になった。
そういえば似てはいる。
「顔のない聖女」、モリナ王女とあの少女総督の行跡は不思議なほどそっくりだ。
「もしかして・・・モリナ王女があの方じゃないよね?」
「とんでもないことを言うな。あの方は帝国の予備皇后さまだよ」
「しかし、クローヤン王国民だったが、戦争の時に捕虜として連れて行かれたと言っていたではないか。モリナ王女もちょうどその年だと思うけど?」
その言葉に人々は首をかしげる。
考えてみると妙だった。
とんでもない話だが、なんだかもっともらしく聞こえる話だ。
「ええ、まさか・・・話にならない」
人々は首を横に振った。
実は、あの少女がモリナ王女かもしれないという疑惑は今回が初めてではない。
あまりにも偶然ではあったのだ。
しかし、話にならない話であるため、デマと見なされ、消えるのが常だった。
ところが、今回はなぜだろうか?
一度火種が燃え上がった疑問は消えず、人々の間に急速に広がり始めた。
まるで誰かがわざと意図でもしたかのように。
影が入り込むようにクローヤン王国民の間にマリに対する疑問が広がった。
マリは自分の噂に耳を傾けず仕事に熱中した。
いろいろなことを解決し、秋が深まっていったある夜。
バルハン伯爵は彼女に会話を求めた。
「王女殿下にお目にかかります」
二人きりになると、バルハンはひざまずいて彼女に礼を述べた。
マリはなぜか彼の礼がもっと手厚くなったと感じる。
以前は形式的な面が多分だったとすれば、今は真心が込められていた。
「どうぞ、伯爵」
マリは彼が結論を出したことに気づき、ドキドキする。
バルハン伯爵は王室騎士団の団長であり、反帝国運動の求心点だ。
クローヤン王国の貴族の動きは彼の決断によって決まるだろう。
「この前おっしゃった事案についてお知らせするために、このように面談を要請しました」
そう言った伯爵は突然頭を下げた。
「すみません、殿下!ずっと考えてみましたが、私はとても殿下の意見に従うことができません。クローヤン王家の再建だけは絶対に諦められません!」
その言葉にマリはすっかり元気がなくなった。
やはりそのような結論を下したのだ。
しかし、当然のことだった。
一生を捧げてきた忠誠であり信念だ。
どうやってー朝ータに変えられるだろうか?
「・・・そうなんですね」
マリは適切な言葉を見つけられず、そう答えた。
(私はこれからどうすればいいの?)
ところがその時、バルハンの口から意外な言葉が飛び出す。
「しかし、私は殿下に従います」
「伯爵?」
「その間、注意深く見守って悟りました。王国民のための殿下の心は、疑う余地のない真実であることを。これまで王家のどの国王も、王女殿下のように国民のための高潔な心を持ったことはなかったでしょう」
彼は再びひざまずいた。
「だから殿下がどんな道を歩いても、その道は王国民のためのものだと信じます!たとえ意味が違っても、王女殿下に命を捧げて忠誠を誓います!」
マリの胸がドキドキした。
ついにバルハンが彼女を受け入れたのだ。
深い深いゴールが彼女を足にして埋められ始めたのだ。
胸がいっぱいになる瞬間だった。
「伯爵、一つだけ約束します」
マリは向かい合ってひざまずいて彼の目を見る。
「私がこれからどんな道を行っても、それはクローヤン王国民のためになるということ。私を信じてください」
彼女は王家の再建を望んでいない。
ラエルとのためだけではなかった。
率直に言って彼女は一抹の愛着もない王家の再建のために自分の人生を捧げたくなかった。
ある人はそんな彼女を見て悪口を言うかもしれない。
王族としての使命に背を向けると。
(しかし、だからといってクローヤン王の国民に背を向けるというわけではない)
彼女は王家の再建だけが全てだとは思っていなかった。
自分がどんな道を行くにしても、クローヤン王国の上にして努力するつもりだ。
それがかつてモリナ王女だった彼女の本心だった。
「最善を尽くすので、私を信じてください」
バルハンは首を横に振る。
「私はすでに殿下に忠誠を捧げることを誓いました。ですから、臣下に信じてほしいという言葉はふさわしくありません。私はただ私のすべてを捧げて殿下に従うだけです」
彼の剛直な性格があらわれる言葉だった。
マリは彼が自分を真の主君として受け入れたことを、今後はどんなことがあっても自分を見捨てないことに気づく。
もちろん彼女もその忠誠にふさわしい姿を見せなければならないだろう。
それが君主と臣下の正しい義務だから。
「もう起きてください。床が冷たいです」
「ありがとうございます」
マリはいっそうリラックスした顔で話し、バルハンもかすかに笑いながら席から立ち上がった。
彼と会ってから初めて見る微笑だ。
そうして二人の間に以前と違う雰囲気が流れていると、思いがけない音がドアの外から聞こえた。
「閣下!閣下!大変なことになりました!」
ポンティル男爵の声だ。
「お入りください。どうしたのですか?」
荒々しくドアを開けて入ってきたポンティル男爵の顔色は青ざめていた。
彼がこんなに驚いた姿は初めてなので、マリは急に不安な気持ちになる。
「男爵?急にどうしたんですか?」
「閣下、敵がこちらに進軍しています!数はなんと3万人です!今すぐ避けなければなりません!」
「・・・」
マリとバルハンの瞳が大きくなった。
急に何の敵だというのか?それも3万人にもなる大軍だって?
「いったいどんな敵が?まさか西帝国が侵攻を始めたのでしょうか?」
「西帝国ではありません」
ポンティル男爵の口から出た話は到底信じられない話だった。
「東帝国の3軍団です!3軍団がこちらに進軍しています!」
マリの手が震える。
信じられない話だ。
東帝国の軍隊がなぜ?
ポンティル男爵は悲鳴を上げるように叫んだ。
「第3軍団の目標は閣下です!閣下がモリナ王女というとんでもないうわごとを言って、帝国を愚弄した罪人の首を切ると進軍しています!」
マリの手に押されてインク瓶が床に落ちて粉々になった。
(これは急にどういうこと?)
マリの顔が青くなった。
想像もできなかったことが起きたのだ。
しかし、彼女はまだ気づいていなかった。
これはこれから訪れる渦の序幕に過ぎないということを。
ついにバルハン伯爵がマリを主人として認めました。
嬉しい話の後に悲しい知らせ。
マリをモリナ王女と疑っている人たちが増えてきましたね。
明らかに誰かが扇動しているのは確実でしょう。