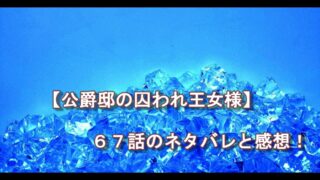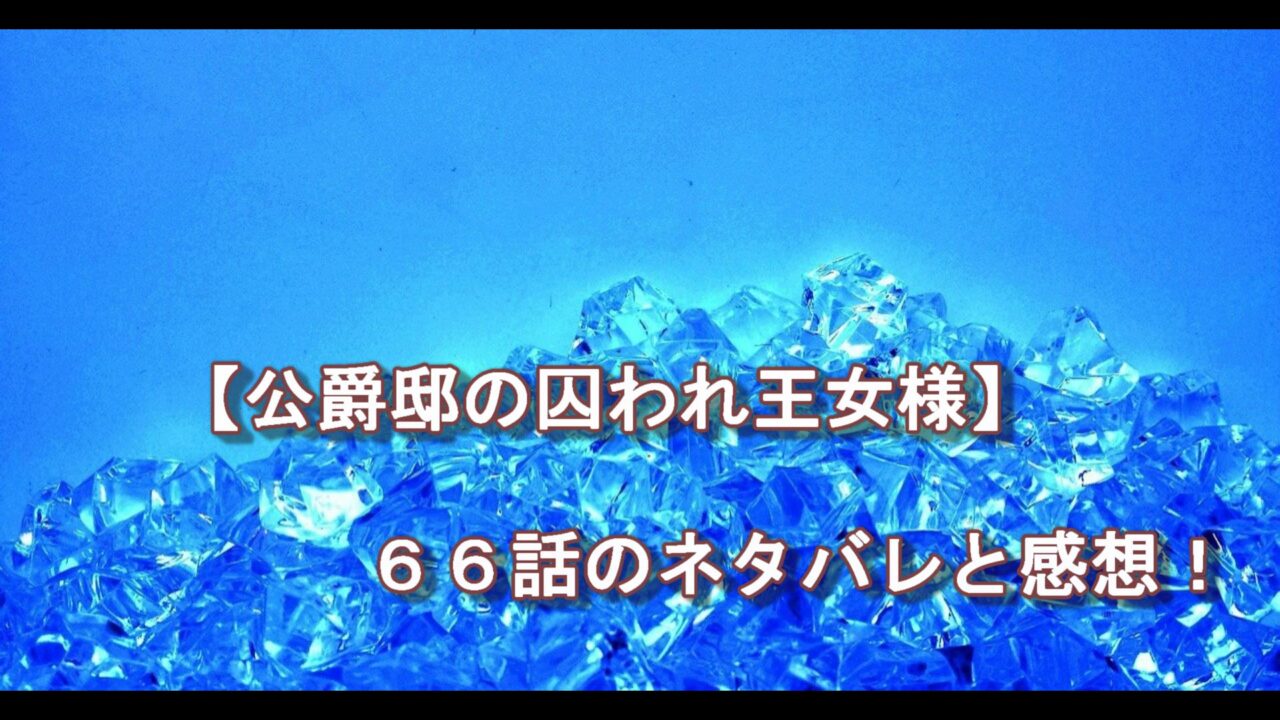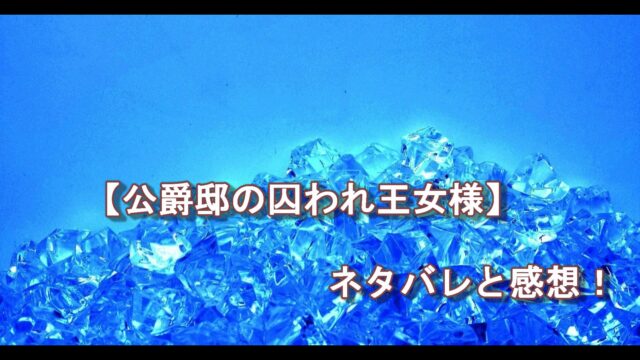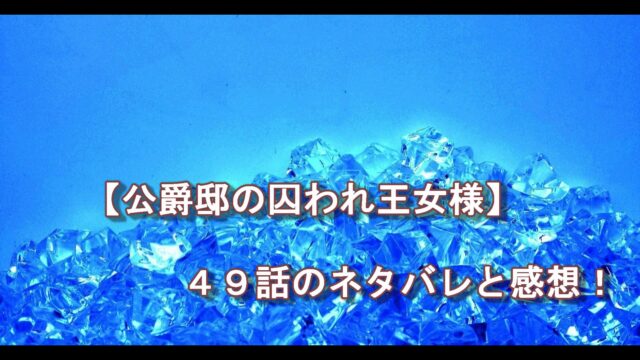こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
今回は66話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

66話 ネタバレ
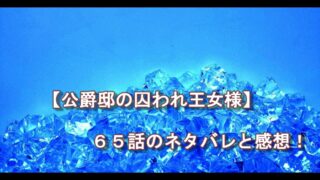
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 少しだけ変わった日常
雨が完全に止み、長い間湿っていた床がすっかり乾き、シェリデン邸宅はすっかり日常を取り戻していた。
クラリスも風邪の余波から抜け出したのはもちろん、壁に擦りつけたときにできた傷も完全に癒えていた。
毎日ロザリーが丁寧に消毒し、薬を塗ってくれたおかげか、痕ひとつ残らなかった。
さらに今では新しい先生を迎え、勉強を始めるようになっている。
新しい先生は若い女性で、とても親切だった。
彼女は同時に厳格に教えることもできる方だ。
クラリスはすぐに先生と授業の時間を好むようになる。
ただし、授業中に壁がクラリスを助けようとして、ひたすら答えを教えようとするのが少し心配だった。(間違った答えを言うことが多かったが)
とはいえ、それ以外に問題はない。
月末になり、シェリデンに来たノアはクラリスをじっと不安げな目で見つめていたが、結局確信は持てなかった。
「ねぇ・・・ノア、私のガンナム豆見たい?」
クラリスはノアが来るたびに、自分の宝物であるガンナム豆をそっと差し出した。
「きょ、今日は触らせても大丈夫だよ!少しだけなら・・・」
以前、彼に豆の株を見せたとき、ガンナム豆の芽が小さすぎて手に取ることができなかった。
しかし、夏になるとガンナム豆は驚くべき速度で成長した。
「・・・」
ノアはその愛らしいガンナム豆から目をそらさなかったものの、特に何も言わない。
クラリスはソワソワしながら何度も豆を差し出したが、最終的にはため息をついて、それを机の上に戻した。
「えへへ・・・」
「少女!」
ノアが突然大声で叫んだ。
どうやら今日はノアの機嫌がなぜか良くないように見える。
クラリスは両手をもじもじさせながらノアの表情をじっと見つめた。
自分に何か悪いことがあったのか気になって仕方なかったのだ。
「この家には少女の名前を書き残してあるのですか?」
「ダメよ。壁に何かを書くなんて、本当に幼い子供がすることだ」
「そういう話じゃない」
ノアはクラリスの部屋の一角を指差す。
その指先には何かを感知しているような雰囲気が漂っていた。
「この邸宅は・・・ただの建物じゃないな。」
「え?」
「最近、お腹が空くようになったんじゃない?」
「うん、成長期だからだって聞きましたけど。」
「馬鹿げてる。なぜ少女が邸宅に魔力を供給しているのか?」
「・・・え、どうしてそれを知ってるの!?」
クラリスはノアに邸宅と因縁を結んだことを絶対に話すつもりはなかった。
ゴーレムマスターであることを秘密にするという約束を守るつもりだったからだ。
「魔力を感知できるレベルの高い魔法使いなら気づくよ。」
ノアはそう言いながら、拳で壁を軽く叩いた。
壁が微かに振動し、骨を叩くような音が響き渡ったため、クラリスは慌ててノアの手を掴んだ。
「叩かないで。痛いのよ。」
「痛い?少女を酷使しておいて、少し叩いただけで痛いというのか?」
「私が魔力を提供すると最初に提案したの。」
「今、少女は能力以上の魔力をこの邸宅に供給している。その干からびた手がその証拠だ。」
「ただ、1日に3回くらいしかしてないのに・・・」
「1日に3回だと?週に1回で十分だろ!」
【不十分だ!週に1回だなんて!】
「この邸宅を変身させて歩かせるつもりじゃない限り!」
【ぎゃあ、歩きたいよ!】
クラリスは壁の方向を驚きながら見つめる。
邸宅に脚が生えると公爵夫妻が困惑することになりそうだ。
ノアは再び拳を握りしめ、内壁をゴンと叩いた。
「とにかく!無計画に魔力を吸い取るなんて、少女の命に危険が及ぶんだぞ。」
彼が放った言葉は、実際、壁への忠告でもあった。
「何より、ゴーレムマスターがいるという事実が知られることは良いことではない。万が一、少女が魔法師団に目をつけられることになったら大変だ。魔力は邸宅の主要機能が維持できる程度にとどめ、最小限に留めるべきだ。分かった?」
「・・・うん、分かった。」
【・・・気を付けます。】
【了解した】
クラリスの返事を受けて、内壁と外壁がそろって返事をした。
彼らのやりとりを耳にするはずもないが、ノアは満足げに顎をさすりながら頷いた。
「良し。」
そして彼はクラリスの手を握ったまま厨房へと向かう。
普段、彼は邸宅の人々とほとんど口を利くことはなかったが、その時はぶっきらぼうに料理人に食事を頼んだ。
「よく火を通した肉がいい。」
彼らは厨房の一角にあるテーブルに腰を下ろし、軽食として出てくる肉料理を待つ。
「たくさん食べなさい、少女。」
「最近はそうしているのよ。知ってる?食事は脳や成長にも影響を与えるんだって。だから、しっかり食べると賢くなれるのよ。」
フライパンでバターを溶かしていた料理人は、クラリスの話を聞いていたようで、「そうだとも!その通りだ!」と同意した。
「もちろんですよ。新しく来た先生がそんな話をしたんですか?」
ノアは興味深そうに尋ねた。
公爵夫妻もクラリスの健康には一定の関心を持っていたが、その分野には特に精通しているわけではなかった。
小説『身体の健康』に特化した一面。
親切なロザリー夫人はクラリスの「心の健康」に気を配る方だった。
そこでこの邸宅で唯一「賢さ」に気を配り、話題にする人物は新しく来た家庭教師なのではないかと推測した。
「ううん、違うよ。」
微笑むクラリスは、何故か両頬を少し赤らめた。
「友人がそう言ってくれたの。」
「シェリデンの翡翠(勲章)は賢いな。」
「シェリデンの翡翠じゃないよ!あるでしょう、私が王都に行った時に・・・」
「ああ、王都の翡翠か。」
「ねえ、ノア、私の友達が翡翠だけだと思っているの?」
「もちろんバウイもいるだろうね。」
「あのバウイも魅力的だけど、それだけじゃないのよ!」
まさにその時、「ジューッ」と肉がフライパンの上で焼ける音がした。
香ばしい匂いが漂い、クラリスはぐっと堪えてようやく「友達」の正体を明かす。
「バレンタイン王子が私の友達になってくれたのよ。見る?」
クラリスは懐から紙を一枚取り出した。
それは彼女が毎日大事そうに持ち歩いている様子を表していた。
【君が私たちの関係を友達だと言いたいなら、特に否定するつもりはない。】
ノアは無言で、洗練された文字が書かれた紙に目を通し、それをまじまじと眺めた。
「・・・これは一体何だ?」
「私が風邪を引いたって聞いて、王子様が励ましの手紙を送ってくれたの。」
「この手紙のどこが励ましという意味を込めているのか、全然分からないけど。」
ノアはそれ以外の文章も読んでみた。
【賢くなりたければ、食事に気を遣うことだ。】
【優れた栄養は脳の発達を助ける。だからその鈍い頭にも少しは聡明さが宿り、雨の日に傘を差す程度の常識くらいは身につくことだろう。】
やはりどこを読んでも慰めの言葉は見当たらなかった。
「良い方なのか?」
クラリスは微笑みながら、疑問が浮かんだノアの口元をじっと見てこう言った。
「王子様は私を友達だとおっしゃって、健康と食事についても心配してくださったのよ。」
「いやいや、あり得ない。友達が心配するのに、どうしてそんな書き方をするんだ?」
「じゃあ、どうやればいいの?」
その時、料理人が温かい前菜の上に完璧に火の通った肉とサラダを盛り付けて持ってきた。
二人の前にそれぞれ一皿ずつ置かれたが、ノアはクラリスの前に置かれた皿をさっと自分の目の前に持ってきた。
「・・・私のお肉。」
クラリスが困った表情で自分の皿を見つめると、ノアはフォークとナイフを手に取り、大きな肉を食べやすいように素早く切り分けた。
「分かった?友達のために肉を切り分けてあげるのは、心配している証拠だよ。あんな皮肉な手紙とは全然違うんだ。」
ノアは素早く肉を切り終えると、クラリスの皿にその肉を戻してあげた。
「ありがとう。でも、ノア。」
今度はクラリスがノアの皿を自分の前に引き寄せた。
「ほら、もう痛くないから、一人でもこうしてちゃんとできるよ。」
クラリスはノアに負けないくらい手際よく肉を切り分けた。
「見て、全然平気でしょ?」
彼女はノアに皿を戻し、少し得意げに微笑んだ。
「よくやったね、まあまあだ。」
ノアはクラリスの隣に置かれていた手紙に目をやりながら言った。
「少女があの手紙を大事に持ち歩いている理由はただ一つ。彼女にはノア王子という生涯の友がいるからですよ。」
その証として、ノアは美味しそうに見える肉の一切れを選び、クラリスに譲った。
美味しい肉を分ける行為は、生涯の友情を象徴する高貴な行いであった。
「・・・王子様も、生涯の友になってくれるのでは?」
「その王子は、病気の友人のために肉を切り分けてくれる?」
「それは・・・そうではないと思う、なぜだろう。」
「利己的な人物なのだろう。友人でもない相手を友として扱うのが恥ずかしい人だ。」
クラリスはノアに興味深そうな表情を向けた。
彼女がノアをそんなふうに注目しているのは初めてだった。
普段は他人の行動にほとんど関心を持たないクラリスだったが、バレンタイン王子の話題だけは特別なようだ。
クラリスに新しい先生がついてくれて良かったです。
ノアがバレンタイン王子に嫉妬してる?