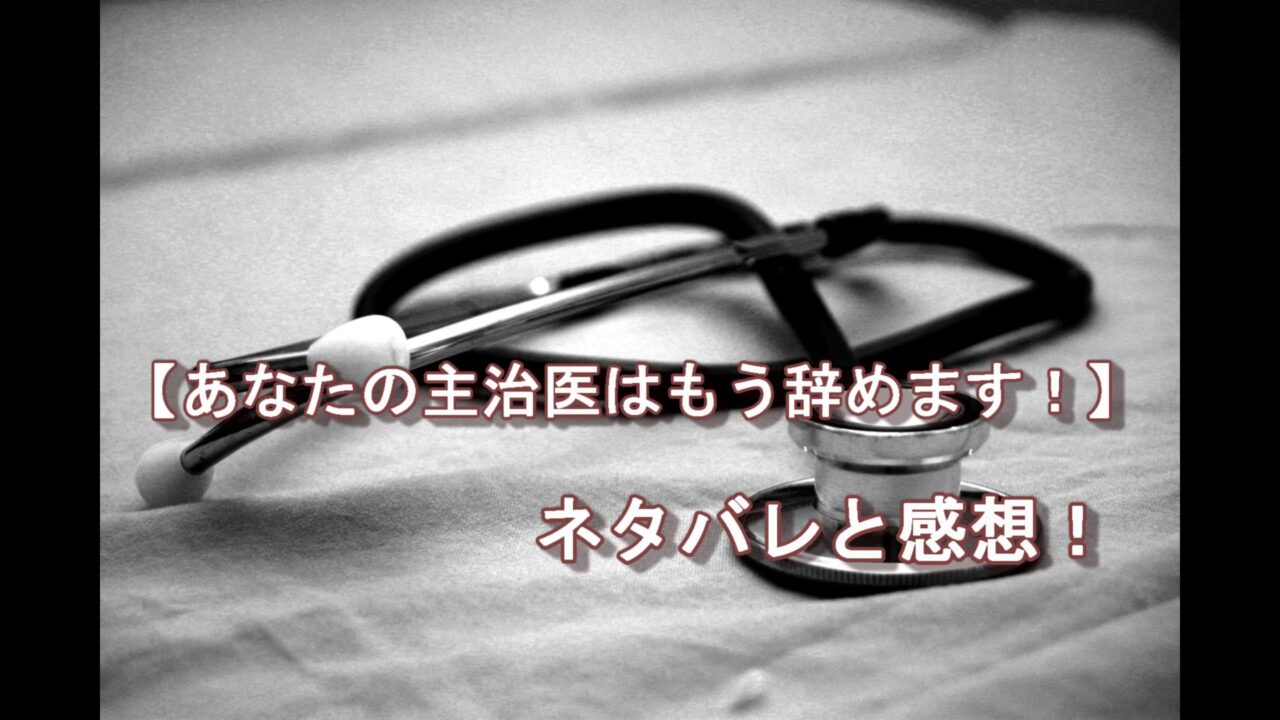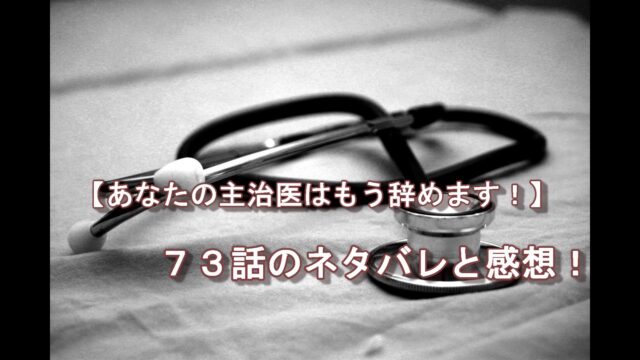こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
今回は114話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

114話 ネタバレ
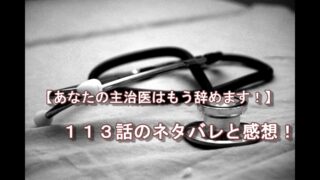
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 尋問
「イシドール男爵が消えただと?」
ハエルドンは報告を聞いた後、聖歌を捧げながら呻いた。
彼は髪を掻き上げながら顔を上げる。
監視塔の暗殺計画さえ失敗した今、最後の手段しか残されていなかった。
反乱軍を武力で制圧し終わらせる以外に方法がないのだ。
ジェイドは戦闘の才能に自信があり、どんな手を使ってでも暗殺を終わらせたかったが、尾行が長引くと明らかに露見する恐れがあることを理解していた。
反乱軍の首都はすでに相当な混乱に陥っており、ジェイドは海上戦闘の経験が豊富なため、まだ勝算はあると考えていた。
もともと彼は今年の秋に降伏するつもりはなかった。
「男爵領全体が荒廃して、使用人たちも全員逃げ出した・・・。」
彼は怒りを抑えきれず、唇を噛みしめて震える。
だが必要なら、ロマンの唯一の息子であるアデルをも失うことを覚悟しなければならなかった。
そしてその土地の暗闇のせいで、すでに銀行に取り上げられてしまった領地のことを思い出した。
ロマンを脅迫できる材料がないという話だ。
「追跡中ですが、まもなく所在を明らかにできそうです。ただ、まさか裏切りなのでしょうか?」
「そんなことはあり得ないと思うが・・・。セルイヤーズ側がどんな変数を持っているかはわからない。まあ、確たる証拠があるわけでもないし、彼らがすぐに私の名前を出すこともないだろうから、時間的な余裕はあるはずだ。」
ハエルドンは唇を噛みしめながら冷静に話し続けた。
「それでも死んでしまう方が安全だ。一歩遅れても影響がないようにすればいい。」
「え?」
「もう行動に移そう。そういうことだ。」
予定していた日程より少し早いが、計画を進めるべき時が来たのだ。
しかし、もともと散発的に行動する予定だったので、特に問題はない。
「ジェイドを出動させるべきだ。最初に攻撃する場所は・・・」
ハエルドンは地図を広げ、迷うことなく軍が初めて動きを見せるべき領域を指差す。
「そして、皇室近衛隊に連絡を取れ。交渉すべき相手が一人いるから。」
皇宮で秘密裏に派遣された調査団は、予定されていた夜よりもかなり早い朝に到着した。
フェレルマン子爵がいない状況下でイシドール領へ到着した。
男爵の尋問が始まった。
地下牢から連れ出されたイシドール男爵の顔は、驚くほどやつれていた。
以前は頻繁に会っていた顔であり、最後に会った時は直接対話も長く続けたにもかかわらず、まるで初めて会ったかのような根深い怒りが込み上げてきた。
この男は、腹の中で自分を消し去ろうとし、シオニー様を追跡してフェレルマン子爵に嘘をついた人物・・・。
以前は単純にエルアンとイサベル様の敵だと考えていた男だったが、今は顔を見るだけでも重要性を感じざるを得なかった。
イシドール男爵は、皇宮で秘密裏に派遣された調査団に全てを暴露した。
少しでも間違ったことを言えば、その場で責められると分かっていたため、彼は真実だけを話した。
彼の言葉によると、エルアンの言動にはウェデリックが絡んでいるため、対処が難しいということだ。
彼は首を垂れ、言った。
「それで・・・伯爵夫人が逃げたことを知ったとき、陛下が密かに数人の騎士を派遣し、追跡させたのです。本当にただお嬢様のためだけにやったことだと言いました。」
彼は混乱しながら頭をかきむしり、続けた。
「伯爵夫人を殺そうなどとは本当に思っていませんでした。私たちの領地を訪れた方が亡くなるなんて、それは私にとっても大きな負担ですから・・・。フェレルマン伯爵が直接否定はしませんでしたが、それは魔力に関連する妨害だと聞きました。私は伯爵夫人を殺していないと言えるだけの自信がありました。ただ・・・確認したら、亡くなっていたのです。」
シオニー様と親交の深かったイサベル様を疑う発言だった。
しかし、その言葉を聞くたびに私の心はさらに痛みを増す。
もしフェレルマン伯爵が戻ってきたら、この罪悪感にどう向き合えばいいのだろうかと思った。
正直に全てを打ち明けようとしたが、シオニー様に関する話題が出ると、ただ委縮するばかりだった。
「これが証拠になるかどうかわかりませんが・・・」
イシドール男爵は自分に下された指令に従って、その手紙を直接差し出した。
<手紙の内容>
観覧塔の失敗による予算不足。
メイリース公国の問題を適切に処理できなかった点を厳しく問う予定。
「この手紙が改ざんされたものではないなら、観覧塔も反乱軍の仕業だったということですね。」
ケインズ卿は腰に手を当てて、深くため息をついた。
「ハエルドン皇太子は、医療研究に興味を持つのは良いことだと言い、王位には欲がないとおっしゃいましたが・・・本当に人の心の中は分かりませんね、とりわけ王宮では。」
「明らかに心が読めるような人は、一人もいないのではありませんか?」
エルアンが皮肉めいて答える。
「これほどになると、帝国の未来について考えるべき時ではないでしょうか?」
「え・・・」
ケインズ卿は困惑したように言葉を詰まらせた。
「しかし、皇太子殿下は若くして既に実力を発揮されており・・・」
「ですから・・・どんなことが起こっても生き残るでしょうし、反乱が起きてもすべて鎮圧できるはずです。さらに運も良いのですから。」
それに、ジェイド皇太子はどのような攻撃を受けても、晴れやかな顔で堂々と戻ってくる人物だ。
「すべて完了しました。」
王宮から派遣された調査官たちは無表情のまま報告を終えた。
「ハエルドン皇太子とイスエラ皇太子妃を含む関係者全員を即刻拘束し、調査するようにしてください。反乱は重大な問題です。」
この後の処理は、ジェイド皇太子が責任を持って行うことになるだろう。
私は例外なく、かつて「処刑令」を下したジェイド皇太子のことを覚えている。
彼は表面的には温厚な人物のように見えたが、決して情け深い性格ではなかった。
この一連の出来事を最初に計画したのはハエルドン皇太子であり、私が処刑宣告を受けた際、あの時のようにジェイドの手で罰を受けることになるだろう。
いずれにせよ、今回の自白を引き出すにあたって私が重要な役割を果たしたのも事実だった。
ウェデリックを捕らえ、イシドール男爵を何にも頼れない状況に追い込んだ。
それでもなお、満足感や爽快感を感じることはできなかった。
ただエルアンの言葉通り、死というのはあまりにも簡単な結末ではないだろうか。
私は何も知らず、混乱の渦中で彼の子どもを守るために最善を尽くした。
「とにかく秘密にしたかったけれど、ジェイド皇太子に耳に入った以上、この秘密が守られることはないだろう。」
(そうなるとは思えないけど・・・)
私が考えに没頭していた時、エルアンが静かに皇宮の調査官に質問した。
「皇帝陛下がこれまで一度も皇宮の魔法アイテムを外部に返還しなかったというのは事実ですか?」
私は少し驚いてエルアンを見つめた。
調査官の中で最も年配の、温厚な人物が軽く頭を下げて答えた。
「はい、皇帝陛下は即位されてから一度たりとも魔法アイテムを外部に持ち出すことをお許しになったことはありません。皇太子の頃から魔法というものが人々を堕落させるものだとして嫌悪されていましたから。」
皇宮の調査官たちは反逆だけに集中しており、シオニー様のような私人に関することには全く関心を持たなかった。
それで、フェレルマン侯爵と私に関する詳細な話は全く耳にしなかったため、エルアンの質問を軽んじている様子だった。
「見てください。」
私は無意識のうちに溜息をついた。
確認したところで、その有名な事実が変わることはないだろうと思った。
「それは・・・うーん、非常に重要な案件なのでしょうか?」
その時、調査官は戸惑いながら慎重に質問を返した。
エルアンは体を傾けながら熱心に彼を見つめ、答えた。
「はい。」
彼は穏やかな目つきを見せながら言葉を続けた。
「反逆の根をさらに追求するには不可欠です。」
反逆とは特に関係がなかったものの、おそらく反逆と直接的に関連があることを述べるべきだと判断したようだ。
調査官の表情を見る限り、明らかに何かがあるが、皇室の内部事情などと関連して話すべきかどうか迷っている様子だった。
「本当に、本当に重要な案件だと思います。うーん、詳しいことは分かりませんが・・・。」
エルアンは目を伏せて微笑みを見せたが、その間、彼と長い付き合いがあるため、唇の震えを僅かに察することができた。
「私は皇太子殿下がいつも忠臣であると口にしており、それに基づいて行動する人物であると信じていますので、安心してお任せいただければと思います。」
彼の演技と嘘は見事であったが、その背後には明らかに何か含みがある。
自分の発言に自信を持っているように見えた。
しかし、その予想は外れてしまい、調査官は深く息をついて冷静に言葉を続けた。
「皇太子殿下が4歳か5歳の時に一度だけ返却されたことがあります。相手は宮廷で働く者でした。」
「ええ?」
心臓が大きく跳ね下りた。
「魔力の石」を返却することができるもう一人の人物、ジェイド皇太子は、私が生まれた時にまだ5歳だったため、それについては考慮の対象にもならなかった。
「何かのおもちゃと交換したと聞きました・・・。だからこそ、今の皇帝陛下から非常に叱られて以来、二度と魔法のアイテムに興味を示していないようです。」
調査官は震えるような表情を隠すことができず、言葉を続けた。
「その彼女はただ珍しい魔法のアイテムを持っていれば愛が叶うという伝説を試してみたかったと言っていました。まぁ、まったく馬鹿げた話ですが、そういう噂が広まるのは事実です。」
もちろん、5歳の子供が遊び心で夢中になることもあり得るだろう。
しかし、皇太子は幼い頃から徹底的に教育を受け、周囲には常に多くの人々がいたはず!
「皇太子殿下は幼い頃から運動神経が優れていて、臣下たちを簡単に惹きつけることができました。それで彼らに内緒で返却を許可されたのではないでしょうか。」
テーブルの下で震え始めた自分の手を感じた。
エルアンは私の手をしっかり握りしめて助けてくれた。
「反乱も特に大事にはならず、特別な事件が起こったわけでもありませんでしたが、皇室の権威が非常に落ち込む事件だったため、外部には知られていません。この事実を知っているのは、私と皇帝陛下直属の臣下だけです。その彼女はそれから間もなく持病で亡くなりました。」
「もしかして・・・。」
エルアンは私の手をさらに強く握りしめながら話した。
「魔力の石のことでしょうか?」
調査官はぎこちなく喉を鳴らす。
「はい、それをどうやって知ったのですか?」
「つまり、シオニー様は私を生んで亡くなったのではなく、魔力の石によって『出産による不幸な死』として偽装された可能性が高いのです。」
おそらく、ハエルドン皇子がイシドール男爵に直接密かに渡した騎士の一人がその石を所持しており、孤独に残されていたシオニー様にその魔力の石を用いて命を奪ったのでしょう。
そうであれば、殺人事件ではなく、出産による事故として判定されて、完全に犯罪として成立してしまう。
すべての内容を聞いていたケインズ卿は口をぽかんと開けていた。
調査官たちが退出し、私は呆然としたままケインズ卿に尋ねる。
「ケインズ卿、私が初めて手紙をお送りしたとき・・・明らかに落ち着いて本を読まれていましたよね。それで、このように5歳の頃から今に至るまで、一度も考えを巡らせなかったとは思いませんでした。」
ケインズ卿は深く息をついて答える。
「それでも戦争が終わった記念として数ページ見ていらっしゃいました。もともと本はあまりお好きではないご様子で・・・。あ、何の本かは聞かないでください・・・私が困惑してしまいますから。」
「いいえ、帝国の未来が本を嫌うようなものであってはどうします?」
「幼い頃から本を読むと頭が痛くなるとおっしゃっていましたが、結局こうなってしまいました。」
その時、私の肩をそっと叩いていたケインズ卿は深くため息をついた。
「私が代わりに謝罪させていただきます・・・。このすべてを隠さず、正直にお伝えするのが私の役割です。それが私の務めです。」