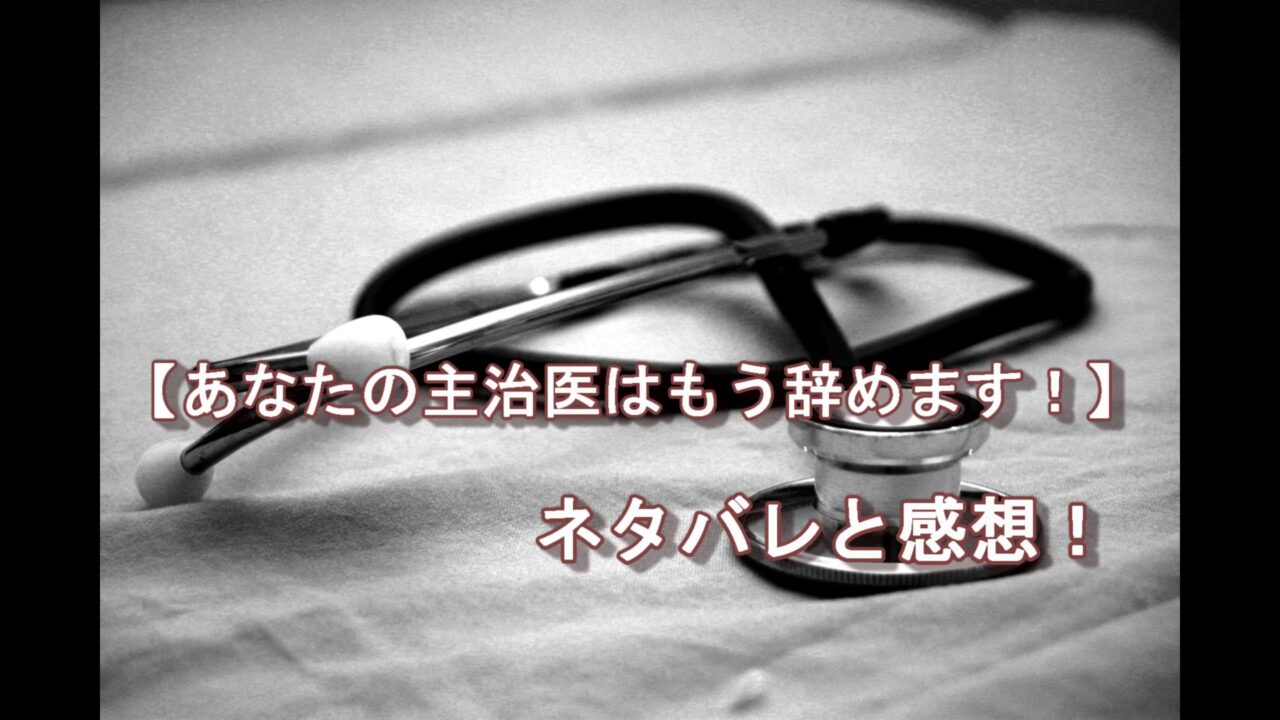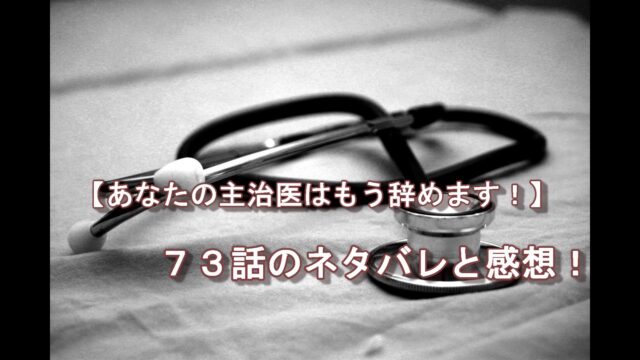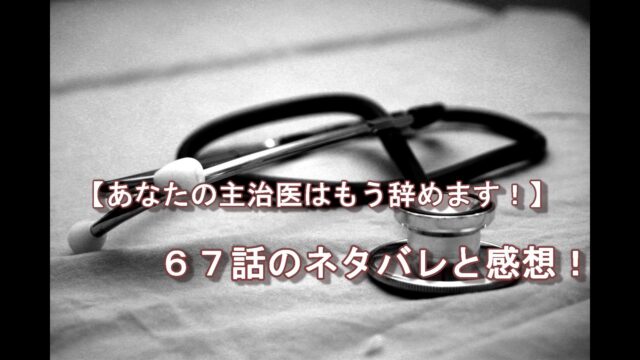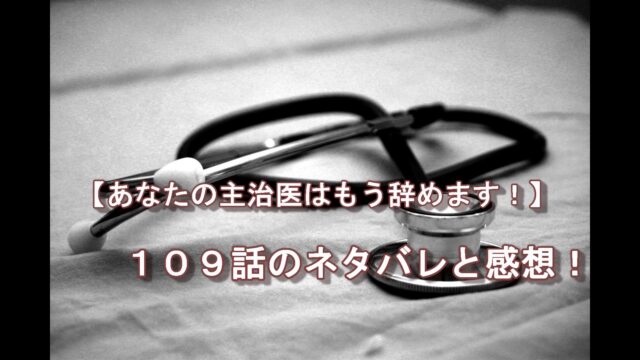こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

117話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 家族として②
おじいさまの話によれば、お母さまの墓はペレルムの屋敷裏手にある小さな丘の上にあるとのことだった。
「私は足が痛くて行けそうにない。」
もちろん、エナベの観察眼を持つ方と一緒に行くのは気が進まなかった。
しかし、叔母さんは別の理由で同行を拒んだ。
「兄がくよくよ悩んでいるのを見るのは嫌なの。だから、たぶんしばらくの間は優しくしてあげたいだけ。」
叔母さんは、自分の目をそっと拭いながらそう言った。
「一人で行ける?」
不意に相手の邪魔をしたくないという気持ちが伝わってきて、私は心の中で小さく笑った。
「そうですね。」
私は首を振って、一人で歩き始めた。
秋が目の前に来たのか、空は青く高く広がっていた。
どこからか鳥のさえずりが聞こえるだけで、周りは静かだ。
一本の小道を歩いていると、低い声が聞こえた。
「シオニー。」
さまざまな美しい花に囲まれた彼女の墓碑には「シオニー・ナニア・フェレルマン、ここで」と書かれていた。
「永遠の安らぎを得る。」 と刻まれていた。
そして見覚えのある茶色い髪の中年男性が静かに立ち、優しげでありながら悲しげな声でつぶやいていた。
「君が僕のところへ来たのは本当に奇跡のようなことだったのに・・・結局守れなかった。」
その声があまりに悲しくて、思わず足が止まってしまった。
「あの時、研究だの論文だの関係なく、一緒にラベリー島に向かえばよかったんだ。」
途切れることのない後悔が感じられる。
私がまだ足を動かせずにいる間、彼は息をつき、震える手で墓石を撫でていた。
「だから今回も、本当に怖いんだ。」
返事のない母が許してくれそうなほど、眩しい美しい日だった。
「私たちの娘は奇跡のように私のところに来たのに、今回も私の未熟さで失ってしまうんじゃないかって。」
再び涙が目に浮かび始めた。
「リチェの才能は6年前でも一目でわかったんだ。だからイザベルとエルアンはリチェをとても頼りにして、安心して遠くまであちこち駆け回っていたんだよ。何か疑いがあれば別だっただろうけど、どうして一度でも疑いを持たなかったんだろう。」
それは私も同じだった。
ディエルが二人は似ていると言ったが、あまりにも近すぎる人だからこそ、疑うことすらしなかった。
だからこそ理解できたのだ。
「私はリチェが公正さを守りながら親族の検査におうとしていた間、利益ばかりを見て、一度も助けようとしなかったんだ。心に引っかかるものが一つや二つじゃない・・・。」
次第にかすれていく声を聞きながら、私の頬に涙がぽろぽろと流れ始めた。
「あの子が修正版の供述書を見た後から『お嬢様』と呼びながら目を合わせなくなったとき、心がひどく痛んだんだ。」
涙を拭おうともせず、私は乾いた唾を飲み込んだ。
「妻と娘を守れなかった自分を責めているようで。」
長い間、堪えきれなかった自責の言葉を吐き出した後、彼はしばし静寂を保った。
「ずっと会いたかった。でも今この瞬間、言いようもなく・・・お前を抱きしめたくてたまらないんだ。」
彼は色のない手で墓石を撫でながら話し続ける。
「うちの娘は一人でも本当に賢くてしっかり育ったよ。優れた医者である点は俺に似たけど、他のすべてはお前に似て、野暮ったくなんかなかった。お前が空から見ているなら、きっと誇りに思うだろう・・・。」
私は一度深呼吸をして、再び足を動かし始めた。
「愚かな俺は、ただ謝ることすらできずに立ち尽くしているんだが、どうすれば許しを得られるのか、お前は知っているのか?」
彼がいつまでも悲しげな言葉を繰り返しそうだったので、私はわざと気にしないふりをしてゆっくり歩き始めた。
乾いた葉を踏む音に、彼は一瞬動きを止めた。
6年前に初めて会った時、決して良い第一印象ではなかったが、いつの間にか家族を離れ、本当に親しみを感じるようになった人。
「お父さん・・・。」
本当は「お父様」と呼ぼうとしたが、祖父と叔母の言葉に従い「お父さん」と呼んだ。
母の墓の前に立っている姿を見て、私も気づかないうちに涙がぽろぽろとこぼれ、慰めのない、子供が泣き叫ぶような声が出てしまった。
「リチェ・・・ごめんよ・・・。」
お父さんは私の目の前でついに崩れ落ちるように泣き始めた。
さっき祖父や叔母と一緒に少し泣いたにもかかわらず、また涙があふれ出てきた。
「本当にごめん・・・。」
私は大切に抱えていたフリージアの花束を母の墓の前に置く。
きれいに手入れされた墓の前で、私は母をきちんと見ることもできず、彼女に聞こえるように見送ったときの最後の表情を思い出した。
「お母さんが私のせいで亡くなった気がして・・・みんなの大切な人を私が奪ってしまった気がしたんです。」
お父さんも祖父や叔母のように誤解しているのが悲しくて、私は涙を拭いながら言った。
お父さんの独白を思い出すたび、その一言一言がとても悲しかった。
「私が生まれなければ、こんなことは起きなかったんじゃないかと思って・・・。」
「何を言っているんだ。」
お父さんは私を抱きしめながらすすり泣いた。
「お前は生まれた時から私たちの祝福であり、私たちの娘だと知らなかった時でさえ、フェレルマン家にとっての幸運だったんだ。」
もし帰郷した後、私が一人で生きると言ってセルイヤーズ領地を離れ、別の場所で人生を始めていたら、永遠にお父さんとは出会えなかっただろう。
『あなたの利他的な選択が失われたものを見つけてくれるでしょう。』
信託はまたもや的中したようだった。
「どんな姿でも構わない、もう一度だけ会えるなら、何でもすると考えていたんだ。あの時はね。それでもこんなに完璧な娘だなんて。」
お父さんの声はだんだんと感極まって震え、私はもう悪い考えはしないと決めた。
「私も・・・どんな親でも構わないと思っていました。イザベル夫人が言うように、お金だけでなく優しい人が親だったらそれでいいと・・・。でも、こんなに素敵な家族に出会えるなんて、本当に嬉しいです。」
母のお墓の前で、お父さんと私はその時間が惜しいほど声をあげて泣いた。
「シオニーがこんなに大きくなったお前の姿を見たら、どれほど喜んだことか・・・。」
お父さんは優しく私の髪を撫でながら、何度か母の話を口にした。
これまで母を話題にすることはほとんどなかったので、知らなかったことがたくさんあったのだ。
とても長い時間が過ぎても、お父さんはお母さんのことを少しも忘れられない様子だった。
胸の奥がさらに痛むたびに、私は抑えきれない復讐心をどうすることもできなかった。
信託を受けて私を排除しようとしたこともそうだが、何の関係もなかった母まで殺されたのは明らかな悪意だ。
それもただの事故死ではなく、出産による死亡だと偽装しようとするとは、あまりにも悪辣だった。
首都から離れた場所で、たいして地位の高くない男爵夫人が亡くなったのは、それほど大きな出来事ではなかっただろう。
だが五歳の皇子を巻き込み、極めて危険な魔法のアイテムを盗んだことは、王室の権威を傷つけるものだった。
無条件で秘密にしたのも当然のことだろう。
それでも、誰も二つの事件を結びつけることはできなかったのだ。
再び見つけた家族が愛おしければ愛おしいほど、過ぎ去った時間が痛ましく、この全ての出来事の真相を探りたくてたまらなくなった。
・
・
・
全員が同じ考えを抱いているとわかったのは、再びフェレルマン子爵家に戻って皆でお茶を飲んでいた時だった。
お父さんや叔母、そしてお祖父様が私の手を優しく撫でながら、じっと顔を見つめてくるので少し気が抜けてしまった。
「やるべきことが多すぎるね。」
叔母は真剣な表情で呟いた。
「何から始めるべきだろう?」
その言葉にお祖父様は使い古された羊皮紙の束をどこからか取り出してきた。
「ここから選べばいい。思いついた時に書き留めておいたものだ。」
お祖父様はポケットからさらに拡大鏡まで取り出した。
熱心に聞きながら、メモを取った。
「家族の肖像画を描く、大陸の五大珍味を味わう、王室の最高級ドレスを着る、最高級のアクセサリーショップに行く、一緒にボードゲームをする、豪華なティーパーティーを開いて各地の貴族を招待する・・・。」
驚いたことに、その中で私がやりたいのは家族の肖像画を描くことだけだった。
一緒にボードゲームをしても、どうせ私が勝ってしまうから、あまり楽しくなさそうだった。
残りは公爵城でもイザベル夫人がやってくれたことであり、豪華なティーパーティーといえば、エルアンの就任式でベティアとシルビアが喧嘩をしていた微妙な雰囲気しか思い浮かばなかった。
「ゆっくり全部やればいい。」
お父さんは満足そうな顔で頷いて微笑んだ。
「今は時間がたっぷりあるんだから。そういう意味では、とりあえず料理人の面接からやり直さなきゃいけないね。全国で有名なデザート専門の料理人を呼ぼう。リチェは甘いものが好きだから。」
おそらくそうするには、セルイヤーズ公爵城にいる料理人を引き抜くことになるだろうが、私はとりあえず黙っておいた。