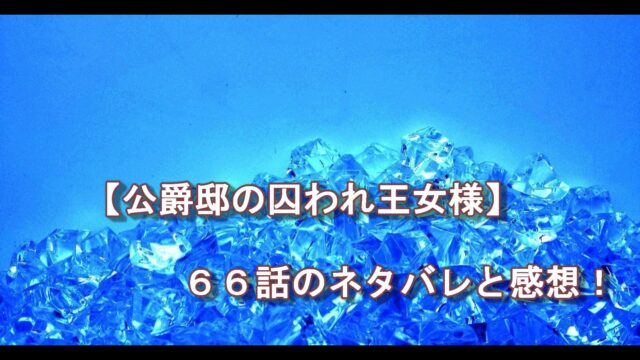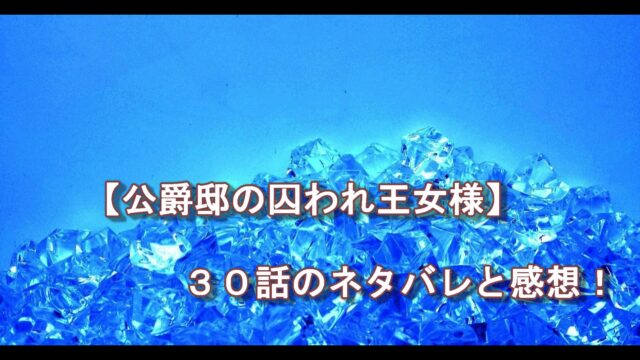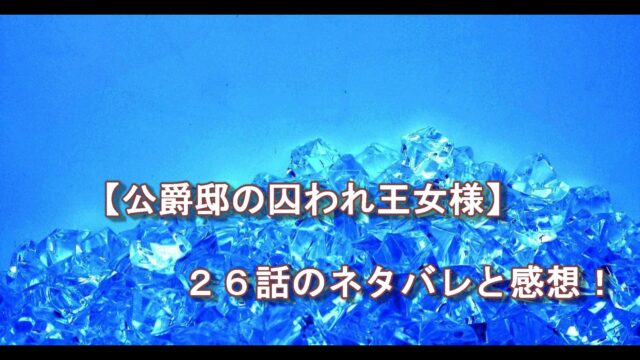こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

117話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 別れ
気を失っていたデビナが目を覚ましたのは、事件が起きてほぼ二日が過ぎた後だった。
彼女はこの二日間ずっと眠っていたわけではなかった。
たまに目を開けることもあったが、そのたびにデビナは必死で目を閉じて、無意識の世界に逃げ込もうとしていた。
けれどもそれも、もう限界だったのだろうか。
仕方なく開いた目で、デビナはぼんやりと天井を見上げた。
空っぽになった頭の中には、何の考えも浮かばなかった。思い出さないようにしていた。いや、思い出すことすら拒もうとしていた。
部屋がまだ薄暗いことからして、まだ夜明け前だろうか。
「ああ、もう少し眠っていられたらよかったのに。」
『……マックス。』
だが、不意に浮かんできた男性の名前が彼女を現実へと引き戻した。
頬を伝う涙は、おそらく恥ずかしさから来るものだった。
「どうしてあんな誤解をしてしまったのだろう?」
彼の心のどこかに、デビナの居場所が今もほんの少しでも残っていてくれたら、と願っていた。
それは妄想に過ぎなかったけれど。
デビナはゆっくりと体を起こした。
ベッドの上のカーテンから漏れる長い日差しが、もう朝を迎えていることを告げていた。
夜明けではなかったようだ。
ドアが開く音が聞こえてきた。
「メイドかしら」と思い振り返ると、そこには彼女の父、ベクスリー伯爵が立っていた。
「……」
彼はしばらくデビナを見守っていたが、やがて近づいてきて言った。
「……大王妃殿下が恩恵をお授けくださった。」
久しぶりに目を覚ました娘に対しても、彼は「大丈夫か?」の一言すらかけなかった。
それが何となく寂しくはあったが、デビナはとにかく「恩恵」とは何か気になって、黙って伯爵を見上げた。
「お前の婚約は書類上無効として処理される。」
「それって……。」
「お前が前から望んでいた学業のために、留学する決意をして国外へ行くことになった。」
「お父様、一体どうして!」
「こうすることで、お前の将来の障害はなくなるだろう。王室の正式な立場としてはお前を支援するが、惜しいが手放すということだ。」
「そんな馬鹿な話が……。」
どうしてたった一晩でそんな決定が下されるの?それも、自分が寝ている間に。
彼女は震える体を動かし、ベッドの端から這い出した。
「お願いです、私が説明します。あの方が私に……そんなこと、あり得ません!私がどれほどのことをしてきたと……!」
「それは私が言いたい言葉だ、デビナ!」
そう言うと、父親が彼女の腕を無理やり掴んだ。冷たく無情なその手の感触。
「もう黙っていろ!」
彼はそのまま、娘の顔を平手で打った。
鋭い音とともに、彼女の髪飾りが横に転がった。
「私はお前をこの地位につけるために、どれほどのことをしたと思っている!それを台無しにしやがって!」
「……!」
デビナは目を見開き、父をにらみつけた。
一瞬で怒りが込み上げるのも無理はなかった。
正直に言えば、すべての原因は自分の父ではなかったか?
「それでお父様は、クノー家の娘を差し出したんですか?」
その件については父の手紙には書かれていなかった。
だが、状況的にそうだとしか思えず、デビナはすぐに察することができた。
父は王妃の座を手に入れるためなら、どんな汚い手段もいとわない人だったのだから。
「それはどういう意味だ?」
「とぼけないでください!私が知らないとでも思ったんですか?お父様じゃないですか!」
デビナは声を荒げた。
「だから魔法師団に宝石まで送ったんですよね?一時的に真実を隠して、その女が侯爵位をもらえないように……!」
彼のあまりに汚れた過去の記憶が蘇り、また頬を叩かれるかもしれないと覚悟した。
だが、実際は少し違っていた。
ベクスリー・ベクジャクは、ただ呆然とした顔でデビナを見つめているだけだった。
その沈黙が長引く中、デビナは誰かが背中を強く叩いてくるような錯覚を覚えた。
「お父様が私に……手紙をくださったじゃないですか。」
「もちろんだ。さっさと後継者になれってな。お前みたいに寝てばかりの子には理解もできんだろうが。」
「ちがう、そんなことじゃない!」
デビナは父の腕を掴み、切実なまなざしで訴えた。
「それ以外に、私に手紙を書く理由があるんですか?」
だが返ってくる答えはそれだけだった。
デビナは、父が嘘をついているわけではないと確信した。
ならば、あの手紙はいったい——?
デビナをここまで追い込んだあの手紙は、一体どこから来たものだったのか?
それは間違いなく父の筆跡だった。
署名はどこにもなかったが、デビナが見間違えるはずもない。
『もしそれが父でなければ、一体どこで……!』
そしてふと、思い出した。
「今回もあなたが代わりに書いてくださると助かります。内容は前回と同じで。」
「殿下が直筆なさったものとしてよろしいでしょうか?」
デビナの代わりに何度も手紙を書いていた侍女。
大王妃が直接選んでデビナの側に付けたあの侍女のことだ!
彼女は誰の筆跡でも完璧に真似でき、特にベクスリー伯爵の筆跡は見分けがつかないほどそっくりだった。
デビナが読んでもいない父の手紙を差し出し、適当な返事を書かせたこともあった――。
なぜ他の誰かが手紙を書いた可能性を考えなかったのだろう?
いや、最初からそんな冷静な思考を巡らせる余裕などなかった。
その手紙の内容だけでも、デビナにはあまりに衝撃が大きく、万一の事態を恐れて誰かを疑うことすらできなかったのだ。
きっと相手は、そんなデビナの心情を見透かしたうえで、手紙を書いたのだろう。
父に確認を取らせる隙すら与えずに。
——つまり、これは…
『大王妃殿下の……陰謀?』
ブリエルの子どもを殺したいから?
いや、もしそうならもっと具体的な方法を手紙で指示したかもしれない。
彼女の完璧主義なら、それでもなお不十分と感じただろう。
だからこそ、彼女が本当に望んだのは……
『私が理性を失って暴走すること……それ……だけを狙ったわけじゃなかったのね。』
デビナは自分を責めた。
マクシミリアンが王に懐妊を報告しようとしたとき、彼女は嫉妬に目がくらむのではなく、王室の法度を思い出さねばならなかった。
王室の子どもは懐妊が王に報告された瞬間から王室の一員として認められ、保護されるということ。
結局、デビナは正統な継承権を持つ王室の子を害した罪人となってしまったのだ。
その罪が明らかになれば、窮地に立たされるのはベクスリー伯爵家だった。
そこで大王妃は伯爵に取引を持ちかけたのだ。
ひっそりとデビナを追放する代わりに、家門の名誉は守ってやると。
名誉を命より重んじるベクスリー伯爵がこれを断るはずはないと分かっていたから。
『それ……だけを狙ったわけじゃなかったはずよ。』
デビナは身体を縮めるようにして、自分自身を抱きしめた。
大王妃は、おそらくデビナが作戦に成功したとしても、やはり警戒していたに違いない。
であれば、今頃はなおさら喜んでいたことだろう。
彼女は、自分の息子よりもマクシミリアンが先に子どもを持つという事実に、耐えがたい嫌悪感を抱いていたはずだからだ。
ましてや、デビナの弱みまで握れば、いつでも彼女を王妃の座から引きずり下ろせる材料になる。
どうあがいても逃れられないという結論に至ったとき、デビナはすべてが虚しくなった。
『私は……いったい今まで、何のためにここまで努力してきたの?』
このような悲惨な最期に、手を差し伸べてくれる人は一人もいない。
「必要なものだけ持っていきなさい。すぐに出発する。まったく、情けなくてここにはもういたくもない!」
父は汚いものでも見るような目で彼女を睨みつけ、バタンと音を立ててドアを閉めて出て行った。
デビナは自室をぐるりと見渡した。
父は必要な物があれば持って行けと言ったが、実際に必要なものなど何もなかった。
これからの彼女の人生には、華やかなドレスや美しい宝石など不要になるだろう。
外国のどこかで、静かに身を潜めて生きていくことになるのだから。
彼女は一番地味な外出着を取り出して自ら着込んだ。
少なくとも、彼女はまだ王妃だった。
その名に恥じない品位を保ったまま、この場所を去りたかった。
たとえ誰にも見送られなくても。
小さく深呼吸して、彼女はドアを開けた。
デビナは誰かが自分を待っているとは思っていたが、まさかの人物が立っていたため、少し驚いて言った。
「そんなに驚くこと?」
ライセンダーだった。
いつもはシャツのボタンを数個外してルーズな格好をしていた彼が、今日はまるでパーティーにでも行くかのように、きちんとした礼服まで身につけていた。
「パーティーか何かに行かれるのですか?」
あれほど嫌っていたブリエル夫人を追い出したのだから、これで気が晴れて、また女性たちと遊び歩く気分なのか?
「うん、貴族の娘とも付き合ってみないと。後継ぎ候補の娘よりもマシな女性と付き合ってこそ、うちの母さんも安心するだろ?」
彼がそう言うのを聞いて、デビナはブリエルの正体が少しずつ見えてきたような気がした。
「……」
デビナはもう何も言う気になれず、ただ背を向けた。
すると、ライサンダーが彼女の前に手を差し出した。
「……何です?」
「とりあえず名残惜しそうに送り出す……っていう設定だろ?な?」
言葉も出なかった。いつからそんなに王室のやり方に従順だったのか!
「跡継ぎを作らなきゃ。」という王室結婚の核心義務さえまともに果たさなかったくせに。
「いいから、握れ。」
彼が再び差し出した手を、デビナは無言でぎゅっと握りしめた。
もう言葉は必要なかった。
長い回廊を歩く間、出会った貴族や侍従たちは深く頭を下げた。
その瞳には複雑な感情が入り混じっていた。
デビナが呆然としている間に、ライサンダーが何も言わずそっと支え続けてくれていたのだと、今さら気づいた。
夢を追い求めるために、最も高貴な座から自ら降りていく女性。
悲しいけれど応援するために送り出すことにした男。
小説の設定が現実で展開されることに、思わず感動すら覚えることもあった。
しかし、実際彼女の夢は……。
デビナはその場でライセンダーを振り返った。
「違う。」
すると彼がすかさずこう言った。
「何が違うって?」
もう王妃ではなくなったという自覚が芽生えたのか、デビナは彼に苛立ちまじりに言い返した。
まるで昔、いっしょに走り回って遊んでいたあの子どもの頃のように。
「あなたは私の隣の席を望んでいたんじゃないの?」
「……」
「本当は王妃になりたかったわけじゃなかったのかもしれない。」
「じゃあ一体何なのよ!」
「……そうだな。」
ライサンダーは肩をすくめ、これ以上ないくらいあっさりと笑った。
「ゆっくり考えろよ。これからは時間だけはたっぷりあるんだから。」
「ほんとに!」
デビナは少しむっとして顔をそむけた。
やっぱりこのうっとうしい男とこれ以上一緒にいたくなかった。
王妃の座を降りるのは嫌だけど、こんな変人の夫と別れられるのは心から嬉しかった。
「知ってる?あなた本当に頭おかしいわよ、ライサンダー。」
彼女は誰にも聞こえないほど小さな声で彼を罵った。
正直ちょっとスッとした。
どんな反応が返ってくるかな?
プライドが高い男だから、もっときつい言葉でやり返してくるんじゃないかと思った。
「知ってる。」
「……え?」
「さあな。俺が頭おかしい奴だってことは……。」
……でも彼はただ……とても寂しそうな顔で黙っているだけだった。
その瞬間、結婚生活の間には決して見えなかった彼の心の一部が、少しだけ垣間見えた気がした。
『ライサンダー、あなた……』
でも、それ以上言葉を交わす余裕はなかった。
気づけば2人はすでに謁見の間の前に到着していた。
デビナが何かを言おうとするよりも先に、彼がデビナの手の甲にそっとキスを落とした。
そして唇を離すとき、小さな声でささやいた。
『……ごめんね、姉さん。』
『……』
それはまるで幼い頃のライサンダーが言っていた言葉のようだった。
泣いて喚くデビナのそばを一時も離れなかった……あの小さくて愛らしかったライサンダーの。
「本当に……。」
けれど、それはほんの一瞬だった。
もしかしたらデビナの思い違いだったのかもしれない、と思うくらいに。
もう一度見た彼は、いつもの“王”の顔に戻っていた。
冷たく笑みを浮かべ、人の心を全く寄せつけない、いつも彼女を怯えさせてきた夫の顔だ。
デビナはようやく体ごと背を向けた。
ライサンダーは彼女を引き留めることはしなかった。