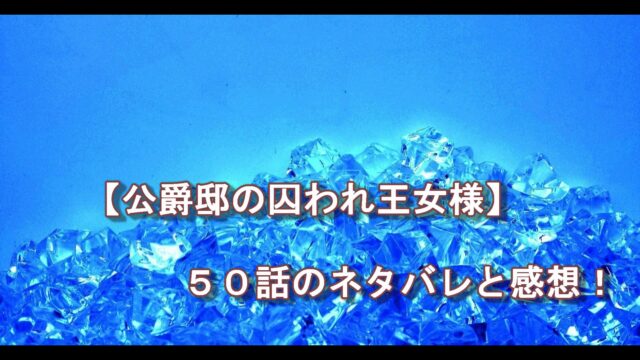こんにちは、ちゃむです。
「公爵邸の囚われ王女様」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

125話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 結婚の祝福③
「絶対にイヤ!」
ノアは両手で仮面をしっかり押さえて強く拒んだ。
クラリスが顔を触ろうとしていると勘違いしたようだった。
『そりゃあ、もちろん触りたいけどさ。』
でも今は、そんな理由じゃない。
「変な目的でそう言ってるんじゃないよ、誤解しないで。思いついたんだけど、ノアの顔にある石が何か話しかけてこなかったかな?」
「……まさか、僕の顔にあるあの変な石たちが君に話しかけてるってこと?」
「ううん、違うの。今まで一度も話してるの見たことない。ノアがいつも仮面をかぶってるからかもしれないけど。私は話してみたいの。」
彼の石は満月の夜に魔力を受けていないせいか、話すことが難しいのだろうと思われた。
「でも、それは明らかに話せる特別な石で、もしかしたら今ちょうど目覚めて話すかもしれない。」
「ないよ。いや、ないって。」
「ノア、どうしてそれがわかるの?」
クラリスはその場でパッと立ち上がった。
「仮面を外してみて。ちょっとだけ魔力を送ってみるから。」
魔力を送る。
それは、魔法使いが呪文で魔力を操作するのと同じくらい、ゴーレムマスターにとってはただの魔法的な行為にすぎなかった。
やり方はマスターによって違っていたが、クラリスの場合は、口づけを通して対象に魔力を伝えるのが一般的だった。
つまり……クラリスが魔力を渡すということは――
「……っ!」
頭の中が真っ白になったノアは、突然身を引いて机の後ろに逃げ込むように座り込み、長い指先で仮面をぎゅっと押さえた。
「ま、まさかそんなバカなこと言わないでください!」
「バカなことって?」
クラリスは両手で机に手をつき、身を乗り出して言った。
「私たちは魔法使いの塔で何があったのかを知りたいだけよ。だから、そこに行って帰ってきた石たちに話を聞きたいだけなんだから。」
「ぜ、絶対に僕の顔にある石には聞いちゃダメです!」
「ノア、顔じゃなくて、他の場所にも石ってあるの?」
そう尋ねたクラリスは、今にもノアの服をばっとめくって確認しようとするような、容赦ない目つきをしていた。
彼は妙な危機感を覚え、慌てて答えた。
「……あ、ないよ!」
「うん、ないのね。」
クラリスは少しがっかりしたような顔をした。
そもそも彼の体に石があったとしても、クラリスがそれを見る機会はないだろう。
「じゃあやっぱり、顔にある石に聞くしかないのね。」
「僕の顔の石はずっと黙ってたでしょ?明らかに深い眠りに落ちてて、何もわからないと思うよ。」
「それは分からないよ。眠りながら話を聞いている石もいれば、そろそろ目を覚ます石もいるかもしれない。それに、魔法使いの城には話す石が多いから、眠っていても精神が宿った可能性があるの。」
そう語るクラリスの顔は、まるで熟練したゴーレムマスターのようだった。
だからノアの顔にキスをするという話も、まったく気にせずに済ませることができるのかもしれない。
それはただ、「石」に魔力を渡す行為にすぎないのだから。
『でも――。』
ノアはごくりと唾を飲み込み、クラリスの唇をそっと見下ろした。
『ぼ、僕にはそんな風に考えられない……』
クラリスが石にキスをしたその瞬間、彼はまったく別のことを考えてしまうだろう。
そしてそれは、かつて公爵様から教わった「紳士らしさ」とはかけ離れたものになるに違いなかった。
『だから今日も、ただハンカチを差し出して、少女に無礼を働かないようにしていたのに。』
正直、その時は「仕方ない」と思いながらクラリスの手をそっと握っていたのも、事実だった。
クラリスはたぶん、そんなにおかしいとは思っていなかっただろうけれど。
幼いころからずっと、そうやって過ごしてきたのだから。
だが、それは哀しいことだった。
その行動で、彼は自分だけの密かな喜びを失ってしまうことになるだろう。
そして、それは顔の石に魔力を注ぐときも同じだった。
「実はノアが……あの石のことをあまり好いていないのは分かってる。だから魔力を注ごうとしないんだとも思って。」
いや、そういうわけではないのだが――
実際の理由を言えない彼は、慎重に扇子をくるくると回した。
「少し前、公爵夫人が本当に大変な目に遭ったじゃないか。もしモチとノアがいなかったら、どうなっていたか……」
不吉な予感が頭をよぎったのか、クラリスはつらそうにしばらく口をつぐんだ。
「それは、夫人の身元が明らかになる過程で起こったことで、私はその件について、何の疑問も残らないことを願っている。」
それはノアも同じだった。
少し前に公爵が彼に優しい心を向けてくれたように、ブリエルもまたノアに対して非常に好意的だった。
だからこの事件にはさらに強い関心を抱いていた。
「最後にお願い、ノア。小さな可能性でも見逃さずに、助けてくれる?」
そう言って、クラリスは彼を切実な目で見つめた。
少しの沈黙のあと、ようやくノアは答えた。
「……夫人のためだと言うなら、僕も心が揺らがないわけじゃありません。」
「それは、ノアが優しいから。私はそれを利用してるだけ。」
『本当にダメだな』とクラリスは自分に対して申し訳なく思ったが、実際にもっとダメなのはノアだったので、彼を責める気にはなれなかった。
どうしようもないと感じつつ、彼女はそっと視線を伏せた。
実のところ、彼は内心わずかな期待感を抱いていた。
「わかり……ました。」
「え、本当に?」
「ただし、これはあくまで夫人のためです。それ以外の目的は何もありません。」
ノアが言ったその言葉は、実は自分自身に言い聞かせているようでもあった。
これは口実のようなものではないから、変に勘違いしてはいけないと。
「うん、他のことは聞かないよ。じゃあ、仮面ちょっと外してくれる?」
クラリスは、たとえ団長であっても彼に手を出す気は……いや、彼の石に魔力を送るつもりのようだった。
「うん、わかった。うん……」
どういうわけか、彼の顔が少し赤くなった気がした。
戸惑いながら仮面を外そうとしたその時、クラリスが両腕をつかんで止めた。
「ちょっとだけしゃがんでもらえる?」
「う、うん……うん。わかりました。」
ノアは抵抗せず、クラリスが引っ張るままに身をかがめた。
顔がさらに近づいた。
「このくらいならいい? ね?」
「……」
「人の体についてる石に魔力を与えるのは初めてだけど、特に違いはないよね?」
「同じ……だと思います。たぶん。」
ノアはすでに、両目がかすかに見えるほど仮面を少し下げていた。
「このくらいでいいですか?」
唇を覆っているのは、やはり少し恥ずかしさがあったからだった。
「もう少しだけ下げてくれる?頬のあたりにも石が多いから。」
「そ、それはちょっと……」
「もー、ノアが自分の顔を気に入ってるの知ってるくせに?」
どうやらクラリスは、ノアが自分の顔を恥ずかしがっているのだと誤解しているようだった。
「実はこの話、しないつもりだったんだけど。」
クラリスはそっと微笑んだ。
「私、ノアの顔を長い間見られないのが寂しくて、って思ってたの。」
クラリスは「寂しい」という言葉にとても力を込めて言った。
「だから、魔力を与えればいいって考えたとき、実はノアの顔が見られるって思って、ちょっと下心もあったの。」
「……下心?」
「うん、すごくいやらしいでしょ?」
いやらしいというより、ただ可愛いだけだった。
特にノアが抱いていた下心と比べたら。
彼は、好きな女の子からキスしてもらえるかもと、すっかり舞い上がっていたのだ。
「う、わかったよ。」
ノアは顔にぴったりつけていた仮面をそっと外し、机の上に置いた。
すると、琥珀色の瞳が驚くほどにドキドキし始めた。
正直、この冴えない顔のどこがそんなに良いのかは分からないが――
「ノア、もっと……きれいになったと思わない?」
「……ば、ばかなこと言わないでください。」
「肌がもっとすべすべになった気がする! 触ってもいい?」
石がぽつぽつと並ぶ肌は、確かにすべすべだった。
けれど、クラリスは興奮を抑えきれず、今や温かい息さえ漏れはじめていた。
「うぅぅ、本当にきれい。」
「お好きにどうぞ。」
ノアはただ、クラリスの好きなようにさせることにした。
むしろその方が、この困ったけれど幸せな状況から早く抜け出せる気がした。
……いや、正直に言えば。
近くで自分の顔を優しく撫でて、じっと見つめてくるクラリスを見ているその時間が、何よりも幸せだったのだ。
何もかもが良かった。
くるくると変わる表情、呼吸の音、そしてなぜか温かいミルクのような甘くて柔らかい香りが……。
『ああ、本当に。』
このまま、もう一度ぎゅっと抱きしめられたらどれだけいいだろう。
しかし、彼の腕はすでにクラリスの両手にしっかりと掴まれていた。
いや、最初から人を勝手に抱きしめてはいけなかったのだ。
公爵様がこうおっしゃっていたではないか。
『神使として守るべき距離を考えなさい、ノア・シネット。』
その教訓を心に繰り返しながら、彼はむしろ両目をぎゅっと閉じた。
目を閉じれば、次々と湧いてくる他の欲望を捨てられるかもしれないと期待しながら。
しかし――クラリスの唇が自分の頬にそっと触れたその瞬間、すべての努力は一瞬で無に帰した。
力が抜けた手先で、彼は机の表面を軽く掻いた。
まったく、こんなにふわふわした存在がこの世にあるなんて、噂すら聞いたことがなかった。
「紳士」なんて言葉を思い出してしまうかもしれない。この強烈な誘惑に心を動かされない人間なんて、どこにもいないだろうから。
――お願い、あと少しだけ。
彼は、いつの間にかその温かな唇がもう少し長く触れていてくれるよう願っていた。
いや、もしできることなら……
「もういいかな?」
慎重に唇を離したクラリスがそう尋ねると、ノアは何がなんだかわからないまま「まだわかりません……」と答えてしまった。
すぐにクラリスがノアの頬の上に両手をそっと置いた。
その瞬間、ノアはこれまで嫌ってきたすべての石たちに、心の底からこう願った。
「空気を読んで、静かにしていてください」と。
もしそれで、さっきのやわらかさがまた自分に触れてくれたら――。
「うん、魔力はもう十分のようだけど。もしかして私が……話したくないから、そうしてるの?」
「そ、そんなはずがありません。もっと魔力が必要な……ようでして。」
ああ、もうやめてくれ、本当に。
ノアは自分でも恥ずかしさを感じず、そんなことを言っている自分に対してうんざりしていた。
どうせ後になれば自己嫌悪に陥るのは間違いなかった。
何も知らないクラリスを利用して、こんなふうに卑しい欲望を満たしているなんて。
これでは紳士ではなく、ただのクズと言われても仕方ない……。
「それなら、もっと魔力が必要みたいだね。」
そう答えたクラリスは、もう迷うこともなく、そのままノアの頬の上に唇をしっかりと押し当てた。
再び触れたときの、そっとした唇の感触が彼の頬をくすぐった。
ほんとうに、この可愛らしいお嬢様は、呼吸さえも愛らしくてたまらない。
ノアはただ、幸せなゴミになろうと決めた。
いや、もうなっていた。
クラリスがどれだけ唇を近づけても、石は何の反応も示さなかった。
「もしかして……そういうこと?」
「な、なんですか?」
ノアは、いつの間にか自分の爪痕が深く刻まれた机の表面をなぞりながら、手のひらでそっと答えた。
「ノアはずっとこの石を嫌がってたよね。」
「……そうだね。」
「だから、もしかすると拗ねてるのかも。昔、塀の外の景色がそんな風に見えたみたいに。ノアがお願いしたら、話してくれるかもしれないよ。」
「でも僕はゴーレムマスターじゃないよ。僕が頼んでも、何か変わるとは思えない。」
「そんなことないよ。セリデン邸の石だって公爵様やクエンティンおじさまの話にも、いつも耳を傾けているんだよ。だから、ノアの石もきっと同じだと思うの。いつもノアの気持ちを気にしているんだよ。」
「……」
まさか、それは――。
ノアは、さっき石がしゃべらないようにと心の中で強く願った。
もしもその影響で沈黙を守っているのだとすれば、クラリスの言葉は的を射ていた。
「……今度はクラリスが尋ねることに、どうか答えてください。」
ノアはどもりながら、たどたどしい言葉で頼んだ。
どこか気まずそうだった。
「わっ!」
すると、クラリスが喜びの表情で目をぱちっと開けた。
どうやら返事が返ってきたらしい。
「なんて言ったの?」
「うん、もちろんだって。ああ……」
ノアの頬に返事を伝えていたクラリスは顔を上げてノアと目を合わせ、答えた。
「本当に今話してもいいのかって、すごく慎重に聞いてきたの。だから私が大丈夫って答えてあげたの。」
「本当に、僕のせいだったんだ……」
彼がそんなふうにうなだれているとき、クラリスは彼の両頬を両手でそっと挟みながら見つめていた。
二人は何を話しているのだろう?
「ノアって、すごく優しいから怒らないよね……何? ブサイク? 可愛いよ。君、本当に可愛いんだから。」
何を話しているのか、はっきりとは聞こえなくても、なんとなく伝わってきた。
[わ、私が……出ても……ノア、怖がらないでね……]
ノアの石がようやく口を開いた。
もしかすると、長い間沈黙を守ってきた後遺症かもしれない。
同じことだろうか?
それとも、いつも仮面の中に閉じこもって「怪物」と呼ばれてきたせいかもしれない。
[ご、ごめん……いや、気を悪く……私を触らないで……]
臆病で自分を嫌うこの石の性格は、もしかしたらノアの一部でもあるのかもしれない。
クラリスは、その美しい石の表面を指の先でそっとなでながら微笑んだ。
「綺麗、君は本当に綺麗な石だよ。」
[……想像力の豊かな人。]
「聞きたいことがあるの。答えてくれる?」
[ぼ、僕は……何も……]
「ただ、他の石が話してるのを聞いたことがあるかってことよ。少し前にノアが魔法使いの城に行ったでしょう?そうでしょ?」
[………]
「今回、その城にある石が何か話してるのを聞いたことがないかなって。なんでもいいの、失踪した灰色のローブを着た魔法使いについてでも。」
石は沈黙を続けていた。
クラリスは黙らずに話を続けた。
「血縁検査に使われた血液のこととか、あるいはどこかの貴族の名前が出てきたとか、そんな話はなかった?」
[……くすん。]
「……!」
クラリスは驚いて凍りついたノアを見上げた。
「どうしたの?」
「うわ、どうしよう? 僕……すごく怖い聞き方をしたのかも。」
「少女は全然怖がっていないみたい。変な石だな。」
[ご、ごめんなさい、ノア……。]
「そんなふうに言わないで、ノア。友達には優しくしないと。」
「僕の友達は君だけだよ。」
「うん、ほんとに。」
クラリスは再びノアの石を見つめた。
魔力の影響か、赤い石が普段よりも少し輝いて見えた。
[ぼ、僕……眠っていて。]
「そうなんだ。満月に長い間会っていなければ、そうなるのも当然だよね。」
[それは……ノアが危なくなければ……静かにしているようにって……今も起きちゃだめなんだ……]
危ないときだけ目覚めるように設定されているってこと?
それはこの石の「主人」がそうしたということだろうか?
「危ないときに起きると、どうなるの?」
[……秘密、ごめん。]
「うん、わかった。じゃあ魔法使いの城で何か聞いた話はないんだね。それで結論づけてもいい?」
[ぼ、僕……ゴミなんだ。]
「ゴミだなんて!?」
あまりにもひどい言葉に、クラリスは思わず叫んでしまった。
すると、なぜかノアの方がびくっと震えながら驚いて、目をぱちっと大きく開けた。
「さあ、ごめんなさいって!」
理由はよくわからないが、彼は謝罪を口にした。
「ノアが謝ることじゃないよ。石が自分を責めすぎてるだけ。」
クラリスはノアの頬を握っている手に少しだけ力を込めた。
「自分のことを悪く言っちゃダメ。」
[……優しい人。す……好き。]
「うん、私も好きだよ。」
クラリスは石がほんの少しでも自信を持てるようにと、優しい言葉をさらに続けた。
「実はね、初めて会ったときからずっと好きだったんだ。心からそう思ってる。」
[魔力……またくれる?]
「うん、ノアと君が大丈夫なら、いくらでも。」
[いい……人。]
「そんなことないよ。私はただ、きれいな石に甘いだけ。今日こうやってお話できて、本当にうれしかったよ。」
[あ。]
そろそろ話を締めようとしたそのとき、石が何かを思い出したかのようにぴたりと止まった。
「どうしたの?」
慎重に尋ねると、石はしばらくうつむいて黙ったあと、ゆっくりと答えた。
[ノア…… 死にかけていたあの魔法使いが…… どうして…… そうなって…… え?]