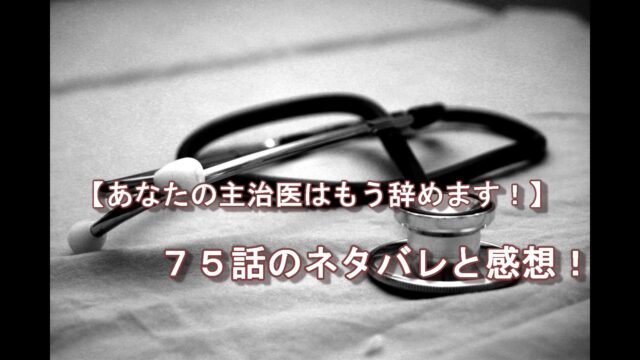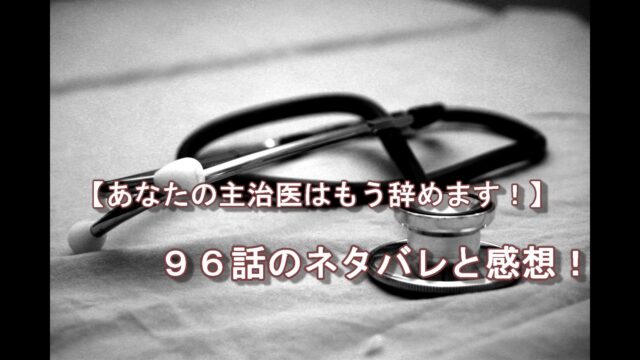こんにちは、ちゃむです。
「あなたの主治医はもう辞めます!」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

166話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- カンシアと子供たち③
リチェの妊娠がわかってから、公爵邸はすっかりひっくり返ったような大騒ぎになった。
落ち着いていたのはリチェだけだった。
「出勤は後にしなさい。完全に安定期に入ってからでいい。」
アルガは安定期までは研究室に来ることも考えるなと言い、すぐに長期休暇を与えた。
「うーん……このモビール、可愛いけど……もう少しお金をかけたデザインはないかしら?」
イザベルは子どものためのあれこれを買うことに夢中になり始めた。
一日があっという間に過ぎ、公爵邸は赤ん坊の物が少しずつ集まり始めた。
「エルアン、しっかりしなさいよ。叩いてあげようか?どうしてそんなにうっとりした顔をしてるの?」
エルアンは誰が見てもどこかおかしな表情を浮かべていたが、イザベルが真剣に問いかけると、次のように答えた。
「ただ……ただ天国にいるみたいで、そう思っただけです。」
その言葉を後に聞いたアルガはこう評価した。
「幸い死にはしなかったようだ。死んで天国に行くような人間じゃないからな。」
ともあれ皆が騒がしくしている中で、リチェはつわりの症状が出始めていた。
ひどいものではなかったが、強い眠気と倦怠感に襲われ、多くの時間をベッドで過ごし、少し神経質にもなっていた。
「リチェ、食べたいものはない?口にしたいものとか?」
イザベルとエルアンは熱心にリチェの枕元を守っていた。
イザベルが問いかけると、リチェは笑って答えた。
「毎日同じですよ。うーん、食べたいものといえば……ぶどう?」
「ちょっと待ってなさい。」
今はまったくぶどうの季節ではなかったが、エルアンにとってはそんなことはどうでもよかった。
すぐさま駆け出そうとするエルアンを引き止め、リチェが慌てて言い直した。
「違います。よく考えてみたら、いちごかもしれません……。」
「そうか?ちょっと待ってて。」
「いや、みかん?」
「三つとも持ってくるよ。ちょっと待ってて。」
三つの果物がすべて違う季節に実ることなど、エルアンにはどうでもよかった。
リチェが王家の果実を味わいながら、ついでに五つほど取ってみようかとエルアンを思案にふけさせている間、イザベルは切実に祈っていた。
「お願いだからリチェに似た娘を……お願いだからリチェに似た娘を……」
四つ目の果物としてバナナを選んだリチェが、微笑みながら言った。
「お母様、息子のような気がします。」
「息子?」
「はい、ただそんな気がするんです。」
五番目の果物を待ちながら、両手をきちんと揃えて立っていたエルアンの顔は、息子でも娘でも、とにかくどちらでも嬉しくてたまらないと物語っていた。
そのとき、掃除をしていた召使いのひとりが口を挟んだ。
「きっと女の子ですよ、奥さま。」
「え?」
リチェが聞き返すと、召使いは自信ありげに言った。
「積雲がよく出る月に授かった子は女の子だといいます。最近は空に積雲がとても多いですから。」
「……え?なにそれ……。」
リチェは呆れたように手を差し出した。
「胎児の状態と子どもの性別が何の関係があるっていうの。医学的な根拠はあるの?」
「医学では解明できない真実ですよ。ああ、それに妊娠中に雨の日に一日中横になっていると、子どもがおとなしくなるって話もあるじゃないですか?」
使用人の言葉に、リチェの顔が一瞬強張った。
子どもの性別については軽く噂話として受け流していたリチェだったが、「一日中横になっていると子どもが穏やかになる」という言葉だけは無視できなかったのだ。
彼女は真剣な表情で問い返した。
「そんなでたらめ、一体どこから出たの?」
「ただの平民ならみんな知っている事実ですよ?」
「ありえない。」
リチェが憤然として言った。
「私だって平民だったけど、そんな話は聞いたこともないわ。」
召使いは「それはただ友達がいなかったからですよ」と言いかけて思わず口をつぐみ、困ったように笑った。
「そんな馬鹿げた迷信が“学問では証明できない真実”なんて言われてるなんて……本当に気味が悪いわ。雨の日に妊婦のお腹を撫でるだなんて、そんな残酷なことがある?」
リチェはまるでアレルギー反応でも起こしたかのように身震いしながら吐き捨てた。
すると召使いが少し躊躇いながら問い返した。
「でも……本当のことかもしれないじゃないですか?」
「何を言ってるの?もし本当なら、私のような天才が知らないはずがないわ。今すぐ考え直して。お父様にも申し上げて、〈医学的根拠のない誤った俗説〉の本でも補充するようにお願いしなくちゃ……」
リチェは初めて、自分が本当に医学的根拠のない噂話に弱いのだと気づいた。
その言葉どおり、胸が詰まるような息苦しさを覚えたのだ。
「世の中、考えれば考えるほど腹が立つ……。ほかでもなく妊婦の健康に関わることなのに、そんな噂が広まるなんて……」
彼女の動揺を素早く察したエルアンが、急いで口をはさんだ。
「リチェ、怒らないで。な?すぐに五番目の果実のことを考えよう。」
結局リチェは悩みに悩んだ末、五番目の果物をスイカに決めた。
五種類すべてをどうにか手に入れて戻ってきたことを伝えると、部屋を出たエルアンはすぐに執事長と家令を呼びつけた。
「使用人たちをちゃんと教育しろ。みんな物盗みでもしたいのか、よくもまあ辛抱強く見逃してやったもんだ。」
エルアンはさらに冷たい顔で、いくつかの罵りを混ぜた容赦ない言葉を吐いた。
リチェの前で決して表情を崩さなかった顔との落差は激しかった。
もちろん執事長と家令にとって、その険しい顔は初めて見るものではなかったが、エルアンがあれほど刺々しい表情を見せるのは本当に久しぶりだと思った。
普段は誰にでもにこにこと笑って接するエルアンが、あんな冷ややかな表情を浮かべるほどなら、リチェの心を誰かが針で突いたように強く揺さぶったに違いなかった。
指先よりもずっと多くを拾い上げてきたのだから、これで終わるはずがない。
「絶対にリチェの前で医学的根拠のない戯言なんて口にしないでください。少しでもリチェにストレスを与えるようなら、私が直接相手をしませんから。」
根拠のない命令ではあったが、執事長と家政婦はすぐに「承知しました」と答えた。
「少なくともセレイアス公爵領では、妊婦に関する非科学的な迷信を誰一人信じないよう、きっぱり断固として徹底しろ。医学教育を受けておきながら、なおそんな話を口にする勇気ある者がいたら、すぐに私の前に引き連れてこい。」
そして消えていくエルアンの後ろ姿を見ながら、皆は心の中でつぶやいた。
「旦那様もずいぶん丸くなられましたね……。まさかこの程度で済ませるなんて。」
水晶の首飾りの箱を見たユリアとセドリアンは、大きな衝撃を受けた顔で呆然とし、瞬きを繰り返していた。
最初に感じた城の雰囲気は二の次で……自分を天才だと言って使用人の考えをすぐさま変えようとする人がリチェであり、「くだらないこと」といった粗野な言葉を吐く人がエルアンだったとは。
実際、カンシアやイサベルの目にはただの平凡な光景であったが、いつも優しく明晰な両親の姿しか知らなかった子供たちにとっては相当な衝撃だった。
リチェの苛立ちとエルアンの乱暴な言葉……考えれば考えるほど今まで見せたことのない姿だった。
いつも穏やかで優しい姿しか見せなかった彼らの両親が……今は。
「子どもたち、ちょっと待ちなさい。」
イサベルが慌てて状況を収めようと必死に言った。
「この時はリチェが妊娠していて……私たち両親もすっかり神経を尖らせていた時期なの。リチェも敏感になっていたし、エルアンも神経質で……。」
もちろん、ユリアとセドリアンはすでに強い衝撃を受けていた。
「子どもたちの夢や希望を踏みにじるのは、いつだって楽しいことだわ。」
カンシアが冷たく笑みを浮かべ、皮肉げに言った。
「完璧な親なんて世の中にどこにいるものか、こいつら。あのろくでもない公爵野郎が戻ってきて、地団駄を踏んで悲しめばいい。今日は実に有意義な一日だった。」
子供たちが震えるような表情を浮かべている間、カンシアはいつになく楽しそうに、ユリアとセドリアンの肩を優しく押して後ろへ下がらせた。
「この愚か者ども、そして世の中のことはすべてお前たちの思い通りにはならないってことを、この際よく学んでおけ。」
「さあ、ちょっと待て!」
カンシアがそっと水晶の首飾りをつかんで立ち去ろうとしたその手首を、イサベルが慌ててつかんだ。
「いくらなんでも、公爵家の使用人の持ち物を――」
子どもたちはようやく期待に満ちた目でイサベルを見つめた。
両親に対する幻想は崩れたとしても、今そばにいるイサベルに対しては、信頼が溢れているような眼差しだった。
というのも、この公爵用居住地の厳格な規律を最初に打ち立てたのがイサベルだと皆が知っていたからだ。
何もせずに怠けているように見えたとしても、イサベルは依然として気品に満ちたマダムのような雰囲気を漂わせていた。
この居住地の人々すべてが認める、本当に冷徹でカリスマあふれる引退したご婦人……。
「ほぅ。」
カンシアが鼻で笑うように薄く笑った。
「この状況であなただけ、完全無欠のご婦人という立場を守りたいわけか?」
カンシアはイサベルをからかうように、水晶をもう一度かざした。
するとイサベルが仰天して驚く光景が、短く再生された。
「結婚してください!私、本当にうまくやりますから。私は公爵様が好きなんです。結婚してください、ね?結婚してくれるまで、ジンドギみたいにくっついて離れません!イサベルはジンドギ!絶対に離れないジンドギ!」
まさにエルアンにそっくりな黒髪の男の背中にしがみついている、若き日のイサベルだった。
「きゃあ!やめて!」
イサベルは思わず驚き、自分でも気づかぬうちに声を上げた。
子どもたちは衝撃を受けた顔でイサベルを見つめた。
彼らにとっては、気高く上品で落ち着いたあの祖母が……いま、ユリアですら出さないような甲高い声を上げているなんて?
「明らかに過去は一度しか見られないって!魔力をかなり消耗するってさっき言ったじゃない!」
イサベルは言い訳するように叫んだ。
「それを信じたの?弟子にすら裏切られたのに、まだそんなに純真なのね。」
カンシアはくつくつと笑いながら、水晶球をさらに高く掲げた。
若きイサベルの声が庭園に響き渡った。
「愛というのは同じ場所を見ることだって聞きましたよ。今から一時間の間、あの白い壁を一緒に見つめてみませんか?ほら、ダーリン、そっちを向いちゃダメですよ!イサベルもあそこを見てるじゃないですか!退屈だって?だったらイサベルのことを考えればいいじゃない!」
自分の名前を三人称で呼びながら、言葉にならない主張をしているあの人が……冷徹さで有名な、あの祖母イサベルだなんて。
子どもたちは大きな衝撃を受けた。
若いころのイサベルがとんでもない美人だったことよりも、到底想像もつかない、目を覆いたくなるような光景だった。
もちろん、その光景を最も見たくなかったのはイサベルだった。
「やめて!やめて!今すぐやめなさい!やめろってば!」
「はっきりとあなたが行けって言ったでしょう?じゃあ私は行くわよ?」
「い、いや、ちょっと待って……」
うろたえるイサベルの言葉に、カンシアはもう一度水晶球をぐるりと回した。
本当に意地悪くも、相手は映らず、イサベルの顔だけがじっとクローズアップされて映し出された。
「あなた、今日は黒い服を着るといいですね。イサベルの澄んで愛らしい瞳を、より一層引き立たせてくれるはずです。」
その時代を知らない使用人たちでさえ、これ以上その場にいられないとでもいうように、静かに視線をそらし始めた。
年配の使用人たちになってようやく、「そういえば昔から奥様は先代公爵にかなり執着しておられた。公爵様は奥様に似たんだな。」と口をそろえて言っていたのを理解できる、というような顔をしていた。
「そしてイサベルの隣には、髪の毛のカールが印象的になるようにと銀色のカフスボタンをつけていて……」
セドリアンとユリアは毅然とした顔で、イサベルの銀髪と黒い瞳を見つめていた。
イサベルはとうとう耐えきれなくなった。
「だめ!お願いだからやめて!」
カンシアは肩をすくめ、気だるそうな声で言った。
「やめさせたいなら、結局私が行くしかないじゃないか?」
「お願い、行かないで!お願い……」
イサベルが震える手を差し伸べる間に、カンシアは口笛を吹きながら悠々とその場を立ち去った。
子どもたちに向かって皮肉を言うことさえしなかった。
「こうして大人になっていくのだよ、純粋な子どもたち。温室でだけ育ったお坊ちゃんたちよ。わかるか?身近にいるからといって、すべての人を信じてはいけない。」
そしてイサベルまでもが「行きなさい」と言ったカンシアを、引き止められる者は誰一人いなかった。
そのまましばらく呆然とし、皆が衝撃に浸っていた。
カンシアが去った庭園には、長い間沈黙が垂れ込めていた。
やがてユリアが自分のルビーの髪飾りがなくなっていることに気づいたときには、カンシアはすでに後を追うことができないほど遠くへ行ってしまっていた。